当サイトのメニューです。
下線部をクリックすると直接ジャンプできます。
第3節 中世期
Ⅰ.因幡国の鎌倉~室町時代
1.武士の台頭
2.「源平の戦」を経て武家政権の鎌倉時代へ
3.「承久の乱」で鎌倉幕府の支配確立
4.守護・地頭の荘園や百姓支配―泣く子と地頭には勝てぬ
5.鳥取が日本の歴史のひのき舞台へ―後醍醐天皇と伯耆船上山
6.守護の権力拡大と守護大名
7.守護山名氏の因幡国支配―布施天神山、鳥取は未開地
天下乱れ、下克上の世に―内紛外患で守護山名氏の弱体化
8.天嶮の鳥取城―目覚める久松山
初期鳥取城の築城
天神山から鳥取城へ本城移転
Ⅱ.浜坂地区の人々の暮らし
1.争乱の時代―要衝袋川下流の緊張
2.農村集落の共同体「惣村」の形成
3.浜坂村の萌芽
4.江津の農村化
5.江津・浜坂の水運業
6.両村の性格はどう形成されたか
Ⅰ.因幡国の鎌倉~室町時代
1.武士の台頭

9世紀末~10世紀初頭、国司と荘園領主の対立や混乱する地方政治の中から武装する地方豪族や開発領主らが出現した。彼らは地方に下った皇族や中・下級貴族を棟梁に武士団を形成していく。武士の登場である。
さらに、12世紀中期の平安末期頃には保元の乱(1156)や平治の乱(1160)など、貴族社会の内部紛争が武力で解決されるようになり、そのために動員された武士の地位が急速に上昇していった。
2.「源平の戦」を経て武家政権の鎌倉時代へ
11世紀半ばには、全国でほぼ国衙領(公領)と荘園(私領)の区別が確定し、以後、荘園・国衙領体制が中世を通じて展開されるが、領域内の土地と人間の一元的支配を目指す国衙領(公領)と荘園の間の対立抗争や、農民の反抗への武力支配などの必要から、いずれの在地領主も自己の立場を強くするためにそれぞれの武門の棟梁一派へ属していく。
こうして地方の武士が平氏や源氏という武門の棟梁のもとに統括支配される動きが始まり、源平の騒乱を経て本格的な武家政権へと繋がっていく。
全国で国衙領と荘園が対立する中にあって、因幡国には極めて荘園が少なく、圧倒的に国衙が支配する所領の郷・保が多い。平安末期に勢力変動が大きく激しい騒乱が繰り広げられた伯耆国と対照的である。これは国内の在地領主=武士の多くが国衙支配力体制の中に統治されていたからである。 (「新修鳥取市史」)
3.「承久の乱」で鎌倉幕府の支配確立
従って、因幡国において、平安~鎌倉初期の荘園や武士の進出による影響は緩やかで、律令の郷体制はあまり変動せず中世郷へと発展してきたと言える。
しかし、承久の乱(1221)を境に東国武士の進出が顕著で体制は大きく変質していく。鎌倉時代の承久3年に、後鳥羽上皇が鎌倉幕府執権の北条義時に対して討伐の兵を挙げて敗れた兵乱が承久の乱である。武家政権という新興勢力を倒し、古代より続く朝廷の復権を目的とした争いで、日本史上初の朝廷と武家政権の間で起きた武力による争いである。朝廷側の敗北で後鳥羽上皇は隠岐に配流された。
承久の乱で朝廷を負かした鎌倉幕府は全国の支配を確立。因伯にも鎌倉御家人を配置した。彼らは在地地頭領主となり、のちに毛利氏・矢部氏のように小戦国大名化したものもある。 (「法美郡鎌倉時代」・「鳥取県の歴史散歩」)。
4.守護・地頭の荘園や百姓の支配―泣く子と地頭には勝てぬ

承久の乱で鎌倉幕府に敗れた朝廷は全ての荘園や公領に幕府御家人の守護・地頭を配置することを認めた。彼らは次第に地頭の税を集める役目や守護の警察の役目などの立場を利用して、荘園、公領の土地や税の横領など、自分の土地や管理支配権を広げていった。
当時の百姓訴状には、抵抗すると百姓を脅した様子が記されている。家長を斬り捨て、妻子を奴隷と成し家財を略奪するなどの事例も多かったという。「泣く子と地頭には勝てぬ」である。
武士による土地をめぐる騒動は室町~戦国時代も続き、豊臣秀吉の太閤検地で荘園制度はようやく終焉する。太閤検地では荘園は廃止され、土地は公のものとなって、戦国大名は公から領地を一時的に預かる存在となった。土地の私有から公有の転換であり、封建制度が解体され、中央集権システムへの転換であった。 (「武士と荘園」・「地頭」)
5.鳥取が日本の歴史のひのき舞台へ―後醍醐天皇と伯耆船上山
.jpg)
承久の乱から100年後、正中の変(1324)・元弘の変(1331)で倒幕計画が露見し、隠岐に流された後醍醐天皇は、伯耆の豪族名和長年に護られて船上山にたてこもり、隠岐守護の佐々木清高らの追討軍勢を撃退、全国に倒幕指令を発信する。このとき鳥取は、はじめて日本の歴史のひのき舞台になったのである。この結果として、鎌倉幕府が倒れ、建武の新政を経て足利尊氏の室町時代が開く。幕府滅亡後、名和長年は後醍醐天皇により因幡・伯耆の国司・守護に任じられた。
(「鳥取県の歴史散歩」・「承久の乱」)。
6.守護の権力拡大と守護大名
鎌倉時代初期の貞永元年(1232)制定の御成敗式目は、守護を軍事・警察的な職務に限定し、国司の職権である行政への関与や国衙領の支配を禁じたが、室町時代、国内統治を一層安定させるため、貞和2年(1346)、武士間の所領紛争を実力行使で取り締まる権限(刈田狼藉)と、幕府の裁判の判決を強制執行する権限(使節遵行権)が新たに守護の職権に加えられた。この両者で守護は、国内の武士間の紛争へ介入する権利と、司法執行の権利の2つを獲得した。
また、文和元年(1352)には、軍事兵粮の調達を目的に、国内の荘園・国衙領の年貢の半分を徴収できる半済の権利が守護に与えられた。応安元年(1368)の半済令は、年貢だけでなく土地自体の半分割を認めた。守護は荘園領主らと年貢納付の請負契約を結んで(守護請)実質的な荘園支配を強め、経済的権能を強めていったのである。
並行して守護は強い経済力をもって、在庁官人、国内の地頭・名主といった有力者(国人)を家臣にしていき、土地の面でも人的面でも、国内の一円支配を強めて一国の主人となる戦国大名へと変化していく。
幕府はもはや南北朝時代の長い戦乱を通じて強い軍事力を手にした守護たちを抑えきれなくなっていたのである。
尚、半済令によって徴税権限が与えられた守護と役割が被っている地頭は次第に力を失っていき、多くは地元の有力者となり、守護と結びついたり、または守護の支配に反発して地方で力を強めていった。これを国人と呼んだりもする。
(「武士と荘園」・「守護」)
7.守護山名氏の因幡国支配―布施天神山城、鳥取は未開地

伯耆では建武4年(1337)に足利系の山名時氏が守護に任命され、以後、この時氏の子孫が統治した。正平18年(1363)、同じ山名時氏が因幡も平定。幕府から守護職へ任命され、以降240年間、子孫が因幡の支配権を握った。
山名氏が守護大名として因幡を統治した240年間を大きく3つに分けると、二上山城の時代、天神山城の時代、そして鳥取城の時代となる。南北朝以来、時代が降ると戦時状態が日常化したことで、城が「戦闘の城」の山城化していく。
鳥取の最初の中世の山城、即ち「戦闘の城」が岩美郡岩美町岩常の二上山(標高346m)の峻険な地形を利用した二上山城である。二上山は巨岩が所々に位置し、標高200m前後からの急勾配をもつ、極めて険阻な山である。
城は山頂部の一の平帯曲輪を中心とし、北東方向へニの平、そして大小8ヵ所の削平地からなる三の曲輪と続く主要部からなっている。このほぼ一直線に並んだ城の状況から、ニ上山城は北側からの寄せ手を意識して築城されたと推測される。
日本中を争乱の渦に巻き込んだ南北朝時代には全国各地に数多くの山城が築かれたが、その一つであるニ上山城は、戦いのための機能のみを備え、住居施設としての役割が完全に分離された典型的な南北朝期の山城といえる。
ここに築城した理由は、巨濃郡(現在の岩美町・福部村)で産出される金・銀・銅といった鉱産資源、当時の因幡の国の中心地であった現在の国府町方面への交通路(山陰道)の確保、そして古くからの海運で栄えた岩本の湊をおさえるといった経済的な面を持つ一方で、天嶮を活かした軍事的・戦略的にも非常に優れた立地条件を備えていたと考えられる。
二上山城の時代は、興国2年(1341)から文正元年(1466)までの125年間で山名氏の第一期といえる。
(「鳥取県の歴史散歩」・「城下町鳥取誕生四百年」・「岩美郡岩美町HP」)
天下乱れ、下克上の世に―内紛外患で守護山名氏の弱体化
しかし、標高300mを越える山城は麓の館と離れていて不便であること、また因幡守護所としては位置的にあまりに但馬寄りであること、また戦国時代半ばになると、城は軍事面以上に、政治・経済といった社会的中心地としての性格をより明確に持持つようになった。鉄砲の出現に代表される戦術の変化なども追い討ちをかけ、やがて二上山城は城としての機能を失っていった。
文正元年(1466=因幡民談記説)、山名勝豊が二上山から布施天神山に城を移し、天正元年(1573)までの107年間に渡る第二期天神山城の時代が始まる。
因幡一円を治めるとき、当時の鳥取付近は沼沢地であり、とても町ができるなど考えられなかったようである。天神山城はかつて内堀・外堀を備え、内堀は天神山を取り囲む南北400m東西300mの長方形に掘られ、外堀は布施の卯山をも包みこみ湖山池に通じる総延長2.6kmに及ぶものであった。
天神山の北を北東に流れている湖山川は、現在湖山池と日本海をつないでいるが、当時は川幅も広く千代川に注いでいたものと考えられる。天神山絵図を観ると水運に重きを置いた「水城」であったとも考えられる。
天神山城は、総構えの南部には多数の寺院や高級給人の居館を配し、東域には釣山城・北尾山城・鍋山城・吉山城といった出城・砦を多く配置している。また、近世城下町のような明確な都市計画ではないが、既にこの時、ある程度の城下町としての都市プランをもった先駆的な事例だと鳥取県史は伝えている。また、湖山池周辺は豊かな穀倉地帯でもある。


この時代は、将軍家や守護大名家の後継者争いのお家騒動が原因の応仁の乱(1467)によって天下は乱れ、足利幕府体制の権威は失われていき、下克上の世になってくる。応仁の乱以降、因伯でも因幡国人層などの争乱が30年余発生して守護山名氏支配は弱体化する。
出雲では守護代の尼子氏は守護職京極氏にとって代わり、西から伯耆や因幡へ攻撃を始める。尼子氏の最初の侵入は大永4年(1525)で、一時、現東伯郡湯梨浜町の羽衣石城、泊の川口城までその支配下においた。安芸国(現東広島市付近)の毛利氏は、高田郡吉田庄の地頭から一代で山陽・山陰10か国を領有する戦国大名の雄にまで成長し、後に、因幡における尼子勢力を一掃し、因幡を支配する。
一方で、天文(1532~)の頃には但馬の山名と因幡の山名は国境問題を期に骨肉相食む関係ともなる。このようにして、因幡の山名氏は、西の尼子氏に対して備える一方、東の但馬にも常に備えなければならなくなったのである。
(「鳥取県史」・「城下町鳥取誕生四百年」・「鳥取県の歴史散歩」)
さらに、後の毛利氏の脅威も尼子の背後に迫っていた。
8.天嶮の鳥取城―目覚める久松山 初期鳥取城の築城
但馬勢の来襲の方法を考えると、岩井口を突破してくるならば二上山城で防御できるが、水軍をもって砂丘に上陸してくる場合は手立てが施されていない。そこで、これに対応するために久松山頂に出城を設けることになり、天文14年(1545)、はじめて鳥取城が築城されることになったのである。 (「城下町鳥取誕生四百年」)
もともと天神山城は山が低くて平城に近く、住居には便利だが防御に弱い。敵の近接を阻み、自然の防御線である千代川を西に渡らせぬために、天嶮の久松山は絶好の前衛基地である。
鳥取城について、因幡民談記の作者、鳥取藩の小泉友賢は、「誠に地形無双の要地、国中第一の城塁なり。国家事ある時、この山をたより、この城にこもらば、外に堅甲利兵幾万の敵ありとも、近寄り得べき地にあらず。いわゆる金城湯地と称するもの、かかる地形をこそ云ふべけれ」と述べている。
この出城の出現により、いままで静かであった久松山をめぐって、ようやく騒然とした戦国の風雲が渦巻き始め、久松山はその黙々とした長い眠りから醒めることになる。
布施の天神山城を築いた頃、久松山下の平野の地は沼地の周辺に小集落が散在するのみで、政治・文化から遠くかけ離れていたと思われる。武田国信は自ら申し出てこの不便な鳥取城の定番となった。一国一城の主への野心を秘める国信は密かに鳥取城の戦備を固め、勢力拡大の後に山名氏への敵対を始める。山名氏と武田氏の内戦において鳥取城は天嶮によるその高い防御能力を見せつけた。
この内戦の過程において、一時期、武田氏が因幡一円を実権支配することになる。 (「城下町鳥取誕生四百年」)

天神山から鳥取城へ本城移転
内乱、外患を通じて久松山と天神山を比べるとき、平城とも称すべき天神山城よりも、天嶮による久松山城のほうが数倍も秀れていることを、後に、毛利の勢力下に入ることで武田氏をやっとのことで降した山名豊国は理解し、天神山の3層の天守櫓を久松山頂に移築し本城を移した(1573年)。そして、仙林寺、仙伝寺、真教寺なども山麓に移すことで、町屋も次第に移り、新しい城下町が形成されていく。
尚、この頃までの鳥取城の姿は、自然地形を巧みに利用し、山を削るなどして造られた「土の城」であった。「石垣の城」としての姿は、秀吉の重臣として活躍した宮部継潤の時代に整備が始まり、世界遺産で著名な姫路城を築いた池田輝政の弟・長吉や輝政の孫・光政の時代の拡張を経て、今日残る城跡の景観が整えられていく。
天正6年(1578)、毛利は尼子を降し、因伯での毛利の勢力は不動のものとなった。山名豊国は毛利の後援を受けて、鳥取城で因幡の管治を続けるが、全国統一の宿望をとげようと西へ進出しつつある織田と、山陽・山陰の中国全土に勢力を確立する毛利が、因幡を対決の地として激突しようとしていた。
羽柴秀吉の最初の鳥取城攻めはこの2年後のことである。 (「城下町鳥取誕生四百年」)
Ⅱ.浜坂地区の人々の暮らし
1.争乱の時代―要衝袋川下流の緊張
中世は「武者の世」、「乱逆の世」であった。保元・平治の乱、治承・寿永の乱、承久の乱、文永・弘安の役(モンゴル帝国の対日侵攻)、南北朝内乱、応仁・文明の乱、戦国争乱と、内乱・外寇の連続であり、そのために全国的に歴史史料は希少である。浜坂関連は皆無に等しいが、本誌ではこの中世こそ現浜坂村が萌芽した時代と考えている。寛文大図(1670年頃)に濱坂村が描かれる一定期間前、少なくとも16世紀には「空白の地」浜坂に鍬が入ったのだろう。
そして、水運拠点の港として発展してきた江津も、この時代に農村としても目覚めていったのだろうと考える。中世は古代と近世を結ぶ重要な架け橋であり、浜坂や江津が村として近世に向けて歩み始めた時代と言える。
世は争乱、因幡の地方はどうだったのだろうか。
「天文10年(1541)、巨濃郡(因幡の北東部、東は但馬国。北は日本海)岩井表で、出雲尼子氏に服従する因幡守護山名久通と、因幡国内に支配権を拡大しようとする但馬守護山名祐豊勢力との合戦があった。
この合戦を一つの契機として巨濃郡に隣接する邑美郡、とりわけ舟運の便もよい法美川(袋川)下流域は両勢力にとって戦術上重要な意味を持つことになった。」 (「鳥取県の地名」)
後の秀吉の鳥取城攻めにおいても、この秋里、江津、浜坂、重箱などは鳥取城への船を使った物流を監視し阻むという戦略上の最重要の要衝であり、中世から江戸時代にかけて緊張が絶えない地域となっていく。
2.農村集落の共同体「惣村」の形成
農村はどう変化したのだろうか。
鎌倉後期、百姓らは戦乱などからの自衛、水利配分や水路道路の修築、境界紛争などを契機に自衛的・地縁的な結合を強め、住宅同士が結合する村落(惣村)が形成されていった。惣村は、応仁の乱などがあった室町時代中期(15世紀)頃に最盛期を迎え、自治能力が非常に高まったとされる。

荘園領主や地頭などへの年貢は、元々、領主・地頭側が徴収していたが、惣村の成立後は、惣村が一括して年貢納入を請け負うことが増えていった。惣村では、生産に必要な森・林・山を惣有財産とし、共同耕作することも広く見られた。
また、農業用水の配分調整や水路・道路の普請など、日常生活に必要な事柄も主体的に取り組んでいった。 (「惣村」) さらに江戸時代になると、領主は村単位で農民を統治し、村請制といって村が年貢完納の義務、戸籍などの行政、橋や用水路などの管理、領主法令の順守などを行った。 (「江戸時代の村」)
このように中世の惣村を継承した百姓の共同体の流れと、江戸時代の村単位の行政ニーズを背景に、現代に通ずる行政ブロック「浜坂村」や「江津村」に進化していったのであろう。
3.浜坂村の萌芽
開地谷など、多鯰ヶ池周辺地から人々が浜坂へ移り住んだであろうことはこれまでに述べてきたとおりである。
しかし、古墳80基以上の開地谷(遺跡)などから全ての人々が浜坂に移ったわけではなく、隣接する湯山、山一つ越えた覚寺や円護寺などにも移り住み、多鯰ヶ池周辺をルーツとしたであろう。では、何故、多鯰ヶ池は最終的に浜坂村に属するようになったのだろうか。
その理由は、当時「空白の地」浜坂が、中世を通じて多鯰ヶ池からの大多数の移住者及び神社移転までを受け入れたことにより、多鯰ヶ池集落の大半と地縁・血縁の共同体(惣村)を成していったことによるのではないだろうか。既に人が住み、田を開き、土地の神を祀った地ではこうはいかなかったであろう。そして、お種弁天がある池北辺にあった集落は隣接する湯山(福部村)をパートナーに選んだのであろう。この自然形成的な農村共同体が、行政村区域を明確に定義した藩政期に引き継がれ、大半が浜坂村、そして北岸が福部村に属することになったと考える。
村づくりはどう始まったのか。
因幡民談記は、因幡国の村落の開発時期を、中世以前の「因幡国郷保庄記」所収の村落を中世とし、近世の「当代郷保庄記」所収の村落を近世の開発として分類している。これによると、江津が含まれる『野見保』は中世、浜坂の『中ノ郷』は近世である。 (「新修鳥取市史」)
同史によると、千代川右岸の中ノ郷を、地理的には袋川合流点の湿原にあたり、「因幡国郷保庄記」にも見られず、「袋川の氾濫と千代川本川洪水の逆流で、常習的湛水に悩まされる湿原として、近世最後まで取り残された地域」としている。
従って、移住時には砂で埋まり、または水が浸いていたかも知れない。昭和に入っても、「子どもの頃にもよく水が浸いた」(浜坂聞き取り)という土地である。農業を夢みて移ってきた人々にとって、水害・砂害と闘う日々の連続だったのではないだろうか。何から手をつけたか。何から作ったのかなど、ただただ想像するしかない。
室町時代(15世紀頃)の執筆とされる教養書『庭訓往来』には、「麦・大豆・小豆・大角豆・粟・黍・稗」といった畠作物の記述がある。救荒作物サツマイモは、江戸時代初期(17世紀初め)に日本に伝来したもので、まだこの時期には登場していない。
(参考)
「新修鳥取市史」は、江津の『野見保』を「自然堤防周辺に位置し、洪水に対し比較的安全な地域であり、野坂川を水源とする『松神西郷』の余水を取り入れる条件を備えていることから、中世開発の耕地とみなすことにやぶさかではない。ただし、『野見保』は中世に『能見郷』」から『保』へ格下げされ、未開発的な村落として扱われている。このような扇状地の端部や自然堤防上の耕地は、治水や利水の視点でも、近世の再開発的な地域とみられる」としている。
また、江津に隣接する晩稲や南隈などの『南北保』をさらに劣環境の近世としている。
江津における安定的耕作は中世以降、浜坂や中ノ郷は大きく遅れて江戸時代ということになろう。
生活を助けた中世の浜坂漁業
藩政期に山役と藪役の小物成(年貢)が課されていることから、材木・薪や竹など近隣の山野から産するものや、山の猟なども生活の糧になっていたのであろう。ただ、移住当初はとにかく日々の食べるものにも困窮したに違いない。そこで何よりも手っ取り早いのが目前を流れる千代川の漁ではなかったか。多鯰ヶ池出の民にとって漁は伝統的な技である。

さらに、近隣の沿岸村では 「千代川では鮭・鱒・鮎などの漁獲が行われ、とりわけ高級魚とされた鮭は、近世にが藩主池田家から将軍家の献上品や諸大名などへの贈答品となっていた。秋里・安長・田島村の三ケ村は一組になって御用漁を行った」(「在方諸事控」)
また、「江津村でも「千代川から鮭・鱒・鮎を漁した」(「因幡民談記」)と活発である。
従って、対岸の浜坂も、漁環境は他村に劣らなかったはずで、まだ農業生産が離陸していない当時においては目の前の千代川漁が人々の生活を支えたことは想像に難くない。
しかし、それは将来(江戸時代)に渡って一定規模の漁業に育つことはなく、自給自足以下であったようだ。また、多鯰ヶ池については「当地の名物として鮒・鯰・鴨」(「因幡民談記」)と記されているが、やはり、川役(税)の対象規模ではなかったようだ。浜坂の漁業については、江戸時代の「浜坂・江津の漁業」で詳細に述べる。
4.江津の農村化の始まり
古代より千代川と袋川の合流地点にあって、因幡国の国津として歴史に登場する江津にも「高庭荘」時代から耕作地があったことは荘園復元図(「鳥取県地誌考」)などで明らかである。ただし、当時の江津が「農村」であったかどうかは疑問である。
「永禄8年(1565)3月、秋里与四郎に『高草郡江津内』」などで計7町8反の地が山名豊儀から宛行われた。」と山名豊儀宛行状にある。秋里氏は南接する秋里の地名を名乗る武士であろう。」 (「鳥取県の地名」)
さらに、「慶長10年(1605)の気多郡高草郡郷帳では、『秋里』がみえ、高一千三三石余、田七七町七反余・圃三五町八反余、物成七六三石。この数値にはのちの江津村も含まれると考えられる。」(「同」)とある。
これらから、中世末期から江戸初期までの江津は水運港を担う水夫や漁民などが住む津(船着き場)であり、荘園の一部であった周辺農地は開発途上、または秋里の出先耕作地のような存在だったと想像される。
一方で、江津の『濱橋家由来記』中の「―源氏滅亡後に浪人となり、348年間15代、諸国を放浪した末に浜坂村で農民となり、天文年間(1532~1555)に因幡守護の山名氏の許可を得て浜坂を去って江津村を開き始める。これを濱橋家の中興の祖としー」(「千代水村誌」)は、かつての「船津里」の、農村としての開花を物語っているようだ。ただし、正式な歴史記録である上記の永禄8年(1565)の山名豊儀宛行状と照らし合わせるかぎり、真の独立時期はもっと遅いようではある。
後の大庄屋松本氏もこの時代(戦国時代)に武士から帰農したとされ、この「開村」の動きに加わったのかもしれない。そして、彼らの登場が、江津地区における武士出身地主の農地寡占につながっていったのかもしれない。
江戸期には寛政20年(1643)の『田畑永代売買禁止令』が出され、土地の売買を禁じている。従って、多くの土地を所有し得たのはそれまでの中世期であり、この富が、明治6年(1673)の売買解禁で更なる土地の所有につながっていく。
浜坂には絶対規模地主はいない。これは「江戸期末には武士の家筋が何軒かあったが、その前にはいない」(浜坂聞き取り)のとおり、江津の帰農武士ような「別格な存在」がいなかったからであろう。
5.江津・浜坂の水運業
古代因幡の「国津」江津は、多国間の商業流通が発展を始めたこの中世には、新しく鳥取の玄関港となった賀露へ主役を譲る。それでも以降、江戸期から明治時代までも、鳥取と賀露の中間に位置し、舟の往還で賑わったとされている。

他方、対岸の浜坂が袋川の水路と但馬往来陸路(丸山―浜坂犬橋―砂丘はま道)の交わる交通の要所となっていくのは但馬往来が整備された江戸時代のことであるが、但馬への防御目的で久松山下の城が誕生してからは、鳥取城側・但馬側に位置することで、江津とはまた違った戦略的価値が見出されていったと考えられる。
そして、対岸の江津水運の賑わいを眺めつつ、自らも同等の地理的重要性に目覚めていき、鳥取城が因幡の本城となる頃(1573年)には、水運業に携わる村人が現れ始めたのではないだろうか。秀吉の鳥取城攻め(1581年)では、浜坂下の千代川~袋川水路は鳥取城への武器・食糧補給を断つための最大要衝となる。
藩政時には、「城下の洪水時に藩が出す御救船には賀露水主とともに浜坂水主が召集された(「在方諸事控」)」とあり、江津に伍するほどに水運業が盛んになっていたことが推察される。当時の賀露村の記録に「廻船業も盛んであったから、漁師のなかには船頭や水主として働く者も多かった」(「鳥取県史」)とあり、水主とは(廻船)水主を指していることが分かる。
6.両村の性格はどう形成されたか
以上のような浜坂、江津の村の成り立ちが、村の性格というものに大きく影響したと考える。
江津は、1.古代より栄えた因幡国の「国津」 2.鳥取平野と高庭荘 3.武家出身の地主 といった特徴を持ち、一方の浜坂には、1.中世に「空白の地」へ移り住んだフロンティア 2.砂丘と山、川に囲まれた狭隘地 3.別格の地主の不在という特徴がある。
人がそれぞれの性格を持ち、幼少期からそれを形成していくように、この古代から中世にかけて両村の性格も醸成されていったのではないだろうか。
.jpg)
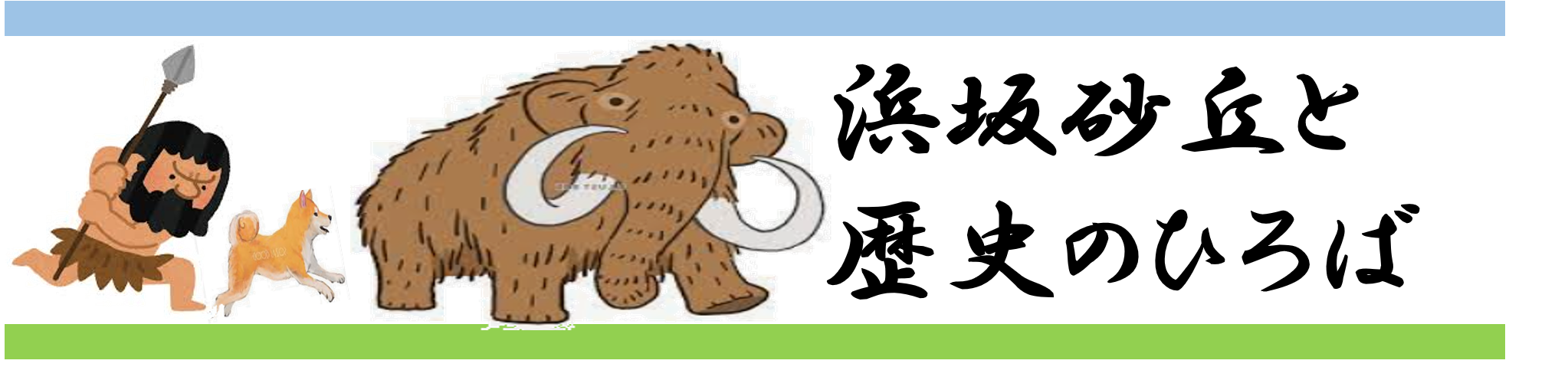
.jpg)
2.jpg)
