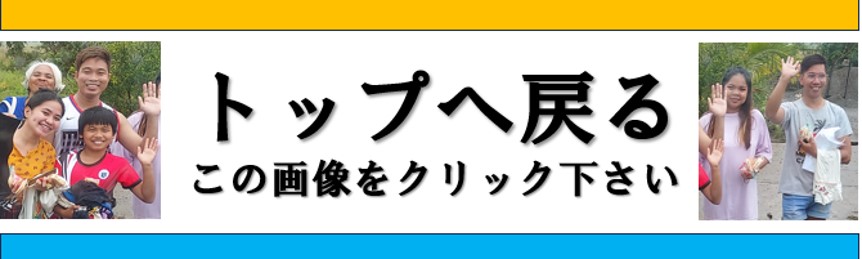バレテ峠の死闘を物語るバレテの木
「バレテ峠」の地名の由来は、バレテの木が数多くあったからという。
バレテの木は、フィリピンでは「神の木」ともいわれ、たくさんの気根が垂れ下がる巨大な樹木。激戦でバレテの木は失われ、峠の中腹に1本だけ残ったという。まさに死闘を物語る。
目次
下線目次をクリックすると、目的位置までジャンプできます。
1.バレテ峠の戦いの概要
・フィリピンの歴史
・大戦におけるフィリピンの攻防とバレテ戦
・比島戦を顧みてーフィリピン戦とは何かを考える
2.バレテ戦生還者・遺族の記憶生還者の記憶
2-1.生還者の記憶
・戦雲の証言台
・我が戦場点描
・追憶ー私のバレテ
・悲運の航空部隊 バレテ峠妙高山で散華
・悲運輸送船乾瑞丸の最後とその前後
・鉄兵団バレテ峠の激闘
・バレテの戦いー陣地づくりから戦闘開始まで 第二大隊の状況
・戦場寸描
・終戦を知らずして山中放浪七ケ月
・追憶ーバレテ会結成
・バレテの死
・比島戦没者遺骨収集を終えて
・英霊は待っている
・カガヤンの亡骸
・戦死に悲し鉄部隊
2-2.遺族・関係者の記憶
・S氏の思い出
・新しい軍装に着替えてーサラクサク峠の死
・遥か虹の彼方より
・初めて書く父への手紙
・父の眠る地を訪れて
・駄目な顔
・五十年忌を迎えるにあたり
・はじめての慰霊祭に参拝して
・フィリピン慰霊ツアーに参加して
2-3.その他
・バレテ峠より発見された認識票
・米国から戦利品の写真遺族に返したい
・大場 薫様からの手紙ーサンタフェ町へ移住し、地域活動中
1.バレテ峠の戦いの概要
フィリピンの歴史
南シナ海と太平洋にはさまれた、7,100あまりの島々からなる。人口は1億1500万人(2023年)、首都マニラ。
タガログ語をはじめ、多数の言語を使う部族に分かれて漁労中心の生活を送っていた中、1521年、スペイン艦隊を率いたマゼラン船隊が世界周航の途次この島を発見。1520年代にメキシコがスぺインの植民地となったが、1564年にメキシコから出向したミゲール・ロペス・デ・レガスピとその一隊は、マリアナ諸島を経て1569年にルソン島に到着、これを征服して初代の総督となり、原住民首長と友好関係を結び、征服を周辺の島々にも拡大、1571年には首都マニラ市を建設した。
征服者は、時のスペイン国王フィリップ二世の名に因み、この群島をフィリピーナスと呼んだ。スペイン人の到着はフィリピン史にとって大きな意義を持つ。スペインによる植民地支配は19世紀末まで続き、イスラム教徒の侵入は阻止され、スペイン人によって様々な修道会(教会)による住民の教化が行われ、この新しいカトリック信仰を通して西ヨーロッパ文化が根を下ろしていった。バレテ会慰霊巡拝行の道筋でも、サンホセ、サンタフェ、サンニコラスなどスペイン風の地名が多く、教会の威容とその美しさに驚く。
19世紀後半に独立運動が開始され、1898年のアメリカ=スペイン戦争時に独立宣言を行うが、同戦争後スペインからグアム島とともにフィリピン諸島を譲り受けたアメリカは独立を認めなかった。第二次世界大戦の勃発後の1942年、日本軍はフィリピンを占領し軍政を布いた。その後、レイテ島、ルソン島、ミンダナオ島などで日本軍と米軍およびフィリピンゲリラ間で激烈な死闘が行われ、ルソン島バレテ峠が日米の最後の決戦となった。大戦後の1946年7月、アメリカはフィリピンの完全独立を認めた。
なお、日本とフィリピン(ルソン)との交流は江戸時代以前から始まり、家康の時代には友好国となり、日本の朱印船が往来し、マニラ日本人町の人口は三千を超えていたという。付近には日本人の子孫だという伝説も多いという。明治になって、マニラ麻の栽培など、続々と邦人の在留が増え、戦前のフィリピン在住の日本人は2万7千人であったと記録される。先の大戦は日比両国にとって遺憾な事実ではあるものの、日比のつながりは深い。


大戦におけるフィリピンの攻防とバレテ戦
昭和16年(1941)12月8日、日本軍は、アメリカの海軍基地があるハワイの真珠湾やイギリスの植民地のマレー半島を奇襲攻撃し。以降、当時のアメリカの植民地であったフィリピンやグアムなどを含む、アジアと太平洋の広大な範囲を勢力圏に収めていく。
昭和16年(1941年)、大東亜戦争勃発と同時に、日本軍は南方作戦の一環としてフィリピン攻略戦を実施した。フィリピン諸島は日本と南方資源地帯の中間に位置し、ここが米軍植民地として抑えられたままだと南方との海上輸送ができないからであった。
ルソン島北端のアパリなどに上陸した日本軍は、翌年1月にマニラを、4月にバターン半島を占領した。5月にコレヒドール島に立てこもる米比軍が降伏を申し入れ、翌日には全在比米軍が降伏した。この際、敵将マッカーサーは、米軍10万人を残しオーストラリアへ脱出し、敵前逃亡として軍歴に傷をつけたとされる。
バターン半島の米比軍が降伏したとき、約7万6千人が捕虜となり、日本軍は捕虜を後方のオドンネル基地に移送した。当初は、30kmを行軍、50kmをトラック輸送する計画であったが、捕虜の数が予想以上に多く、またトラックの必要数が確保できず、半数以上の捕虜が全行程を徒歩で移動することになった。日本軍では1日数10kmの行軍は特に珍しいものではなかったが、食料が尽きマラリアが蔓延していた米比兵の体力は極端に低下しており、行軍の際に1万人あまりが命を落とした。これは後にアメリカで『Bataan Death March(バターン死の行進)』と呼ばれ、アメリカ国内での反日感情を煽る宣伝材料とされた。
昭和19年(1944)年6月、マリアナ沖海戦(ミッドウェー海戦)は日本の敗北に終わり、7月9日にはサイパン島を失陥してマリアナ諸島の喪失も確実なものとなった。
10月、フィリピン奪還を狙うマッカーサー率いる米軍はレイテ島沖へ700隻の艦船を投入し、レイテ島に上陸を開始した。日本海軍は米輸送船団を攻撃すべく戦艦「武蔵」をはじめとする大艦隊を送ったが、米艦隊の戦力は強力であり、「レイテ沖海戦」で「武蔵」を含む多数の主力艦艇が撃沈され、日本海軍は事実上壊滅した。制海権を取られたままレイテ島を決戦場に選んだ日本陸軍は、輸送・補給もままならず多くの戦力を失った。米軍は、2か月で日本軍8万人をせん滅し、このレイテを拠点に北のルソン、南のミンダナオ攻略を進めていく。フィリピンを完全に失うことは、日本本土への攻撃を容易に許すことになる。日本軍は、戦力を「尚武」「振武」「建武」の3集団にわけて防衛態勢に入った。
昭和20年(1945)1月9日、連合軍は、3日間以上の激しい事前砲爆撃に続いて、ルソン島リンガエン湾に上陸を開始した。「建武」3万人は、リンガエン湾南方のクラーク地区にある13の飛行場群を防衛し、連合軍による飛行場利用をできる限り遅滞させることを目標とした。米軍は猛攻でこれを制圧し、主力部隊はそのまま首都マニラへ突入した。その後のクラーク地区は、激しい空襲と戦車火力で陣地付近の森林は焼け野原となり、日本軍は壊滅した。
「振武」が迎え撃つマニラでは、1か月間の激しい市街戦が行われ、このときの死者は日本軍約1万2千人のほか、市街地中心部は廃墟と化し、10万人以上のマニラ市民が巻き添えとなった。2月、マニラは陥落した。その後も、「振武」は各地で終戦までゲリラ抗戦を続けるが、初期兵力約10万5千名のうち、終戦直後に米軍施設に収容された者は約1万3千名とされる。戦死6万名、マラリヤや飢餓などによる戦病死1万5千名、行方不明1万3千名などである。

一方、日本軍主力「尚武」は、ルソン島北部山地における防衛戦を展開した。司令官の山下大将は、艦砲射撃を多用する米軍相手では、水際より艦砲砲弾が届かない山岳戦が望ましいと、敵をルソン島に一日でも長く可能な限り引き付け、持久戦によって「本土への直接進攻を遅らせる」方針を決断していたのである。
比島ルソン島は、カラバリヨ山系によって南北に画されている。中部ルソン平野から北部ルソンのカガヤン河谷に通ずる唯一の自動車道が国道5号線であり、このカラバリヨ山系を越える最高地点が「バレテ峠」である。こここそ、日米の両軍が百日の凄絶な攻防の死闘を繰り広げた戦場である。
カガヤン河谷は、食糧を多方面に移出する豊穣な米生産地である。日本軍は、このカガヤン河谷を内懐とし、ここに自活自戦永久抗戦の根拠地を構築しようとしたのである。そのためには、その南に位置する天嶮の要害バレテ峠及びサラクサク峠で堅固に守備し、南から迫る米軍をそこで食い止めることが不可欠であった。
峠の守備は第十師団(鉄兵団)及びその同配属部隊が担った。そして、その主軸が鳥取、島根県人などで構成される歩兵第六十三聯隊であった。
昭和19年(1944)7月25日、「鉄」動員下令なるものが師団司令部に届き、当時、北満でソ連国境の警備にあった六十三連隊も「鉄五四四七部隊」として臨時編成され、4千5百人中より2千3百20人が鉄部隊に編入された。六十三連隊主力は9月3日釜山を出港、門司、台湾基隆、高尾を経て比島ルソン島へと向かった。
昭和19年12月23日、ルソン島サンフェルナンド港に着き下船命令で上陸作業の始まった頃、僚船乾瑞丸が魚雷4本を受けて港外5マイルの沖合で轟沈、この日、乾瑞丸に乗船していた第三大隊660名の中で290名が海没・戦死したほか膨大な兵器弾薬糧秣を失った。更に、夜を徹して揚陸作業を行った山積みの物資も、敵の艦砲射撃と空爆で一度に吹き飛んでしまった。鉄部隊は上陸第一歩から追いつめられていたのである。
上陸後、空襲をのがれて夜行軍を続け、1月中旬、海抜千数百メートル千古の謎を秘めた密林のバレテ峠に到着、直ちに陣地構築を始めた。ハレテ峠までの道は、デグデク河の谷に沿って南麓のサンホセから50キロのつづら折りの山道であり、嶮しい山々が両翼に聳えている。そこは、日光が地面に届かぬジャングル地帯であって、マラリヤ蚊と高熱を出させるヒルに苦しみながら砲兵陣地、対戦車、対歩兵の障害陣地を構築、狭い谷と険しい山を利用して長期抗戦の態制を整えていった。
しかし、国道5号線に沿って北上する米軍によって、最前線のウミンガンやプンカン、次いでデグ デグ、ミヌリの玉砕が続き、3月には妙高山・妙義山・金剛山・キリ・カシ・ヤナギ陣地等と山岳地帯の激闘へ移っていく。米軍による威力偵察も始まり、B29をはじめとする敵機の間断なき銃撃に対し、兵団は一発の応射も許されず、毎日敵機が頭上に乱舞するのを切歯扼腕しつつ眺めているだけであった。米・比軍の地上砲火は、鉄兵団の一発に対して十倍以上、ところによって千倍、しかも火啗放射器及び黄燐弾は山容まで変えていった。この間に日本軍機は一機も飛来せず、米・比軍は日本軍が戦車の進入は不可能と見ていた如何なるジャングル、如何なる急峻な山頂迄も「ブルトーザ」をもって道路を構築し、1日に100メートルから200メートル前進。前進陣地の攻撃は観測機をもって周辺を捜索し、陣地らしいものを発見すると、後方の砲兵陣地より砲弾の雨を降らせ、守兵のいないことを確認した後、戦車を中心にした歩兵部隊が初めて攻撃した。
5月30日、遂に峠は米軍に占領され、6月1日、日本軍残存部隊は退却を開始した。実質的全滅であった。こうして日本軍残存兵力は、6月から終戦を迎えるまでの期間、北へ北へ、カガヤン河上流地域を「ピナバガン」 に向けて雨季を迎える密林を転々とすることになったのである。「死の転進」である。ドシャ降りの豪雨が落ちゆく兵の全身を容赦なくたたく。飢餓、極限の疲労と絶望、マラリヤなどで兵は次々に倒れ、密林の枯骨となっていった。
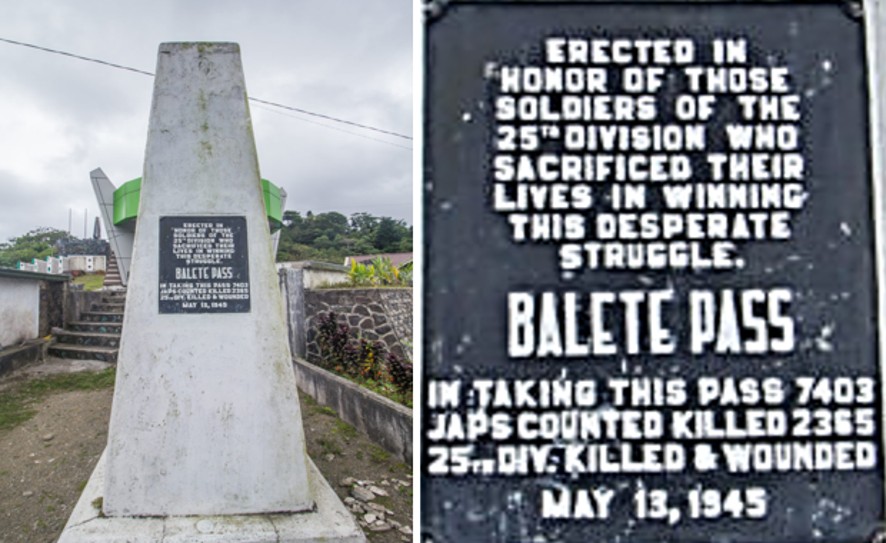
マッカーサー戦記は、バレテの激闘を「ここは、アメリカ史上最も野蛮に激烈に戦った戦の一つであり、アメリカ軍にとってこれほど補給上の困難が大きかった地形はなく、これほど天然自然に難攻不落の利を敵に与えた地形もなかった・・・」と回顧している。また、バレテ峠の頂上に立つダルトン記念碑は、バレテ戦で戦死した米軍ダルトン将軍を悼むものである。
碑に刻まれた「THIS DESPERATE STRUGGLE」 (この絶望的なる戦い=直訳)は、この戦いが米軍にとっても、いかに凄惨・困難なものであったを物語る。
終戦の4日後、8月19日に山下大将は停戦命令を受容した。しかし分散した各部隊への連絡は困難で、半年かけてようやく全軍が降伏した。降伏までに日本軍は20万人が戦死あるいは戦病死した。バレテ峠やサラクサク峠の戦いの後は、そのほとんどがマラリア・赤痢などの病死、餓死、ゲリラ等の抵抗勢力の襲撃によるものとされる。フィリピン防衛戦では、大東亜戦争の戦線の中で最も多い33万6千人の日本軍将兵が戦病死している。日本とフィリピンのあまりにも深重なる関係を思い知る。鉄兵団は、配属部隊を含み総員2Ⅰ,727名、生還者3,001、六十三聯隊は満州を出発したと時の兵力は2千3百20人、生還者は、わずかに90名にすぎなかった。
比島戦を顧みて ー フィリピン戦とは何かを考える
先の大東亜戦において、 フィリビンの第十四方面軍は、レイテ島に始まった十一ヶ月に及ぶ悲惨な戦いの末、殆ど壊減状態で、八月十五日の終戦を迎えた。もともと大東亜戦争の天王山と目されていた比島方面決戦=捷一号作戦Ⅱでは、「地上決戦はルソン島に限定して行う」という基本方針が確定されていた。
ところが、敵がレイテ島に来攻するや、大本営、南方総軍は、山下大将の強硬な反対を押し切って、ルソン島決戦方針を急遽レイテ島決戦に変更した。その理由は一に、昭和十九年十月十二日に始まった「台湾沖航空戦」における海軍の誇大戦果発表にあった。即ち海軍が発表したその戦果というのは、次の通りであった。
大本営発表 (十月十六日一五〇〇)
台湾沖航空戦の戦果次の通り
轟撃沈 空母十、戦艦二、巡洋艦三、駆逐艦一
撃破 空母三、戦艦一、巡洋艦四、艦種不祥四、更に撃沈破五と追加戦果が発表された。
この戦果が真実とすれば、米空母は全滅という正に驚嘆すべき大戦果であった。然し事実は、空母の損害は一隻もなく、巡洋艦二隻を大破したというのみであった。
その後、海軍もこの戦果に疑念を持ち検討に入ったが、その疑念も、誤報についても、国民に対し訂正しなかったのは勿論、大本営陸軍部にさえ通報しなかった。
この結果、海軍部の大戦果を信じた陸軍部は、愈々敵情判断を誤り、敵空母が全減した今こそ、 レイテに来攻した敵に痛撃を与え、一挙に戦勢を決する好機と誤断し、急遽ルソン決戦方針をレイテ決戦に変更した。この方針変更については、山下大将以下方面軍首脳部は極力反対したが、最後には命令として強行されることとなった。このような経過で、無理なレイテ戦が強行され、徒らに八万の将兵の命が、 レイテの山野で失われるという結果を招いた。もしこのような誤報がなかったならば、 レイテにおいてあれ程の犠牲者を出さずに済んだであろうと想えば、残念というより、憤りさえ覚える。
レイテに始まった凄惨な戦いは逐次比島全島に繰り広げられる事となった。しかし、いつの時代でも、またどのような戦争でも、戦争による最も大きな犠牲者は、その地域の罪もない住民であるということは比島でも例外ではなかった。当時フィリピン国民の間では既に「スペインは宗教をもたらし、アメリカは学校を建て日本は何も与えていない」と云われていた。与えるどころか、食糧をはじめ必要物資の補給がなかった日本軍は、軍票をもってそれらを現地調達したのでフィリピンの経済は混乱した。更に米軍上陸後、山中に包囲されてしまった日本軍は、山岳原住民や米や畑の藷までも奪う結果となった。
このようにして、殆ど総てのフィリピン人は、次第に反・坑日に転じて米軍に協力し、激しいゲリラ活動やスパイ活動を展開した。この為日本軍は、優勢な米軍との戦いの他に更に一七〇〇万人のフィリピン国民をも敵として戦わねばならなかった。このように全住民を敵にした激しい反日坑日の下での戦いは、ビルマやインドネシア等他の戦地とは異なる比島戦の大きな特色であったと言えよう。
このようにして日本軍の動静は、フィリピン人によって米軍側に通報されて筒抜けとなり、これによって日本軍の作戦がどれ程阻害され、また将兵の命が失われたか計り知れない。レイテ戦だけでも、八千人の将兵が、ゲリラや住民の犠牲になったという。この為、これらのゲリラやスパイに対抗する為に憲兵等によって厳しい摘発が行われ、フィリピン人は日本に対する反感を益々増幅させるという悪循環が繰り返された。
しかし何れにしても、日米戦に関係のなかった一般フィリピン国民をも戦火の中に巻き込み、多くの犠牲者を出し、また計り知れない戦禍をフィリピン国民に与えたことは、真に申し訳ないことで、これは少々の経済的支援などでは償いきれるものではないであろう。
一方日本軍においても、比島において五十万人という多くの尊い命が失われた。これを大東亜戦争の中で、最悪の激戦地として一般によく知られている戦域の数字と比較すると別表の通りである。
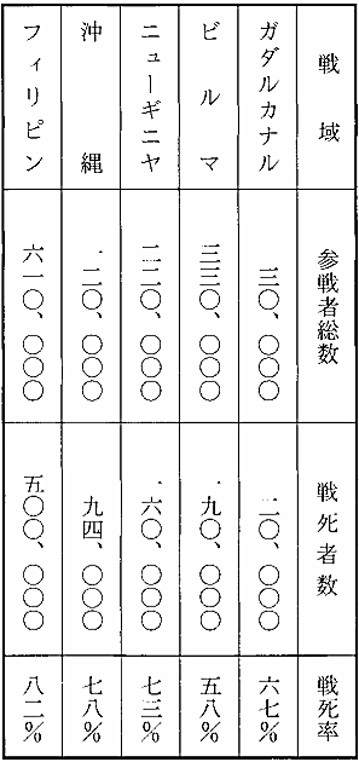
この数字を見てもよく分かるように、戦死者の総数においても、また戦死の率においても、フィリピンのそれが最も厳しく、如何に比島の戦いが激しく、また悲惨であったかということを、この数字から窺い知ることが出来よう。
兵器、爆薬、軍需物資は勿論、肝心の食料、医薬品まで枯渇した過酷な戦いの中で、山下大将が最も恐れたことは、フィリピンの日本軍が米軍に無視され、 ラバウルのように、ただ自活するだけの遊軍化することであった。
この為フィリピンの第一四方面軍は、祖国に直接戦火が及ぶことを深憂しつつ、勝利については一縷の望みさえない中で、持久戦を企図し、時には攻勢に出て、一日でも長くアメリカ軍をフィリビンに拘束し、その本土進行を遅滞せしめ、その間に本土防衛準備の進捗することを希求し、祖国防衛の捨て石となることを使命として、悲惨な状況のもと、よくその苦難に耐え戦い続けた。
このようにして、 ルソン島だけでも、 アメリカ軍六ヶ師団以上の兵力を、八ヶ月にわたり拘束した。 フィリピンの日本軍将兵が、山下大将の意図に従い、苦難に耐えてよくその使命を達成したことは、 アメリカ軍の戦史も之を認め、賞揚している。
一方敵のマッカサー司令官は、 昭和二十年五月三十一日、早くも九州進攻作戦(オリンピック作戦) と、関東進攻作戦(コロネット作戦) の両上陸作戦の準備を下令していた。その兵力としては、九州に十四個師団と一戦闘団を決定していたが、 これらの師団は当時我が第一四方面軍と、 フィリピンにおいて交戦中の師団で、第一四方面軍を壊馘し次第、直ちに宮崎、鹿児島方面に上陸する予定であった。
若し、第一四方面軍が玉砕戦法をとり、早期に全滅していたならば、アメリカ軍は予定より早く一斉に九州に上陸し、その結果は沖縄の例を見るまでもなく、本土は凄惨な戦場と化し、将兵は勿論、一般住民まで更に想像を絶する犠牲と惨禍を蒙っていたてあろう。
フィリビンにおける日本軍将兵の苦闘は、筆舌に尽くし難い程、悲惨を極めたものであった。それだけに生じた戦死者は、五十万の多きに達し、しかも結果は全滅に等しい惨敗に終った。その為に、比島戦を或いは無駄な空しい抗戦であったと言う人がいるかも知れない。結果だけを見れば、 それは真実であろう。然し比島の将兵は、 山下大将の意図に従い、安易な玉砕に走ることなく、玉砕よりも苦しい持久拘東作戦に徹し、祖国を護る防波堤として、最後までよく敢闘した。これによって本土はアメリカ軍の蹂躙を免れ、八月十五日の終戦を迎えることが出来たと言うことが出来よう。アメリカの戦史も、「どのような見地からも、尚武集団は、山下大将が希求した米軍拘束の使命を完全に果たした」とこれを認めている。
この点から考えても、比島軍将兵の戦いは決して無駄ではなかったと、声を大にして言いたい。若しそうでなかったならば、過酷な戦場に立って、祖国や肉親同胞を守る為と信じ、命令のままにその任務に殉じ、敵弾に、病に、あるいは飢餓に斃れ息絶えていった五十万の戦友の霊を、何と言って慰めることが出来ようか。
さきの大東亜戦争を、侵略戦争と簡単に決めつけることは容易であろう。しかし、祖国を護る為と一途に信じ、かけがえのない一命を捧げた数百万の人みの忠誠心までも否定することは出来ないし、またその犠牲の上に今日の日本の平和と繁栄があること忘れてはならないと思う。然し、その散華はあまりにも大きなそうして痛ましい犠牲であった。
戦争とは、どのような戦いであっても、敵味方双方共に多くの尊い命が失われ、親は子を失って泣き、子は亡き親を想って涙しなければならない。然し、国家間の利害や民族、人種、宗教等の対立から、世界の至る所で今なお依然として戦いが行われ、硝煙の絶ゆることがない。世界平和が訪れるのは、果たして何時のことであろうか。
南十字星の下、再び日本人が訪れることもないような名もなき山野に、また大海原の底深く、或いは南溟の雲の彼方に、遺骨さえも拾ってもらうことなく、祖国を思い、親や妻子を恋いつつ無念の想いを胸に、ただ殉国の一念で空しく水漬き、草むしていった多くの戦友の死を、心から悼まずにはいられない。
また在留法人婦女子の目を覆いたくなるような惨状も決して忘れることが出来ない。特にあの山中で出会った、いたいけな幼子達の姿や、その澄んだ瞳は、五十年を経過した今でも、はっきりと瞼に焼きついていて、消えることがない。体力も抵抗力もない幼子故に、その後も続いたあの苦境の中では、飢えと病でその殆どがおそらく生き残ることはできなかったと思われる。戦争の意味も分からず、あの未開の山中で飢えと病に苦しんだ末、路傍に、あるいは藪陰に、母の手で一人淋しく埋められたそれ等の罪もない幼子達は、再びその母に訪れてもらうこともなく、小さな体はやがて朽ち果て、比島の土となっていったことであろう。
銃砲爆弾に晒され、飢餓疾病に苦しんで幾度となく死の渕に臨みながら、奇跡的に死線を越えて以来半世紀、私は比島戦を顧みて、深く戦争の悲惨さ空しさを思うと共に、戦野に斃れていった人々のご冥福を心から祈り、平和を願う次第である。
金丸利孝 元一四方面軍参謀部情報課 「惨烈の比島戦」抜粋 ルソン山中会会報より転載
2.バレテ戦生還者・遺族の記憶
2-1.生還者の記憶
戦雲の証言台
昭和五十七年一月から約二カ年の期間、 山陰中央新報紙に、「戦雲の証言台」とうたって、三六七回にわたり掲載された下田美知夫記者の "鉄鳥取部隊の足跡“。本稿は、これを縮小要約したものである。
朝鮮-釜山へ
鳥取の将兵を主体とした鉄第五四四七部隊は、昭和十九年八月十三日、十四日の両日、満州(中国東北部) 三江省鶴岡駅軍用ホームを「ウ号演習」の名目で出発した。
貨車数十両連結という軍用列車はワラを敷いて ”客車”にしたもので、夜になれば"寝台車”にもなって完全軍装の将兵を満載、 一路南下を始める。釜山までざっと五日間の旅である。
真夏日の八月
関東軍の冬季演習に「体感気温零下五〇度演習中止」などという"号令“が残っている。零下三〇度であっても、 シベリア嵐の荒れぐあいでは人体に感ずる気温は零下五〇度ぐらいとなり、風を避けて顔、 とくに鼻など外面に出ている部分をマッサージしないと凍傷にかかる。 ところが七、 八月の盛夏には、水銀柱がうなぎのぼりして三〇度を越え、 ”屋根の小鳥が焦げ落ちる“ ほどの真夏日となる。大陸気候の本家である。 鉄五四四七部隊の将兵二千三百人は、馬三十頭とともに、この真夏日である十九年八月十三日、十四日北満を出発し、朝鮮釜山港に着いた。 松永元一さんは「釜山では海難訓練が主で、高い飛込台の上から海中に飛び込み、竹で組んだ筏につかまる練習を十日余りやったように覚えています」と話す。
釜山出港
十九年九月二日の夜、釜山港の岸壁にドラが鳴った。灯火管制下で暗い港内であったという。 兵を満載した貨物船二隻は出帆し、 九月三日つつがなく門司港入りした。 船内待機の日がよく続く。夜になると列車の汽笛がよく響く。"山陰線上り列車かナ“、満州生活が長かった古参兵には望郷を誘う夜列車であったようだ。
門司出港
門司港に到着した鉄鳥取部隊など鉄兵団(第一〇師団)主力は、同港に六日間停泊 、七日目の九月九日に任地の台湾へ向け出港する。
「門司から私たち第二大隊は乾端丸のご厄介になった。・・・出港の翌日か翌々日、船団の一つ千早丸という油輸送船が魚雷を受けて沈んだのであるが、敵潜情報がひんびんと入り、そのたびに中条船長はうまくジグザク航法のS字運動をとって、何回か魚雷をかわして無事、台湾基隆へ着けてくれました。到着して台湾守備が任務であることを初めて知ったものです。」会津若松市根本直さん (第二大隊長、少佐) の話。千早丸はポルネオに油を積みに行くため、鉄兵団に加わっていたそうだ。従軍看護婦や兵隊も乗っていたそうだ。十日の正午過ぎ、朝鮮海峡から東シナ海への出口に当る済州島沖で魚雷を受けて沈没した。
基隆上陸
十九年九月十八日鉄兵団の主力は、無事に台湾基隆へ上陸した。港湾内あちこちの海上にマストだけがポつンと浮かぶ。空爆による沈船とすぐ分かり、 いよいよ戦場という緊張感が、兵団各部隊の将兵間に漂ったという。松浦丸など鉄鳥取部隊の基隆到着は十八日の朝方のようだ。しばらく港内に停泊し、岸壁に並ぶ倉庫群とその中には、どうやら砂糖袋と思われるものが満ばいだーそんな風景を眺めていた。やがて下船の号令がかかり、兵器、弾薬など積み荷の揚陸作業が急テンボで始めれる。
苗栗進駐
「九月二十日 連隊は軍旗を先頭に堂々苗栗に進駐した。駅頭には師団の柏井高級副管、苗栗街長以下在郷軍人、国防婦人会、小学生等手に手に日の丸の小旗を打ち振りながら熱狂の歓呼で歓迎された。」 山本照孝さん著「比島バレテの思い出 (以下、「山本戦記」という。) は、このように記している。
差し迫る運命
「大本営陸軍部、第十師団(鉄兵団)をフィリピン方面に投入することを内定。(防衛庁刊「陸海軍年表」による)。これは十九年十一月十日の日付になっている・・・・。総師部でこのような立案が行われると、当然将兵の運命に操られる。ただ、部隊長以下の将兵が目的地をはっきり知るのは出発後の船の上、一兵士にいたっては上陸して知るのが普通であった。
鉄鳥取部隊の将兵は、差し迫る運命を十一月下旬に察知しているようだ・・・この時期鉄の将兵の多くが内地の肉親へ航空郵便を送っている。「・・・お蔭を以って元気狂盛、新聞紙上にてご承知の如く愈々ご奉公の誠を尽くすべく・・・」、これは鉄鳥取部隊足立隊西村喜美夫軍曹が、実父の八頭郡郡家町西村勘治さん(故人)に送ったハガキで十九年十二月一日「苗栗局」の消印がある。・・なお、この足立隊はサンニコラスで全減している。
高雄出港
台湾高雄港の四番岸壁に鉄兵団主力を乗せる乾端丸、江の島丸が横着けされ、 ひと足遅れて大威丸が人ってきた。十二月九日夕刻のことであった。四日間で搭載作業を終え、十四日夜の出航となる。
「私ら鳥取部隊は、十二月四日までに高雄周辺地区に集結すべしという命令で、苗栗を出発したが、この時、苗栗の国防婦人会、小学生等各種団体の人たちが日の丸の小旗を打ち振って、嵐のような熱狂的見送りをされた。 これは後日の戦に計り知れない勇気づけになりました。( 鳥取市山本照孝さん(連隊本部准尉) の話。
敵潜水艦動く
まず、主力を運ぶ輸送船団の動きー「高雄港を離れると同時に「敵の有力なる潜水艦が目下台湾近海及びバレー海峡において盛んに活動しつつあり」との情報。船は少し進んで錨を下ろした。夜が明けると高雄港の北 “岡山港″ の沖にいた。そこでそのまま三日ほど待機した。」と故森本春美さん著の「死闘の鉄」にある。公刊戦史である「ルソン決戦」でみると「船団は敵機動部隊が去るのを待って、十二日十八日台湾南部を離れた。・・・船団(三隻)は十九日サブタン島地区、二十一日カミギン島地区にあったが、その後分進し、江の島丸はアバリ、大威丸、乾瑞丸は北サンフェルナンドに向った」とある。
乾瑞丸轟沈
カミギン島でアパリへ直行した江の島丸(岡山歩兵主力) と別れた大威丸(鳥取歩兵主力)と乾瑞丸(姫路輜重主力) は二十三日早朝、指示されたリンガエン湾に入った。ひしめく将兵を満載した老朽船乾瑞丸が最後の力を絞り切るように北サンフェルナンドの港に直進しようとしていた午前十一時半、敵潜水艦発射の魚雷四発を受け轟沈した。第一弾命中から沈没まで二十八秒前後であったという。・・・まさに轟沈で、 一,二〇〇余名(鉄鳥取部隊二九〇名)が上陸地を目前にして恨みの涙をのみリンガエン湾深く眠りについた。
米軍上陸
戦艦二、航空母艦十隻などの艦隊群を先頭に、続いて五列無数、 二組の輸送船団が、ルソン島バターン半島の西北方海上に姿を現したのは二十年一月五日である。この艦船群はそのまま西海岸を北上して、五日夜にはリンガエン弯沖に達した。六日未明から艦砲射撃を始め、七日、八日と浜の姿が一変するほどたたきにたたいて九日午前七時二〇分に、上陸用舟艇の第一波が白波をけり、湾底部のリンガエン市からその北約二〇キロ地点のサンフアビアンの町まで約二〇キロの浜に橋頭保を築いた。上陸軍はマッカーサー軍直属W・クルーガー中将指揮の第六軍で、五個師団基幹約二〇万人の陸軍部隊。・・・
このとき日本陸軍初の海上挺進特攻隊長・高橋功大尉以下七八勇士が陸上艦船群に体当り攻撃して大戦果をあげ玉砕した。全長五.ハメートルのケヤキとべニヤ板製挺進艇に百二〇キロ爆雷二個を装備して駆逐艦ホッジスなどへ突込んだもの。全フィリピン作戦を代表するルソン攻防戦は、この日このようにして幕を切って落とした。
サンホセ集結
「私らが大威丸の軍需品を揚陸し、北サンフェルナンド市を後にしたのは十二月二十七日早朝でした。揚陸作業が不眠不休で将兵みんなが疲れ切っていましたが、米軍上陸の気配が濃いかったため、慌ただしく満載の輜重車両をひきサンホセに向かったわけです。二〇年の元旦早朝にサンホセに着き、路上に大休止して新年遙拝式を行い、東天に必勝を祈願しました。軍旗を掲げ棒銃の敬礼をしたとき、名前は忘れましたが尺八の名手がいて君が代を吹奏。早朝の冷気にしみわたるようなあの尺八の音はいまも忘れることができません」、山本照孝さんの話。
サンホセすぐ背後(北)がバレテ峠、五号道路が抜けて北部カガヤン河谷へ延びている。「日本人婦女子がマニラを離れて北へ北へと逃れていました。サンホセで宿泊する人が多く、この山の町で日本人に会えるとは・・・。これは懐かしかったですね」と山本さん。
防衛軍の骨幹
ルソン島で戦った山下防衛軍の総兵力は約二十六万二千とある。この大兵力のうち鉄兵団約一万五千人、 そのうち鳥取部隊約二千八百人をして防衛軍の“骨幹”と記するのは、数のうえで無理がある感じがする。ルソンに陸軍第四航空軍(軍司令官富永恭次中将)がいて、山下軍の隸下ではなかったが、 これがにわかに隷下となった。戦闘可能な飛行機は、 ルソン九五機、中南比一九機(公刊戦史)で微々たる数だが、地上配備の部隊は大変な数だ。・・・マニラには海軍地上部隊も相当数がいた。
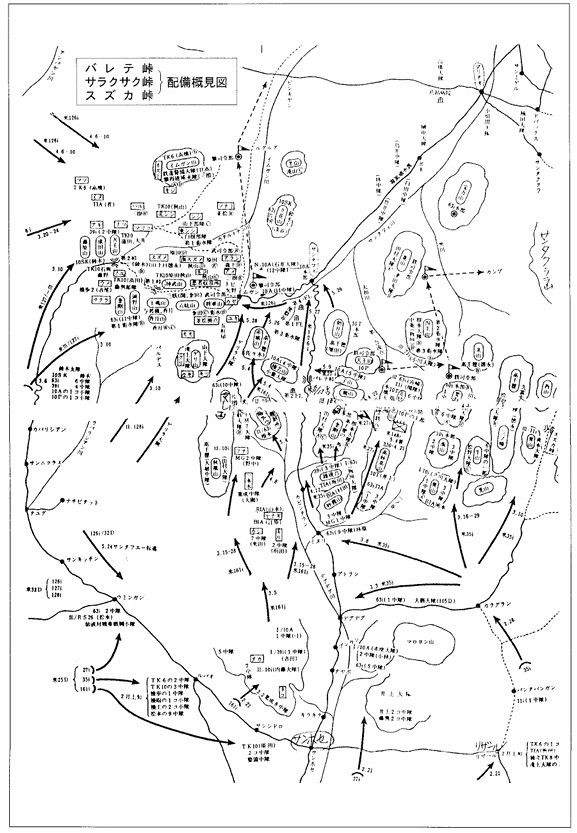
悲劇の第ニ中隊
親部隊(主力) から切り離されて他兵団の指揮下に入り、近くの町付近を守っていた二つの中隊が、相前後して鉄砲水のような猛攻をまともに受けることになる。
その一つは第六中隊(長、足立安長中尉、米子市富益出身、戦死大尉) で、サンニコラス付近の守りについていた。・・・一月二十二日には全陣地が猛射を浴びて戦いが始まる。
いま一つが、五号線上のサンホセがほど近いウミンガン守備についていた前田公夫大尉(陸士五十五期、戦死少佐)指揮する第二中隊だ。この中隊はくるくる変わる命令で転々と歩き回り、ウミンガン到着後、陣地強化がまだできていないうちに包囲攻撃され、敢闘わずかで二月二日には全滅。鉄鳥取の玉砕第一号となった。
第二中隊は当然のことだが、第一大隊に属していた。第一大隊長は、板垣肇大尉(陸士五十四期、戦死少佐) で、 この人の実父成記さん(故人)は海軍少将で終戦時、軍令部勤務。また伯父の板垣征四郎陸軍大将 (A級戦犯、絞首刑) は陸相も勤めた。
家人から本紙に寄せられた便に「征四郎伯父は、肇をことのほか可愛いがっていました。肇は素直な子で陸士に進み、昭和十三年十一月松江六三連隊補充隊へ隊付勤務を命ぜられてから戦死の日まで、ずっと松江六三(鉄鳥取部隊)で通しました」とあった。・・・
十二月三十日「第二中隊」 はバルンガオ三角山に向かい、同地を守備すべし」(要旨) の師団命令。 その後命令変更があり師団参謀の指示で拠点を点々と渡り歩く運命を背負う。・・・一月十九日、残存の長谷川小隊約三〇人のバルンガオ三角山正面に米軍戦車が押し寄せ、長谷川小隊は夜陰にまぎれて同二十五日ウミンガンの中隊本部まで帰ってくる。この直後に砲爆撃はもとよりウミンガンの中隊本部正面に米軍歩兵が姿を現してくるあわただしさ。
二月一日には、 玉砕戦の修羅場となり、翌二日には完全包囲され前田中隊長はじめ大半が戦死する。三日に約三十人の残存兵がミヌリの大隊本部に向かって後退、十五日に板垣大隊長の元に帰り戦闘報告がなされた。 歩く命令だけをもらったような悲運が思われる。最後の修羅場では夜間切り込みを二陣、 三陣と繰り出し砲兵陣地や戦車に爆薬を投げ、いつばいの戦果をあげる。 だが、先頭切った前田中隊長が戦死、以下幹部ことごとく倒れ、指揮班と各小隊間の連絡も全く絶える。いわゆる包囲せん減で第二中隊は消えた。
足立玉砕中隊
足立隊はサンニコラスという町の北約四キロ地点のカバリシアンという山中で、ほぼ全隊まとまって戦闘、生存者は一人又は二人というまさに玉碎中隊である。
兵団命令により林葭一連隊長は、第六中隊を指定して捜索第十連隊長の指揮下に入るよう命じた。六中隊は十九年十二月三十一日未明、隊長足立安長中尉の指揮により、捜索第十連隊の待つサンニコラスへ向かった。隊員数は約百十人、出発地はロザリオというところで、リンガ工ン浜から一〇粁前後の町。ウミンガンで玉碎の第二中隊と同様、上陸直後の命令下達であるから浜が近いわけである。
捜索連隊長は鈴木重忠少佐。部隊が何台の装甲車(豆タンク)や自動車を持っていたかは分からないが、「連隊本部四九名、前田車輌中隊百七二名、重機関銃一個小隊(重機四つ)」と記録され、歩兵部隊でいうなら中隊に毛の生えた程度といいたい連隊だ。・・・兵員は総計約六百人であった。
ともあれ六中隊は騎兵の助け人よろしく、カバリンアンへ配陣する。到着と同時に墓所を覚悟の陣地構築、台湾防衛時代に次ぐ二度目の築城作業であった。
一月二十二日、鈴木支隊本部付近に長射程砲による数一〇発の急襲射撃を受ける。敵機の爆撃は既に全陣地が受けていた。・・・
この記録が第六中隊の戦闘入り初日のもようを示しているものだ。サンニコラスの北約四キロ付近、カバリレアン川とアンバヤバン川に挟まれているカバリシャン部落北方一帯の密林内に構えた支隊陣地に、どこから飛んできたのか長射程砲の弾丸が豪雨状に落下、土煙が天に達したという。・・・
二十二日から二十八日頃までの戦况で、「陣地全面に敵軍現る」と記録される場面だ。
二月七日足立隊陣地の全面に大部隊が近接する。砲約七〇門と多数の戦車を伴った米第三二師団歩兵第百二七連隊が、このときの攻撃部隊とある。鈴木支隊との戦力の比較は五〇対一 (三万人対六百人)。装備にいたっては比較にならなかった。そうするうち、日本軍将兵は初めて見るというプルドーザがぞろぞろとはい出し、高地の斜面に戦車道をつけ始めた。六中隊は手投げ弾やにわかづくりの爆薬を持って肉弾切り込みし、このプルには相当な被害を与えた。また、夜間切り込みに出かけ、砲座と機関銃座を祭りにあげ「足立隊の戦意は益々高かった」(根本戦記)とある。
格別、足立隊長の戦戦指揮は、楠公の千早城の故事にならい、米軍の予期せざる時機、地点に不意かつ急襲的に切り込み、米の歩兵攻撃気勢をくじき進行不能にさせたという記述も見える。
その中隊長足立安長中尉について、実弟の勉さんはー「長兄の安長は米中から東京高等師範体育科に進み、昭和十四年に卒業してすぐ松江中学の教論になりました。・・二十年二月二十三日サンニコラスで戦死。当時二八才でした」と語っている。三月一日には陣地に一発の銃声もしなくなったという。全減である。足立隊は五〇倍の米軍を相手に二旬余にわたって敢闘した。
撃兵団玉碎
五十五年四月、鳥取砂丘の護国神社で行われたバレテ会の鉄鳥取部隊慰霊祭に、元「撃」兵団の参謀中佐河合重雄さんが川崎市から来鳥、参拝して遺族を前に戦闘図を広げて説明した一端に次のような話があった。「満州から転進した私ら「撃」の二百四三輌の戦車は、サンホセ付近における二週間前後の戦いで、わずか一二両を残すだけになるまで戦いました。もとより戦死した将兵は多数です。これは、山下司令部がバレテ峠を越えてカガヤン河谷に移動する在畄邦人や諸部隊、それに多量の軍需物資を北部の拠点へ搬人するよう厳命され、またバレテに陣地を構築中の鉄兵団は一日でも長く築城時間が欲しいときでした。これを果すためには「撃」の玉碎もまたやむなし、という(山下司令部の)考え方でした」。
鳥取市の豊田賢一さん(「撃」兵団の曹長)は、「なにしろ相手のM34戦車は、こっちの砲弾をピン・ピンとはね返す。装甲板が七〇ミリと厚く、日本の九七式戦車備砲五七ミリではビクともせず平気な顔でやってくる。九七式の装甲は二五ミリで、M四の半分以下。反対にM4備砲の九〇、または一〇五ミリを一発くらうと、たちまち炎上する。もっともこのことは初めから分かっていたので、こちらは要所に戦車を埋め、砲塔だけを出して相手のキャタビラなど狙った。戦車による急造トーチカで、戦車兵が死なないかぎり有効でした」と語る。・・・当時の国力の差が装甲板の比較にはっきり現れているような豊田さんの話だ。
五号道路の要衝サンホセがついに落ちた。機甲兵団としての命運を断たれた「撃」が北に撤退した二月六日、米軍はサンホセを含む付近一帯を完全占領した。
プンカン攻防戦
サンホセから北へ直行すれば、次はプンカンという町だ。プンカン守備隊にいささかの反撃手段も与えない勢いで襲った米軍の歩兵は、第二五師団に属する第二七歩兵連隊と第一六一歩兵連隊の二つ。この兵員数は一万人弱とされているいま一つの第三五歩兵連隊は迂回路(東回り)を攻め上った。二個部隊が正面攻撃し、一個部隊が迂回して背後から挾撃しようという作戦である。これに対する日本側のプンカン守備隊の総兵員は明らかではないが、米軍戦史によればここで日本軍戦死者は、 一、二五〇名(北部ルソン持久戦、小川哲郎著)とある。玉碎だからこれが大半とみて、総員は一、五〇〇人前後と推定される。
ほぼ一〇対一となる兵力の差。加えて前記のように守備隊の火砲一門につき一万発の砲弾をぶち込む火力では比較にならぬ。わずかなアリの群れにバケツで熱湯を注ぐようなものといえる。
「二月二十七日にいたリ「クマ」陣地よりの小銃音は絶し、中隊長三橋中尉以下中隊幹部ことごとく玉碎」。(山本戦記)
三橋隊はざっと一〇日間奮戦して、プンカンの地に消えたたのだ。
二月二十七日、三橋隊など守備隊はその責任を全うしたが、この死闘直後に鉄鳥取が総力で奪還作戦に繰り出し、激突寸前にU夕-ンという緊迫の局面が演じられた。(以下その状況は割愛する。山本戦記参照)
敢闘の三橋隊
サンホセを占領、付近の掃討を終わった米軍は、二月十日頃から第二五師団(長・マリンズ少将)を北に向け進撃させた。サンホセから五号線に沿って北へ直進すると、プンカンという町がある。その直線距離は約一六粁と極めて近い。プンカンは鉄兵団の防衛担当区域で、その最前線陣地であった。ここにはクマ、サル、トラ、 シシ、タカ、スズメなど、動物と鳥の名をつけた陣地があり、歩兵と野砲の特科など計二個の部隊がいた。
守備隊長は井上恵少佐。井上守備隊長指揮下の主な部隊は、鉄鳥取第五中隊の三橋賢二中尉(戦死大尉)指揮する三橋隊、隊員は一一〇人であった。ほかに、鉄岡山の内藤大隊、鉄姫路の吉田中隊、鉄姫路野砲の赤座大隊、独立速射砲、機関銃隊など。
さて、前記のクマ、サルなどの陣地は密林内に設けられていたが、千古斧を人れざる大森林もしだいに焼土と化し、このうちサル陣地第一線分隊は昼間の猛爆を浴び戦わずして玉砕。二月十九日米軍攻撃以来一日間にしてクマへ陣地を縮小した。
クマの三橋隊は昼間の爆撃を待避壕で避け、夜間斬り込みを連続敢行・・、・死闘が続く。(山本戦記)
こうして三橋隊は二月二十七日の玉砕まで頑張り通す。
サラクサクへ
重量装備の米軍部隊は侵攻不能と予測していたV・V道や旧スペイン道の密林悪路を、ブルトーザーなど土木重機を用いて開拓、思わぬところにM4重戦車や自走砲が無造作に顔を出してきて、参謀も砲に将に驚いたようだ。豊田賢一さんは、「バレテ峠の北にドバックスとかバンバンという諸部隊の集結地があった。そこへ突然「撃」はサラクサク峠へ配陣せよという命令がきた。このとき動ける戦車二〇両、装甲自動車四〇〇余両、機関銃は戦車からはずしたもの多数、兵力約四、〇〇〇人であったとされている。
私らのほか航空、陸上船舶、海軍、鉄道、飛行場設営、測量、空挺(高千穂)、教育隊、情報、通信などあらゆる雑多な付近の部隊がかき集められ、臨時野戦補充隊の名でサラクサクへ急いだ。一個大隊五〇〇人編成で終計四十余大隊。これは二個師団相当の約二二、〇〇〇人という兵力であったと聞いている。」この豊田証言と公刊戦史記述の数字はほぼ一致している。なお、このとき鉄鳥取の第一〇、第一一両中隊もサラクサクへ出動の命令を受けた。
松岡第一中隊
三月上旬、ルソン島中部に屹立するあちらの山、こちらの峡谷に砲爆撃音がとどろく。中央五号幹線のバレテ峠、その西のサラクサク峠、東の迂回路鈴鹿峠、この三つの峠の連山にこもる日本守備軍を制圧して山下軍司令部の本拠地、北部へなだれ込もうとする米軍の砲爆撃だ。この総兵力は合計四個師団と判断された (公刊戦史)とある。 一個師団の標準兵力約二三、〇〇〇人で計算すれば、計約九二、〇〇〇人となる。
この矢面に立つ日本主力軍は鉄兵団と、歩兵に編成替えされた戦車の撃兵団の二つ。この時点、鉄は・・・約八、〇〇〇人。撃は、約二二、〇〇〇人。この総計約三〇、〇〇〇人とされている。
まさにあちらの峠、こちらの峡谷でこの三対一の両軍が激突し、日米のルソンにおける雌雄が決せられる局面となった。最先端のとりでの第一中隊は、二月中旬第から徼しい砲爆撃にさらされていた。この隊は偵察隊のような役回しで、せつかく頂上近くに作った陣地を離れ、裸の捜索隊よろしくデクデクへ出向いていた。・・・
カラングランを出発した米軍は三月一日、このミニ砦を襲った。松岡中隊長は急を知り、伝令一人だけを連れてこの陣地へ戦闘指揮に出向いた。戦いは時間刻みで激化。松岡中隊長が主力の出陣手配を取ったときには、主力のホシ陣地付近も頭が上げられない程の射撃を浴びており、遂に主力は陣地へ釘付けのまま。に主力は陣地へ釘付けのまま。この結果二日の夕刻までに、砦の小隊員全部が手投げ弾をもって応援全減した。敵味方入り乱れた文字通りの白兵戦であった。
この戦局にあって三月二日第一中隊長松岡昌晴中尉(戦死大尉、倉吉市出身)が戦死、前後して半数約六〇人の隊員が散ってゆく、残りの半減中隊はその後約一〇日間ゲリラ戦を行い後退する。
林原第九中隊
林原修一中尉(戦死大尉、名和町出身)指揮によるミヌリ守備の第九中隊は、旧満州・関東軍時代に、”射撃の第九中隊“で鳴らしたという。しかし、海上輸送は沈没した乾瑞丸、この儀牲中隊でもあった。沈没、補強再建の各中隊が兵器、訓練、チームの総合戦闘力で本来の力を大きく割っていたという実情の中で、この九中隊は押し寄せた米軍に、百発百中の反撃を加え、犠牲の大きさにあわてた米軍歩兵がいっとき総退却。・・・
ところで、公刊戦史など多くに「ミヌリ守備の林原中隊」として表れるが、実際の戦闘地はミヌリから約三キロ南のプトランである。「・・・プトランの陣地で戦死した林原修一君は、私と初年兵時代から寝台を並べた無二の友であった。彼は自分の中隊が全減したことを確認後、拳銃で自決したーと当時通報を受けた。・・・彼の陣地は谷底のような所にあった。後部(北部)上方の私の陣地(雄健台)で見ていると、その後プトラン陣地は。約一週間砲煙に包まれ続け、 やがて全滅。」当時第一大隊副官中尉中原清重さんが語っているところだ。・・・(林原中隊の戦闘状況は、山本戦記に詳しい。)
カシ陣地の攻防
「三月十八日右第一線キリ陣地から『小数の敵歩兵我が陣地を攻撃しきたるも、前線歩兵よくこれを撃退せり」の電話報告が金剛山の連隊本部へ入った。」 (山本戦記)
この三月十八日の米軍キリ陣地攻撃をもって、鉄鳥取部隊本陣地の決戦人りとなる。・・・
右第一線全域は根本少佐の第二大隊担任で、その第一線は米田貴次中尉指揮の第七中隊であった。
米田中尉(戦死大尉)は安来市荒島町出身。・・・上陸後の一月中旬からざっと二か月間、山岳利用の築城工事に心血を注いだ鉄鳥取バレテの本陣だ。ここを墓所に一日でも長く米軍を足止めし、祖国日本本土攻撃を遅延させよう。その合言葉は「祖国を守れ」、「東京を守れ」となり、陣地即墓所作りに懸命となりこの日を迎えた。
ところで、この前後の食糧事情はどうであったか。松永元一さんの話では「バレテ峠付近の金剛山陣地に着いた一月いっぱいは、だいたい一人一日米四〇〇瓦(約三合) でした。これは扨米が約六〇〇瓦ずつ分配されるので、各人が鉄帽に入れて搗き、精米にして約四〇〇瓦です。弾薬、食糧は峠の背後(北)サンタフェという部落付近に運び込まれていたので、ここまで受領に行くわけです。庁道約八粁で夜間の往復。・・・三月中旬、右第一線の米田隊が激戦人りするころ、この米田隊陣地にやはり背負袋で籾を届けたのですが、もう砲弾が雨あられのように撃ち込まれた感じでした」と。
三月十八日、キリ陣地をうかがって追い返された米軍は、翌十九日には本格攻撃をしかけ、キリと西隣のカシの両陣地へまず迫撃砲の猛射を浴びせる。歩兵攻撃の支援射撃なのだ・・・ここの戦闘は三月二十八日まで旬日にわたり激烈を極める。カシ陣地の攻防が激烈を極めたのは、戦略上の要点であったからで、それだけに米軍も歩兵戦闘上、ここはどうしても占領したいという作戦に出、わが方も守備の米田中隊はじめ、第二大隊の総力で一回、二回、三回と決死隊を編成して切り込み反撃に出て、大きな犠牲を出した。
伯太町 角田唯久さん(二大隊本部曹長)は、「三月二十二日二大隊主力による第一回白兵夜間反撃のとき、二大隊のこれら諸兵合わせた計は百五、六十人位であった」と語っており、米田中隊を合わせ二百五、六十人がここでの総兵力ではなかろうか。・・・
カシ、キリ両陣地上空には連日観測機(軽飛行機)がくいついて離れない。この通称“蚊トンポ”が米軍各砲座と無線連絡を取り、弾着は益々有効となる。角田さんが、米田中隊ただ一人の生存者谷巌衛生兵長に聞いたという「二十一日夜、隊長切り込み、脚又は腰部重傷。部下と離れ行方不明。あと推定すれば二十二、三日をたこつぼ壕で生き、二十四日最後の力を出して自決」と。・・・カシ陣地で死守命令を果たした米田中隊は玉砕した。だが要地カシ奪回の切り込み特攻戦はまだ続く。
カシ陣地奪回作戦
師団、部隊、第二大隊が打ち合わせて決行した第一回カシ陣地奪回作戦は、三月二十二日夜、大隊長の指揮の下、主力を上げて決行。米軍の弾幕に遮えぎられて不成功、隊は消されてしまう。大園隊の消減で大隊本部ほか諸隊は後退して第二回戦に備える。カシ陣地奪回第二回特攻出撃は三月二十五日、第三回は同二十七日、いずれも決死隊編成の夜間切り込みであった。決死隊による二、三回の攻撃とも不成功。二十八日にカシ陣地は完全占領され、翌二十九日には次の(北側)ヤナギ陣地付近へ米軍歩兵が姿を現す。
右第一線の攻防
第二大隊の重火器隊は第二機関銃中隊と第二歩兵砲小隊の二個隊である。第二機関銃中隊はバレテ峠本陣の右第一線カシ陣地後方(北側) フナ陣地に配陣築城作業に移る。中隊長は野中章中尉(江府町出身、戦死大尉)、戦争は野中中隊長に配陣後わずか二か月間しか余命を与えなかった。部下隊員に重機関銃の火を噴かせることなく陣内戦に入らない三月七日、不運にも爆死してしまった。
後任には連隊本部付き、陸士五六期の多田博中尉(倉敷市出身、戦死大尉)が発令される。この頃からバレテ本陣の攻防戦が濃厚となる。北東の鉄は精強の名と裏腹に格別哀れで、陣中日誌も戦闘詳報も消滅して功績の詳細を残していない。カシ陣地からバレテ峠の頂上までの直距離は約六キロである。鉄鳥取部隊は三月から五月上、中旬にかけて南北約六キロ、東西約三キロ (地形上の実距離はこの約二倍)地内で死闘を展開する。兵力は連隊本部、大隊本部と歩兵各中隊の残存兵、重火器各中隊がその主力。これに増強の鉄道第八連隊と、レイテ決戦に降下させて名をはせた「高千穂空挺隊」 の別動バレテ回し「高千穂隊」 の一個大隊など。
なお、鉄鳥取のさらに東寄り鈴鹿峠方面にかけてのバレテ戦域には、僚友である岡山歩兵十、姫路野砲十、同輜重十各連隊などが広く展開敢闘中だ。
左第一戦の攻防
こんどは東側で起る左第一線の板垣第一大隊の攻防戦を見る。最先端に妙義山という陣地がある。守っていたのは三月上旬現在で、部隊のうち健在はただ一つの第三中隊であった。隊長は陸士五六期、山口県出身の大浜久助中尉。隊員は百二、三〇人でタコつぼ壕と横穴壕を築いて激戦の日を期していた。
このすぐ背後(北側) は雄建台の大隊本部本陣。各陣地(山) の標高は北にのぼるほど高く、八〇〇米から一、〇〇〇米強となって続き、 これらの中腹から頂上にかけ多くの壕が設けられていたわけだ。妙義山には歩兵の第三中隊に策応する第一機関銃中隊、東隣の一の谷に第一大隊砲小隊の一部、 西側の稜線に速射砲など重火器隊も配され・・・ここを先述の態勢に。
「三月十八日、妙義山の前方に米軍のパトロール隊と思われる小部隊が姿を現した。すぐ大隊命令が出され、最低の炊事要員を残し、全員が稜線上のタコつぼ壕や横穴壕に入り戦闘態勢に入った」と中原清重さんが記録している。米軍はゆっくり時間をかけて日本軍の洞窟陣地を遠巻きにし、 この間爆撃、砲撃、火えん放射を浴びせる。それでも日本軍は怖く、夜間は前進地点よりずっと後退、戦車で壁を作って眠る。
この三月現在になると鉄諸部隊や配属の特科部隊とも、 日中には砲弾で動きがとれず、もつばら米軍の戦車村へ夜間切り込みの決死隊を繰り出している。ブルトーザーで道を開き鉄守備隊の背後に戦車を回す。歩兵は防弾盾をかざして、 のろのろとやってくるとあって、白兵対決には時間がかかった。「米軍は、われわれの陣地を攻めるのに、直距離なら僅か一キロを三週間以上費やした。友軍の頑強な抵抗ぶりを改めて知る」と中原清重さんの戦闘記録にある。・・・
しかし、この死闘の詳細は不明で、大浜中隊生存者五人とだけ記録に残る。
三月下旬から四月にかけて、 いよいよバレテ攻防戦はピークを迎える。グラマンF4F 、 ロッキードP38の編隊が急降下爆撃と機関砲射撃を繰り返す。 ノースアメリカンB25が水平爆撃を、砲撃は一秒間に一発の割。「さすがの大密林バレテ峠の一帯が清野になった」と公刊戦史が述べている。徹底した砲爆撃で陣地を暴露させ、歩兵が止めを刺す戦法だ。妙義山付近には第三中隊と協同して戦った第一機関銃中隊も陣していた。隊長は倉吉市出身の船越正道中尉。「五〇年病没するまで宮司と皇学館大学助教授をしていました。・・・」と家人の便りにあった。
さて、妙義山の背後(北側) 一キロ強のところが雄建台で第一大隊の本部位置である。
「四月十二日、板垣第一大隊長は雄建台洞くつに船越第一機関銃中隊長以下を呼び戻し、反撃計画を説明していた。突如、敵が洞くつ入口に殺到してきた。板垣大隊長は抜刀して洞くつから飛び出した。このとき敵兵の手榴弾で壮烈な戦死をした」(公刊戦史)。
林連隊長は翌十三日、本部付の中条次作少佐(石川県羽昨市出身)を後任大隊長に任命、すぐ部署につかせた。急迫混とん、修羅の戦場でバラバラの隊員をよく指揮して敢闘、終戦まで生き続けるピナパガンで戦病死。右第一戦中条第一大隊最後の抵抗のころ、右第一戦根本少佐の第二大隊も、わずかの残存将兵が、増援の他部隊員とともに修羅の姿で奮闘していた。カシ、ヤナギといった主要陣地の奪回を図って切り込むが、その都度全員戦死。だが最後の一兵まで「血ニ染ミタル痩驅骸骨ノ如キ傷兵」(公刊戦史の表現)がどこまでも食い付くので、米軍側は「この絶望的なる争奪戦」(バレテ峠に建つ米第二五師団ダルトン記念碑文)と嘆き、泣きわめく場面があちこちに起こって、攻撃前進はインチ単位遅々たる状況であったと伝えられている。
ニつの慰霊碑
「バレテ峠の攻防戦は、アリの業列(鉄兵団)に、煮え湯(米軍)をぶっかけるようなものでした」と、大栄町、バレテ会副会長穐山宇太郎さん(速射砲中隊長)がよく話す。ドラム缶が雨のように降ってくる、焼イ弾がバラまかれる。山はたちまちにして大火事だ。当林がまる裸になったら戦車が歩兵を伴ってやってくる。こちらが一発でもぶっぱ放すと、そこを目がけて百発のお返しだ。物量、装備あらゆる面に開きがあり過ぎている日米の決戦・バレテ峠の戦い。
一月下旬に火ぶたが切られ、五月末転進に移るまで四カ月間にわたって、このアリと熱湯の闘争が続いた。いま、バレテ峠の頂上に二つの慰霊碑が立つ、 一つはバレテ慰霊会建立の追悼碑、いま一つは米軍の碑。追悼碑は五十七年春の総会で発案があり、直ちに募金を始めて昨年末までに約一、三〇〇万円の浄財が集まった。鉄のほか同戦域で戦った泉兵団、戦車の撃兵団の戦友会からも支援があり、予想外(目標五〇〇万円) の募金額となった。石工の花原さんも献身的な施工。碑、台座、傍碑を立派に仕上げ、 この二月に神戸港まで送って船積みし現地据え付けにかかった。渡航した山本、花原両氏らがよく現地民の協力を得、全く日本式に基礎も強く固めたという。
傍碑文(戦跡碑)には「鉄・撃・泉の日本軍と米比軍が凄絶な死闘を続け阿修羅の鮮血で染められた天地慟哭の戦跡である。・・・祖国のため当一七、一〇〇余の両軍戦士が(以下略) とうたっている。
いまひとつは米軍の碑。指揮官ダルトン将軍の戦死を悼むものだ。碑文に「この絶望的なる争奪戦」 の言葉が見える。日本軍の肉弾戦にはばまれ、インチ単位の前進しかできない激烈さを極めたと嘆いている。
玉砕戦決行
いま一つ、連隊守備の宮崎三雄少佐指揮する第三大隊は・・・。前記の板垣、根本の二つの大隊が苦戦に陥った四月初め、カシ、キリ、妙高山各陣地奪回反撃戦の助っ人として四月三日出勤、十五日ごろまで奮闘する。しかし、この時点には第三大隊は実力約一個中隊(公刊戦史) のありさまで、それも重火器中隊の一部が主力。・・・このため第三大隊は出撃と同時に岡山歩兵第十連隊長の指揮下となり鉄道第八連隊員などと協同して玉砕戦を行った。重火器隊の一つ、連隊砲中隊が断末魔を迎えたのもこの頃(四、五月)である・・・
中隊総員は一六〇人前後。射距離は小さかったが弾道が湾曲して地形にうまく合う小回り的性能を持っていた。
連隊砲中隊長は米子市出身の山本正孝中尉(戦死大尉)で、右第一線の要衝ヤナギ陣地西側に配陣して当初痛快な戦果をあげる。
・・・昼間に砲を撃てば百雷のようなお返しがあるので沈黙し、この間に近接米軍の休息地を十分確認、そして明け方を待ち、射撃。寝込みを襲われた格好の米軍が悲鳴をあげて逃げ惑う。そこを退路捕そくの斬り込み隊が待ったをかけ、時には食糧を分捕ったり、 M4重戦車やプルトーザーを破壊するなど、勝ち進む米軍の戦意を大きくそいだ。
玉砕戦の渦中で、ひと時は大活躍した連隊砲も、四月中旬に陣地(砲座)が狙い撃ちされた。砲門は飛散埋没し、山本中隊長は壮烈な戦死(四月十八日)、後任中隊長伊田守彦中尉(戦死大尉、倉吉市出身)も、山本中尉戦死後三日にして戦死を遂げた。健在火砲わずか一門となる。林連隊長は、直ちに本部情報将校吹野俊英中尉(戦死大尉、淀江町出身、東大卒)を三番手の後任中隊長に任命し、健在な一門の砲を金剛山に転進するよう命じた。・・・五月十三日、米車の警戒電線(別名ピアノ線)にふれ、これを合図に自動小銃の連射を浴び、吹町中隊長戦死。連隊砲中隊もここで実体が消えたと伝えられている。
五百人が脱出、転進
峠を占領されたのは五月九日、四月末から天王山を含む付近一帯は米軍包囲網がじわじわと狹り、迫撃砲弾が降りしきる。全山薄ぼんやりとかすむ砲煙のバレテ峠であったという。鉄鳥取部隊本陣の金剛山は、この頃城を枕に全将兵自決を覚悟の最終局面。・・・
林地区隊長は、十二日午後五時転進命令を下した。矢弾尽き果て落ち延びる鉄となる。五月十二日夜十一時、林地区隊長指揮の全隊員が敵中突破の転進スタートを切った。天の幸いで小雨、真暗やみでまさしく咫尺を弁ぜざる夜陰に惠まれる。五〇〇人弱の諸兵が「大和川」と名付けられていた小川を頼りに北東進して要山の兵団戦闘指揮所方面に向かう。集団にはぐれたら死が待つ。夜光木という螢のように光る枯れ枝があり、これを背につけて目印にした。
こうして十五日朝までにほぼ全員要山へ到着した。・・・軍旗と残存主力が四王山のさらに北、宝満山へ到着したには六月三日である。宝満山ーカナッアンと落ち延びた残存将兵は、六月二十六日、カナッアンの北にある、これまた草深いビルクという部落に着いた。ビルクで足踏みし休養しているうち、兵団戦闘指揮所へ派遣していた将核連絡班が帰へてきた。この時点指揮所は比較的五号線に近いビノンという部落にいた。連絡班が伝えた兵団命令は「速やかにビノンに終結すべし」(要旨)であった。
一日の行軍行程八キロ前後であったとされ、二十九日にビノンへ到着した。このビノンで「鉄鳥取部隊はカガヤン河谷を経てピナパガン北側高地に陣地を占領し、師団の背後を援護すべし」(要旨)の命令が出され、翌三十日約五日分の食糧を持ってビルクに反転、ここから北進の途につく。ビルク出発は七月四日、目指す次の部落はトオンであった。
消えた塩取隊
壊滅部隊は夜叉(しゃ) の姿となって密林内を歩き、七月十二日に原住民部落のトオンに達した。バレテ峠から東北に直距離約六十キロの地点服も靴も破れ、食べ物もない、マラリヤ熱病に襲われる。まさに死の転進で、トオンにたどり着いたものは二〇〇余人、道中で半数が枯骨となった。
ここで、 このまま塩をとらずに歩けば、残った二〇〇余人も全員死ぬ恐れがあると、・・・七月十二日、塩をとって本隊へ届ける任務の「塩取隊」が編成され、ルソン島東海岸のバレル湾岸へ向った。隊長として出発したのは本部付の木島重徳中尉(溝ロ町出身、戦死扱い大尉) に間違いない。・・・二大隊付き砂田久主計中尉(溝ロ町出身) のほか、次級幹部に本部付山代虎雄曹長(松江市出身)、吹野理次郎軍曹(淀江町出身)、 それにいま一人一大隊本部付熊谷稔曹長(倉吉市出身)がいる・・・一隊計約三〇人と推定されている。・・・なお、この塩取隊は現在まで消息不明である。
死臭の中転進
トオンから本隊が北に向かって進んだプコという部落。これを結ぶ密林と草原内の道は、 一つのけもの道で、道路などという常識的なものではなかった。ここを七月中旬、鉄鳥取部隊が通った。米軍を避けた他の部隊も同じように歩いたのか。死臭が漂っていたという。鳥取の将兵はこの死臭を磁石代わりにして方向を定め、北へと進んだ。行軍中に倒れたら最後、その死体は三日で臭気鼻をつき、 一週間で白骨化。・・・撃ち合いはないが、自分の体力との戦いが続く。
従って、トオンとか、プコとかいう草原部落の木の実やイモのある地点に着くと、やれ、やれとほっとする。安心して放心状態になり、眠り込んでしまうと、それが永久の眠りにつながってしまう。「肉体の極限を精神力で支えているのだから、この "つつかい棒“を置き忘れると最後だった」と、 ここを生きた元隊員は口をそろえる。「私は幸運にも体力に恵まれ通しでした。歩けなくなった連隊長を背負い、谷を登り川を渡るなど、 いま思ってもあの元気さが不思議です」と、山本照孝さんの回想。
七月二十日、プコという部落に到着した。精も根も尽き果て、衰弱し切った連隊長林葭一大佐が、プコ到着を限界のように寝込んでしまった。代って第一大隊長中条次作少佐が連隊の指揮をとることになった。ピナバガンはカガヤン河の上流で大きく開けた平野の南端。畑がたくさんありトウモロコシなどがあった。このピナバガンには八月五日に到着、九月一日まで滞留。 この間にカシプという部落に陣していた兵団司令部がやってきた。隷下の諸部隊残存将兵も終結して、鉄兵団が再び生き返ったような状况になったという。兵団命令により、九月一日ウルトウガンという部落へ向ってなおも北上する。・・・九月十日、突然この地で「大命ニヨリ戦闘ヲ停止ス」(要旨)の軍命令(山下最高司令官命令)が届いた。・・・「九月十二朝、命により軍旗奉焼式がウルトウガンの地で行われ、林連隊長以下九〇人の将兵が万こくの涙をのむうち、軍旗は一条の煙と化した」。(山本戦記)。この後武装解除と続く。・・・
連載を終わるに当り、世界恒久平和を願い、祖国の難に殉じた先人の冥福を深く祈る。 (後記)
「戦霊の証言台」は、山陰中央新報鳥取支社の故下田美知夫氏が執筆されたと聞いている。同氏は、昭和五十年まで日本海新聞編集局部長と活躍され、昭和四十四年発刊の「ビルマ戦記・渦巻くシッタン」の編集にも当たられている。
また、氏は、鉄六三の第六中隊足立隊故西村喜美夫曹長のご令弟で、バレテとは特別に縁がある身近なお方である。生還したわれわれは、友が枯骨となったあの時、自分自身が生きる極限に追い込まれた、あの悲劇を子々孫々にわたって伝え、二度と戦争を繰り返さないことを誓って、同氏の貴重な遺構をお借りした次第であります。(文責・松永)
我が戦場点描
生還者 松永 元一 鳥取県淀江町
記憶を辿りて
心友同志が寄ると、私は何時の間にか比島戦の話に熱中する。これをみて家内が又始まったと笑う、自分でもそう思う。それは、あの当時の悲惨な体験を忘れることがてきない、強烈なものであったからのことである。
同じ運命の十字架を背負いながら、戦友はルソンの海で、また密林の奥深く第国の難に殉ぜられた。今その俤を想起するとき、いろいろな記憶が甦える。戦火に斃れ、また山中に仆れたまま生命の灯火を消していった、夥しい将兵の姿を、しつかりと網膜に焼き付けて帰国した私は、この惨状を語らなくてはとの思いにかられる。
戦友の非情な最期を思うと、涙なくしては書けないが、約半生紀前の幻げな記憶の糸をたぐりよせ、あるいは、思い違いもあるやもと、それを怖れつつ、あえて、かっての戦場での片鱗を点描する。
プンカンへ
私は連隊本部の主計下士官候補者として、昭和二十年一月十日の朝、土民が水牛の手網をとる牛車に、十円札の軍票五梱包ばかりと豚を積んで、 サンホセの街を発った。途中、四粁程進んだ処で、敵機グラマンに狙われ、急降下で機銃掃射を浴びた、その時、初め私は牛車の下にもぐったが、すぐに危ないと直感し、山の斜面をかけ登り木蔭に隠れた。掃射で木の葉と薬莢がパラバラと落ちてきた。掃射は三回旋回し繰り返したが、終って身体を撫でてみると掠傷一つなかったので、道路に降りてみると、車の下には豚の血がタラタラと落ちている。あの時やはり車の下にいなくてよかったなあと思った。
この騒ぎで土民は、水牛と車をほったらかして逃げてしまった。水牛や車よりもわが命が大事と思ってのことであろう。本当に住民こそいい迷惑である。仕方ないので、私が水牛の鼻を挽いて、 五、六粁程歩きプンカンに到着した。
バレテ峠陣地到着
この頃連隊は、プンカン附近の陣地配備を、バレテ峠(標高九百メートル位)前面に陣地占領と変換になった。私達は、一月十三日夜、完全軍装をして、 五号国道をバレテ峠へと急いだ。
周りは真暗闇でどんな所かわからない、 ただ前を歩く人を頼りに歩いているだけだ、小休止で背嚢を負うたまま道端に倒れると、側を無灯火の日本軍のトラックや、小部隊が喘ぎながら北へ北へと登ってゆく。夜の往来は賑やかである。
バレテ峠までは四十粁程だが、昼間の行軍は危ないので昼間は木蔭に休み、夜だけの行軍であり一気には進めない。私達は一月十六日朝、 ガスの中でしとしとと雨の降る、バレテ峠の一粁ほど手前の溪間に、 へとへとになって到着した。足許はじめじめして腰を下せないので鉄帽を裏返してそれに尻を下した。そして、 ほどなく一つ下の連隊本部溪に移動した。
経理室は、 国道から約三十メートル程溪を上った処とされた。 ここは陽の目もみえぬ大ジャングルで、 岩が多く、溪にはきれいな清水が流れていた。
掘立小屋
我々は息つく間もなく、 山の斜面に床上げ掘立小屋(バハイ) を建てた。柱は近くの立木を伐り、屋根は天幕の上に枝葉を覆って擬装し、床は細い丸太を列べて座を張り、その上に毛布を敷くと立派な座敷が出来上がった。寝心地も上々で、料理室の十二、三名が車座になって夕食もとれる、気楽な起居の場となった。
そして、少し離れた処に穴を掘り露天の共同便所もできた。車座になってタ食をとっていると、突然敵の長巨離砲弾が、トン、ヒューン、ブーと無気味に唸って、頭上を飛んだが、 これは後方を撃っているので心配無用とのこと、始めての体験であった。
洞窟壕
バハイができ上がると、次に洞窟壕の構築にかかる、爆弾にも耐えるため、壕は山の斜面に横穴のコの字型の洞窟を掘る。工具は歩兵用の鶴嘴と円匙で、土を掘り、石を抜き、岩を砕き、掘り出した土石は、空箱に入れて引きずり出し溪を埋める。まるで蟻の巣造りにも似た原始的手段である。掘り進む程に洞窟の落盤を防ぐため丸太で坑柱を組んだ。誰に習ったということもなく、生きるための知恵でなんとかでき上った。壕の入口は二か所で、 一方の入口が崩れても別の出口から出られように、洞窟はコ型とし、奥行きは七、八メートル、間ロと高さは各一、八メートル位であった。この中に吉村高級主計以下十二、三名が、上級者から奥にすし詰めのように人って寝た。
糧秣受領
昼間は壕掘りに精を出し、夜になると毎夜五号国道に立って、自動車輸送のわが連隊の糧秣を受取るため、夜霧に濡れながら、ライトを消して登ってくるトラックを呼びとめ、大声で「鉄四七の糧秣ではないか」と呼び掛けて、探さねばならなかった。ようやく五夜目に待ちに待ったトラックが来て、ホッと胸を撫で下した。
一日八七〇瓦(約六合)の定量を約四日間に食い延し、明日はいよいよ一粒の米もない矢先だったので、その喜びは大きかった。然し、この時一か月分として与えられたものは一人一日籾六〇〇瓦、食塩五瓦で、籾六〇〇瓦が八割となるとして四八〇瓦(約三、二合)、定量の約半分である。連隊将兵はこれで築城工事に従事せねばならなかった。
マラリヤ
私は一月下旬、経理室と行李班が一緒になって夜間行軍で輜重車による糧秣収集に出たとき、二回参加したが、二回共途中でマラリヤが出て歩けなくなり、輜重車の厄介になって、ようやく経理室に帰へることができた。
マラリヤの症状は急に熱の出る発作があり、始めは寒けがし、ガタガタ震えがきて、 一時間程すると身体の中が焼ける程熱くなり、四十度ぐらいの高熱を発し、ロが乾き、頭が痛む。約二時間もすると全身にビッショリと汗をかいて、急に熱も下り平熱となる。この発作が三日熱では三日毎、四日熱では四日毎、熱帯熱では不規則で毎日出ることもある。そして発作を何度も続けていると疲労で衰弱する。
転進中よくみかけたのは、 マラリヤが起きると一人で草の上に仆れて苦しんで寝ていた。 マラリヤに抵抗するだけの体力もなく、そのまま立ち上ることもできなかったようだ。
ひどいのになると、脳を侵して突然倒れて意識不明になったり、痴呆になるものもあった。肉体はいきているのに、理性は死んでしまい、声をかけても知らん顔である。マラリヤハマダラ蚊に刺されて発病するという。私は始めの頃は三日熱、後に熱帯熱に変わり、ピナパガンで再発したときは立ち上がることもできなかった。復員後も発作があった自然になおった。
無煙かまど
私は糧秣収集に出ても途中でマラリヤで倒れ、皆に厄介になったので、それからは、連隊本部渓で留守番役をして、経理室の賄いることになった。賄いといっても副食を作る訳でもなく、無煙かまどに飯盒を吊って飯を炊き、握り飯を作るだけのことである。陣地での焚火は厳禁である。煙が昇ると兵隊の所在を暴露し、砲爆されるからである。各隊では炊煙の昇るのを防ぐため、無煙かまどを作った。
このかまどは山の勾配を利用し、尾根に向かって長さ二十メートル位も溝を掘り、溝が潰れないように溝に小枝を並べ、薄く土をかける。炊煙はこの溝を煙道として伝い、尾根に向かって這い昇る。這い昇りながら煙道の隙間から、フス、フスと煙を漏らす、漏れた煙は樹間を伝い山全体に拡がり、あたかも霧がかかったように陣地を偽装してくれる。戦場の知恵が生んだ敵機の下での炊餐方法である。
五月八日頃、私がここで飯炊しているとき、同郷の金川伍長 (連砲)が「腹をやられた」と云って、駈込んでこられたときのことは、以前の会報に記した。
虱
バレテの陣地や山中では、上衣や襦袢や袴下に虱がひっついて這い回り、血を吸って身体が痒いので、天気のよい日には、上衣や襦袢を脱いで裸になり、皆がしゃがんで木洩れ日にこれをかざしたり、また袴下を拡げたりして虱退治をした。縫目に蠢いている虱や、銀色に列をつくっている虱の卵を片端から爪で潰しても到底退治し尽せるものでなかった。私がピナバガンでマラリヤで寝ていたときは、夜中に虱が胸や腹をゴソゴソと這いずり廻り、又血を吸った跡が痒くて、 一晩中ガリガリと身体を掻いて眠れぬこともあった。
連隊本部渓急迫
五月の声を聞くと、私達が住みついていた連隊本部渓周辺も、熾烈な集中砲火に晒された。敵は尨大な鉄量と優勢な航空兵力、戦車力、迫撃砲、大砲、火焔放射器、ブルドーザー、装甲車、輸送車両、通信機器等、その量、質とも全く比較にならぬ戦力で襲いかかってきた。
欝蒼としていた密林も、爆撃や砲撃で大木が薙ぎ倒されて折れ重なり、山は明るくなり、拓け、雑然となった。そして、ここに住みついていたのか、山猿の一族も住む処を追われ、あわてて群をなして移動する光景もあった。そして、前線で傷ついた将兵も、この渓まで逃れ、中にはもうこれまでと手榴弾で自決する者もあった。
戦局は愈々急を告げたので、林連隊長は一日も長く敵を喰い止めるべく、各隊長に金剛山に集結を命じられ、五月七日頃には各隊が、金剛山に円陣形に陣地をつくり、最後の抵抗をはかることとなった。
経理室周辺も山腹に迫撃砲の集中砲火を浴びた。瞬発する炸裂音は地上で碎け、山腹は弾痕ができ、土石が転がり落ちた。
五月九日頃の早朝には、対面の山稜に突然敵の戦車が現れ、金剛山の頂き方面に、ドカン、ドカンと甲高い金属音を響かせながら戦車砲を射ち出した。経理室の我々は寝耳をかかれ、戦車が目の前だ、さあ大変だと、洞窟壕を飛びだした。経理、医務、兵技各部と行李班を合わせて小銃一ケ小隊を編成し、南側稜線の蛸壺陣地に入り、ここを死場所と考えた。
周りは既に米軍に囲まれており、北側山稜には米比軍がテント幕舎を建て、登ってくる米比軍の姿も見える。この頃、私は徊窟壕に忘れ物を取りに帰った処、壕の中には既に負傷兵がいっぱい入っていた。壕の前の渓川には、両足をもぎ取られた惨ましい姿の兵隊が、這って水を汲もうとしていたので、水筒に汲んでやった処、これを一気に飲み干した。あるいはこれが独り死路に旅立つ末期の水になるかもしれないと思った。
五月十日頃に、私は国道方面に斥候に出された。一人で経理室の渓に下りようとした処、昨日とは様子が変わり、米軍は渓に入って、医務室壕のすぐ上にも、迷彩服を着た米兵が腰にカービン銃を構えて立っていた。咫尺の間にいたが、幸い木の蔭で気付かれず、 私はすぐ方向を変えて別方向から国道に出た。
陣地撤退
五月十二日の夕方、私は寺垣経技曹長(岩美町)に随伴して命令受領に行った。この時、連隊本部前は混然として、暗号班は暗号書等を焼いており、班長の桑谷軍曹は、何時準備したのか帷子の白装束であった。私は、 これはいよいよ最期の時かと感得し、 母の写眞一枚を残し、他の軍隊手帳や入営時貰った知事以下島根県農務課の皆さんの寄せ書きの国旗等手持ちのものを火中に入れ焼いた。ところが、命令は「今夜二十三時を期して、金剛山稜線にある敵を攻撃しつつ、十五日朝までに大和川第三合流点付近に前進すべし」とあった。即ち、 ここを撤退せよということである。早速我々は蛸壺陣地から逃れて連隊本部に集まり時刻を待った。
その中には、片足をなくした兵隊が、どうしても随いて行くと頑張っており、出発時は一緒だったが、途中でとうとうだめだったようだ。
二十三時、小雨が降る中を出発、あたりは墨を流したような闇、前を行く行く兵隊の背嚢につけた、青白く光る夜光木(湿った枯れ枝等が霊菌で怪しい光を発する)を頼りに、 一列縦隊になって無言で進む。金剛山の稜線からは、敵の曳光弾が白光を放って一瞬明るくし、時々機関銃を射つ。我々は金剛山の急峻な斜面に足をとられつつ、前の人に離れないように一歩一歩よじ登った。私は途中で手に持つ小銃が、手から離れてしまった。それを拾えば、前と離れ、また後続の人に迷惑をかけるので、捨てたまま進んだ。ようやく稜線に達すると、米軍の声も聞こえ、また探知器の電線も張ってあったので、無言で注意深く歩いた。そして、夜の白みかけた頃、稜線を少し下った金剛山鞍部に進出し、それから部隊は昼間はじっと隠れて待機し、夜暗を利用する隠密行動で、敵の包囲網をかわし脱出に成功した。私は急坂で小銃をなくしたが、その代りは、稜線付近で落下傘部隊が持つ折半式の精巧な銃を拾い、以後この銃を背嚢に括って歩いた。
山 蛭
連隊本部渓の滞在中、また撤退後、大和谷川、四王山、宝満山、鈴鹿谷と転進中の山の中で、何時も悩ませたのが山蛭だった。山蛭は糸のように細い蛭で、人間の臭いを嗅ぐと高く頭をもちあげ、ゆっくり首を振りながら、尺取虫のように体を伸縮させて、靴や巻脚胖の中等にもぐり込んで生血を吸い、また、木の枝や草にたれ下がり、人の臭いを敏感に嗅ぎとって、フワーと落ちて身体に觸れると、すばやく動いて服の中や眼の中で吸血し、プクブクと大みみずのように丸く膨れていた。足が痛いなあと靴をぬぐと、靴下の中に何匹も蛭が大団子のように喰いついていた。痩せ衰えた兵隊の、残り少ない大切な血を吸い、その跡も長いこと痛むなど、山蛭は将兵泣かせの最たるものだった。
宝 満 山
私は六月八日宝満山に到着した。この山は一、 二〇〇メートルの高い山で、数日間の滞在中は雨の多い日が続き、頂上は雲の上にあった。夜下界の国道を眺めると車の往来がはげしく、また、仕掛花大のように燃えて、激しく戦火を交えているようたった。
私がこの山に着いた日は大雨だったので、岩の蔭にひそんで飯盒炊餐をした。薪は濡れた生木を割箸のように小さく裂き、これを井桁に三糎位積み重ね、その下に、小銃弾の中の煙硝を撒き、それに火縄(マッチがなくなっていたので、布切をなって火縄を作り、行軍中持ち歩いた。) の種火をつけて発火させ、木を燃やした。しかし、雨に濡れているのでなかなか燃えず、三十分も口が痛くなる程吹いて、やっと燃え上がり、飯を焚くのに一時間もかかる有様だった。
また、夜通しの大雨にテントもなかったので、衣服は勿論褌までびしょ濡れになり、靴の中もグシャグシャだった。落葉がズブズブに水を含み、腰を下ろす処もなかったが、木株に腰を下ろしてまんじりともせずに冷えを凌ぎ、ひたすら夜の明けるのを待ったことは、今なお忘れることができない。
先発糧秣収集班
吉村高級主計は、食糧を確保するために先発隊の派遣を考えられ、私は六月十二日橋本少尉、寺垣曹長、蔦原軍曹ら数名と宝満山を発った。サンタクララ山を下って鈴鹿峠方面に向かい、峠の手前から山地を北東に山越ええして、ママヤンに着いたのは六月下旬のことであった。ここは既に他部隊が収集し尽くした後で、何の成果も得られず、ここから山越しをしてビノンの本隊に合流した。その間、旧スペイン道の峠手前では、道の眞中に褌一つの真裸の兵隊か仆れており、まだ生きているのに、被服、銃剣、背嚢等装備一切を、まるで追剥ぎにあったように盗られた情けない姿は、眼を背けさせるものがあった。
この頃には、各人が自分が生きることに精いっぱいで、他者に対する同情、親切心、愛情などはもう欠落しつつあるようだった。また林の中には、航空大尉が、死期を悟られたのか熱帯のこの地で、肩に肩章のついた詰襟の軍服で正装し、 一人静かに最期を迎えて、永久の眠りについておられた。誰れも見取る者もなく、誰れにも知られず、苔むす屍となってしまわれるであろうかと思うと、 いとど哀れを感じ、心の中で、南無阿弥陀仏と呟くのみであった。
ママヤン
六月三十日吉村高級主計が、本隊に遅れてビノンに着かれるとすぐ、私を呼んで「連隊は明朝ピナパガンに向け出発するから、君の直ちに後方ママヤンの谷川べりに、マラリヤで寝ている稲田曹長を迎えに行き、本体を追及せよ。」と命令された。私はすぐに午後三時頃発って山に向かい、山の中腹で日が暮れたので、大木の下で一人夕飯を食べ、ゴロ寝して一夜を明かした。翌朝は夜が明けるとともに歩きだして山越しをし、七月一日の夕方、ママヤンの川辺で寝ている稲田主計曹長らのテントを見つけた。テントの周りは屍が異臭を放っており、テンとの中には、曹長と垣外軍曹(独速十八大隊)、伊藤上等兵、(連隊本部)の三人が寝ていた。
迎えにきた旨を伝えると、 二人は早速明朝ビノンに向けここを発つことになった。そうして暫く経つと、伊藤上等兵が、家族の写真を並べて泣いている。曹長は「伊藤上等兵、君は自決しりやせんか。」と糺したところ、上等兵は「ハイ歩けないから今夜自決しようと思っています。」と答えたので、曹長は「短気をだすな、早く元気になって追及せよ」と訓して励ました。それで自決はしなかったが、歩けないので一人残ることとなり、他の二人は熱も引いていたので、翌朝私と三人でここを発ち、山越しをし二日の夕方ビノンに帰った処、本体は前日既にここを発った後で、病兵が四、五人残っているだけだった。食糧は高級主計がママヤンを通られた時曹長に扨七、八升を残して行かれ、私も一升程度は持っていた。それで曹長の回復をまちビノンに二日程滞在した。七月五日の朝、私達三人は、 マラリヤでここに残留しておられた小西曹長(連隊本部)を加え、計四人で本隊の後を追い、歩き出した。マラリアあがりの一行は、灼熱の日を浴びながら、草原の土民道を本隊が歩いた跡を辿っていった。
ビルク
三日目かの七日頃の午後、ゆるやかな丘に畑が広がる中に二、三軒の小屋があった。ビルクという。カバナッアンは外れたようだ。そのビルクの手前の坂道で、ふらふら降りてくる土井軍曹(速砲)に出会った。軍曹は悪性マラリヤの重篤な症状で、言葉をかけても返事がなく、我々と反対方向に歩かれるので、稲田曹長が「土井軍曹、その道は反対だぞ」と呼びかけても、全く通じなかった。ビルクの土民小屋に入って旅装を解き、ここに二日ほど、滞在した。早速畑に出て甘藷堀りをしたが、部隊が散々掘り返した後で、いくら掘ってもだめで小芋が少々だった。その芋と僅かにあった芋蔓と一緒に炊いて食べた。また、持っていた籾もここが最後でなくなってしまった。籾はそのまま掛盒で炒って黒こげのまま食べていたが、ついに掛盒一杯分となり、「いよいよ今日で米ともお別れか」と慨歎しながら、二人でモグモグかみしめながら食べた。
ビルクに滞在中、野砲第十連隊副官小川大尉(倉吉市)の率いる、二十人足らずの一団がここを通られた。我々のような小集団は危ない状况下、幸い稲田曹長は副官と面識があったので、同行方頼んだ処了承を得、曹長外二名が同行することになった。小西曹長はマラリヤで一緒に行けずここに残られた。
一緒に歩いた野砲連隊とて飢に悩み、戦いに疲れ切っていた。自分の身体が精一杯だのに、連隊長の荷物や本部の重要書類の入った行李、梱包を担がせられていた。また、飢とマラリヤで落伍兵が続出した。共に戦い、共に苦しんだ友は殪れんとする友に力を貸そうとして、荷物をとってやったりもしていた。「今少しだ。頑張れ、ここに残ると死ぬぞ、立ってついてこい」と上官が叱咤激励しても、泣いて「先に行ってくれ」としゃがみこむ兵がいた。落伍すれば即ち死であるが、もう起き上がれないのである。
山中彷徨
ジャングルに入ると、軍刀や短剣で枝を払い、萱原になると草を踏み倒した足跡を道とし、川に至れば岩伝いに、雨が降れば雨に打たれて、空の飯盒を提げて、あたりをうろうろしながら食べる物を求めて歩いた。この頃の食べる物は、野草の山春菊、木の実、渓の岩の間をチョロチョロする沢蟹、川にいる蜷貝であった。山春菊や沢蟹は歩きながらロに入れた。木の実は落ちたものを拾い、一
応何でも噛んでみた。この頃の露営は、丘の上や渓間に携帯天幕を敷き、その上にゴ口寝である。軍靴は履いたまま、巻脚胖をしたまま、木の間を洩れる星空を仰ぎつつ横たわった。遥か北の北斗七星の空に向かって祖国を偲び、母を想った。
霜に立つ母の姿を描きつつ
今宵も月に健在を問う
そして、ぼた餅やしょうけ飯のうまかったこと、いろいろな身の上のこと、子供の頃川で鮒を釣り、川蟹をさぐったことなど、話し合って眠りにつくのであった。ビルクを発って一週間程後、小西曹長が一人で歩いておられた。みると軍刀やピストル、背嚢もなく、丸腰で空の飯盒だけ持っておられた。声をかけても悪性マラリヤの為か反応もなく、どうしてもあげることもできなかった。
私達の先を行った部隊は鉄六三を始め、鉄一〇、鉄野砲、徳永支隊、津田支隊、航空隊等だが、先に行ってしまったのか、これからの大集団には会うこともなく、出会うのは流浪の群のようだった。
この頃には、病み、飢えて衰えた将兵が、破れかけた靴、汗と垢にまみれた軍衣で、一途に生への執念をかき立て、歯を喰いしばって、山を登り渓を伝って歩いていた。道なき道に斃れ、あるいは岩蔭に、巨木の根方に精魂尽き果て、仆れ、また、水を求めた侭倒れ込み、再び起き上がれなかったのか、川のほとりに突伏して蝿と蛆にまみれ、死臭を漂わせている腐爛死体を散見し、涙をそそるものがあった。しかし、酸鼻を極める屍があまりにも多いためか、我々は何故か黙って片手拝みをして見過ごす戦場心理に変わっていった。私達も早晩、こんな姿になるのかと、自分の末路を見る思いがした。
蛆虫
陣地や山野で負傷したり、斃れたりすると、臭いをかぎつけてすぐ無数の大きな蠅がとまり、不思議にすぐ白い蛆虫や油虫のような虫がわき、傷口、目、鼻、 ロといわず、内臓や腹と処きらわず、くさみも生身もおかまいなしに動き出し、肉を喰い尽くして一週間程で白骨にしてしまう。哀れなことだった。
トオン
野砲と同行の私達は、七月十八日頃山中に焼畑と土民小屋が点在するトオン集落についた。鉄六三の本隊と東海岸に向かったまま消息を絶った、幻の塩取隊は既に発った後だったが、あちこちの小屋に若干の兵が残っているようだった。ここにも既に食糧は取り尽くしていたので、長居は無用とばかりに先を急ぐことになった。しかし、鉄野砲の弱った兵隊は若干ここに残留したようだ。
食塩は命の綱であるが、もう一週間程も前から切れている。塩分をとっていないので足がひょろづいて困っていた処、トオンにいた兵隊と稲田曹長の交渉が成立し、腕時計と塩を掛盒一杯と交換した。私達は早速掌に塩をのせ、歩きながら摘んだ山春菊にこれを付けて食べた処、たちまち足取りがよくなってきた。トオンは千メートル位の高所にあったので、 これからはゆるやかな草原を降りる一方だった。そして、密林に入ると岩石の渓となり、渓間には沢蟹がおり、歩きながらこれを撮み口にいれた。お蔭で食欲を満たすと共に塩分を補給したようだ。さらに渓を下ると、渓の底に地下水が流れる音が聞こえる、水無川があった。渓を下るうち、水量も次第に増えて、渕も澱み大きな渓川となってきた。
山春菊と川蜷
陣地に入って以来野菜の補給は、主食さえ補給困難という状況ではやむを得ないことだった。そうしたとき野生していた山春菊は、随分とお世話になった。 これは香りが春菊に似ているからそう名附けたのだろう。転進中は何一つ食べ物を持たなかったので、 この野草を歩きながら摘んで食べた。また、川の中に入ると蜷(にな)が多くさん取れたので、 この蜷と春菊を飯盒で茹て食べたが、糧秣がなくて身体をなんとか維持できたのは、この蜷で蛋白質を補給できたればこそと思う。私は故郷に帰れたら、 一年の内一日だけでも当時を思い出して、蜷と野草だけ食べて過そうと思っていたが、喉元過ぐれば何とかで今日まで実行できずにいる。
長谷川中尉と残る
渓川のほとりの大木の根っこに一人の將校が横たわっていた。稲田曹長は中尉と昵懇だったので、すぐにうちの二代目集成第二中隊長長谷川晴光中尉であるという。中尉は作業中隊小隊長の頃サンホセの北ナチビグットの敵砲兵陣地に斬込みをかけて大手柄をあげ、師団長から感謝状を貰った勇士で、師団でも名が通っていた。
小川大尉は直ちに「君達の部隊の、有名な中尉だから、君達はここに残って介抱せよ」と命じられたので、曹長と私はここに留まることになった。ここでも手持の食糧は皆無である。私は沢蟹をとり、また渓川に入って川蜷をとり、 これと山春菊を煮たものを唯一のメニューとして三人で食べた。その時私は川の中で二十糎程の小さい山椒魚らしきものを掴み、これを煮て三人で頭も骨も内臓も余すところなく食べたが、 それは全くうまかった。
私はここに三日間滞在し、この附近の蜷は全部取り尽し、ここに居ても死を待つばかりとなったので、 三日目の朝、 三人でここを発とうと、私が背嚢を負い起ちかけた処、 私の脚が立たなくなっていた。 これは困ったと思っている丁度その時、わが連隊の玉川大尉、飯塚少尉、曽川曹長等の一行が通過された。その中にいた谷上等兵が、靴下の中から米一握りを分けてくれた。早速その米と山春菊で雑炊を作って飲んだ処、脚にカがついて歩けるようになった。 一握りの米が泳いでいるような雑炊でも有難い効果があった。本当に一粒の米の有難さが身に泌みてわかった。そこで長谷川中尉には谷上等兵が付くことになり、 稲田曹長と二人でここを発った。 その後長谷川中尉は元気になって進まれ、ピナバガンに出る直前に斃れられたと聞いた。残念だったことと思う。 心からご冥福をお祈りする。
暫く渓川添いを下った。絶壁が行手を塞げばロッククライミング式によじ登り、 山腹を逼い、 また川に下りて岩を伝いながら進むうちに、 カガヤン河の本流に出た。
カガャン河本流
本流は、河幅も広く、水量も豊富である。ここも巨岩が前進を阻む、神々の造った大自然の秘境を石伝いに歩いた。河に入って岩をこさげると大きな蜷貝がゴロゴロと掌にいっぱいになる、この蜷と山春菊を飯盒で茹でて腹いっぱいに食べた。蜷貝がある処では、日が高くてもそこで露営をし、満腹感を覚えつつゴロ寝して、清流の音を聞いて眠った。この頃から兵隊の離合集散があり、また、垣外軍曹と一緒になった。次第に河岸が平坦になって歩き易くなった。
その頃歩いていて、木の実を拾い、毒でさえなければ何でも食べた。ある時は卵大のバイバスという木の実の青いのを食べた処、それが腹の中で固まって便秘をし、汚い話だが稲田曹長と私は河原にうづくまって、木の枝でほぢくり出し、やっと事なきを得たが、垣外軍曹は出せなくて、それがもとで落伍してしまわれた。これも人の生きる死ぬの大事なことだった。
河添いを進むうち、流れも緩やかになり、河岸も広くなり竹藪に出た。筍を見つけ、 ゆがかずにそのまま飯盒で煮て腹いっぱい食べた。 いま八月に入ったようだ、宝満山を出てからもう五十日にもなるのに、ビナハガンには何時出られるであるか。 この間、我々も飢え、 マラリヤ、下痢等で衰弱して倒れる者があり、連れも減ってきた。また、破れた軍靴が脚に重く、解くことのない巻脚胖の下で肢が蒸れ、身体を洗うこともないので、栄養失調も重なり尻や手足も爛れて熱帯性潰瘍ができた。もう歩けないという兵隊が続出した。重い足をひきずりつまづきながら、さながら夜叉の彷徨の姿である。
筏乗り
この付近は竹林があるので竹を伐って筏を組み、 それで河を下ることを誰かともなく思いついた。 二日位かかって二十本位の竹を伐り、 それを蔦かずらで東ねて筏としたが、 ここの孟宗竹は肉部が厚く重いので、筏の浮力が乏しかった。穏やかな流れに数組の筏が乗り出した。私は稲田曹長と一組で、筏に小銃や背嚢を縛り付けて乗った処、身体の重さで筏が二、 三十糎も水中に沈んだ。河の中程に出た処深くて棹がととかず舵がとれない、致し方なく流されていたら、 巨石が乞立し激流渦を巻く急流となった。筏が岩に引っかかったが、棹がきかないので激流に翻弄されるままに流されて二、三十分も経った頃、河の中の中洲に筏が乗り上げてようやく助かった。
そうする内、大きなスコールが降って河の水嵩さは増し、中州が次第に狭くなり出した。幸い、 これもことなきを得、安堵の胸を撫でおろして、その夜は中州に寝た。衣類は濡れても、熱帯地のこととて、いつの間にか乾いていた。
翌朝は、 河の水嵩さが減ったのを幸いに、小銃、背嚢を頭の上に乗せ、首まで水に漬かって対岸に上った。丁度河岸には棗(なつめ)に似たピンズという木の実がいつばい実っていたので、それを満腹する迄食べた。ここから又筏で下れば死ぬから歩くという組と、もう歩けぬから死んでもよい、 又筏に乗って下るという組と二つに分れ、私達は歩くことに決めて先を急いだ。
暗黒と曙光
ピナバガンに行くと云っても、当時は地図がある訳でなく、 山の名も地名も知らない、今日は何日であとピナバガンには何日かかるか、その道程も全くわからない。勿論ペンも紙もないから記録もなく、成り行き委せの遠くて長く、そして悲しく惨めな、あてどなき彷徨である。しかし、なんとなく拓けたこのあたりから、河添いに土民の道があり、食糧も筍、木の実、芭蕉の茎の芯、檳榔子の芯、羊歯の茎、ひまの種子等があり食をつないだ、よくもここまで木根木実を囓ってがんばってきたものかと思った。クワイの葉に似た里芋らしいの食べて口唇が痺れ、また、内地で軍事用にひまを栽培して種子は毒だから食べるなと教わったが、ここでその種子をおかまいなしに食べた処、おいしくて何等の異常はなかった等、色々な体験も得た。
もうピナバガンも近いというのに、道端の岩蔭に骸骨のような兵士が、枕元に家族の写眞と国旗を並べて、目だけパッチリ明けて仰臥していた。すべてを運命に任せて、死期を待つ諦観した聖僧のような姿で。死の寸前で魂は既に故郷に帰って、両親の幻影を追い、楽しかった故郷や家のことなどを思い出し、最後の別れの言葉をしているのであろうと想像され、涙を誘われずにはおられなかった。
この転進中は死も重いものでなく、カ尽きればあっけないものであり、それは人間一人を簡単に結着つける儚ないものであった。前面は絶壁でカガヤン河が大きく迂回し、溜場のような河岸には、明日目前の山を越えればビナバガンに出られると云って、私達数名の外に、空挺隊員、須村伍長(一中隊)等の兵士が、吹き寄せられた吹き溜めの落葉の如くうごめくようにして集まっていた。遭難した筏も河岸に乗り上げている。また、「日本は敗けた」と云いながら、迎えに行くのか逆方向に歩く兵士もいた。
誰れも骨と皮の極限状態であるが、明日は平野に出て食にありつけると、生への明るい望をつなぎ、もう一息だと皆明るい表情である。
八月十一日ピナバガン盆地に進出を果たした。最後の山越しは辛かった、もう限界だった。しかし、山の頂きに立って広漠たる盆地を一望し、青々とした耕地の緑をみたとき、とうとう生き残ったと思った。生きることの如何に苦しく、また、哀しいことをいやと云う程味わったことかと、思わず嬉し泣きした。山を降って麓の丘の一軒屋に辿りつき、稲田曹長、須村伍長、私の三人で早速調理にかかった。干した玉蜀黍や青いバナナを炊いて、団子にしたり、それを焼いたりして腹いっばい食べた。今迄まともな物を食べていなかったので、その喜びは格別で盆と正月が一辺にきたと夜遅くまで食べ物を囲み語り会って、楽しい一夜を過した。
そして翌十二日は元気を回復し、本隊を追った。各隊は各地に分散し、土民の家に人ってのんびりと暮していた。私達は連隊本部に着き、稲田曹長以下数名が本日追及した旨を田中連隊副官に中告し、経理室に復帰した。
経理室では、六月三十日ビノンで別れた吉村高級主計以下五名と、四十数日振りに再会し喜びあった。他方この間に橋本亀矩夫少尉を始め寺垣直之曹長、同僚の中田福夫、宮本満徳、 田中一郎、 日々野利喜蔵、 西村樹郎の各上等兵は、転進中山中で消息を絶ち、再び相見ることができなかった。ここでは食糧が豊富だった。主食は、干し玉蜀黍の砕いたのを飯のように炊き、副食には、水牛の肉、里芋、名も知れぬ野草等で、兎に角腹いっぱい食べれるのが嬉しかった。又畑に出ると砂糖黍、パイナップル等にありつけた。
水牛と仔豚
八月下旬、 田中連隊副官が林連隊長をプコから誘導して、ビナバガンに帰へられた直後の頃だったか、 経理室前を野生の水牛が遊んでいたので、 これはよいものを見附けたとばかり、小銃を持ち出して一発射った処、水牛の尻に当りいきなり走り出した。それを逃がさじとばかり二、三人で追いながら更らに一発射った処、いきなり家の中から田中副官が飛び出して「連隊長殿が休んでおられる家の前で、銃を射つとは何事か」と大声で一喝された。しかし、我々は家の前を通り過ぎて牛を追って走っており、今更止められない。山裾の道を五、六百メートルも追った処で、水牛が仆れてしまった。早速止めを刺し、応援を得て、鉈や短剣、ナイフで解体にかかり、技肉、臓物等を手曵き橇に積んで持ち帰った。
経理室には、吉村中尉、稲田曹長、蔦原軍曹、松本兵長、古田、宮浦、松永各上等兵の七人いたが、とても一頭分の肉を食いきれるものではない。早速医務室等他にも裾分けし、また、保管用に窯の上に肉を吊して 燻製にもした。そして肝臓、 舌、 脳味噌、等は珍味として味わい、 肉は焼いたり煮たり贅沢な響宴であった。
そんなことがあった直後、私はマラリヤが再発して歩けなくなり、寝たきりになってしまった。小用も窓からという始末だった。 そして夜中になると、虱が私の熱のある体温で気持よいのか浮かれだし、 丁度子供が運動会で遊ぶように、 胸といわず、腹といわず這い廻り、少しも眠らせない。そんな時、家の裏でしきりに、ブーブーと豚の泣き声がするので私は小銃を持出して、窓から一発ぶちかました処、見事命中小豚を射止めた。この小銃は戦争中はあまり役に立たなかったが、 その後の放浪生活では少しはお役に立ったようだ。仔豚の始末は戦友に委せたが、皆でおいしくご馳走になったという。また、 この仔豚は先日持ち帰った水牛の大骨の、腐れた臭いをかぎにきてご用になったという次第である。
ウルドーガンに追及
連隊は終戦の近きを感得し、米軍に近いウルドーガンに前進して、終戦情報を得ることになり、九月五日、連隊本部は、ビナバガンを発ってウルドーガンに前進した。その時私はマラリヤで寝たきりだったので、 そのまま取り残され、捨てられたような孤独感に襲われつつ一人淋しく寝ていた。
その後病状は少し回復した。集団からの離脱は不幸な運命に繋ることをよく知っている私は、病状も若干好転したから、ウルドーガンに追及しようと考えていた矢先の九月十一日の夕刻、畠中衛生伍長がウルトーガンから引き返して、 ピナパガンに残っている病兵に「九月十日、山下大将の軍使より終戦の伝達があったので、連隊は十三日にウルトーガンを発ち米軍に降るから、歩ける者は明日中にウルドーガンに追及せよ」と伝えて廻られた。この伝達は有難かった。若し、知らずにこのまま取り残されていたら私の今日はなかったのだ。
翌十二日は早朝、近くの家でやはりマラリヤで寝ていた本田上等兵(連隊本部)と二人でここを発った。本田上等兵はまだ回復しておらず、一粁ほど歩いては倒れ、坂道では倒れ、倒れては起き上り、倒れ、起き上りを繰り返しながら、励ましあって二人で頑張って歩いた。そして、連隊旗も焼かれ、 日もとっぷり昏れた暗闇の中の本隊に、やっと辿り着くことができた。
本当に間一髪で間に合った。私達の生死は紙一重の岐路にあって、私は幸運を掴むことができたのだ。
降伏翌九月十三日、連隊は病弱者を残しウルドーガンを出発、十六日ヨネスにおいて林連隊長以下九十数名が、米軍に降り武装を解除された。林少將(三月一日付進級されていた。) は米軍に収容後、九月十八日ムニオス米軍病院で、長い間の戦いで衰弱の極に達し、遂に病歿されたのであった。なお私達は降伏後エチアゲからカンルバン捕虜収容所に送られ、バタンガスに移って約一年間服役し、私は翌年の十月末母国に帰還した。
カガャンの亡骸
(昭和二十年六月十四日宝満山を発ち、 ヨネスで武装解除を受けるまでの約三か月間に、無念の涙を呑んで逝かれた、鉄六三の将兵約三二〇名の英霊を憶いて)
ポタリ、ポタリ、冷い山の夜露の雫がたれたとき、俺はふと目覚めた。静寂なあたりを見廻すと、 おおなんと、窪んだ瞳に映ったのは、俺の亡俺のムクロではないか。
哀れにも叢にうづくまって、氷ついた月の光の中に、硬直して永久に動かない。かっての俺の体驅は、ここに取り残されて、これからどうなるというのだ。
俺が食うべき糧もなく、 マラリヤと下痢に悶え苦しみ、カガヤンのこの山中に、骨と皮で横たわる。もう誰れも通らない、可愛そうな俺の亡骸、俺はお前を凝視して、餓死と知り病死と知ったとき、両親や妻子の慟哭を、また千里の道を遠しとしない、彼等の心を想って哭き続けた。俺は一途に生への執念を燃やし、歯を喰いしばって、必死に頑張ったが、ここで仆れて再び起き上れず、悲しい打ちひしがれた、数日を過して、俺の恐れていたものが、遂にやってきたのだ。皮と肉とは南国の灼執にむくみ、爛れ、頽れ、俺の亡骸は、死臭が鼻をついて、蛆が食い散らした。にぶい蛆の動きを見つめて、俺の戦慄は高まり、俺は声をあげて泣いた。ああ、俺は何故亡骸を、この悪魔の使者達に捧げねばならぬのだ。
地上に打ち捨てられた亡骸の恨みは、湿った山の夜風に、時折りゆらゆらと燐を燃やした。 この寂しい憤りの焔を見た人は、果たして何を想ったであろうか。なけなしの皮と肉が、 スコールに洗われて、俺の亡骸は、次第に形を変えていった、唇はなくなり、息絶えた時の苦痛のままに、食いしばった歯が露れ、落ち窪んだ眼孔に、月の光も届かなくなって、臭気もなく蛆も去った、俺の亡骸は、 地上に一組の白骨を残して、土に還っていった。
だが、この俺の霊魂は、一体何処へ還ろうというのだ。俺の亡骸を置き捨てた人々よ、俺の亡骸の傍を通り過ぎた人々よ、生きて永らえし人々よ、カガヤンの山中には、永久に故郷を恋い続けて、さまよう霊魂のすすり泣きが、夜毎聞こゆると、故郷の人々に、語り伝えくだされ。
追憶ー私のバレテ
生還者 松永 元一 鳥取県淀江町
フィリッピンで戦っていたとき、私はまだ二十才そこそこだった。亡くなられた戦友と運命を共にしながら、五中隊で只一人今日まで命永らえ、亡き戦友に本当に申し訳ないと思いつつ、早や八十路五くの高齢となった。遺族様には何年経っても亡き戦友の生前を偲ばれ、悲しみは生涯去らないこととお察ししていますが、生還した私達もいつも心の中を占めるのは、亡き戦友う とであり、五十六年前の筆舌に尽くせぬ凄惨な戦い、敗れて後の悲しい山中放浪は忘れることができない。
人は命の消えさる死によって一生を終るが、七、八十年も生きらるべきその命が、亡き戦友はあまりにも短く二十年そこそこの生啀だった。また残された遺族様言労も多く、何かにつけお欷き(たこととお察ししている。私は今お経をあげて戦友に只祈り、製旧に耽っていた矢先、山本さんから何か書けとの話があったので、せめて拙文ででもとペンをとった。 さて、私は既に小冊子や会報にも書いているし、今回は私の眼に映ったバレテ会発足当時の足跡や、 私の頭に浮かんだ入隊から台湾までのことどもを思い出すままに記すこととしたい。
1.第五中隊のあしあと
私は昭和十九年二月二十九日、北満興山兵舎の六七九の五中隊に現役兵四六名の一人として入った。(写真7参照) その時、中隊には昭和一八年九月入隊の補充兵が約三〇名、」 その外古参兵が約四〇名位いたようだ。中隊長は田中仁中尉 (陸上五五期)、 教官筑紫豊少尉(陸上五六期)、 助教は平野軍曹外三名、助手は福山兵長外七名位のようだった。(写真6入隊時の現役兵)

三か月の教育訓練は寒風吹き荒ぶ広漠たる原野の練兵場に出て、凍てついた大地を駆け這い廻って補充兵と共に日夜訓練が続いた。訓練の終りには弊社東側約二粁の日の出山への突撃だった。私は擲弾筒だったので、 第一線の後方から「突撃に」 の声で一気に日の出山に駆け登らねばならず、 遅れてよく叱られた。
七月には動員下令で南方転出となり、 八月十三日に約四九瓩の完全軍装で身を固め鶴岡駅を発った。汽車は貨物車の中に藁を敷いて牛馬並の扱いだった。一路南下し五日間かかってやっと釜山鎮駅に着き、釜山に十四日間待機した。九月二日出航のときは、第二大隊は貨物船乾瑞丸(六、五〇〇総屯) に乗った。船艙内は総員三、 五〇〇名の将兵がつめこまれ、 馬と貨物で超満員だった。九月十八日、台湾の基隆港に上陸し、 約三か月間台湾にいた。台湾は食糧が豊富な楽園で、 兵隊の顔は明るく生き生きとしていた。
2、 第五中隊 (三橋隊) が戦ったプンカン付近の戦斗概要につき、戦後鳥取地方世話部次のように発表している。
プンカン付近の戦斗
二月上旬、撃兵団を撃破した敵は、破竹の勢を以て「プンカン」の前進陣地に殺到した。敵は本道及び西方山地帯に攻撃道を開拓しつつ、我が左側背に迫った。三橋隊は、「キタキタ」北方高地を占領し、本道を北進する敵を迎え撃った。敵の砲撃と爆撃は物凄かった。平地より数十門の砲は一斉に咆哮し森林を薙ぎ倒し、陣地は瞬く内に破壊されていった。第二小隊長檀床少尉以下敵の猛爆のため生埋めとなり、第一小隊長筑紫中尉は果敢なる反撃肉弾戦を繰り返し、遂に両腕を敵の手榴弾に奪われ壮烈なる戦死を遂げた。三橋中隊長又負傷し最後迄担架の上で指揮をとったが、遂に戦死し中隊殆ど全員陣地に玉砕した。
比島民の心情
昭和二十年九月十六日米軍に降伏して、トラックに乗せられて南下したとき、住民は拳を振り上げて 「馬鹿野郎」、「泥棒」、「人殺し」の罵声を浴びせ石を投げつけたが、言われてみれば成程その通り 日本軍は住民を追い出してわがもの顔に家を横取りし、家畜を殺し、作物を荒し食糧を盗んだ。住民が怒るのも当然である。私は今でも罪の意識が沈澱している。
しかし、比島民は戦後数十年を経て、昔のことは忘れ友好的である。やっぱり比島はカトリック教徒が九五%のキリスト教国だ。どこの教会でもミサには老若男女の教徒が堂内に満ち、敬虔な祈りを捧げている。心が清純な国民である。
2.哀しきルソン戦
北満にいた鉄兵団一万二〇〇〇余の精鋭は、台湾を経て昭和十九年十二月下旬には、ルソン島北サンフェルナンドに上陸した。上陸直前に歩六三の第三大隊等が乗っていた乾瑞丸が、敵潜に沈められて
二九〇人が海の藻屑となった。兵団は直ちに山下大将指揮下に入り、バレテ峠やサクラサク峠に布陣した。海抜千メートル級の山が連なるここには、配属を含め二万余の兵が壕を掘ってたてこもった。
戦斗は激烈を極め、爆撃機、戦斗機は一人の日本兵も見逃さなかった。敵の強力なM4戦車、迫撃砲、機関銃、自動小銃、火炎放射器等あらゆる近代兵器が炎の尾を引き、飛びかい炸裂して山は燃えた。
守るわが兵は火砲に飛び散り、生き埋めになり炎に焼かれ、陣地には屍が折り重なった。負傷で動けねば手榴弾で自決せよ。また人命を消耗品扱いの死守せよとの命令が出ていた。そして夜になるとわが軍は、しがみついていた蛸壺陣地から抜け出し、斬込みで夜襲を繰り返し敵に恐れられた。しかし火力の差はどうしようもなく次々と陣地を奪われていった。
ここでの日本軍の戦死者は、バレテで約九千七〇〇人 サクラサクで約五、四〇〇人は、その戦いの 苛烈さを物語っている。包囲され全員玉砕あるのみと覚悟していたわが連隊の残兵四九〇人は、五月十二日峠の陣地を撤退し、六月中旬師団命令により二か月間の悲惨な死の転進を開始した。この時連隊は更に約三百五十人に減っていた。
転進当初は、 ジャングルで吸血する山蛭やマラリヤが将兵を悩ませ、雨期の霖雨が一層みじめにさせた。食糧の補給は全くなくなり、 栄養失調やマラリヤ等で歩けない病兵と、行き倒れの屍が目立つようになった。落伍すれば即ち死である。 倒れている病兵に声をかけても、うつろな眼で見上げるだけである。
私は六月末、高級主計より「マラリヤで倒れている轡長を迎えに行き、追及せよ。」との命令を受けて引き返し、五日位遅れて四十日間本隊の後を追った。 道のない山を先行部隊の足跡や屍を目印に歩き、 持っていた籾も十日程でなくなり、 それからは春菊に似た野草を摘み、 川に至れば蜷貝をとって主食とし、 沢蟹を見つければそのまま口に入れ、 木の実をを拾っては腹の足しにした。 露営は丘や川辺に携帯天幕を敷き、 軍靴や巻脚胖のままゴロ寝した。
夜空に輝く星空を仰ぎ、 祖国の山河、 老いた母、 懐かしい友の面影を偲び、 また餅や赤飯などの夢を描いて眠った。 進む程に、岩陰や巨木の下に精魂尽きて仆れ、また水を求めて渓谷に突っ伏し、蠅と蛆虫にまみれている屍もあり、 全くこの世の地獄絵であった。 明日はわが身かと思いつつ、 ただみ霊安かれと祈るのみであった。
大きなカガヤン河になると、 山や断崖、 水量豊かな流れ、 逆巻く急流と、人跡未踏の大自然の秘境である。ここでも行く先々に無念の涙をのんで仆れた病兵や、 枕許に寄せ書の国旗や家族の写真を並べて眠る屍もあり、 涙を誘うものがあった。 私達も骨と皮で体力の衰えと共に、 思考カも失せ死ぬことの哀しみも感じなくなって、 ただ食物をあさり今をどう生きるかが総ての飢との戦いであった。竹で筏を組んで河を下りもしたが、巨岩乞立し逆巻く激流に奔浪されて中州に乗り上げ断念したこともあった。
私達は八月十二日、 玉蜀黍等の食糧があるピナバガン盆地にやっと進出を果たし、 命拾いして本隊に復帰した。この転進で連隊はバレテ撤退以後三百数十名を失った。終戦により山下大将の命を受けて、わが連隊は林連隊長以下九二名が米軍に降ったが、林連隊長はその二日後に衰弱であの世へと旅立たれた。戦争とは哀しきものである。バレテ会では山本照孝氏を団長として毎年比島巡拝を行い、国の前途の繁栄を信じ命を捧げられた、連隊の二、五七六柱の英霊のご冥福を折りご供養を続けている。
悲運の航空部隊 バレテ峠妙高山で散華
和田 昇 (臨時野戦第二補充隊 元第四飛行師団司令部)
このたびは、いい方たちとルソンの地に戦跡訪問、そして慰霊巡拝の旅をすることができ有難く感謝しております。バレテ峠の戦いは大変悲惨で多くの将兵が戦死されたところであります。私はずっとその生々しい戦況を身にしみて体験し、胸に秘めて語りたくないという心境で耐えて今日まで沈黙してきました。
戦後五四年過ぎ戦争体験者は皆高齢となり、また他界する者も少なからず、このたびの慰霊巡拝を機に私のルソンでたどったみちと体験の一部を寄稿いたします。
昭和十八年一月満州チチハル独立飛行第五三中隊に赴任、その後第四飛行師団司令部に転属、昭和十九年五月大陸令により所属する第四飛行師団は第四航空軍の戦闘序列に編人されフィリッピンマニラに進駐した。
昭和二十年一月師団は軍命令により司令部戦闘指揮所をエチアゲに、主力はソラノ付近に転進航空作戦の任務を遂行していた。昭和二十年一月九日、米軍はリンガエンに上陸、ルソン各地で激しい戦闘が繰りかえされ戦況は悪化の一途をたどっていた。第四飛行師団は連日の戦闘で多くの飛行機をなくし、出撃可能な残存飛行機を全機特攻に投入すべく企図されていた。
その頃エチアゲの部隊内では良からぬ噂が流れていた。それは第四航空軍軍司令官富永恭次中将がツゲガラオの飛行場より軍偵察機に乗り台湾に飛んだらしいという信じられない出来事であった。(後日、噂でなく事実で護衛の戦闘機と共に一月十七日命令によることなく台湾に飛んでいた。日本陸軍史上司令官が敵前退避したのはあとにも先にも富永中将ただ一人であろう) 飛行場で軍刀を握り高くあげ若き少年飛行兵の操縦する特別攻撃機を見送っていたが、あれは何だったのであろう? 私も少年飛行兵第十期の出身であるが、苦々しく、又くやしく震駭に堪えない、
航空部隊をルソンの地に置いたまま離れていった司令官は、二度と帰ってこなかった。残された航空部隊は、内地より飛行機が輸送されて来るのを待ち望んでいたがそれは空しい願いであった。航空部隊は逐次地上戦闘に投人されて行く事になった。
昭和二十年三月第四飛行師団所属の将兵三〇〇余名は、行く先目的を明示されぬままトラックに乗せられエチアゲを出発南進した。道中オリオン峠に差しかかった際地雷が埋設されている、ゲリラの攻撃がある、との情報が入りトラックは徐行し長時間をかけ警戒しつつ峠を通過した。
サンタフェに到着全員下車し密林の中に入った其処で始めて野戦補充隊を編成しレバレテ峠に行き地上部隊と共に戦闘することが告げられた。編成された部隊は、臨時野戦第二補充隊 部隊長 小妻修少佐 第一中隊長 内山鉄二郎大尉 第二中隊長 中沢孝一中尉 私は第二中隊第三小隊第一分隊長を命ぜられた。第三小隊長は小野島少尉(後日石井曹長に交替)
第一分隊は甲斐正義伍長 横田勇司伍長 大城義兵長 我孫子六郎兵長 山本武夫兵長 新井梅次郎上等兵 松尾鼎上等兵 加茂野静夫上等兵 の八名であった。
野戦補充隊員は、司令部では、電報班、通信班、警備班、また飛行場で勤務していた関係で初めて顔を合わせる者ばかりであったが、 このときから同じ部隊で戦うんだという真に迫った状況となり思いっきり手を握りあい勇躍バレテの戦場についた。金剛山の壕の中に入り背嚢その他直ぐ必要でないものを整理し置き、松尾上等兵を監視員として残した。(松尾上等兵は監視中爆撃により戦死した)
部隊は妙高山に移り配置され、隊員は蛸壺と称する一人が入れるだけの穴を堀りそのなかに入った。連日砲爆撃を受けた数日後我が分隊は、敵の進攻を速かに発見報告すべき特命を受け谷間に降りて洞窟に入り哨戒の任にあたった。この頃より食糧が底をついて来た。僅かばかりの米を小分けにして雑炊にして食べた。次第に体が衰弱して来て苦しい日が続いた。雑炊を煮る時には煙を絶対に出さないように注意を払った。敵の砲爆撃の目標にされない為に。顔を真っ黒にして口を飯盒につけるようにし、フウフウと吹き火を燃やしたものだ。バナナの芯や根っ子など何でも口に入るものはすべて水炊きにし食べ飢えを凌いだ。岩穴の中でいつも内地でぼた餅を食べたことや白いめしに卵をかけて食べた話を何度も繰り返し専ら郷里を思い出していた。
昭和二十年三月十八日谷間より引き上げ本隊に合流するよう命令があり、即日夕暮れの砲撃の止んだ時を見計らって岩穴から出て妙高山に登り始めた。しばらくして谷の向い側の森の中より、一斉に物凄い勢いで機関銃による攻撃を受けた。敵兵の姿は判らないが夢中で応戦手榴弾を思いきり遠くに投げた。私はこの戦闘で右腓腹部に貫通銃創を受け創口を包帯代りに巻袢でグルグル巻きにして、山を登り本隊に合流した。休む間もなく嶺から少し下りた斜面に横穴を掘りその中に身を隠し穴の外側を付近に倒れていた木を拾い集め覆った。
山の斜面には戦死したものの遺体がたくさん横たわっていたが、助けることも、どうすることも出来ない地獄の世界であった。かねてよりバレテ峠には、満州から来た鉄兵団、撃兵団、それに高千穂部隊の精鋭が配置され勇猛果敢に戦っていると聞いていた。山の尾根を中腰になり警戒しつつ行ったり来たりする伝令がいた。頭に汚れた包帯を巻いて通り過ぎていく兵隊もいた。それらのものはすべて鉄兵団の兵隊であった。
毎日砲弾が飛んでくる。ヒュル、ヒュルと音をたて頭上を通り過ぎる。そんな時はまだ大丈夫だがそのうちシュッ! シュッ!と鋭い音がしてくる。間近で炸裂する音である。大きな声を出しわめき、死んで行く兵士もいる。まるで修羅場である。
私の入っていた蛸壺の上で一発が炸裂した。ガン!、同時に穴の中で飛び上がった。直径四糧程の真赤な破片が左大腿部に突き刺さる様に当った。ジュジュと焦げて臭い。痛い。左手で体を支え右手で破片を取り除こうとしたが破片の表面はギザギザで熱くて触れない。咄嗟に布(手拭だったか上着だったか覚えがない) をかぶせて取払った。無言でじっと堪え創口を押えた。創ロは、ざくろの様に開いていた。そのときはまるで気が狂ったようで鉄帽を頭にかぶっていると砲弾が胸に、いや腹に、顔に、当る様な気がして心配で一つしかない鉄帽をつぎつぎと位置を変えて置き身を守った。
おびただしい砲弾が撃ち込まれ多くの犠牲者が出た。誰も負傷者を助けようとしない。いやとても出来ないのだ。自分のことは自分で処置するより仕方がなかった。妙高山の南の方の山中で、ガラガラとブルトーザーで山路を造っている音が聞こえてきた。戦車の通る道を造っている音であった。
最後の決戦が近づいているのを感じていた。
第三少隊長である小野島少尉が体調を崩し砲弾が炸裂する中を平気で敵の方に向かって行こうとするので止むなく大城上等兵が付添い後退して行った。後任には中隊付の石井曹長がなった。(小野島小隊長ら二人の消息はその後どうなったか判らない)
四月十五日小妻部隊は、最後の決戦を覚悟し北部妙高山に移動した。私の分隊は敵監視のため、 一時そのまま残留した。砲爆撃により山の立木はすべて倒され土は掘り返されていた。私は二回の負傷で、汗とし虱(しらみ)と蛆(うじ)と血と土で創ロは腐敗し蛸壺の中は異様なにおいがしてきた。
四月十九日、速かに本隊に合流するようにとの命令があり敵の攻撃が止んだ隙をみて移動を開始したが発見されてしまったらしく、突然数発の銃声がした。誰かが「新井がやられた」 と叫んだ。後方を振り向き、見ると新井上等兵が倒れていた。 這いながら側により見ると胸をうたれ既に絶命していた。狙撃されたのだ。急ぎ土をかぶせ襟章を形見にはぎ取りその場を離れ本隊のいる北妙高山に着いた。またしても自分の鉄帽で蛸壺を掘らねばならぬ。体力がなくても自分の身を守る穴を掘るのだ。 一生懸命である。皆夕方までに掘り終りその中に入った。
いつ敵が来るのか判らない。悲痛な気持ちでじっと蛸壺の中ではやる気持を押え待機していた。各人手榴弾をしつかり持っていた。
四月二十一日朝四時頃であったと思う。まだ早いから敵の砲撃はないだろうと思い分隊員を激励、掌握するため蛸壺から出た。大腿部を受傷していたため体が思うように動かせない。匍匐(ほふく)前進し隣の横田伍長の蛸壺の中を覗き声をかけようとしたその瞬間その日の第一波の攻撃が始まった。しまった大変だ、と思い自分の蛸壺に飛び込もうとしたが遅かった。
物凄い数の砲弾が、シュ!シュ!と音をたてて飛んでくる。蛸壺の近くで大きなはげしい炸裂音がする。頭上で炸裂した砲弾の破片が腰部に当った。思いきり棍棒でなぐられた様な衝撃を受けひっくり返った。気が遠くなってあとの事は分からない。
何時間かが過ぎた。遠くで私を呼んでいるような声がした。その声で気がついた。誰かが穴の中に引きづりこんでくれたらしい腰と腹に激痛が走る。右腰部に破片が当り体内に入ったことは間違いないのだが、その破片が何処に止っているか判らない。しだいに不安になってくる。出血がある、苦しい、そして無性に淋しくなってきて涙が出てくる。死ぬかも知れないという気がして来て心細くなり、いろんな事を考えたり思い出したりした。苦しさに耐えて数時間が過ぎた。創口を押えていたのでどうにか出血も止まった。今度は、何とかして生きたい、・・・生きられる、と思うようになり少し勇気が出て来た。
夜になって砲撃も止んだ。石井小隊長が私の所に来て、「たくさんの死傷者が出たので、部隊長から重傷者を後方に移動させるよう命令が出た、みんなを誘導してさがってくれ」といって電報用通信紙にその旨書かれた「命令書」を渡してくれた。退って行くものは何名で誰であるか判っていない。小隊長の合図で移動を始めた。重傷者といえども人の助けは受けられない。自力で動くより仕方がない。渾身の力をしぼり暗闇の中を互いに言葉をかけ合って退った。
重傷者の中に、 マニラでいっしょに勤務したことがある林上等兵がいた。上等兵は足首より下が飛んで無かった。「連れて行って」と何度も必死に叫んでいたが衰弱と出血多量で遂に途中で息を引きとった。上等兵の血のにじむような悲痛な声は五十余年を過ぎた今も耳についていて離れない。魔の山の中を随分後退したようだったがその距離は恐らく四、五百米くらいだったと思う。衰弱し然も負傷している者にとっては何倍も何十倍もの距離に感じたに違いない。重傷者はひとまず穴を見つけ身を隠し、穴のない者は倒れている木のかげに隠れて横たわった。
四月二十六日夜、形相物凄く興奮した兵士二人が私を探して来た。穴の中に飛びこんで直ぐ、「部隊全員やられました」とくり返し報告した。しばらくして少し落ちつき全減の模様を話した。「一昨日から砲弾をどんどん撃ち込まれ、多くの者が死んだ。今日的が滅茶苦茶自動小銃や機関銃を撃って来たので銃を撃ち持っていた手榴弾を投げ応戦したが、全員戦死した。もうどうするとも出来ず、夜になって敵が後退して行ったので報告に来た」ということであった。
万策尽きたので私は意を決して、二名を使い負傷者にこれから各人で自力で再び後退し傷の手当をするよう命じた。重傷の者たちに山の中を勝手に退って行けということで血も涙もない仕打ちであるが、それが戦場での精一杯の策であった。どれだけの兵士が後退して快復したであろうか。神のみそ知るということである。
当時、妙高山で負傷するということは一面死を意味することでもあった。私は二人の兵士も含め負傷者と共に杖をたよりにバレテの山中をさ迷い歩き、専ら退ったそのうち一人になってしまった。力のあるものはどん先に退いて行った。私の所へ報告に来た二人の兵士は何という名前であったか、ずっと思い出そうとしているが今もって思い出すことが出来ない。山の麓に破壊されたトラックがあってその付近に籾が落ちているのを発見むさぼるようにして口に入れた。
サンタフェまで来たその付近には在留邦人や負傷兵が北に向かって歩いていた。中には元気な兵士もいた。昼は林の中に潜み夜になると歩き出すのだ。疲労のためうっかり道端で眠ってしまうことがあった。油断すると携帯品は盗られる。靴も脱がされてしまう。もう誰も人間らしい根性はもっていなかった。バヨンボンを通りキアンガンの山にたどりついた。キアンガンの山の中には第四飛行師団司令部の将校や顔見知りの有田曹長などがいた。彼らはエチアゲよりキアンガンの山中に移動して来た者達でバレテ峠の悲惨な戦いの体験者ではなかった。ニッパウスの中に調達して来た籾をしっかり積み上げていた。私は内心喜んで彼らのそばに寄り妙高山の激戦の顛末を報告しようとしたが、素っ気なくあしらわれ多くを語ろうとしなかった。
当時の状況から考えてバレテの方面より北に向かって退避して来た邦人や負傷兵はたくさんいたに違いなかったがその者達は皆「穀潰し扱い」で招かれざる客であった。私は又、 山野に食を求めてその地を離れた。谷を流れる小川の中を歩いていると小さな声で「兵隊さん、兵隊さん」と呼んでいる女の子が二人、草むらの中にうずくまっていた。 その横に長い髪を乱して死んでいる女がいた。
きっと母親であったに違いない。可哀想てあったがどうしてやることも出来ない。靴下の中に入れて持っていた貴重な米を幼い女の子に渡してその場を通り過ぎた。それから今度は山の麓で休んでいると、痩せ衰えた女の人が私の所に寄って来て足にしがみつき「米を下さい」 と懇願して来た。断わり切れず遂に靴下に半分程入れ腰にぶらさげていた籾を、身を切られる思いで与えた。女は涙を流しし礼を述べた。籾は山の中を段段畑で摘み残されていたものを一粒、一粒集めて持っていたものだった。
お互いに日本に帰ることが出来たら知らせ合いましょう」と郷里の所を紙片に書いて交換した。彼の女は、ダイヤのついた指輪を持っていた。お礼にあげると言って差し出したが当時指輪など全く関心がなく断った。後日私が復員し判ったことであるが、その女性は山田ふじゑという人で私より一年も早く内地に帰って居られた。マニラのピイバレデス、アベニダ、リサール街に住んでいて海軍下士官食堂の管理人として勤めていた。内地に帰り神奈川県寒川町に住み米軍キャンプで通訳をしておられ再会を喜び会うことが出来た。
昭和二十年九月十九日、暑さと飢えと風雨を凌いだキアンガンの山々に別れを告げ、しっかり自爆用に残し持っていた一個の手榴弾と、内地からずっと腰につけていた軍刀を、涙を流しながら米軍に渡し武装解除を受けた。妙高山で受傷し砲弾の破片を体内に残留させたまま二〇〇粁余をさ迷い歩き杖をたよりに衰弱した体に鞭を打ち遂にキアンガン収容所に入り私のルソンでの戦いは幕を閉じた。復員後、臨時野戦第二補充隊がどうして編成されたのか私なりに調べてみたが、部隊の詳しい編成、隊員の住所氏名は判らなかった。
厚生省援護局調査資料室保管の資料の中につぎの様な記述があった。
「野戦補充隊の編成」
『旭盟兵団の補充を指導して二月下旬バンバンにきた田中参謀がまず着手したのが多数の野戦補充隊の逐次編成であった。さきに触れたように、サリナス塩をもらいにくる者を利用して諸隊を掌握するに伴い逐次野戦補充隊を編成した。臨時第二野戦補充隊長翼司令部附小妻修少佐(五二期)。 ニ個中隊、計三〇〇名。航空部隊の人員を充当。のちこの編成のままバレテ戦を終始。』
◎第十八回バレテ会ルソン慰霊巡拝の折、山本団長さんより歩兵第六三連隊副官、田中大尉の手紙をお借りし拝見したところつぎの様な記述があった。
『一.小妻大隊長小妻少佐
人員装備本部及一中隊(M51小隊含む)本部、指揮班二七、行季二九、計五六、第一中隊一七七』
以上の記述はルソン・エチアゲ方面にいた航空部隊の中より三〇〇余名が集められ野戦補充隊を編成、妙高山に投人されたもので、航空部隊としてはそれぞれ優秀な技能能力を持った将兵であったが、地上戦で、薬もなく、炎熱のもとで悲運な戦いを強いられながらも精いっぱい頑張り祖国の平和を念じ亡くなって行った数少ない「誌」である。妙高山に想いを寄せ比島戦史の一頁に残ること願ってやまない。 合掌
・彼の山も此の山も皆亡き戦友の御霊静かに鎮りてあり
・最期迄戦い勝つと信じつつ飢えに斃れし友の尊し のぼる手記「鉄窓の涙」より
悲運輸送船乾瑞丸の最後とその前後
後藤智男 会見町
昭和一九年一二月一四日日本最後の船団として、台湾高雄港を出発、第十四方面軍山下奉文大将の指揮下に入るべく南進を開始するも、当時の太平洋全域は既に敵連合軍、特に階水艦の跳梁著るしく從って友軍の厳重なる対空、対潜監視は昼夜間断なく実施されていた。
それもその筈、昭和一九年一〇月一二日我が軍の夢想だにも予測し得なかった、台湾冲の大海戦と共に、台湾全土に丸三日間連続の大空襲により、飛行場その他の軍事重要基地は、その機能を完全に壊滅させた。当時我が軍として台湾は日本最南端の「不沈空母」として絶対の自信と期待を持ち続けていた。それがため連日の如く戦爆連合の編隊は陸続として轟音を響かせながら南洋の空に飛び続けていたが、大空襲以来全くの沈黙となり不安を隠すことは出来得なかったのであります。
輸送船乾瑞丸は明治年間の建造船であり、既に其の任務を終り廃船同様との事であったが、昭和一九年代に入って現役輸送船の大半は、あの膨大な地域南太平洋作戦の輸送作戦に従事して、その大半は海底深く沈役し是れがため、輸送能力は激減し、遂に乾瑞丸も再び重要任務に返り咲くことになった。六、五〇〇屯の老船に全力を傾注して船団の一員として勇躍巨大なる軍需物資を満載しその上、更に兵員約四、五〇〇余名を搭載するも自艦の能力を遙かに越したものであり、あのバシー海峡の荒波に乗り上げては船体がギシギシと軋み、全くの不気味さを響かせていた。
船団中他の一隻は荒波高いバシー海峡の眞只中附近にて、敵潜水艦の攻撃を受け寸秒の間に轟沈し、船体は二つに折れその半分は逆立状態の儘タ陽迫る南海の海面にいつまでも浮き続けてゐた。眼前に展開されたあの惨状は数千の若き生命と共に銃後国民皆様方の身血を注がれた軍需物資は其の目的を達すること無く、戦いの犠牲とは言え余りにも大きい惨事であった。
又、 この様な悲劇が幾日の日か我れ等の身の上に振りかかるとは夢想だにも感ずることは無く船に身を任せてゐた。灼熱の南海は船上に居ても暑い。况してや船室の中は蒸熱く丸で湯の中で蒸される様、僅かに在る通風筒は効果も無い苦しみであり然かも、船倉の中を幾重にも仕切り坐しても尚頭部がつかえる高さ、身動きさえも出来ない寿司詰め状態は是又呼吸困難、甲板上は勤務兵以外は上ることを厳禁されていた。
余りの熱さ辛さにそれと無く抜けだして甲板上に出て腹一ばいおいしい空気を吸い込んだ。丸で生き返った魚の様に両手を一ばいに張って海上を眺めた時、船上勤務の将校に見付かって叱られ又元の船室に舞い戻る。悪条件から好条件に移るのは蘇生であったが、好条件から悪条件に帰るのは全く無惨な体罰にさえ感じられた。船の南進に従って熱さの体感が一層強く成って来た。
船酔の激しい兵士達は甲板上の通路に倒れ、自分の吐き出した嘔吐の中でのたうち廻ってゐた。勿論小便大便共々にミックスした悪臭は強く鼻を突いた。最早や乗船者総員は酷暑の中の緊張であり永い輸送船路の旅であり避けることは出来得無い、その様な中に於ても一日当りの一人の配給水量は約一合程度であり全くの水分不足であった。その僅かな水は呑んでも又後からすぐ喉が渇く、然かもその様な状能が一〇日間連続した。それは是れを体験した者のみが知る苦しみであった。
兵士達は、三、四日の中に一度のスコールに使乗して携行天幕を張り、汚れた天幕の上に溜った雨水を我れ先にと頭を摩り合せながら最後の一滴までも嘗め尽して居た。配給僅か一合程度の水は将に焼石に一滴、耐えかねた兵士達は甲板上に在る急造の天幕張りの炊事場に、海中より吸い上げられて居る五、六ミリ程度の吸管から吹上つる糸すずの様な海水を夢中でロに当てていた。小生も一度強い喉の乾に耐えかねて塩水を口にした。呼吸を止め吸い込んだ一時は塩分の感じは無く更に吸い続ける内に強い塩分を感じて口を離した。強烈な塩分で喉がピリピリとする。
輸送航海中連日の如く甲板上の対空、対潜監視の勤務を命じられ、若しその任務の万分の一つにも怠たって、自船に被弾を受ける様なことあらば、四、 五〇〇余名の生命は瞬時にして、此の世から消え去ることは、 火を見るよりも明らかでありやがて来る戦況に重大な影響を及ぼすと自覚するとき、昼夜連続の不眠でも勤務を続行した。幸いな事には敵機の飛来は、後に来る魚雷被弾までは一度も無かったが、輸送指揮官輜重聯隊長、鍋島大佐の激しい連日の陣頭指揮は最後まで緩めることは無く、朝から夜まで一瞬の間も軍刀の柄を鞘やごめで握っての大声の連呼は物凄かった。やはり四、 五〇〇余名の生命と、軍需品の無事輸送の大任を最後迄持たれる最高指惲官であればこそと、つくづく尊敬の念を禁じ得なかったのは乗員一同同感であったろうと思われた。
台湾高雄港出向以来九日目、乾瑞丸は喘ぎながらも船団の一隻として追従し続けていたが、夜半突然機関に故障を生じて、一隻の護衛艦の警備の上に停船し其の修復に全力を傾注した。然かし乗船して居る大半の将兵達には、故障の発生や停船位置も全く知らされて居なかった。前述のバシー海峡で轟沈された僚船以来敵潜水艦の再攻撃は、其の後無かったがおそらく再攻撃の好期を待ち続けながら、船団に追従して百獣の王である獅子が、獲物を狙うかの様にチャンスを今か今かと血眼になって伺っていたのは間違い無いものであった事と推察された。
本団より離れた輸送船一隻、それに護衛艦一隻然かし之の好機は敵に取って手の出る程の好期とは云え、一方我が護衛艦も最悪のピンチとして船団航行中より、更に一層の厳戒に入って居るだろうと、流石百戦錬磨の敵潜水艦も察知し、より以上の絶好のチャンスをじっと待って居たであろうと後にして推測された。
幸いにして無事修復し早朝の出航のため、ほとんどの将兵は故障停戦も知る筈も無かったが、夜明けと共に船団中の僚船の姿が見当たらないのに不審の感はあっても別に気にする者は無かった様であった。船団の出港以来一〇日目の昭和一九年一二月二三日、遙か左方海面に島の遠望が見え始め、甲板上の将兵達は南方群島の一部であろうと、皆が感じ取りその推測が始まった。
やがて午前一〇時頃には陸地近くを航行し、陸地に椰子の木が明瞭に解かる様になって来た。
海上は風も少なく、全く波静か、輸送船乾瑞丸の機関の音も心無しか静かな快音の様子であったが、やがて来る激戦の地、地獄絵図と成るであろうとは夢想だにも出来得ない静けさ、輸送中の緊張した心も解けて、丸で一幅の油絵でも見てゐる様でもあり漸らくの間は、心まで奮われ居る様な気持であった。
対潜監視の任務を又しても命ぜられ、船の最後尾附近に監視哨を設け、其の任に当って居た小生でさえ暫し眼に写る対岸の美しい景色であったが、我に気付き海面の航跡監視に神経を傾注し始めた、と其の時突然船内放送が発っせられた。
乗船以来初めての船内放送であり、全員何事かと耳を傾ける。それは「本船は現在フィリピンのリンガ工ン湾を南下しつつある。本隊は既にサンフェルナンド港に上陸し、目下揚陸作戦に全力を傾注して居る現状とのこと。本船乾瑞丸も後二時間程度で本隊に追及する予定のため只今より揚陸準備に入る、各ハッチを全開するため勤務中の将兵以外は全員船内に入り、揚陸作戦に支障無き様厳重に命令する!!」(との放送であったが、然かし船倉に入り込んだ将兵は海没船の船倉より浮び上って助かった者はほとんど無かったと聞いた)四、五〇〇余名の将兵一同は心の中で、 日本最後の輸送船団が、無事目的地に到着出来たことに安堵の胸を撫で下してゐたであろう。
やがて船は船員達の見事な手捌きで鉄の軋む大きな音と共に、次々と大きなハッチのロが開き始めた。漸くの間鉄の軋む音は止らなかった。やがて初年兵達が甲板上の炊事場に昼食受領のため集合しつつあった。其の兵達の顔色も無事目的地に後一歩で到着出来る喜びは、隠し切れ無いものが伺われ、食事受領の態度動作もキビキビとした行動に見えた。対潜監視哨は各部隊中、各中隊毎に一組出されてゐたため、甲板上には数多くの監視哨が至る処に出されていた。
第三大隊第一一中隊岡野中隊も早朝より小生の指揮下数名の監視兵が最後の勤務、後二時間程度の任務と意気込み、丸で小皿の様な大きな眼を開き、真剣な態度で船尾方面の見張りおさおさ怠り無く警戒に当ってゐた。
約一〇米近くに岡山三九聯隊と思える監視哨は船尾右舷の方向の哨戒に入ってゐた。
と其の時である。将に突然如何にも驚いたと思われる様な異様な叫び声をあげた。その瞬間反射的に小生の脳裡を掠めたものは、さては魚雷航跡発見かと、振り返ろうとす間も無く全身を甲板上に叩きつけれた。
倒れながらも上体のみは振り返りつつ、眼に写ったものは船の中央部船橋附近から物凄い黒煙が数十米以上も吹き上げられ、何物とも判断し難い種々の物体が爆音と共に吹き上る凄い状能を目撃した。敵潜艦の魚雷命中と思う間もなく、続いて第二、第三弾連続の命中最後第四弾の止めの命中は船の全型が完全沈没する直前であった。
流石老船六、五〇〇屯も、最後の勇を振り絞り盡しながら後一歩の土壇場まで良くぞ盡し切って呉れた、乾瑞丸の悲愴なる最後であった。被弾僅か二八秒間巨体輸送船も再び、見ることは無く、比島呂宋島北部リンガエン湾沖合約六粁米、水深約二〇米の地点を、四、五〇〇名余の将兵と莫大なる軍需物資は、再び海上に浮ぶことは無く永眠したのであった。
輸送指揮官鍋島大佐も、全将兵一名の犠牲者も無く、無事上陸を心に念願され、日夜を問わず安全輸送を叱咤激励十日間、流石の大声も次第次第に枯れ果て、哀れさえ感じられたのに、而かもやがて来る戦闘に敵に一矢も与え得なかった、軍人としての残念無念さはさこそであったこと、深く推察された。
被弾と共に其の衝撃で打ち倒された小生は、甲板上に一時横転してゐたがハッとして我に帰り、 海中に飛び込み退避することは釜山の港で特訓を受けて居たが、立ち上ろうと思う間もなく海水が全身を浸し始め見る見る内に足も立たない水深になり、もがいてももがいても何か知ら身体を海中に引きづり込まれる感じで、泳ぐ事も、浮き上る事も不能となり、遂に全身海中に全没し、
尚も引き込まれて行く、其の状態は何故か咄嗟の出来ごとであり次第次第沈んで行くことのみしか解らず、倒れて後は幾多の戦友の姿を一人見ることも無く輸送船と共に沈んで行く、突然の出来事でもあり予め空気を腹一ぱい吸込む余裕も無く、次第に呼吸困難となり塩水をがぶがぶと呑み込む、艦上で呑んだ海水の塩辛さを感じ無かったのはその時既に生死の境、意識朦朧として居た関係であろう。
ああ、もう駄目だ、とかすかに意識を覚えた時、不思議にも脳裡を僅かにかすめたものがあった。それは故国の肉親兄弟、長兄、次兄、三兄とまでがさながら走馬燈の如く走り去った。そのことまではうっすらと記憶に残ってゐた。
何程の時間の後か恐らく数秒後であったたろうとふと、何か知ら身体の微動を感じ無意識の中に自然に眼を開いた。海水が眼に滲みる感じも無く徐々にではあったが、次第次第に浮き上り海面に小波の打つ状態が海中より眼の中に写った。そして遂に水上に頭が浮き上りそれと同時に、将に「溺れる者藁をも掴む」のことわざ通り浮遊物の小さい物、何んでもかでも夢中で掴み始めた。
やがて其の内に一米余の木片に確と掴み付き、ようやくにして身の沈まないのに気付き手足のバタ付きも自然と止って居た。多分浮いたと云う安堵が手伝ったのであろう。
その時初めて、ああ、俺は助かり生き帰ったのだ、 一瞬の仮死状態から生き還ったのだ、将に無限大の喜びとは此の様な時の事ではなかろうかと、後にして思い出されたが束の間、陸地迄無事上陸するのが先決であり然かも僅かの木片でと思うと不安の気持が走る。漸くにして意識も少しづつ蘇みがえってきたのか其の時初めて救命胴衣を装着しているのを意識した。
輸送船上の勤務は必ず救命胴衣を装着することが厳命されて居たのであり、乾瑞丸の轟沈した時には対潜監視の勤務中であった。それがため同船の沈没地点の水深僅か二〇米余の浅地では、船の沈没により生ずるは渦巻現象は無く海底接触の際、何かの弾みで自己の装具の一部が外れ、救命胴衣のお蔭で浮き上がり再び生命を得たことを今尚確信して居る。
慚くにして身の安全を得てふと前方陸地方面を見渡すと、数百人程度の将兵達が乾瑞丸の甲板の上に設置されて居た、救命器具の何か大きい物体に、五六名宛てづつ多分掴りながら集団で遙か数百米先を波状的に見え隠れつつ、陸地方面に向って漂流しているのが眼に写った。沈役船からは絶え間も無く浮遊物が次々と浮び上って来る。
自分の周辺には早くも人影は無く時折り海没死体が、救命胴衣を装着した儘波の間に浮遊してゐた。そっと片手を顔に当て、黙疇する。続いて見馴れない異様な物体は多分、船体の一番下に積み込まれて居た軍馬の臓物であろう、それが長々と波に漂って居た。物云わぬ軍馬動物だけに一層の哀れさを感じさせられることを禁じ得なかった。遅れて近づいて来た兵士の顔から鮮血が流れてゐた。「おいもう陸地は近いそ頑張れよ。」と励ましながら夢中で陸地をめざした。
そうこうする内に五、六人も掴って居た大きい筏が横の方から来て声を掛けて呉れた。其の内の唯かが「班長殿ではありませんか、無事で良かったですね、早くこの筏に乗り替えなさい」と呼び、掴まる場所を譲って呉れた。
よくよく見ると中隊の森本一馬兵長であり至極元気そうであった。嬉しかった、本当に嬉しかった。此の危機の中で部下の善意が強く身に滲みた。
兵長は中隊一番の文武両道の立派な人格であり誰からも信頼されてゐた。(後にサラクサク峠の激戦場で最終頃、敵戦車の発する火烙放射機により火の玉となり遂に恨みは深く、サラクサク戦場に散り果てられたのであった)
流石六人乗りの筏は六倍の人力の増大であり、一人乗りより早く対岸に近づいて来た。丁度その頃、輸送船の護衛の任務を最後迄果した護衛艦が敵潜水艦を発見したのか突然爆雷投下が始まった。さては何事かと振り帰って見れば高い水柱が立ち上ってゐた。然かし其の強烈な衝撃は強く、水中の我々の腹部に大きく重圧を与えたのであり、その瞬間には筏の上に飛び乗り腹圧を避けた。
其の頂より風速もやや強くなり海岸近くは白波が次第に高く成りつつ見え始めた。船の沈没後より四、五時間後漸やくに海難者も次々と海岸近くに辿り着いたが、想像以上の高い白波に卷かれて、先に進んだ筏が次々と砕かれ、決死の思いで辿り着きながら、後一歩のところで又しても海中に押し戻されて行った。之がため数度の打ち返しに会った将兵が遂にカ尽きて海の藻屑と成られた惨劇を後で知った。
然かし其の白波に跳戦するしか生きる道は外に無く意を決した我々も、後から押し寄せる白波の中にも筏にしっかりと掴りながら突き進んだ。その瞬間筏は何処へ飛んだのか? 又同乗して居た戦友達の姿も影もかたちも無く、 又しても海水を厭と云う程呑み込まされた。然かし幸いにも強い一部の波に押されて珊瑚礁の上に打ち上けられた。そのことは対岸に打ち上げられた何寄りの証拠であることを半ば無意識の中に感じ取り、やれやれ漸くにして命を拾い助かったのだという実感の喜びを感じたのであります。
広い砂浜には既に数百人の遭難者達が小単位の集団を造り、何かに忙しく右往左往してゐた。海岸に上陸し疲労もそこそこに、各隊の将兵共々に上官、部下の生息を一生懸命に探し廻ってゐた。
第一一中隊岡野中隊も中隊長と小林准尉以外の将校は明るい内には助かっていた。夜分に入り潮中尉が彼の白波に四度も押し流されて、ようやくにして上陸出来たと、疲労の色も濃く中隊位置に帰ってこられた。然し夜に入っても指揮班の下士官達はほとんど帰ること無く、兵達と共々に枕を並べて轟沈した船倉の中に護国の鬼と化して居られるものと推測する。
中隊の犠牲者は第三小隊長野津曹長以下実に六二名、編成一〇九名中の五六%の海没者を出した。大東亜戦争の決戦場と成る比島の地を眼前にしながらも、一戦も交える事も叶わず無念にも散って行かれた英霊に対し、暗闇の中で生存者一同、 心よりの成仏を静かに祈った。
又、其の合間合間に海没戦友の尊い屍ねが、 一夜の内に半身を砂に埋づまり、早くも死臭を漂わせて居た。爆発等の関係で顔面の捐傷も激しく、確認不能の遺体も在り、軍衣の注記を調べ七名の戦死体を確認し、 一ヶ所に集結して、それぞれの遺骨遺髪を懇ろに取り上げ、生存者の兵士達の携行した白布に包んで胸に胞かせた。英霊も漸くにして、生ける戦友の肩から胸に胞かれて、成仏の喜びを語り合って居られる感がした。
思えば酷寒北満州の凍土の中で各種の厳しい猛訓練を共に励み、苦しさも楽しさも分ち合った数多い戦友も一瞬のうちに、その尊い命を御国の為とは云いながら捧げ尽され、永遠に不帰の客と成られた運命のいたずらは余りにも無常であった。
故国の肉親達が、ひたすらに其の健在、帰国を待ち詫びられる妻子の悲しみその心境は察しても計ることは到底出来得ません。
ふと我に帰り心よりの埋葬を早くと一同も同感で取り掛った。だが兵士達全員、昨日の海没の際兵器弾薬一切を失い、装具の円匙十字鍬も無く、只在る物は腰に着けて居た帯剣のみだった。
英霊の埋葬であり少しでも海辺の高い所を選んだが、其の場所は蔓草が繁茂し用意には掘れず海岸の浮遊物板切れの厚い物を探して掘りあげた。何分にも昨日の朝食以後四食の食事抜き、水の一滴も吸む事は無し。それに加え、過半数以上の戦友を一挙に失った海難の悲劇と共に、精神共々の極限の疲労であった。埋葬中、時々其の様子を探るように繁みの中から、現地人比島の男性の鋭い眼光も決して心は許せなかった。
既に戦場でも有り何は無くとも埋葬と思えども一本の線香、 ローソクとて無い只両手の合掌のみであった。誰が供えたか花の替りに名も知らない雑木の小枝を一本づつ供えられたのが精一ばいの手向けでありました。連合軍の北進以来、其の戦果は悉く敵の手中に有り、特にレイテ湾の激戦以来極端にして顕著であり、従ってフィリッピン全土の比島人は既に日本軍を敵視し、厳しい敵対感を燃して居た。それが為海難部隊としては、夜間防備が必要と成り幾日までも海難犠牲者を偲んで居てはならなくなり現地人の夜襲を警戒防備の必要が判断された。
然かし前述の様に兵器は皆無、是れでは例え現住民の蛮刀とて危険度は充分に有り、疲労極限に在りとも飽く迄外敵を阻止し、防禦せねば成ら無い。戦時中、国民総動員の日本国では竹槍を最後の手段として、女性達も真剣に訓練を受けた様に、他に武器の無い当時の現况では帯剣を抜き取り海岸の一部に密生して居た手頃の木を切り、先端を固く結び付け近代戦場には当らない内地訓練同様、木槍防備の警戒網を設置した。幸いにして当夜、案じてゐた現地人の夜襲は無く夜は明けた。
ダリガヤスの海面は昨日の尊い人命一、二〇〇余名の犠牲者を呑み乾し、将に阿鼻叫喚の惨劇は何処へやら、南国の強い朝日を受けて煌めきながら静かな海面を漂よわせて居たのは、余りにも無情の自然の姿に云いえない寂しさを実感したのは一人小生だけでは無かったでしよう。如何に軍人で在るとも人間としての欲望の一つでも在り、又生命の糧で在る食糧抜きでは、精神的ショックと共に昨夜の不眠も手伝って、眼も虚ろ之れが嘗っての日本軍人かと疑がわしさえ抱く様であった。
漸くにして遭難二日目の昼前頃に、先に無事上陸し敵空襲の合間にも敢然として軍需品の揚陸作戦に死力を尽されて居た本隊から、第二中隊第三小隊、第一分隊長田村正人伍長を救援隊長とする一行が、地理不案内の中を少数良くも海難地を捜索されながら無事白米の握り飯と其の他が届けられた。将兵共にまるで餓鬼の如く口に運んだ、然かも噛むことさえ無く丸呑みし胃袋に直通し、漸くにして腹半分目、それでも大きな満足感を味い、本隊の配慮と戦友の友情に深く感謝すると共に、昔満州で唄った戦友の軍歌「タバコも二人で分けて呑み」の歌詞を繰り返し頭に浮べながら味わった。
先着本隊の位置も判明し、腹も出来た。今は本隊追及が急務である。昨日この海難海没者の英霊に対し深甚なる哀啅の意を捧げ本隊誘導者田村伍長の後に随行し、久方振りに満州出発当時の第三大隊の威容を整え林聯隊長の指揮下に入り、彼我決戦の天王山の戦いには海没戦友の弔い合戦を固く決意して、本隊の力強く暖かい心温まる雰囲気の中に解け込んで行った。
合掌
鉄兵団バレテ峠の激闘
日米の決戦部隊となった北部ルソン・バレテ峠の攻防戦および苦難の転進行を克明に綴る
山本照孝 (当時歩兵第六十三連隊本部書記・陸軍准尉) 鳥取県鳥取市

ルソン島転進
昭和十五年八月以来、北満・興山にあって警備についていたわが歩兵第六十三連隊(第十師団日鉄兵団)が、決戦場突入の命を受けたのは、昭和十九年七月二十四日のことであった。爾後、諸準備のあと、朝鮮海峡を渡って内地の門司に入港、ここで五千総トンに満たない松浦丸に配船替えをして、玉三七船団の編成に入り、タ闇迫る同港をあとにした。
これが九月七日のことである。途中、同行の千早丸の沈没(敵潜の雷撃) などがあったが、九月十七日、松浦丸は無事に台湾・基隆(キールン)に入港した。ここで我々は、台湾防衛の任務を命ぜられることになるのだが、予期に反した任務とあって、いささか気抜けしたように感じたものである。
しかし、ここでさらに部隊の練成を図り、来るべき決戦において必勝を期するためには、絶好の試練場でもあった。十月十二、十三日の両日にわたって、台湾全土は百機におよぶ敵艦上機の銃爆撃を受け、相当の被害をこうむった。このように敵の反撃作戦はしだいに惨烈を極め、 レイテ島の死闘もいまやむなしく、 ルソン島が急を告げるに至ったのである。
そして十一月六日、突如、 ルソン島への転進命令を受けた。師団は第十四方面軍隷下に入り、 ルソン島マニラに集結を命ぜられたのである。制海権もなかば敵の掌中にある情況にかんがみ、配船も海没を考慮し、第一船は師団司令部、歩兵第三十九連隊主力、砲兵一大隊、通信隊等で、 マニラに向け十ニ月三日、高雄港を出港した。十三日には、すでにマニラ到着の連絡があったのであった。残余の師団主力は、左記船区分により乗船を行なった。
有山丸=歩兵第十連隊(一コ大隊欠)、砲兵一コ大隊、輜重一コ大隊
大威丸=歩兵第六十三連隊(一コ大隊欠)、砲兵第十連隊(二コ大隊欠)
乾瑞丸=輜重兵第十連隊(ニ大隊欠)、歩兵第十連隊の一コ大隊、歩兵第三十九連隊の一コ大隊、歩兵第六十三連隊の一コ大隊
かくて、乗船大威丸の入港により、連隊は四日間の搭載作業を終わり、十二月十四日、タ闇迫る高雄港をあとに玉一七船団の編成に入り、 一路ルソンへと航行をつづけた。
しかしながら、敵潜水艦の跳梁するバシー海峡突入後まもなく、敵潜水艦出没の情報により、台湾西南方海上で待避。爾後、船団指揮官は各輸送指揮官と協議し、有山丸はアバリに直行、他は北サンフェルナンド港に向け航行することに決定した。そこで急遽、針路を変え、 ハシー海峡を横断するや、 ルソン島陸地沿いに北サンフェルナンド港へ直行したのであった。十二月二十三日未明、北サンフェルナンド港沖に投錨するや、師団より土屋参謀長来船し、次のような敵情、ならびに兵団の任務を説明されたのであった。
すなわち、 レイテを陥れた敵将マッカーサーは、クリスマスまでにマニラを占領すべく豪語しありて、数群よりなる敵船団はミンダナオ島を経て、逐次北上しつつあり、句日を経ずして上陸すべきが予期せらるる状況である。しかるに軍のルソンにおける決戦態勢いまだ整わす、南部、中部、北部にわすかの守備兵力を有するのみにして、軍司令部は山下大将以下、 マニラよりバギオに転移し、上陸兵団を陣地配備につかしめ、敵を中部ルソン平野に入れ、航空勢力と相俟って、北部より一挙に敵を捕捉殲滅せんとする企図であった。
そして、軍はカロバロ山系扼守を鉄兵団に 命令し、兵団はわが連隊をして扼守せしめんとする企図であった。すなわち参謀長の説明によると、歩兵第三十九連隊(一コ大隊欠)、砲兵一コ大隊は マニラ上陸と同時に軍命令により軍直轄となり、 バターン半島守備隊に配属せられ、また、歩兵第十連隊(一コ大隊欠)、砲兵一コ大隊は、アバリに上陸と同時に駿兵団(一〇三師団) に配属、守備陣地到着までに約一カ月を要し、わが連隊を基幹とせねばならぬ状況である旨、説明せられた。
したがって、火急を要する場合とあって、揚陸作業は戦闘に直接必要なるものより実施するごとく指示されたのであった。よって連隊は、船舶部隊の協力により、人員の揚陸作業より開始したのであった。船舶兵以下すべての者が褌ひとつで揚陸作業に懸命の努力をしている 姿。椰子林にかこまれた市街地は、敵の爆撃でその影もなく、すでに廃墟となり、崩れかけた壁に「勝利、しからずんば死か」と大きく書かれた落書こそ、上陸したわれわれへの最大の贐(はなむけ)であった。
ルソンの戦いはすでに始まったのである。市街地を離れ、 一歩椰子林のなかに入れば、海難者の収容せられしもの六千名を越え、あちらの木陰にもこちらの木陰にも、敵の銃爆撃による負傷患者と海難患者がうごめいていた。時あたかも僚船乾瑞丸は、北サンフェルルナンド港北方二十キロの海上にて、十二月二十三日午前十時、敵潜水艦の魚雷攻撃三発を受け、轟沈の悲報に接したのであった。 一瞬にして海の藻屑と化した千有余名の英霊と、軍需資材の消耗は、師団戦力に一大痛撃であった。
わが連隊では船団の関係上、第三大隊(第七中隊百十名を含む)大隊長官崎少佐以下六百六十名が乾瑞九に乗船していたが、轟沈の悲運にあい、二百九十名の尊い犠牲者を出したのであった。
サンホセへ進駐
さて、 揚陸作戦 は、敵の空爆撃にさらされながら、三昼夜続行で、ようやく終わったのであった。そして一刻の猶予もならす、陣地配備のための終結地サンホセへ前進することになった。しかし、 輸送力なき部隊の行車は哀れなるもので、連隊は自動車隊に若干の輸送援助を受け、残余の梱包装具は配当された輺重車両に積載、 一週問の行第計画のもとに十二月ニ十七日未明、凄然たる北サンフェルナンド港を出発したのであった。長途の船舶輸送に加え、不眠不休の揚陸作業に連隊将兵一同は疫労しきっていた。その疫労せし体に加えて、 ルソン特有の灼熱下の行軍とあって、滝のごとく流れる汗を拭き、満載せる輺重車襾を「エンサエンサ」と曳きながら前進したのであった。これがため夕方には六、七十名の熱病患者が出たほどであった。
このような状況にかんがみ、連隊は昼間行軍をさけ、夜行軍により前進をつづけたのであった 越えて三十日、 ロザレスにおいて、左記要旨の師団命今を受けたのである。
要旨命令
一.歩兵第六十三連隊をもって速やかにロザレス平野の監視台パルンガオ三角山に陣地を占領し、師団の前進拠点たらしむべし。
二.歩兵第六十三連隊長は歩兵一コ中隊を速やかに捜索第十連隊長の指揮下に入らしむべし
よって連隊長は第二中隊(中隊長前田大尉) を三角山に、第六中隊(中隊長足立中尉)を捜素第十連隊長の指揮下に入るべき連隊命令を下達し、翌三十一日未明、両中隊は、「立派に戦ってくれ、 一同の健闘と武運を祈る」との連隊長の訣別の言葉をあとに、「しつかり頑張ります」と生きてふたたび相まみえざる決意をもって出発したのであった。
戦場には大晦日も元旦もなかった。連隊はわすかの酒と栗で大晦日を味わい、 明けて昭和ニ十年、凄惨な戦場に迎えた正月、連隊は星のまたたく早朝三時に出発、夜の街道を東へ東へと前進をつづけた。かくして連隊は灼熱下の行軍を終わり、サンホセに進駐した。ここでは、はじめて邦人婦女子に接し、本当になつかしかった。これらの人々は戦況の悪化に伴い、 マニラ方面より引き揚げ、北ヘ北ヘと移動して行くため、 一夜の宿をとっておられるとのことであった。異国の地にあって、粒々築き上げたすべてのものをなくして、着のみ着のままにて去り行く心境、同情するに余りあるものがあった。
連隊のサンホセ到着と前後して、北サンフェルナンドに残置してあった隊属貨物が、自 動貨車によりつぎつぎと集積された。しかし北サンフェルナンド港においては、われわれが出発後、「旭」(第二十三師団)・「撃」(戦車第ニ師団) の兵団が上陸を開始、 いまだ上陸を終わらないうちに敵機動部隊の主力がンガエン湾沖に姿を現わし、艦砲射撃を開始したのであった。よって軍は急遽、「盟」(第五十八旅団)、「旭」の兵団をもってリンガエン正面の敵上陸作戦にたいする反撃作戦を開始したのであった。 このため、北サンフェルナンド港一帯はしだいに焼土と化しつつあるとのことであった。
バレテ峠に陣地構築
憩う間もなく、連隊長は任務による陣地偵察を実施し、プンカン付近に陣地占領を決心し、各隊にたいし陣地占領命令を下達したのであった。そして、各隊はこの陣地配備命令にもとづき、 一月六日、それぞれ配備についたのであった。
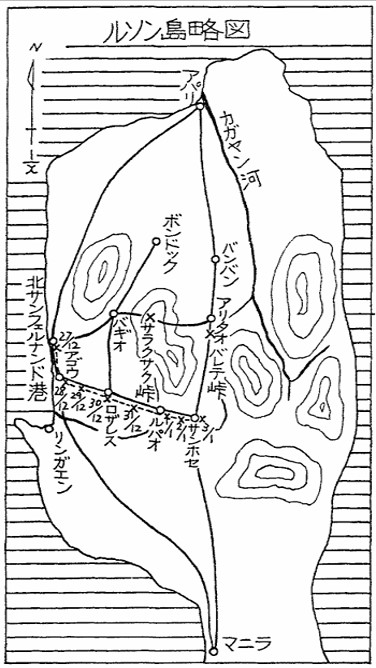
仮の陣地もいまだできない二十年一月八日、敵艦上機グラマン数機の銃撃を受けた。敵機は友軍の所在を知ってか知らずか、約一時間にわたり急降下しては銃撃の雨を降らせて帰って行った。
この銃撃のため、プンカン平地に集積してあった師団の燃料、砲兵弾薬、エ兵爆薬等がつぎつぎと炸裂し、夜半に至るも、その炸裂音は山野にこだまして止まず、損害多大なるものがあった。師団長は縦深なき現陣地は爾後の作戦行動に非常に不利なる点を認め、パレテ峠に陣地占領を変換するごとく命令されたのであった。
よって連隊は一月九日、昼間行動をさけ、日没を期し前進を開始して、 一路バレテ峠へと向かったのであった。バレテ峠はマニラよりアパリに通ずる縦貫道路の要地であり、標高千メートルに近かった。この峠を含む八キロの地帯には、急峻、傾度十五度の坂道もあり、密林鬱蒼として四季霧がたちこめ、湿潤この上もなき要塞地帯というべきところであった。軍はバレテ、サラクサク、バギオの線を扼守することによって、 ルソンの宝庫カガャン平野をわが掌中に入れ、敵殺戮の根拠地たらしめる計画であった。陣地は縦深四十キロの間に地の利を得て配備せられた。
すなわち、サンホセ以北プンカンにわたる五キロの間に、師団前進陣地としてプンカン守備隊を編成し、 一〇五師団の歩兵一コ大隊、連隊の第五中隊、野砲兵一コ中隊、独立速射砲一コ中隊を第一〇五師団井上少佐をして指揮をとらしめ、遊撃作戦を樹立する。そして洞窟陣地を構築し、この線により敵を阻止し、右兵団と相俟って一挙に捕捉殲減すべき計画であった。また、プンカン守備隊後方のデグデグには、カラングラン方面よりの敵機動部隊の進出を考慮して、遊撃隊を編成した。神出鬼没、敵殺戮にあたるべき潜伏拠点を配備し、第一中隊松岡中尉をしてこれの指揮をとらしめた。
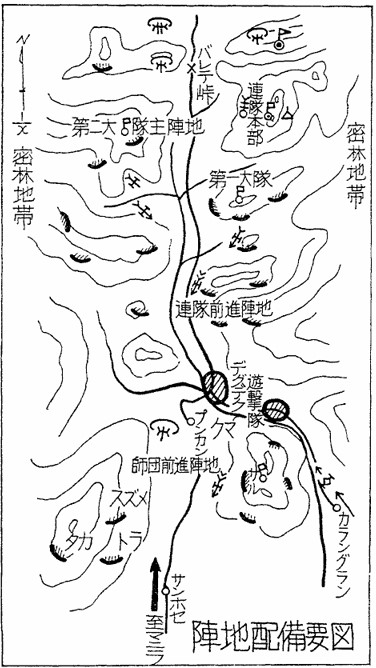
さらに、主陣地の前進陣地として陣地前方十四、五キロの地点、 ミヌリ平地に第九中隊 (独立速射砲小隊属)を配備し、中隊長林原中尉が指揮をとったのであった。主陣地は、五号道路を中心にバレテ峠に至る縱深十キロにわたり、連隊を主力とし、右第一線を第二大隊(第五、第六中隊欠)、集成第十二中隊、作業小隊、連隊砲中隊、独立速射砲中隊、速射砲中隊(一コ小隊欠)を配備、第二大隊長根本少佐が指揮をとった。左第一線は第一大隊(第一、第二中隊欠)、独立速射砲第五大隊(三コ中隊欠)、作業中隊(一コ小隊欠)、速射砲小隊、歩兵第三十九連隊の第三中隊の半数、臨時機関銃中隊を配備し、第一大隊長板垣大尉がこの指揮をとった。予備隊として第三大隊(第九、第十、第十一中隊欠)を配備、第三大隊長宮崎少佐が指揮をとった。
以上のごとき主陣地防禦編成をもって・ハレテ地区隊として、連隊長林大佐が指揮に任じたのであった。また、師団は直轄部隊たる中迫撃砲第七大隊( 一コ中隊欠) 、師団砲兵隊( 三コ大隊欠) 、師団工兵隊をバレテ地区隊に協力せしめた。連隊は陣地配備を終わるとともに、来るべき決戦に備え、陣地構築に懸命の努力を行なった。この間、敵は観測機をもって陣地上空の低空捜索を開始した。戦闘に企図の秘匿は絶対の要件であり、航空勢力のないわが軍にとっては、とくに必要であった。
したがって、暴露陣地の行動、昼間の炊煙、夜間の火光はもちろん、陣地構築の槌の音、人声に至るまで細心の注意が必要であった。一兵の過失は全バレテ地区隊を死地に陥れる結果となるので、地区隊命令をもって、厳に注意するごとく、各隊に注意を喚起していたのであった。
第二中隊の斬り込み戦闘
ミンダナオ島沖を逐次北上しつつあった敵機動部隊(主力艦船三百隻におよぶ)は一月初旬、堂々とリンガエン湾を制してしまった。特攻隊あるいは突貫隊の一部の攻撃にもかかわらす、敵艦上機数百機は、リンガエン湾一帯に爆撃を開始、帯に爆撃を開始、加うるに艦砲射撃は猛烈を極め、黒煙もうもう、 つぎつぎと焼土と化していった。敵の上陸作戦に反撃すべく守備していた「旭」 「盟」兵団はなすすべもなく、多大の損傷を受け、後退したという。
この砲爆撃の猛射は、 一昼夜にして完全に敵の橋頭堡をなさしめ、 一月八日、敵は堂々上陸用舟艇をもって、わが軍の阻止を受けることなく上陸を開始したのである。決戦を企図する方面に敵に優る兵力を集中し、 一挙に戦果を拡張するのは、どこの軍隊における戦術にも変わりはなかった。上陸した敵は、中部ルソン平野に「旭」「盟」 「撃」の兵団をぞくぞくと撃破した。
とくに皇軍の虎の子兵団といわれた撃兵団 (戦車第二師団)は各所に多大の損傷を受け、再編成のやむなきに至り、二月八日、戦闘司令部をサンホセより十師団の前進陣地プンカンに転移し、残存部隊も逐次集結した。また、撃兵団の中部ルソン平野における機動作戦を考慮して、連隊は当初、兵団前進拠点の三角山に配備されたわが第二中隊にたいし、左記要旨の命令を下達し、第二中隊を主陣地に撤収したのであった。
要旨金令
一、三角山占領部隊は歩兵一コ小隊、通信一コ分隊を残置し、原所属に復帰すべし。
右の要旨命令に接した中隊長前田大尉は、長谷川少尉以下一コ小隊を残置し、前任務を続行せしめ自らは中隊主力を率いて一月十三日、主陣地へ帰還したのであった。
しかるに上陸した敵機動部隊は、戦果をしだいに拡張していった。撃兵団はこれら機動部隊阻止のために橋梁爆破、道路阻止等、わが兵団に協力を求めたので、ふたたび第二中隊をして、 これに当たらしめたのである。
一月十五日、第二中隊はサンミレドローウミンガンータユグ間の橋梁爆破命令を受け、主陣地のミヌリより出発したのであった。越えて一月二十二日、ウミンガンに集結と同時に撃兵団の指揮下に入った第二中隊は、ウミンガンの守備についたのであった。敵はすでに三角山の長谷川小隊正面に現われはじめ、 一月二十日、敵の戦車はコンザレス北方よりウミンガンにたいし、砲撃をはじめてきたのであった。長谷川小隊は敵と接触しつつ三角山拠点を撤収。二十五日、中隊に復帰したのであった。前田大尉は同日夜、 コンザレス方面の敵にたいし、河原准尉以下二十一名の斬込隊を派遣、戦車大破三、自動貨車一を破壊 、多大なる戦果を挙げたのであった。
中隊は一月二十九日、撃兵団松本大隊の指揮下に入り、ウミンガン防禦陣地を構築すべく、敵の砲撃下、けんめいの作業を続行した。しかし、敵はコンザレス方向よりその主力を市力、あるいはタユグ方向より包囲攻撃してきた。三十日夜半を利用し、松本大隊長以下斬込隊を編成、敵砲兵陣地にたいし斬り込みを決行した。斬り込み寸前、敵の猛射により中隊は尾沢少尉以下四名の犠牲者を出したのであったが、この斬込隊により、敵の砲撃は一時衰えたのであった。
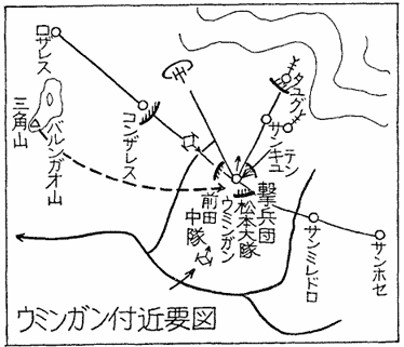
二月一日にいたり、敵機(P38を主体とする)は編隊をもって守備陣地にたいし、猛烈なる銃爆撃を実施した。加うるに、敵の砲撃もいままで以上に熾烈となり、さらにこの間隙を利用し敵歩兵は三百メートルの至近距離まで接近してきた。しかし、全員士気旺盛で、死守をもって抵抗した。夜間に入るとともに、河原准尉以下十五名、山家軍曹以下八名を斬込隊として派遣、敵の機関銧陣地を粉砕し、陣地に帰還したのであった。敵は、わが方の斬り込みを極度に恐れ、夜間は子想以上の距離を後退したとのことであった。
越えて二日にいたり、夜明けとともに敵歩兵約一コ大隊は、陣地の三方より戦車の砲塔射撃と、砲兵の援護射撃のもとに、攻撃を開始してきたのであった。戦闘はいよいよ惨烈を極め、午後二時ごろには指揮班と小隊、小隊と分隊間の連絡がまったく杜絶した。砲煙と土煙の充満した陣地は、血にうずまってしまったのである。
かくして、中隊長前田大尉以下、中隊幹部はことごとく戦死してしまった。夜陰を利用し、敵の警戒網をくぐり、プンカン前進陣地に三々伍々生還した者は、南場軍曹以下四十八名であった。本戦闘による戦死者は、中隊長以下六十名を数えた。
プンカン前進陣地の奪回
敵は中部ルソン平野を攻略し、その主力は直下してマニラへの進撃を開始するとともに、一部は二月上旬、師団前進陣地にたいし攻撃を開始してきたのである。前進陣地の攻撃は、観測機をもって陣地を捜索し、陣地らしきものを発見するや、後方の砲兵陣地より砲弾の雨を降らせ、守兵なきを確認したのち、戦車に随伴した歩兵部隊がはじめて攻撃してくるのであった。
また、攻撃にあたっては、陣地正面より攻撃することなく側面より攻撃し、いかなる急埈な山頂までもプルドーザーをもって道路を構築する。その設定速度はじつに一日に百ないし二百メートルであった。大森林もしだいに焼土と化し、左第一線「サル」障地も、昼問の砲爆撃のため、第一線ニ線分隊は戦わずして玉砕し、夜間に入り、第二分隊が辛うじて陣地を守備していた。敵攻撃開始いらい一旬、左第一線は二月十九日、ついに第一線の補充を断念、「クマ」陣地に陣地を縮小してしまった。
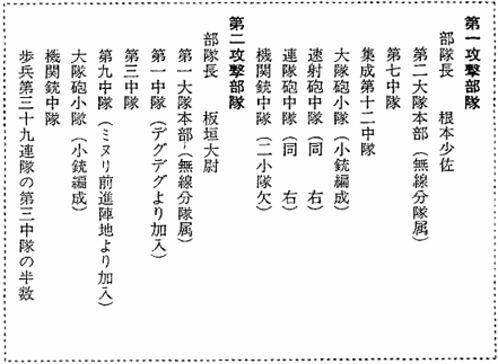
二十日にいたり、敵は井上大隊正面の「トラ」「シン」陣地を占領するとともに、「タカ」「スズメ」の陣地はしだいに蚕食されていったのである。師団前進陣地に集結していた撃兵団も、十九日にいたって岩伸兵団長以下、アリタオに転進したのであった。かかる状況において軍は、 一挙にこの敵を撃滅して、南部ルソン、とくにマニラ攻撃部隊を脅威することによりルソンにおける戦勢を有利に導かんとはかり、当面の敵にたいし攻勢を命じた。師団はこの軍命令にもとづき、連隊主力をもってプンカン前進陣地の奪回を命じたのであった。
よって連隊長は、主陣地防備に支障なき最大の兵力を右下の表のごとく区分し、プンカンに向かい前進したのであった。師団は平林参謀をして、 この作戦指導にあたらしめたのである。各攻撃部隊はミヌリ南方五キロ、三国川上域の×地点に二十八日薄暮までに終結を命ぜられ、二月二十七日、薄暮を利用し、主陣地を出発したのであった。しかしながら、部隊は夜間のみの行動に制限され、加うるに道なき道、山また山と、ジャングル地帯内の行動は意のごとくならなかった。かくして予定の三三〇高知付近に到着したのは、三月二日午後八時ごろであった。
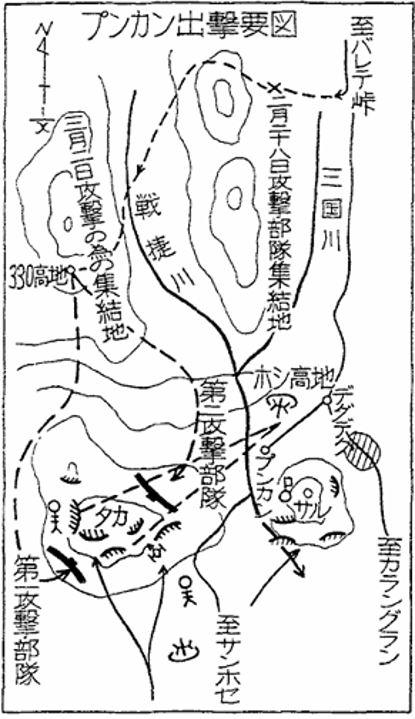
翌三日、平林参謀、ならびに第一攻撃部隊長、第二攻撃部隊長以下各小隊長にいたるまで、敵情捜索をなすとともに、将校斥候を派遣して、敵の背後を捜索した。そして、攻撃奪取目標「タカ」陣地の敵配備状況を詳知するとともに、午後六時、攻撃命令を下達し、同夜二十四時を期して、プンカン守備隊砲兵隊の支援射撃開始と相俟って、 一挙に斬り込みを敢行、陣地を奪取すべく第一線攻撃部隊は着々準備を進めていた。そこへ突如として、本攻撃を中止して帰還すべき師団命令を、将校伝令(後原少尉)にて伝達されたのである。
連隊長は攻撃前進の部署配置を終わり、発進直前なるにかかわらず、命令致し方なく、第七中隊を斬込部隊として残置、連隊将兵は陣地に帰還した。状况は刻々変化し、バギオはすでに敵手に陥らんとし、兵団の右翼隊たる鈴木少佐の指揮する鈴木支隊は、戦闘不利となったため、アリタオに転進して再編成した撃兵団を急進させ、サラクサク峠を扼守させた。しかし、これまたしだいに不利となり、 バレテ主陣地の側背より脅威を受けるような状態になったので、攻撃による兵力損耗等を考慮して、攻撃中止のやむなきに至ったのであった。
かくして戦果を拡張することなく帰還したため、プンカン守備隊は、苦戦よく陣地を確保し、敵殺戮に多大の戦果を挙げたのであるが、敵の物量の前には抗するにあたわず、 ついに主力部隊が主陣地帰還後、 日ならずして玉砕してしまったのである。
プンカン守備隊配属の第五中隊も、「クマ」陣地を死守すること一週間、昼間の砲爆撃にたいしては待避壕により損耗をさけ、夜間に斬込隊を編成、敵の心胆を寒からしめた。しかし、しだいに兵力を損耗していった。後方部隊としてはなすすべもなく、二十七日に至り、陣地よりの小銃音杜絶し、中隊長三橋中尉以下中隊幹部のことごとくが、プノカン陣地に玉砕してしまった。三月一日、部隊本部への報告によると、戦死、生死不明七十四名、戦傷者として入院、後方にある者二十九名におよんだ。
第一、九中隊の激闘
当初、デグデグ遊撃隊として、第一中隊はデグデグ東方三キロの地点付近に、カラングラン道よりの敵戦車にたいする肉迫攻撃を準備、陣地配備していた。そこへ敵は「トラ」「タカ」陣地に浸透、北進してきたため、中隊主力は二十五日、 「ホシ」高地東北側三キロの地点に陣地を占領、陣地の補強工事に従事していた。
三月一日、カラングラン道方面より敵侵入の情報に接し、中隊長松岡中尉は第一小隊位置にいたり、拠点の警備補強をはかった。三月二日、敵は本道に沿って百名ほどが攻撃して来たので、これと交戦、突撃を反復し、撃退をはかったのである。
しかし、敵迫撃砲のため成功せず、中隊長負傷、以後、第一小隊は第二橋梁付近に後退、同橋梁北側高地に陣地を占領して、敵と交戦した。敵は火焔放射器および黄燐弾により陣地の焼却をしつつ、各散兵壕を逐次攻撃してきたので、 つぎつぎと玉砕して行った (第二橋梁付近において、中隊長戦死)。
三日にいたり中隊は中隊長、第一小隊の玉砕により再編成し、四日、中隊主力はデグデグ東方北側台地に集結を終わり、反撃作戦を準備した。敵はすでに「ホシ」高地を占領、幕舎を構築していた。中隊は八組の斬込隊を編成、斬り込みを敢行したが、いずれも不成功に終わったのである。
以後、西村少尉が中隊を指揮し、五号道路を北進する敵にたいし、三月十日、斬り込みを決行したが、戦果を挙げることができなかった。かくて第一中隊の斬込隊は、三月十六日、左第一線の勝鬨橋付近に集結したのであった。第一中隊の生還者は西村少尉以下五十二名。デグデグ遊撃地点を突破せる敵は三月八日、連隊前進陣地にたいして攻撃してきた。ここには第九中隊林原中尉以下百余名(海難後、補充する)と独立速射砲一コ小隊が陣地配備をしていた。
射撃においては連隊随一の中隊は、これら敵歩兵部隊にたいし百発百中の戦果を挙げ、一人で二、三十名、多き者は四十名ぐらいを射殺したという。しかし、敵は逐次火砲の増強をはかり、歩兵部隊の損耗を考慮して一挙に歩兵部隊を後退させ、わが配備陣地にたいし、猛烈な砲撃を開始した。このため第一線小隊は、前進も後退もできず、散兵壕にかみついたまま、 つぎつぎと玉砕していったのである。
十七日夜には林原中隊長は、六名の生き残りの部下とともに陣地を後退、潜伏拠点より敢然、斬り込みを決行、十八日夜半、敵陣地に突入、壮烈なる戦死をとげたのであった。
すでにサラクサク峠では激戦が展開され、鈴木支隊(捜索第十連隊)は、支隊長鈴木少佐戦死、矢折れ弾つき、撃兵団に収容されたが、その撃兵団がまた累卵の危うきに至った。そこで鉄兵団はこれを支援すべく、連隊に一部兵力の派遣を命じた。連隊長はこれに応え、予備隊たる第十、第十一中隊を急進させたのであった。
鈴木支隊配属の第六中隊は、中隊長足立中尉以下、将兵のことごとくがサラクサクの地に散華したのであるが、その武勲は支隊長より詳細に報告されたのである。足立中隊は鈴木支隊配属いらい支隊の主軸となり、敵を阻止攻撃すること二カ月余、鈴木支隊はまったく、足立中隊によって保持されたといっても過言ではないという。
主陣地による決戦
一月中旬、バレテ峠を縦深にわたって陣地占領していた連隊は、主陣地決戦を予期し、陣地構築に専念するとともに、糧秣弾薬の陣地内集積をはかり、土民軍の粛清討伐等を行なっていた。こうして二カ月有半を経て、充分とはいいがたいが、陣地配備を終わり、決戦に備えていたのであった。
三月十八日、右第一線より、「少数の敵歩兵『キリ』陣地にたいし攻撃し来るも、第一線歩兵をもってこれを撃退せり」との電話報告を受けた。連隊長はその後の敵の状況ならびに企図を偵察させるとともに、敵の攻撃にあたっては、断乎これを撃退すべく厳命した。また、左第一線にたいしても警戒を至厳にすべく命令した。
翌十九日、敵は主力をもって「カシ」陣地西側より、 一部をもって「キリ」陣地を、迫撃砲の支援射撃により攻撃してきた。とくに迫撃砲の支援射撃は、分秒を間せず射撃してきたため、第一線分隊は対抗の余地なく負傷者が続出し、戦閨カ皆無の状態となった。
「カシ」陣地の一部は奪取されたのである。「カシ」陣地は右第一線の制高地点にして、防備陣地の最大要点であるため、敵にこの陣地を奪取されると、爾後の戦闘は非常に不利になる地点であった。しかし昼間、敵のこの攻撃にたいし第二線陣地の中隊主力は、一発の支援射撃も、負傷者の後送もできず、つぎつぎと斃れ行く戦友を見守るより致し方なかった。これは、第二線陣地の位置の発見を敵に許せば、直ちに敵迫撃砲の集中射を受け、壊滅をまぬがれないからであった。
「キリ」陣地もまた、 「カシ」陣地同様の損傷を受けたのであるが 小隊長日野少尉が、小隊予備隊をもって実施した支援射撃により、敵を阻止し、攻撃を頓挫させることができた。夜間に入り「カシ」陣地を奪取すべ 第七中隊長米田中尉は、中隊予備隊をもって、北側高地稜線上より肉迫攻撃を敢行した。敵機関銧の猛射を浴びつつ突入、ようやく奪取したのであった。
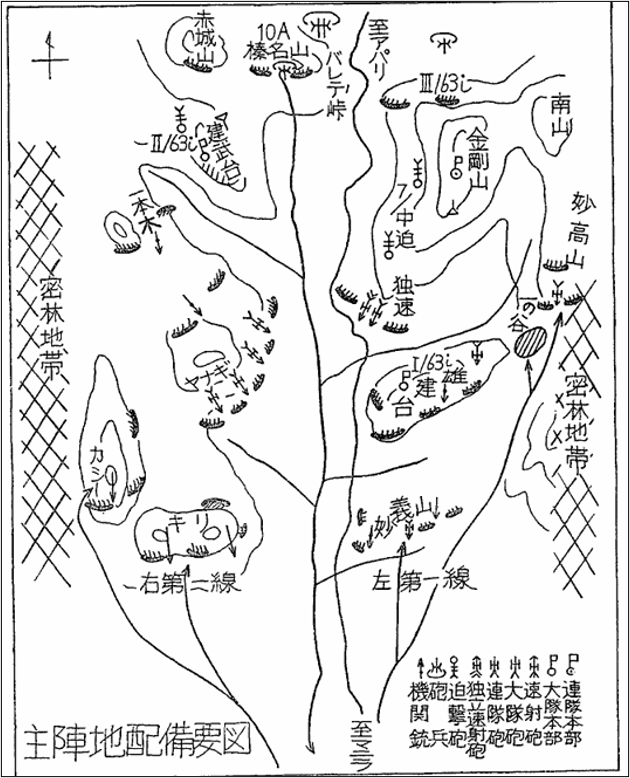
しかしながら、払暁となると、敵はまず迫撃砲の猛射を浴びせるとともに、 戦車による火焔放射をなし、陣地を炎上させ、しかるのちに攻撃をしてきた。また、友軍後方陣地よりの支援を恐れ、敵観測機は、友軍陣地上空を偵察飛行し、蟻一匹といえども発見すればのがさず、という態勢をとった。一兵でも発見すれば、幾を失せず機上連絡により砲撃の嵐となり、右第一線陣地は、修羅の巷と化した。砲煙は陣地をおおい、分隊と小隊、小隊と中隊との連絡はいっさい遮断され、 ただ第一線陣地からときに聞こえる小銃音を耳にして、陣地はまだ健在なるを判知する状態であった。
「キリ」陣地は日野少尉の陣頭指揮により、敵に多大の損傷を与えたのであるが、増援の手兵なきため、五日間の孤立勇奮力闘もむなしく、全員壮烈なる 死をとげたの であった。
「カシ」陣地第一線分隊も同様、敵の猛砲撃により全員戦傷、戦死し、 ついに戦闘力皆無の状態となり、敵に制せられてしまった。
ここにおいて第七中隊長米田中尉は、 ふたたび同陣地を奪取すべく、指揮班と予備隊たる第三小隊の一部を指揮し、夜陰を利用して、斬り込み攻撃を敢行したのであるが、突入寸前、敵機関銃の猛射を浴び、中隊長以下ことごとく戦死、 ついに不成功に終わったのである。「カシ」陣地は、右第一線の関ヶ原にして、死力を尽くして固守すべき陣地であった。そこで連隊長は、榛名山に位置しあった砲兵隊と、建武台に陣地を占領していた中迫撃砲隊の支援射撃により、同陣地を奪回すべく、右第一線大隊長根本少佐にこれの奪回を命じたのであった。
三月二十五日、薄暮迫る建武台をあとに、大隊長は新たに配属された乱部隊高千穂隊 (空輸挺身隊) の第五中隊(再編成)、大隊本部を指揮し、まず「ヤナギ」陣地に推進した。そして、第ニ中隊長大園中尉を攻撃部隊長として夜陰を利用、 「カシ」陣地北側稜線上より「ヤナギ」陣地の機関銃の支援射撃と、砲兵支援射撃の最終弾に膚接して、肉迫攻撃を敢行させるとともに、高千穗中隊をして「カシ」陣地後方に迂回、敵の退路を遮断させ、 一挙に「カシ」陣地奪取すべく命令した。
しかしながら、齟齬は戦場の常識で、友軍砲兵の支援射撃の弾着点は、敵前二百メートル付近まで肉薄していた第ニ中隊の待機地点付近に落着し、有線班をして射弾の延長を要求しても、連絡を得ることができなかった。加うるに敵は攻撃を予察してか、機関銃の猛射撃を浴びせるため、死傷者が続出した。大園中尉は詮方なく、中隊指揮班を指揮し、喊声を上げて突入、全員ことごとく壮烈なる戦死をとげたのであった。
このように夜間攻撃のみに依存する攻撃は、歩砲の協力円滑を欠き、戦闘は甚だしく不利となった。しかし、航空勢力なきこととて、 いかんともしがたく、根本少佐はふたたび第二回の攻撃を企図し、自ら「カシ」陣地に突入奪取すべく準備したのであった。
しかしながら、 敵は、天明とともに「カシ」陣地に兵力を増強し、さらに夜間の反撃に備え、重火器を無数に配置した。このような状況下、「ヤナギ」陣地の第一線将兵たちは、 友軍機の飛来をどれほど待ちこがれたことであろう。飛行機があれば、 この「カシ」陣地を一挙に奪取して見せるものを、 と蛸壺陣地のなかで歯ぎしりしていたのである。
妙高山拠点の攻防
二十六日夜、根本少佐は、薄暮とともに砲兵との支援射撃の協定をなすとともに、右第一線の出撃可能な兵力を「ヤナギ」陣地に集結した。そして翌朝三時を期して「カシ」陣地を奪取すべく、攻撃部隊は夜陰を利用、敵前二百メートルまで接近、待機したのであった。
かくて時計の針は三時を刻み、榛名山の砲兵隊、 建武台の中迫撃砲隊、 「ヤナギ」陣地の機関銃は、 闇を裂いて一斉に「カシ」陣地にたいし、砲撃を開始したのである。砲兵との支援射撃の協定時間十分間を経たる後、 攻撃部隊は一斉に突入を開始した。敵は猛烈なる反撃射撃をはじめた。 このようにしてふたたび突入しようとしたが、 支援射撃の最終弾不明療、 かつ敵の反撃射撃は熾烈を極め、 突入時期を失い、 攻撃部隊は多数の損傷を受けた。そして、 ついに奪取の機を失い、天明とともに「ヤナギ」陣地に後退したのであった。
一方、左第一線は「ラン」陣地において、終日砲撃のみにて終始していた。攻撃を予期していた連隊長は、敵の機先を制すべく、左第一戦大隊長にたいし、敵戦力の消耗と精神的攻撃力挫折を主眼とし、連日、 二、三名よりなる斬込隊を、 数組ずつ派遣すべく命令したのであった。
これら決死の挺身斬込隊は、遠く敵の部隊集結地まで進出し、戦車やプルドーザーの擱坐、 火砲の破壊、 人員の殺傷等、 また敵の兵力の配備、戦法、攻撃企図等、貴重なる教訓を得たのであった。とくに新たなる敵の進出企図(妙高山に指向) にたいし、連隊は、師団に報告するとともに、妙高山拠点に兵力を増強し、妙高山東側地点に、作業中隊安部准尉以下一コ小隊の潜伏斬込隊を派遣し、敵の企図を封殺せんとしたのであった。
妙高山は、 バレテ陣地の最左翼に位置し、陣地占領当初は、まったく対敵考慮を要しない地域とされていた。それが中途において、大隊砲一門、機関銃一小隊をもって、妙高山突角に陣地を占領していた。 敵の攻撃企図がいよいよ妙高山に指向する気配を感じ、兵団は輜重兵第十連陣隊第二大隊」を急派して、陣地配備につかしめたのである。米倉大隊は、陣地到着と同時に、連隊長の指揮下に入り、爾後、左第一線を中第一線とし、米倉大隊を左第一線として、戦闘指導にあたったのであった。
右第一線においては、根本少佐苦肉の策も奏効せず、 「カシ」 地の奪取は、不可能な状態になった。師団は戦況を予察し、右第一線部隊を急援すべく、 マレコ山付近に配備してあった歩共第十連隊第三大隊(大隊長田村少佐) にたいし、晴風山方向から「カシ」陣地奪取をするごとく、命じたのであった。師団より、 田村大隊攻撃に関する命令に接した連隊長は、右第一線部隊を激励し、 田村大隊に協力、陣地奪取を命じたのであった。
田村大隊は無線連絡により砲兵隊と協定し、晴風山を経て、 「カシ」陣地西側より斬り込みを敢行したのであった。 これに前後して、根本大隊攻撃部隊も、機関銃の支援射撃により、敵陣に突入したのであるが、わが攻撃を予期していた敵は、猛烈なる射弾を浴びせ、突入寸前に死傷者続出、後退のやむなきに至ったのである。
このようにして右第一線は、 「カシ」「キリ」陣地の奪取を断念し、陣地の縮小、配備の変更等を行ったのであった。敵は「カシ」「キリ」陣地を確保し、五号道路に沿う河谷を逐次肉薄してきたのである。「ヤナギ」陣地西側台地に陣地占領し、 二カ月有半の偽装工事により、完全に近いまでの掩蔽工事をしていた連隊砲中隊は、敵の猛砲撃にたいし、耐え得る自信を持っていた。
「われ健在ならば不抜台落ちず、もって『バレテ』の不抜台たらしめる」
と豪語し、自ら不抜台と命名していた連隊砲中隊長山本正孝中尉の不抜の闘魂は、連隊砲中隊をして、右第一線随一の戦果を挙げしめていた。そして、痛快な戦果が、連隊砲中隊より報告されたのであった。すなわち、河谷に沿い、北上しつつある敵歩兵部隊にたいし、山本中尉は、 これを捕捉殲滅せんとして昼間、敵の行動、休宿状態等を監視させた。そして、火砲は休宿地にたいして照準を終わり、薄暮を利用して、斬込部隊を編成、敵の退却路に潜伏して黎明を待った。
東天にようやく黎明を告げるころ、射撃を開始したのであった。不意を襲われた敵は、「ワイワイ」泣きながら退却をはじめたので、斬込部隊は、頃はよしと退却する敵をことごとく殲滅したのであった。そして糧食不足の折からとて、彼らの休宿地より糧食数個を分捕り、陣地に帰遠したのであった。またあるときは、 はるか敵陣後方台上に、参謀肩章をつけた敵将校数名が、自動貨車より出てわが情勢を偵察中なるを発見して、砲撃を加え、見事彼らに命中させたという。
四月に入るや、左第一線の戦闘はしだいに白熱化してきた。迫撃砲、戦車砲の射撃は百雷一時に落ちるがごとき様相を呈したため、第一線分隊は昼間攻撃する余地がなかったのであった。
とくに一の谷拠点、妙高山拠点東側地区よりの攻撃は甚だしかった。妙高山拠点においては、米倉大隊の陣地配備の中間弱点より、戦車をもって攻撃して来たため、突角拠点の小隊と第二拠点の小隊は中断され、連絡不能となった。両拠点の小隊は、それぞれこの敵を撃退せんとしたのであるが、至近距離内のこととて、射撃できなかった。夜間に入り、大隊予備隊の増援と突角拠点の大隊砲、機関銃の協力を得て、 これを撃退したのである。
翌日、敵は昨日に倍する熾烈なる戦車、迫撃砲の砲撃を加え、 ふたたび拠点中間に陣地を奪回、機関銃、散兵壕等の掩壕を構築、夜間の反撃に備えた。配備兵力のすくない米倉大隊は、敵の企図を察知しながらも、なす術もなく、これを黙認せざるを得ない状態であった。とくに突角拠点の小隊は、昼間、敵の 砲撃のために、半数以上の死傷者を出したのであった。大隊砲小隊、機関銃小隊は全滅の状態となったものの、米倉大隊は援兵の手兵なく、辛うじて第二拠点に兵力を増強し、敵の反撃に備えたのであった。
蚕食されるバレテ峠
爾後、突角拠点の兵力は、敵の包囲攻撃を受け、しだいに戦死者の数を増し、戦略的価値を失いつつあった。そのため撤退命令が伝達されたのであるが、生還者は数名をかぞえるにすぎない状態であった。中第一線において、敵は攻撃の重点を一の谷拠点に指向してきた。配備中隊たる第三中隊は、中隊長大浜中尉の指揮のもと、伏撃射撃、夜間の斬り込み等、敵の虚に乗じ、敵戦カ消耗へと挑んだ。これが奏効し、第一線よりの報告によれば、人員殺傷数百名を越える状態であった。
しかしながら、多大の戦果のかげには、第一線将兵の骨肉を削るがごとき、不眠不休の苦闘がつづけられていた。第一線分隊は、 昼間、敵の乱射乱撃を受け、蛸壺より一歩も出ることができなかった。夜間に入り、第二線分隊より送られてきた握り飯を噛りつつ斬り込みを決行、夜となく昼となく死闘をつづけ、 つぎつぎと散華していった。
絶対的な航空勢力による砲爆撃と新鋭部隊の攻撃によって、不抜の精神力を堅持する皇軍将兵とはいえ、術策ことごとく尽き、陣地はしだいに蚕食せられる状態であった。とくに、妙義山拠点は、陣地占領当初よりの計画であったため、 陣地配備に死角をつくらせず、 数カ月にわたる糧秣を確保し、 絶対不敗の堅陣であった。しかし、 一の谷拠点の敵は、 しだいに奪取陣地を拡張して、 雄健台、 妙義山拠点中間に侵入し、 両陣地にたいして攻撃を加えてきた。
そのため、妙義山拠点との連絡が中断され、雄健台の大隊本部は、敵と対応する射撃音を耳にして、 妙義山拠点の第三中隊の健在を知るのであった。戦場はしだいに蚕食され、敵の砲爆撃は日々熾烈を極めてきたのである。とくに敵の編隊爆撃は、 陣地を変容させたのであった。妙高山の第二拠点も累卵の危うきに至ったため、連隊予備隊である第三大隊 (大隊本部、第九中隊の生存者ニ十名〈病院の退院患者など〉、機関銃中隊〈二コ小隊員〉)、 大隊砲小隊を急進させ、防備にあたらせたのである。
しかし、敵は戦車をもって陣地を蹂躙し、一挙に奪取しようとしたのである。 これにたいし第一線分隊は防備に万策つきて、白昼堂々と肉迫攻撃を敢行し、敵戦車を擱坐、随伴歩兵を殺戮し、 自らはつぎつぎと戦死していったのであるが、士気はまことに旺盛なるものがあった。このように壮烈なる白兵戦が連日、随所に展開され、しだいに第一線部隊が損傷を受けつつあるとき、鉄道第八連隊(約五百名) が軍命令によりバレテ地区へ急進を命ぜられ、妙高山へ増援されたのであった。
しかし、すでに第二拠点は落ち、第三拠点の攻防戦が展開されていたが、軍の集成部隊である鉄道第八連隊は戦力低下することおびただしく、 拠点を確保することができなかった。師団は駿兵団より配属を解かれた歩兵第十連隊を南山陣地に進出させ、妙高山拠点正面の戦闘を担任するように命じたのであった。
かくて、 連隊長指揮下の戦闘部隊は指揮転移し、歩兵第十連隊長指揮下にて、戦闘を続行したのであった。壮惨なる「バレテ」の決戦は月余におよび、敵の砲爆撃の硝煙は、戦線を覆い、千古斧を入れざる大密林も、焼土と化し、戦況はしだいに不利となりつつあった。
このとき、敵はすでにバギオを落とし、 ポンドック街道を北進しつつあった。方面軍司令部、旭、盟、虎の諸兵団は戦闘不利となり、サラクサク峠へ急進、防備についていた撃兵団もまた、急を要するに至っていたのである。
「カシ」 「キリ」陣地奪回を断念した右第一線も、戦場を「ヤナギ」 「一本木」の線に整理していた。しかし、配備の第七中隊は中隊長以下、中隊幹部ことごとく戦死し、下士官以下十数名にすぎなかった。また、再編成の第二中隊も中隊長大園中尉戦死後、長谷川中尉が指揮していたが、兵力は三、四十名にすぎなかった。
第一線は重火器部隊である連隊砲中隊、速射砲中隊、機関銃中隊、大隊砲小隊、 独立速射砲中隊、勤兵団の大藪大隊により保持さ れていたのであるが、熾烈なる砲爆撃のために、なすすべがなかった。 「ヤナギ」陣地にあった速射砲中隊は、中隊特有の真価を発揮することなく、火砲を放棄するという止むなき事態に至り、同中隊の人員をもって、小銃部隊を編成し、第二線に収容されたのであっ 。
急迫する連隊本部
五月に入るとすぐに、敵の攻撃が増し、熾烈を極めるとともに、敵歩兵部隊は河谷に沿い、建武台陣地にたいし攻撃を加えて来たのである。建武台の大隊砲はこの敵歩兵部隊にたいし、伏撃射撃を浴びせ、人員殺傷数十名の戦果を挙げ、敵のこの攻撃を撃退したのであった。しかし、一方、一本木方向にたいして攻撃してきた敵は、同地点の配備についていた大藪大隊を撃破し、建武台陣地西側より、赤城山方向に攻撃の矛を転じた。このため、「フナ」陣地の配備についていた第一線部隊は完全に包囲され、建武台の大隊本部との連絡を遮断されたのであった。かくして、「フナ」陣地配備の第二機関銃中隊、第二大隊砲小隊の一部は、敵陣にたいし斬り込みを実施、大隊本部位置へ撤収するごとく命令された。こうして辛うじて、 一部兵力を残し、建武台に撤収したのであった。
中第一線においても、大隊長板垣大尉が敵迫撃砲弾のために壮烈なる戦死をとげ、後任大隊長として連隊本部付中條少佐がこれに代わって指揮をとった。しかし、妙義山拠点は、敵の手中に入り、雄建台陣地も、 一の谷拠点方向よりの敵の包囲攻撃により、月余におよんだ善戦苦闘も空しく、 いまや、全員壮烈なる玉砕寸前にあった。こんな状況にあるとき、連隊長は金剛山陣地への撤収を命じたのであった。
このようにわが部隊の兵力の損耗は甚大であったのであるが、敵攻撃部隊の状況より推定するとき、敵もまた多大なる兵力を損耗したと思われた。歩兵一コ中隊百二、三十名の編成が三、四十名程度に減っていたという。連隊本部は金剛山に陣地配備していた。当初、その陣地近辺は密林鬱蒼として、太陽を見ることもできない状態であった。にもかわらず、両第一線の急迫を告げるにおよび、金剛山付近に敵の砲爆撃が集中され、しだいに焼け落ち、 つぎつぎと焼土化していったのである。連隊本部は、金剛山河谷の山腹各所に洞窟陣地を構築していたのであるが、昼間はつねに敵観測機が不気味な爆音をたてながら、上空の空を飛翔していた。そのたの、洞窟外に一歩の行動も許されなかったのである。とくに、この狭い河谷内に各隊の命令受領者、第一線の連絡兵等が、砲撃の間断を利用し、決死の連絡に任していたのであった。
戦場がしだいに急迫するにおよんで、連隊本部付近にはそれぞれ任務を帯びて右往左往する将兵が多くなった。加えて第一線より負傷、後退した者等で、雑然としていた。そんなところへ敵迫撃砲の乱射はますます激しさを加え、一瞬にして阿鼻叫喚の巷と化していった。とくに配属高千穂部隊の行動は、悲壮極まりなかった。
第一線で負傷しても、戦友に看護を受ければ、それだけ部隊の戦闘力を減殺することになると思い、後退することかできないと思う者は、携行する手榴弾で従容として自爆していった。こうした戦死、戦傷者は、日々その数を増していった。しかし、これらの戦友の屍を埋葬することもできない状況にて、屍は腐敗し、臭気鼻をつき、何隊の誰すらわからないままに、つぎつぎと白骨となっていった。建武台陣地は敵の包囲を受け、孤立の状態となったため、連隊長は中第一線中條大隊と相前後して戦場を整理し、金剛山周辺の配備につくべき命令したのであった。かくして敵は五号道路を逐次浸透、金剛山周辺に 肉迫するとともに、榛名、赤城山方向に攻撃の矛を転じたのであった。
五月八日にいたり、いよいよ金剛山陣地は全面的包囲を受け、戦力はおびただしく消耗した。林連隊長以下一兵に至るまで、最後の覚悟のもとに洞窟陣地を放棄、蛸壺陣地についたのであった。
四天王および宝満山陣地占領
十日十六時にいたり、連隊は師団戦闘司令所より左記要旨の親展電報を受け取った。
一、軍旗は速かに要山師団戦闘司令所付近に奉移すべし。
二、戦局により、地区隊遊兵となりたる場合は、要山付近に転進すべし。
敵は、しだいに肉薄し、一刻の遅延も許されない。連隊長は軍旗奉移を決し、同夜二十四時、旗手小川少尉がこれを捧持し、連隊本部付村上曹長、軍旗護衛兵五名を付し、夜陰を利用、敵の重囲下を突破、無事要山に奉移したのであった。迎えて十一日、師団戦闘司令所との有線、無線が杜絶し、いよいよ敵の包囲縮小を受けるに至った。「バレテ」峠を占領する敵は北進を開始、守備兵力八百(配属部隊を含む)は遊兵の感あるにいたった。
十二日夕刻にいたり、バレテ地区隊長林大佐は決するところあって、同日十七時、要山への転進命令を下達したのであった。かくして部隊は、道なき道を縫い、夜暗を利用、敵の包囲のもとを突破、十五日、ようやく大和川第三合流点付近に到着したのであった。指揮下の斬込部隊も、逐次集結を終わり、要山師団戦闘司令所に到着した。集結した部隊将兵は連隊長以下四百九十二名であった。
連隊は到着と同時に、 バレテ地区隊の編成を解かれ、指揮下部隊を原所属に復帰させ、新たに四王山に陣地占領すべき命令を受領したのであった。よって十八日、連隊は四王山に到着、陣地配備と決定陣地構築をなし、次期作戦に備えたのであった。 北進した敵は師団最後の抵抗線、要山-天王山-榛名山-赤城山の線に迫った。師団は全力を挙げてこの敵を撃減しようとしたのであった。とはいえ、師団には他に攻撃兵力かなく、四王山に陣地占領していた連隊にたいし、師団主力となり、天王山を攻撃すべく命じたのであった。
よって連隊は、 ふたたび四王山より前進、大和川第三合流点付近に位置し、攻撃準備を整えたのであった。
五月二十一日、アリタオ河谷に位置していた師団砲兵隊と、攻撃に関する細部協定をなし、攻撃を敢行したのであった。連隊は転進後、戦闘部隊の兵力が少なく、かつ装備が不充分であったため、わずかに斬り込みによって人員殺傷百数十名の戦果を挙げたのみであった。敵は、天王山、榛名山の線を確保すると、一挙に五号道路に沿い北進を開始したのであった。かかる戦況にかんがみ師団は、新たに連隊にたいし宝満山に陣地を占領し、斬り込みにより敵を殺戮するとともに、五号道路以東より侵入する敵を拒止するよう命じたのであった。
よって連隊は、五月三十日に師団命令を受領、六月三日、宝満山に陣地を占領したのであった。敵に企図秘匿しての陣地構築、至厳なる警戒、炊煙に注意しながら、休むときもない戦闘であった。加うるに、糧秣の補給が少なく、 一日一合の米では、空腹のためにどうすることもできない状態であった。対する敵は、五号道路以東に陣地配備してある残存諸部隊を突破し、宝満山西側平地、ポネー付近にゆうゆう飛行場を設定するとともに、補給のための自動貨車が行列をなして北進をつづけていた。 これをはるか山岳地帯にて観測する連隊将兵にとっては、わが方はまさに敗残兵の感があった。
糧秣は金剛山より転進いらいわずか一日一合宛、後方より連隊行李班が収集確保していたのであるが、敵が一挙に北進したため、補給路を断たれてしまった。 いまは一粒の米の補給すら受ける方法もなく、食するに野草もない状態が到来したのであった。餓死の一歩手前に到着したわけで、総力を挙げて糧秣の収集に努めなければならない状態に立ち至ったのである。
戦闘を回顧して、敗戦の主因は何かと私見を述べると―
一、建制の編組を解き、各個に兵力を使用したため、戦力の重点発揮ができ得なかった
こと。すなわち、バレテ峠死守は、鉄兵団の主任務であるにもかかわらす、歩兵第三十九連隊(砲兵一大隊属)をバターン防備に転用され、アパリに上陸した第十連隊 (砲兵一大隊属)は駿兵団に配属され、わが歩兵第六十三連隊のみを基幹としなければならない状況であった。
しかるにわが連隊は、第二中隊を口ザレスにおいて撃兵団に配属、第六中隊を兵団右翼隊である鈴木支隊(捜索第十連隊) に配属、第十、第十一中隊をサラクサク峠扼守の撃兵団に配属、第五中隊を師団前進陣地のプンカン守備隊に配属、第一中隊をプンカン後方、デグデグ遊撃隊として使用、さらに第九中隊を連隊前進陣地に配備する等、主陣地決戦時における中隊は、わすかに二コ中隊にすぎない状態であった。
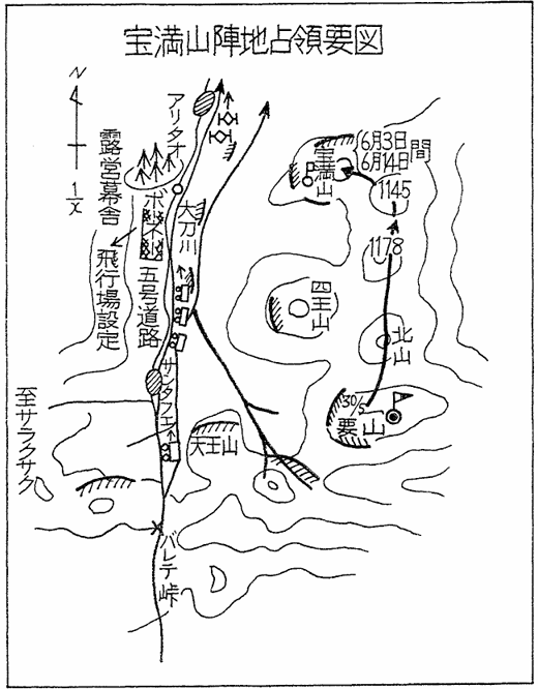
決戦を企図する方面にたいし適時必勝を期すべき兵力を集中して、諸兵種の統合戦闘力を遺憾なく発揮させるべきことは、典令に明示されていることである。にもかかわらす、状況の変化に応ずることなく、累述のごとき配備をして、主陣地における防備の手薄を感じた師団は、後方部隊である鉄道連隊、軍教育隊、海没部隊の残存兵力等を急援させたのであるが、これらの部豚はいずれも戦力はゼロにひとしかった。
「建制のわが一兵は混成の兵百に優る」とは、連隊砲中隊長山本中尉がしみじみと洩らした言葉であるが、わが建制部隊たる第三、第七中隊が全減するや、パレテ峠は急を告げたのである。このようにして連隊は建制の編組を解かれ、各個に使用されたのは、まことに遺憾の極みであった。
ニ、主陣地の陣地配備を誤断したこと。
陣地占領にあたり火砲の射向、陣地配備等、すべて本道に指向し、本道両側は密林であるのを奇貨として、両翼の防備に一顧をもしなかった点であった。しかるに敵は攻撃にあたり、両翼より攻撃して来たため、急遽、手当をしたのであるが、すでに後の祭りにして、逐次、蚕食されてしまったのである。
当初、陣地占領にあたっては、ことごとく師団参謀長の指示によったのであるが、このような陣地占領をするにいたったことは、残念であった。
以上、バレテ峠戦の二大原因を挙げてみたが、 いま一度視界を広くすれば、国力の差によるものであった。航空勢力において、はたまた火砲において、敵に比肩すべきものは全くなかったのである。敵機の跳梁下、洞窟陣地のなかより敵機の耳をつんざく爆撃音を耳にして、友軍機の飛来を一途の願いとしたのは、全将兵共通のものであった。
死の転進への旅立ち
戦況の推移により連隊は、新たに転進命令を受領したのであるが、携行糧秣がないため、出発を延期した。しかし、師団からの糧秣の補給も途絶しているとあって、 いまは補給の見込みもなく、六月十四日、 ついに宝満山を出発、いよいよ二カ月間の死の転進の旅に出発したのであった。連隊はルソン島上陸いらい七カ月、皇国の必勝を誓いつつ、バレテを最後の地として散華することを覚悟し、その大半は護国の神となってしまった。最後の必勝を確信したとはいえ、残存将兵にとっては、この転進は、敵撃滅のためではなく、生きるためのものであり、それが、すなわち戦闘であった。
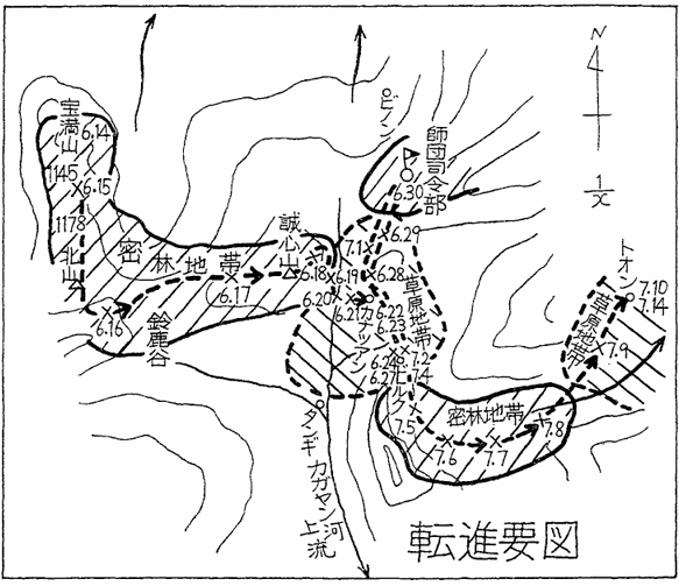
しかしながら、このような悲惨な転進間といえども、連隊に果せられた任務には、 いささかも変わりはなかった。対敵を考慮し、わすかとなった小銃、手榴弾は温存携行した。生命につぐ大切な携行品であったのである。途中、 一一四五高地において、連隊行李班が命がけで糧秣を収集したが、 これを五日分として各人籾一升、食塩少量の補給を行なったのであった。しかし、 このあとふたたび何日後に補給できるかについては、何の術策もなかった。 この密林内より一日も早く脱し、食糧にありつかねばならない状態であった。
この両手に一杯の籾に誰一人として不平をもらすことなく、黙々として行軍をつづけたのであった。 一日二合の籾は、そのまま煮て、三等分して食べたものである。とくに空腹のため、少ない量を少しでも多く食べたいという心理からでもあった。このため、胄腸を害して、血便を催す者が大部分であった。加うるに、 ルソンは雨期に入ったため、毎日雨に濡れながら、密林内の行軍ならびに露営をつづけた。食するにも野草すらなく、精神力だけが頼りとはいえ、空腹と疲労、それに加えてマラリアによる発熱などによって、つぎつぎと落伍者が出て行った。
しかし、それを助ける術もない。隊伍より離脱することは、すなわち死であるが、「いま一息だ。気をゆるめたら駄目だぞ」「頑張って追及してくるんだぞ」と別離のことばを残し、 一歩一歩と前進をつづけた、「喰うに食なく、病に薬なし」とはこのことをいうのであろう。 「空腹」と「マラリア」-すなわち餓死と病死。所詮は連隊の最後も、かくのごとく終焉することであろうと思うと、 「バレテ」の地に玉と砕けて散った戦友がうらやましいほどであった。思えば、 このぞくぞくと落伍した戦友は、部隊に追及することなく、名もなき密林内に白骨をさらしていることであろう。
このようにして行軍すること五日、不気味な敵観測機の爆音内よりは脱したが、部落らしきところを発見するに至らなかった。連隊は籾一升で五日分を予定したが、携行地図上にあるカナツアンの部落に到着することができなかった。しかし、部隊が一日休宿すれば、 一日早く餓死することになるので、疲労しきった将兵を励まし、 一歩でも多くと前進をつづけたのであった。 このようにして水を呑んで行軍すること二日、ようやく部落らしきものを発見した。八日目の夕方のことであった。
生か死か、 ようやく喰えるものにありついたのであった。将兵は、気違いのように甘藷芋やらカボチャ、パパイヤ等をむさばり喰ったのであった。
当時、師団との連絡は杜絶して、戦闘の推移はいっさい不明であった。連隊長は連隊の爾後の行動に関し、師団の指示を受けるため、 六月二十三日、連隊本部の木島中尉を長として五名の連絡班を派遣した。それとともに糧秣の確保、戦力の回復をはかるため、部隊をカナツアンより一日行程のビルクに集結したのであった。
ビルクはイゴロット族の部落で、糧秣が豊富であった。この地の原住民は連隊の到着直前、山中に逃避したものと思われ、逃げるときに取り残された豚、鶏等が散在し、甘藷、 カボチャ、 パパイヤ、 モンゴなども手に入った。また、一部少量ながら陸稲の籾などがあり、 かなりの糧秣を収集することができたのであった。
このイゴロット族は精悍な種族で、皇軍が大東亜戦の緒戦にルソン島を占領したさい、この地において皇軍三百余名が全減させられたということで、部隊は警戒を要した。目撃者の話では、 いまなお日本軍の鉄帽、雑嚢、水筒などが谷間に散乱しているとのことであった。連隊長はビルク到着後、各大隊長をあつめ、繭後の行動に関し意見徴し、次のように決定されたのであった。
一、連隊は生きる事、即ち戦闘である為、糧秣の確保を先決要件とする事。
二、直後の戦闘より遠ざかりある現在、極力兵力の損耗をさけ、戦力の回復に勉める事。
三、師団へ派遣した木島連絡班の連絡の成否は、不確実なるを以って、戦力の回復を待って、速やかに「カガヤン」河谷を「ピナガヤン」平地に進出、糧秣を確保すると共に戦闘を準備する事。
なお、連隊将兵にたいしては、左のごとき注意を与え、転進のための行軍を準備したのであった。
注意事項
一、各隊長は将兵の士気を昂揚すると共に、部下の掌握を一層厳正ならしむべし。
二、原住民は弓、矢、火器を以って自衛手段を講じあるを以って、各個小部隊の行動は特に注意を要す。
三、各隊は所在の資材を活用し、創意工夫を以って靴の修理を実施し、行軍力の保持に留意するを要す。
四、各隊は燐寸の使用を制限し、之が確保に勉めるを要す。
五、塩の重要性に鑑み、之が節用に勉めるを要す。
六、糧秣確保の為に別命なく、各隊毎に部隊の前方に兵力を先行せしめ、又部隊の糧秣収集地に於て別命なき限り、各隊各個の糧秣収集を禁ず。
このようにして転進行軍を準備しつつあった六月二十六日、木島班が帰り、左のごとき師団の要旨命令を伝えたのであった。
要旨命令
一、師団は隷下指揮下部隊を速かに「ビノン、附近に集結、戦力を整えると共に北進する敵に対し、 一大反撃作戦を実施せんとす。
二、歩兵第六十三連隊は速かに師団戦闘司令所位置「ビノン」に集結すべし。
ピナバガン平地進出を企図していた連隊は、戦況の不利、兵力の消耗等を考慮したのであるが、命令いたし方なく翌二十七日、ビノンに向かい前進したのであった。日の行軍行程は八キロで、充分な休養をとっていない将兵にとっては、いばらの道であった。
一夜の休宿地といっても、まことに哀れなもので、行軍中、宿営地が決まれば、わずかばかりの薪をひろい、草をしき、頼りにならない形だけの天幕を覆って、名朝、昼と心ばかりの三食分の飯盒炊事をして、横に臥せる程度である。夜半に雨が降れば、全身ずぶぬれのまま一夜を明かさなければならない。わけてもマラリアによる熱発に苦しむ者、疲労の甚だしい者は、休宿地に到着しても、薪をひろうことも、炊事をして喰うこともできず、ただ疲労しきった体を休めるだけである。何ひとつする気力もないのだ。
かくして空腹のまま夜を明かし、翌日は一歩も歩行することができず、その地で終焉を迎えなければならなくなる状態であった。戦場の常とはいえ、このようにして斃れていった上司、戦友の、家郷にある肉親に思いをいたすとき、愁傷、哀惜の情切なるものがあった。
かくして三日間の行軍により、十数名の落伍者を出し、ようやくビノンに到着した。ここで爾後の行動に関し、後命を待った。
飢餓と戦いながらの難行軍
宝満山転進いらい、阿修羅のごとき砲爆撃のなかより離脱すること半月、まったく対敵考慮を要しなかったのであるが、ふたたび砲声いんいんと耳をつんざく戦場に来たのである。
敵はすでにバンバン、バヨンボン平野に進出していた。師団司令部では方面軍との連絡が杜絶し、戦局の推移はいっさい不明であり、戦略的価値皆無のごとき状態であった。師団司令部より帰られた連隊長の話では、師団司令部も糧秣皆無の状態であるという。師団長閣下も一日米七勺宛しかなく、参謀長以下は野草、甘藷等で生命をつないでいる有様とのことであった。
夕刻、師団より次のごとき要旨命令を受けたのである。
一、歩兵第六十三連隊はカガヤン河谷を経てピナバガン北側高地に陣地を占領し、師団の背後を援護すると共に、随時「サンチャク」平野に進出を準備すべし。
よって連隊は翌三十日、ビノンよりビルクに反転、約五日分の糧秣を確保し、地図上の部落トオンに向かい七月四日、ビルクを出発したのであった。起伏重畳たる山脈をぬって、滔々として流れるカガヤン河、山また山、谷また谷、加うるに携行した地図は正確を欠き、前進は意のごとくにならなかった。連隊は八月八日にピナバガン平地に進出したが、それまでの三十日間は、連隊将兵にとっては、筆舌に現わし得ない血と涙の転進であった。
連隊は疲労による将兵の消耗と連隊に課せられた任務とを考慮して、ます地図上に示されている部落を目標に行軍計画を立案した。その上で、その日程に要する糧秣確保と併せて、休養をとりつつ前進することに決したのであった。なにぶん、不正確なる携行地図、加うるに人跡未踏、千古斧を入れざる大密林のなかを、磁石等により方位の判定をなしつつ前進するとあって、一日の行程も数キロにすぎないこともあった。この死の転進ともいうべき転進行の、第一目標トオンまでの行軍は、地図上で五日問の日程で充分到着できるという判断をして出発したのであった。しかるに五日目の夕刻に至るも、目的地のトオンは発見できなかった。
しかし、部落まではぜひ前進しなければ部隊の自減をまねくと思い、 一歩でも多くの前進を期して行軍をつづけたのであった。喰うに食する何物もなく、衰弱しきった将兵は、誰もが暗然として重い足を運んでいた。落伍すれば死を約束されたようなものとあって、将校、兵の区別なく、お互いに相助け、相励まし合い「もう部落はそこだぞ」
との言葉を相言葉のようにして歩を進めた。かくして六日目の夕方、すなわち七月十日、トオンに到着したのであった。
死神につかれたような連隊将兵には、昔日の面影はなく、目は窪み、頬は落ち、骨は張り、軍服はその影とてなかった。すでに靴より足が現われ、否、靴すらなく、素足のままの者もあった。人間か魔物か、その判別さえつかぬがごとき様は、全くたとえようもなかった。しいてたとえれば、地獄の餓鬼仏の再来のようであった。かかる悲惨な行軍により、しだいに連隊の将兵は減っていった。苦しい行軍をかさねたあげく、部落に到着しても、充分なる休養もできない状態であった。なぜなら、当時、兵団配属の残存部隊の一部、および兵団の一部部隊は、三々伍々、ピナバガン平地進出を企図して部隊を追い越し、前進をつづけていたため、トオン部落の糧秣はこれらの他部隊に先手をとられ、充分に収集できなかったためである。しかも早く前進をしなければ、次の部落もまた、これら他部隊のために荒される惧れがあり、部隊は餓死するばかりである。したがって、わずか四日間の休養にて、 ふたたび次の部落へと前進をつづけなければならなかった。
この休養の四日間に、われわれは次の部落までの携行糧秣をつくらなければならなかった。
休養とは、 いわば次の行軍への懸命な食糧準備のことであった。生芋を掘っては干して、乾燥芋として携行するが、 これも最大限四日分を持てばいっぱいであった。
かかる灼熱下の苦難の行軍に、一握りの食塩すらなき現状にかんがみ、連隊長は部隊のために食塩の収集を企図した。各隊より強健なる者十余名を選び、収集班を編成し、木島中尉を長として、七月十二日、 ルソン島東海岸へ派遣したのであった(この食塩収集班は、現在まで杳としてその消自は不明である)。
越えて七月十匹日、連隊は次の目標地のプコまで前進をつづけたのであった。「バレテ」金剛山より死の転進をした四百九十二名の連隊将兵も、戦闘に、あるいは苦難かつ悲惨その極に達した難行軍により、いまや二百余名を数えるばかりとなっていた。これら生き永らえた将兵は、灼熱のカガヤン河谷を無言のうちに前進をつづけて行ったのである。
このカガヤン河は下るにつれ、河幅も五十メートル余の大河となった。滔々と流れると思えば、激流の渦巻く急流あり、また、両岸は丈余におよぶ奇岩、巨岩が併立し、まことに天下の奇景を成していた。しかし、それがわれわれの前進をはばみ、幾度となく岩をよじ登り、河を渡ることを余儀なくされた。その苦難に堪えつつ次の部落のプコへと前進をつづけたのであった。
この河谷ぞいには、われわれの部隊を追い越し、前進をしていった他部隊の落伍者が冷たきな亡骸となって点々と倒れていた。これらの亡骸は南方特有の暑さにより、三日ぐらいで臭気が鼻をつき、一週問もたてば白骨と化している状態であった。連隊がのこしてきた二百余名の人たちも、すでに白骨化して、名もなきカガヤンの地に、風雨にさらされているのであろうか。それを思うと、そぞろわが身の将来を思うのであった。
とくに部隊で印象に残ったのは、連隊本部の松本兵長であった。
満州において動員下令されるや、選抜されて軍旗護衛兵となり、いらい衆の模範として率先、事に当たった。転進間においては行軍に、宿営に、元気いっぱい奮闘精励している姿は、頼もしい限りであった。
しかし、体力には限りがあった。この元気な彼もしだいに弱り、痩せ衰えつつあった。責任観念旺盛な彼は、軍旗護衛兵としての責務を痛感、しだいに弱りつつあるのを意識しながら、気力にて行軍をつづけた。あるときは、彼が落伍しようとしたさい、旗手小川少尉は軍旗を捧持しながら彼の背嚢を背負って行軍したこともあった。また、トオン部落到着前、バッタリ倒れた彼を、「部落は近いぞ、いま一息だ」と同僚の旗護兵が引きずるようにして部落に到着したこともあった。
かくして目は窪み、頬は落ち、骨は張り、衰弱甚だしかったが、なおも自分の心を励ましつつ行軍をつづけており、その悲壮なる姿は、部隊一同、涙なくしては見られなかったほどである。しかし、その彼にも、 ついに最後の時が来たのである。七月十六日、部隊が休宿地を七時に出発して間もなく、彼は疲労、衰弱その極に達し、 ついに視力を失い、一寸先も見えない盲者となってしまった。
旗手小川少尉の前を前進していた彼は倒れたまま、手を前へやりながら、
「松本は目が見えなくなりました」
といってパックリ伏してしまった。
「松本、気をしつかり持て」
と駆けよった小川少尉の目には、 いっぱいの涙が宿っていた。
それもそのはず、在満いらい一年間、苦楽をともにした最愛の部下と別離する心情を察せば、胸に 迫るものがあった。糧秣を得るまでは一刻も早く前進しなければならない部隊は、彼を残し、前進したのであった。
別離にあたり、松本兵長は幹部に、戦友に、入隊いらい数々のお世話になったことを感謝し、ともに行軍できないことを嘆いた。さらに、部隊が一刻も早くビナバガン平地に進出することを念願するとの言葉とともに、悲憤の涙を見えざる眼にいっぱいためて、離別を惜しんだのであった。このはかない彼の死は、二日遅れて部隊に到着した吉村主計中尉によって伝えられた。
連隊長と分離先行
この河谷ぞいに行軍すること四日、またもや部隊は糧秣欠乏と、目指すプコ部落を発見できないという一大障害に当面したのであった。このため、強健な者を選抜して斥候を派遣し、部落捜索をするとともに、河辺のタニシや赤蟹等をとって食糧とした。さらには携行している手榴弾を河へ投擲して魚をとるなど、あらゆる努力をしながら、生命の延長をはかったのであった。
このようにして、トオン部落出発いらい七日目にしてプコ部落を発見した。数多くの落伍した戦友をつぎつぎと残置しながら、七月二十日、プコ部落に到着したのであった。
再度、食糧にありついた部隊は休養、すなわち次の食糧準備に懸命の努力をつづけたのであった。この「ブコ」部落はわれわれにとって、比島上陸いらい、もっとも食糧に恵まれた場所であった。連隊は、六日間の休養と食糧準備後に出発を準備したのであるが、悪難路の行軍とルソン特有の灼熱のため、ついに連隊長林大佐が病気に倒れ、出発が困難となった。しかし、任務にもとづく連隊は、連隊長以下一部の人員(連隊本部伊藤准尉以下八名、また、護衛兵として第三機関銃中隊花川軍曹以下八名)を残置し、さらに行軍をつづけることになった。すなわち、第一大隊長中條少佐が連隊の指揮をとり、軍旗とともにピナバガン平地を目標に、四日間の行軍計画により、七月二十六日に出発したのである。
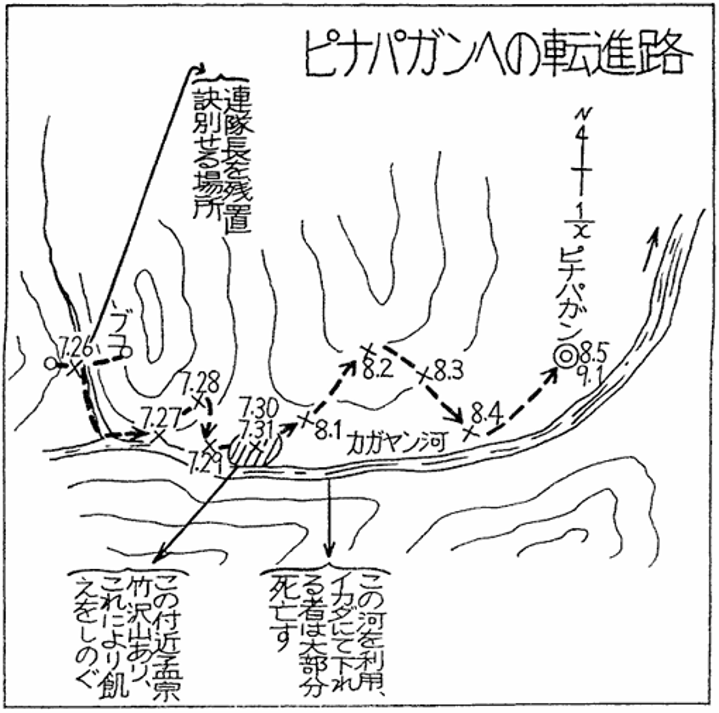
この朝、カガャン河の巨岩をぬって整列した連隊将兵は百四十名。 一段高い巨岩の上に、満州出発いらいはじめて覆いをとった軍旗を捧持する小川少尉の姿は、山渓に燦然として見えた。部隊指揮官中條少佐の「捧げ銃」の号令が山渓にこだまし、身の引きしまる思いであった。いまは出発もおぼつかなくなった白髪の連隊長が、挙手の礼をされて軍旗に訣別されたが、その姿は、病のためとはいいながら、その心情を察すれば、万感胸に迫るものがあった。慈父のごとき連隊長と訣別する将兵は、 一抹の寂しさを覚えたが、その背には一粒の米もなく、最大限、生芋、カボチャ等を辛うじて匹日分携行するにすぎなかった。
転進いらい糧秣の欠乏により、餓死の一歩手前に当面することを幾度となく迎えたが、いよいよ最後を覚悟しての前進であった。かくして、連隊将兵百二十名数名は、相励ましつつ歩一歩前進を開始したが、その姿はまことに哀れなものであった。このようなとき、全将兵を無言のうちに叱咤、激励してくれるものは、旗手小川少尉の捧持する軍旗であった。つねに部隊の最先頭を、颯爽と前進する姿は、後続する将兵にとっての心の杖であった。
かくして地と涙の行軍をつづけたが、予定の四日夕刻にいたっても、部落を発見することができなかった。数組の斥候を派遣して捜索させたが、受ける報告はどれも部隊を落胆させるだけであった。加うるに携行した糧秣はすべて喰いつくし、暗然として休宿したのであった。連隊指揮官中條少佐は将校を進め、餓死寸前にある連隊繭後の行動に関し、協議をしたのであった。論議は二つに分かれたのである。すなわち、
一、連隊長を残置したブコ部落に引き返し、充分なる糧秣を準備し、ふたたび前進すれば、四日間の空腹のみにてすむ。一番確実な方法であり、現在の作戦任務にも支障なしと思う。
二、連隊長を残置したプコに充分なる糧秣が収集でき得るや否やは疑問であって、 餓死は覚悟のうえ、 一歩でも多く前進し、 ピナパガン平地に進出、 任務に邁進すべきである。
この二つの意見のうち、大部分は後者を希望した。死しても引き返さざる決意を示し、部隊は明日より食すべき何物もなかったが、前進することに決し、 野宿の夢路をたどったのであった。
越えて七月三十一日、 冒険的な前進をつづけることとなった。
連隊長への「連隊決死の前進」第一報は、連隊本部の木原軍曹により報告したのであった。しかし、 元気溌剌たる木原軍曹も、これが最後となってしまった。その後、 連隊長が連隊に追及したあとの話では、 連隊四日間の行軍行程を、 その日のうちに到着した木原軍曹は、全身濡れねずみのごとく額の汗を拭きながら、 直立不動、挙手の敬礼をし、報告書を渡した後、 バッタリ倒れてしまった。まことに劇的な場面であったとのことである。
ビナパガンへ集結す
さて、精神力は偉大なる成果を発揮した。全将兵、骨と皮になりながら、 ビナバガン平地進出を念願する気力は、八月四日、平地進出までの五日間、糧秣の欠乏を克服、劇的な死の転進を終わらせたのであった。すなわち糧秣皆無の五日間、空腹に耐えっつ、 川岸を通ればタニシ、赤蟹などを取っては昼食にし、 山吹のような草を採っては夕食に供した。あるときは空腹のまま、木の実、草の実、 川の藻草に至るまで、およそ喰えるものはすべて食い尽くした。かくして平地進出をなしとげたのであった。
この間、暑さと空腹、あるいはマラリアによる熱病、 猛毒をもった木の実を喰って死亡する者など数知れず、 ピナバガンに到着した連隊将兵は九十数名であった。
思えば、無念の涙を呑んで落伍、倒れし戦友に救助の手をさしのべることもできず、 これらの戦友は餓死し、白骨と化し去ったことであろう。
かくて九死に一生を得た連隊将兵九十数名は、玉蜀黍、水牛の肉などをはじめて満喫したのであった。そして元気を取りもどした部隊は翌五日、軍旗を先頭に目的地たるビナバガンに進出、糧秣の確保と戦力の回復につとめる等の対策を樹立、準備したのであった。とりわけ、糧秣確保は作戦任務達成の唯一の手段なので、まず四カ月分の糧秣を確保すべく次定し、将校を長とする収集班を編成、糧秣収第に着手したのであった。
同地区は水田、陸稲などは全然なく、原住民は玉蜀黍を常食としていたと思われる。したがって、玉蜀黍は豊富であったので、倉庫、畑地等の地等の玉蜀黍を主として、パパイヤ、バナナ、カテモ、カボチャ、生芋等を収集した。また、砂糖キビによる砂糖の製造なども行った。
越えて八月十日、あわただしきルソンの戦場に、連隊は第四十回軍旗拝受記念日を迎えたのであった。この日、天気晴朗にして集う将兵五十名 (収集班は参加せず)は、連隊指揮官第三大長宮崎少佐(八月八日、連隊に追及)の指揮により軍旗を奉拝したのであった。
思えば内地に、満州にと、あの往時の盛大なりし軍旗祭を回顧するとき、 一抹の寂しさは禁じ得なかった。
このころ、サンチャク平野にあった友軍も逐次南下し、ビナパガン周辺地区に集結したのであった。また、カンプに在った兵団司令部もピナバガンに転移し、岡本兵団長は周辺の部隊を統轄指揮して自活態勢を確立した。
しかしながら、この砲声の杜絶えたピナバガンにおいては、世界の大勢、否、 ルソンにおける戦況すら不明であった。将兵は局部作戦の不利はまぬがれざるも、 日本は必す攻勢をとり、必勝すべきを確信して、幾年でも頑張る决心をしていた。
かくしているうちに八月十六日、敵は観測機をもって左記要旨の降伏文勧告を散布したのであった。
「 皇軍兵士に告ぐ 世界の平和は再び来る 大日本帝国天皇陛下の命に依り連合国は講和するに至った。 最早や米軍の砲爆撃は中止されたのである。皇軍兵士は天皇陛下の命令に依り勇敢に克く戦ったけれども、今は一日も早く武器を捨て、家郷に待ちある肉親の許に帰る事を、我々は責任を以って御送りするであろう。
一日も早く将校の指揮に入り、白旗をかかげ米軍の許へ来る様お勧めします 」
以上のごとき降伏勧告文も、戦局を知らぬわれわれは、単なる敵のデマ宣伝と思っていたのである。
しかし、八月二十日にいたって、第十九師団第四野戦病院携行の無線機の傍受により、ソ連軍の満州占領、広島、長崎における原子爆弾の投下、日本がポツダム宣言を受諾し、ついで八月十五日に聖断が下され、停戦の大詔が渙発されたことなどを知ったのである。
これらは疑いなき事実と思われたが、それでも夢であってくれることを願って、なおも糧秣確保等、任務に邁進していたのである。元気を回復された連隊長も、二十日、部隊に追及され、連隊の指揮をとられたのである。
停戦、収容
兵団は、方面軍との間に連絡が杜絶していたが、現任務の続行により、自活体勢を強固にすべく、新たに連隊を北上せしめ、ウルトウガン地区における糧秣確保、収集に当たらせることとなった。よって九月一日、連隊はピナバガンを出発、ウルトウガンに集結、糧秣確保に当たったのであった。
越えて九月十日に至り米軍、ならびに尚武集団命令を伝達された。
「大命により戦闘を停止す」との尚武集団(第十四方百軍司今部)命令を見たとき、冷水三斗、闇のなかへ突っ込まれたようであった。皇国の必勝を期していたのに、無条件降伏しようとは! 悲憤の涙が頬を伝い、自失の状能であった。
かくて連隊は兵器の拠置、書類の焼却等をなすとともに、光輝ある軍旗もまた、 連隊長以下 涙を呑んで九月十二日、連隊長の手にて焼却したのであった。思えば思うほど残念でならなかった。
連隊はすべての処置を終わり、病弱者十数名を残し、九月十二日にウルトウガンを出発、十六日、 ヨネスにおいて、 米軍に収容されたのであった。
このビナバガン一カ月間の駐留間、 マラリアのために第一大隊長中條少佐以下二十数名が戦没された。停戦後の尊き犠牲者となったのであった。また、 米軍に収容途次、 サンホセにおいて、連隊長林葭一少将は (収容後に昭和二十年三月一日付進級を知る) 疲労衰弱その極に達し、 ついに病歿された。
さらに虜囚生活半年にして、 比島収容所において、 山下大将の戦犯処刑を聞かされた。すなわち、昭和二十一年二月二十三日、マニラ郊外ロスパ二ヨスにおいて、絞首台上に消えられたのであった。大将の戦犯処刑を聞かされた。すなわち、昭和二十一年二月二十三日、マニラ郊外ロスパ二ヨスにおいて、絞首台上に消えられたのであった。 以上
バレテの戦いー陣地造りから戦闘開始まで 第二大隊の状況
(島根県藤義郡伯太町字母里) 第二大隊本部曹長 角 田 唯 久

国運を図して戦い惨敗してから四十余年が経ち、敗兵であった我々は未だ生きている。そして祖国は其後復興して経済大国となり平和で満ち足りた生活となった。明暗両面を見て来た我々は祖国の将来のために、また死して還らなかった戦友と遺族のために。何かを語り書き残すべき義務感を覚える。そして残された時間もいくらもない。
日米両軍が最後の天王山と呼び、主力激突のルソン島に於いて、東洋のベルダン戦とも言った、ハレテ峠の攻防戦については語り盡せないが。先ず峠一帯に守備布陣が第十師団で其の中央を越えて行く唯一本の国道である峠道五号道の両側に真正面から陣地を据えて死守でストップをかけたのが、我が六十三連隊で我々は知らなかったが到底勝目のない、生きて還れぬ戦いで有った。昭和二十年一月初旬ころ。全般の戦況はレイテ島は既に勝負がついて、ルソン島ではリンガエル湾に米軍機動部隊が続々上陸中で上陸軍の先峰部隊は中部ルソン平野に展開し、盟旭と交戦中、更に先頭では戦車の撃兵団とも砲撃戦が始まっていた。
パレテに到着した我々の立場は、勝目はないが方面軍の敵を本土に近づけない、 持久作戦の一環として編成された。 尚武振武の二大集団の内で方面軍の直属であり北部持久の入口となり最重要地点でポイントのバレテ峠で有ることなどは何も知らず。 やれやれ目的地到着かと、安心と疲れからぐっすり寝た。明くれば一月十日ごろか、道辺でかぶって寝た天幕から顔を出すと天幕は夜露に濡れて重く、朝は白く霧に包まれていた。 谷間は毎日朝霧となるらしい。 朝は陽も当らず寒かったと思う。 やがて命令受領とか連絡兵など往来して、 陣地で有る山に登ることになった。 其の前に道路から百米位いの崖を降り、其の下は谷川となる清洌な深い水が流れて橋もなく、 一部の兵で先ず架橋が始められた。 川から先は水辺から群生する丈高い草や木を切り開き乍ら進んだが、 建武台上までは一日位いはかかったと思う。 まして高地で有る第七中隊の 「カシ」陣地などは、 最初の開拓登山迄には数日を要したのでは有るまいかと思う。
陣地
さて初めは各中隊共に自分等の所しか解らず周囲は皆目森林の内でどの山に友軍の陣地が在るのか心細い限りだが、日か経つにつれてだんだん知れて来た。 建武台から説明すると後方「ハルナ」山と呼ぶ峠の頂上附近に野砲陣地。右側台上はフナ陣地の野中機関銃中隊で左側は谷川となり野病か設けられ、馬匹なども其の附近に居たらしい。前方は一段低く台上か南に流れて「ヤナギ陣地」 で頂上に江原大隊砲小隊で一段降って中腹に連隊砲山本中隊か在り、南に流れる低い台地には戦車を迎え射つ坂田速射砲中隊が陣取り。最前線で一番高く前方も遠望出来る 「カシ陣地」 が歩兵第一線となる米田第七中隊で有った。どの中隊も総べて険しい登りで、先ず道路工事から初まったが、道と言っても斜面ばかりで段々とか足掛りを造り急勾配は迂廻路とした。そして、道らしくなると、次は膨大な荷物の運搬で踏みかためられ次第に道らしくなって行った。
道路から陣地までの弾薬食糧を初めとする諸物資の連搬は、到着初日から戦闘開始後もつづき総ては兵隊の背負いで有り、降る時は単身乍ら帰りは必ず肩に喰込む。『行きは良いよい帰りは恐い』山村育ちの兵隊は「かずらのつる』や木の枝で自分専用の背負子などを作り重い物でも強かったが、町家育ちの兵隊は肩が鍛えてなく、他より軽くても難業苦役であるし、五号道の下で物資置場の川辺には関所が有り関所代官の下土官が居て陣地に帰る兵隊には何かを背負せて空身で通すことはなかった。
小屋造り
最初山上陣地に登った時、陣地場所だと言われても大木の中で薄暗くて何も見えないから伐採作業から始めたが山蛭に血を吸われたのも此のころで足基では体長二糎位いの大蟻が無数に生息しからだに喰いついた。此の場所で我々は先ず雨露をしのぎ陣地を造り期限のない生活を初めねばならぬ。ため息も出たが、先ず、小屋造りから取りかかる。伐採した太い生木を柱とし枝を垂木として葉や草で屋根を葺いた。本職の大工が居て割と順調に仕事は出来て床には横木を組み座張り迄で出来たが、上は歩くといつも「だわだわ」と揺れていた。
また、踏場によって足が「スポリ」と落ちることも有る。或る日初めて雨となり天井から大変な雨漏となり慌てて屋根に天幕をかけた。小屋と言うより「セプリ」と言うべき代物だが、 我が建武台では先ず隊長室、将校室と事務室兼用で下士官室、次に兵室も三棟位いで別に物資置場に便所など台上に造り、別に少し降りて谷間には行李班の兵隊が三棟位いと炊事場も屋根が出来た。十数棟が建ち並ぶと結果として、台上の樹木が斬られて風通しも良くなり遙かに遠方も見えて来た。となりの陣地や往来する兵隊の姿、五号道路を行く車輛などでなんとなく人間臭くなり、 これなら生きて行けると思う様になってきた。
壕堀り
さて小屋が出来ると次の急務は戦闘の陣地壕で、敵に面して反対側の死角となり樹林で上空より見えない場所を定めて早速に穴掘りが初まった。これが最も重要な作業であり、亦辛い仕事で有って、誰れも『のがれる』 ことは出来なかった。全員が交替制となり、休むことなく掘りつづけたが。一月下旬頃からは前線急迫の戦況で遂に二十四時間の夜間作業となって来た。 建武台での本陣地壕の場合は出来上りの格好をコの字形に設計し両側から掘り進み両側奥行十数米位いで、折れて奥で継ぐと言う具合で、常時十名程度が作業に当り夜間もやれば直ぐ交替が廻って来る。
皆文句も言わず空腹を抱えて一生懸命働いた。工具については軍用円ビ 「スコップ」と「十字鍬」「つるはしのこと」だけで、 農家出身の兵隊は「田甫用の鍬」 が有ればもっと能率が上るのにと話していた。 亦工法は 「つるはし」 で崩した土を木箱に入れて、箱に綱をつけて有り入口まで引張り出す。穴の入口は毎日の捨て泥で次第に広場が出来て来た。洞穴は一日中掘っても、とても一米とは進まず何十糎づつであつた。奥へ進むにつれて其の次は神社の島居の様な抗木を組み、 天井に横木を差込み落磐を防ぐ。眼には見えぬが日が経つにつれ、少しづつ穴は深くなって行った。考えて見ると測量器具もなくて兵隊各自の感と見当だけの作業だが後日両側からの穴が多少の段差は有れ合致した。
食糧と食事
さて喰物の話しとなる。バレテ着から陣地造りの作業まで暫く間は、 飯盒めしで、各自の飯盒炊事班が集めて炊き配分したが、 いつか釡が来て共同炊事の飯盒配給となって来た。 釡が有るのは大本部だけではなかったか。各中隊は最後まで飯盒で有ったかも知れない。我が本部の炊事班長は池田一行軍曹(大阪市戦後阪和工材) であり、なかなか権威を持っていた。人間いつの場合でも食を司る人は強いが、特に空腹を抱えて飢餓状況下重労働のつづく戦場では将校と謂えど池田氏には一目置いていた。兵隊は陣地に来て少しづつ体力を回復するにつれ腹が減って来た。そして作戦の為重労働が続く。其の頃の糧材は後方サンタフェ方面から送られたと思うが。最初は米が来ていた様で、 いつごろ変ったものか籾が来る様になって来た。当時の 本部主計曹長で現在大阪市の鈴木良次氏にきけば、米と籾との時期を知っておられるかも知れぬ。籾は搗かねば食えず鉄帽に入れて短剣の握りで搗いた。全員が搗いていた。
自分の食ふ籾ではなく割当作業であったかも。此の様な状況は我々だけでなく、バレテ各隊共に同じであったと思う。何か食う物を捜さばならぬ、食糧集収班が出来て附近の山々を歩いた。我々か此地へ来た時は人間の住める場所ではない。人跡のない未踏の奥地と思ったが、附近を歩く内に、山地民族のイゴロットが点々と住み、焼畑農業で甘藷とか僅かな陸稲など作り生活するのを発見して、先ず彼等の畑を荒した。住民は危険を知り逃げており、主として甘藷だが遇に唐辛子、生姜など副食物や運に恵まれると鶏一羽などの時も有り、 一度で有ったが野豚と称する子豚を持帰った組が居た。そんな時には功績甚大で肉は僅かでも汁の中に油が浮いて居り、最高の栄養源となる。食糧集めは先ず現地で自分等が腹いっぱい食える役徳が有り、志願者が特に多かった。
さて戦況について我々には、詳細は知らされず一月下旬となっていたが、噂話しでサンニコラスの足立隊が奮戦後全減らしいとか。三角山の前田隊が僅かとなり生存者だけ撤退して来た等をきいたが時期的に定かでない。バレテ本陣地では既に真近となった持久決戦に備え、其の勤務は壕掘りの工事班、物資の運搬班、食糧の集収班、ゲリラが出没するので警備班など不休であった。兵を使うのに大隊副官田辺正春中尉「鳥取県日野郡日南町戦死」は支那事変から歴戦の経験有り要を得ていた。決して兵を叱らず勤務割もすべて平等で文句なし、言葉も個人の場合は鳥取県の方言で、兵下士官の区別なし、にこにこと笑顔で戦況急迫につれて夜は女の馬鹿話しなどで皆を笑わせ、相手をするのは指揮班長の長谷川巧曹長「鳥取県鹿野町戦死」で共に支那事変を生き抜いた仲で度胸が据っていた。長谷川曹長は其後の戦闘で「カシ」が破れ「ヤナギ」が突破されて建武台に敵が迫り陣地隊は砲の直撃で天井から土砂が降る中でも唯一人泰然と筆を取っていた。其の精根の陣中日誌や戦闘詳報も曹長と共に何処かで消えた。陣中の或る日公用公李から二、三個の陶器製の茶碗が出た。台湾を出発時、都合で入れたもので、必要品でなく忘れていたが。「これは良いモノが有「た大隊長用にする」と田辺副官が一個を残し、隊長当番岡克己兵長(烏取県西伯町生存) に渡された。食糧不足でいつも空腹の兵隊には岡兵長がお膳替りの板ぎれに乗せて運第。茶碗には特別な山海珍味と写ったかも知れぬ。中味は兵食と全く同しで時折り岡兵長個人の努力に依り雑草の「ひたし」位いがついていた。
一方食糧収集についても各隊がそれぞれに毎日大勢で出掛けるので、だんだん少なくなり、近い処は荒らされてから遠くマレコ山やイムガンの方迄も泊りで行く様になっていた。
二月末か三月となったが、サンホセからプンカンでの戦闘を聴く頃に同地戦勢挽回のため連隊総力での斬込が企図され全員参加したが、山本照孝氏「バレテの思い出」に詳記されて居り省略する。但し此の時期には遠雷の如き砲声と共にバレテ地内に砲弾が炸烈し、特に道路は要所に一日中射込んで反転帰途に米田
入江秀吉伍長「鳥取県赤碕町」戦死其他数名の負傷者も出た。いよよ本陣地戦闘が近づいた。あれ程バレテを越えて北部へ行く人馬車輛と兵隊達、逃げ遅れて子供を連れた婦人、パレテ銀座の人影がびたりと絶えた。道辺には、梱包衣類生活用具など雑多な品々が捨てられて新戦場近しの感深し。観測隊は夜明けと共に飛来して日没まで、其の間に双胴の初めて見るロッキードが来て所かまわず銃撃した。いよいよ洞穴壕を急がねばならず壕堀りに報賞制度が出来た。松田某と呼ぶ元炭抗夫がいて、他人の倍を掘る。 さすがに専門で道具の使い方がよくて能率を上げ、報賞として飯盒半分位いの飯が出た。それが例となり誰れの場合も予定以上掘れば少々の食事加給の制度とった。今から思えばささやかな子供の「おやつ」 にも足らぬ僅かな報賞に頑張る兵隊は哀れで有り笑えぬ悲劇であった。
大隊長接敵
さて話しは前後するがプンカン出撃以前のこと陣地防禦に備えてか、根本大隊長は時々兵を連れ建武台周辺の山々を地形兵要調査のため出掛けたが。或る日マレコ方面で山中に於て突然有力な米比ゲリラと遭遇した其の時は亦運悪く味方は四名であり一名戦死で大隊長自からも負傷して包帯を巻いてようやく帰って来た。此の状況につき直接根本氏の言を借りる。
「歩兵六十三連隊誌九六四頁二十一行から簡単に記述の通り大隊の守備陣地西方高地の偵察が必要と感じ。よもや接敵するとは予想しなかったので指揮班の三名を連れ、軍刀を小銃に換え、一月下旬かと思いますが出掛けました。河崎伍長(鳥取県浦安死亡)と板上等兵ともう一人の上等兵ですが、此の上等兵の氏名が私も河崎氏も板氏も思い出せないままになっています。秋風山の中腹に近い三叉路で西側から来た小部隊の米比軍と鉢合せしてすぐ小銃で撃合とある。南から小生と上等兵及び河崎と板君。暫くして右隣りの上等兵が頭部破弾して、まもなく次は小生が頭部に衝撃を受け、 「ガクツ」 となって後は覚えなし。敵の位置は低くてこちらは高かった。河崎君に呼ばれて気が付く。
「敵が下がりました、火砲を射って来ると思われます。早く退りましよう。との献言でした。上等兵が戦死したので、近くに運び土を掘って埋め土をかぶせる。終って駆け足で来た方向へ戻ること約五十米位いの処で。今戦闘した場所に西方面から砲撃を見る。ゆっくりして居れば全減の所であった。大隊砲程度の火力を持つ一個小隊位いの兵力ではなかろうか。これを報告したので、後日西の山を越えての討伐を命ぜられ。指揮班と米田中隊の田中小隊長及び配属になっていた片岡隊「第三大隊第十中隊」の第一小隊で「当時の小隊員坂田武男「八頭郡智頭町生存」氏などよく覚えていますが。其等の兵力で一月下旬より二月上旬にかけて討代行になり。又三月初めには此の山つづきのマレコ山への片岡隊の配備になったものと思われます。」
右の如く語られて、西側では最高指揮官が小兵力で先に接敵し危うく指揮者を失うところであった。さて陣中の日常は台湾以後内地からの便りは絶え。兵隊は持って来た妻子家族写真など時々出して見る程度。衣服は着た侭の一着で靴が破れても換えがなく、少々の下着など川辺に降りた時洗濯した。洗濯物が敵機にねらわれ銃撃を受け乾すことも出来なくなった。ドラム罐が谷間に据えられ風呂があったと思うが。湯に入った覚えがない。運搬のため谷川に降りた時、水浴は気持よく、この頃で最高のたのしみであった。二月初旬、どこから米るのか長距離砲弾が落ちるようになって食事は一段と低下した。お粥に似た雑炊めしで副食もなかった。これ等は輸送に原因が有り、輸送隊の生存者山根作次氏「鳥取県西伯郡日吉津村」の言に依る。
「最初は昼間往来したが観測機が毎日飛び砲撃と爆撃が激しく。被害が多く夜聞輸送となった。而し砲撃は夜間もつづき、 いつか大隊の行李は車輛三台と馬三頭となった。これでは大隊人員の食糧だけでも不足するが、弾薬や資材も有る。車輛以外の人員は背負いとなって来た。」と話されて、それ等の輸送も道路まで、その先は手が足らず各陣地から取りに出て、砲爆の合間に運ぶ有様で、陣地 は届かなかった。R本部鈴木主計曹長から戦後になってから問われた事がある。暫く間第二大隊に食糧輸送が出来な「時期」が有り。其の間は、お前達は何を食っていたか ? と其時は池田炊事軍曹の裁量で、日毎の乏しい食糧を更に節約食いのばしていたので、どうやらつなぐことが出来た。
さて作戦を批判する気は毛頭ないが。連隊総力でのプンカン出撃は無駄であり、又取止めて良かったと思う。当時の時期と戦況を思えば実施であれば兵力消耗し、バレテは早々に突破されたと思う。そうでなくても敵に対し寡少の兵力である。二月中句もすぎた頃、陣地には敵砲が届く状况となって来て、或る日全員洞窟に移る。今迄は別々の小屋で寝起きも別と自由であったがとたんに窮屈となった。
事務処理、医務の各部負傷者迄で一緒だから出入には相当他人を踏まねば通れなかった。それでも行李班だけは初めから別穴を造り幸いで有り、但し炊事は煙も出るので此時期になっても命がけで外で「めし」を炊いていた。隊長室は右奥角を横に掘り人口に天幕を垂らしたが、手足も充分伸ばせぬ程で、坂口軍医や砂田主計中尉が入りよく話して居り誰れも自分の場所を持てなかった。此頃砲撃は時々台上に落ちて小屋は自然破壊される。穴に直撃を受けた時は潰れる程の土が降ったが。戦闘の経過から思うとまだ序のロで、兵は志気旺盛であった。
その頃のこと余談となるが、或る日のこと任務でヤナギ陣地に行く。途中常時に砲撃を受ける谷間があり、ヤナギへの経路でカヤ原であり、隠場がなく必ず通る場所、土台だけの廃屋跡で暫く伏せて合間を待つ。ふと眼前に大根の葉に似た野菜らしきものを見付けた。現地人が残したものか早速引抜いて雑袋に入れ、合間に駆足で無事通る。江原隊は私の場合原隊で江原少尉も初年兵の頃に於て教え子全員が在満時の戦友と旧部下で我が家同然。到着すると早速隊長が出て来て『やあよく来たなあ。客が来て今「めし」炊いてをる。調度よいお前も喰って行け」と挨拶がわりに喰物の話しとなった。其節の私の任務は何で有ったか忘れたが、穴の奥には暗い所に連隊砲の山本中隊長が居た。声をかけると「陣地はお互い近くても仲々会えぬ、本部の方はどうか」など話して例の野菜らしきものを取り出すと、二人は大いに喜んだ。「これは良いモノを持って来た。此処に来てから初めてだ」などと江原隊長が「よし漬物を作る」と洗いもせずに葉をちぎり塩で揉み暫くすると葉パ漬に似た様なものが出来、飯盒めしも湯気が立ち、三人の食事となった。「酒がなくてさみしいな」など勝手な事を言い乍らすぐなくなったが。熱いめしに漬物は最高のもてなしで江原隊長も兵の手前一人て喰えぬ、お客接待の言訳で私迄お陰を受けた。よい戦場の一駒だが其の日が山本隊長 「米子市戦死」との最後の別れの日となった。
当時江原隊の壕はH字に掘り前面に掘抜いて射撃するつもりかまだ工事途中で 『もし敵か来たら外から射つなどと言っていた。豪放磊落の江原中尉も其後三機中隊長に転進しており三月末のカシ陣地攻撃時再会出来たかどうか定かに覚えない。やがて三月に入ると日毎戦況は変り砲撃に迫撃砲が加わり空からはロッキードの銃撃の外に爆撃が多くなり油人りのドラム罐などが落ち陣地焼土戦術に出てきた。いよいよ本陣地戦の初まりで。前哨の松岡中隊遊撃の林原隊など兵力僅少で全減近くなっており、自力で歩ける負傷者が少しは帰って来る。或る日負傷したプンカン三橋隊の連絡兵が辿りつく。誰れであったか覚えない。 報告は「戦闘は全く無茶苦茶で砲爆で穴から出られず兵は穴や「タコッポ」 で戦死する。
一方的な戦いで減多に敵影を見ず。こちらから射てない。敵が近づく前に戦死が多く、残り各隊との連絡が取れず、様子がわからない」 と話し、野病に退って行った。野病は既に建武台下の谷川辺から地獄谷に移っていた。誰れか付けたか『地獄谷』前線からの負傷者は、谷間でごろ寝して屋根もなし、ロクな治療も受けてなく食事もまちまちで余りのひどさに最後には陣地の方が良いと負傷のまま帰って来た兵もあり。名実共に地獄の様相ときいていた。
二機では中隊長野中中尉が「日野郡江府町」砲撃を受けて路上で戦死。連日の敵砲を圧えるため斬込隊が編成され長谷川斬込隊が 『ナチビダット』 迄でも行き戦果を挙げたのも此頃だが。実情は敵陣に出掛けても警備網で電線、鉄條網、警報器や逆に釘を打った踏板など設備して容易に近づけず犠牲多く戦果は少なかった。斬込は方面軍の方針で有ったか接敵以前から最後まで続き志願者も多かったのは、遇々運に恵まれた連中が持帰る敵の糧食にあった。米軍野戦食でレーションと言う箱入や罐詰には栄養価の高い食品から煙草、 コーヒーに到る迄詰めてあり。腹をすかした兵隊には命に替えても欲しかった。「正に腹いっぱい食えたなら死んでも良い」 とは言葉だけではなかった。「そして昔から孫子の兵法として「糧を敵に求む」」 の兵法はインパール作戦の例も有り現代戦には通用しなかった。
さて当時は月日と時間の覚えがなく総て戦後の割出しだが三月中旬頃かデグデグも突破されミヌリ台上に敵戦車が見えて来た。 雲煙遙か地上は砲煙に霞み反転上下する敵機もトンボの様で肉眼で良く見える。いよいよ来た。林原隊も全減の頃。大隊本部も全員が台上の「たこつば」 に配置、 戦闘配置臨戦態勢となる。 先ず多忙となったのは医務室で三宅軍医は「広島市」既に転出後で坂口寿丸軍医「長野県軽井沢戦死」唯一人を毎日増して来る負傷者に手が廻らず軍医同様の働きを前田嘉美衛生軍曹「鳥取県岩美町戦死」北山増徳衛生伍長「鳥取市吉岡温泉戦死」 がさばいた。又此の期の食事は多分「めし汁煮込」 のお粥の様で有ったと思うが記憶がない。やがてハルナ山の我が野砲が射出した。 力強い轟音で頭上を飛ぶ。次いでヤナギ陣地の連隊砲も射出した。本陣地戦の初まりであった。
其ころ陣地にはどれ程食糧弾薬が蓄積されたか知る由もないが、大隊砲は発射弾が制限されて一日五発と言っていた。小銃、機関銃皆同様で、無駄弾は射てず敵影と目標物のない限り威嚇射撃なし。対する敵砲弾は制限なく一日中で比較にならぬ。又兵員についても当初から編成中隊が欠々であり、混成雑多な兵力が次々補充されたが期待の戦力には遠かった。三月初めから中旬に掛けて暫くの間敵機の爆撃と砲撃戦が続いた。敵の戦法は砲爆で地上部隊を概ね殲減する。殆んど生存兵力を消耗させたと見た上で用心し乍ら歩兵が近づく。
此度の中東での湾岸戦争をテレビで見乍ら時代と科学特に兵器に於いて、格段の違いで比較すべくもないが、其の戦法に於いて何か似通った点を見た様に感ずる。往年のバレテ戦の時も来攻する敵部隊が先ず先頭は米比ゲリラの比島現地軍で黒人のニグロ部隊がつづき、赤い顔の豪州兵「オーストラリア」最後にアメリカ正規兵となった様に思う。
勿論混成で指揮官はアメリカの場合も有ったと思うが。別談乍ら此の頃の我が方の戦死者の扱いに付いては茶昆に付したか、埋葬出来たか良く覚えぬが地上接敵する迄は、何か処置した様で指か腕か一部を切取って焼き、遺体は陣地に埋めたかも知れぬ。其の小さな遺骨も仲のよい戦友が所持し其の本人が次に戦死するので結果としてバレテの遺骨は一体として故国に還らなかった。そして地上戦闘となってからは戦死者は山野に満ち散っており手を掛けることが出来得なかった。悲愁の限りであった。
さて三月中旬すぎ米田隊から報告が来た。「我が守備陣地キリに小数の敵が来た。日野小隊が戦闘の結果撃退」とのこと。其の時小戦闘と思ったのは間違いで後程から考えると敵の威力偵察であり、直後に始まるカシ攻防戦の初日であり西側本陣地戦の開始となった。
(以下カシ攻防戦は別稿)
◎兵隊は悲しきものぞ知らされず ただ眼前の敵を撃つのみ。
◎会者別れ生者死すとは釈迦の言ふ 諸行無常は戦場の日々。
以上
戦場寸描
元歩兵第六十三聯隊本部 (千葉県)
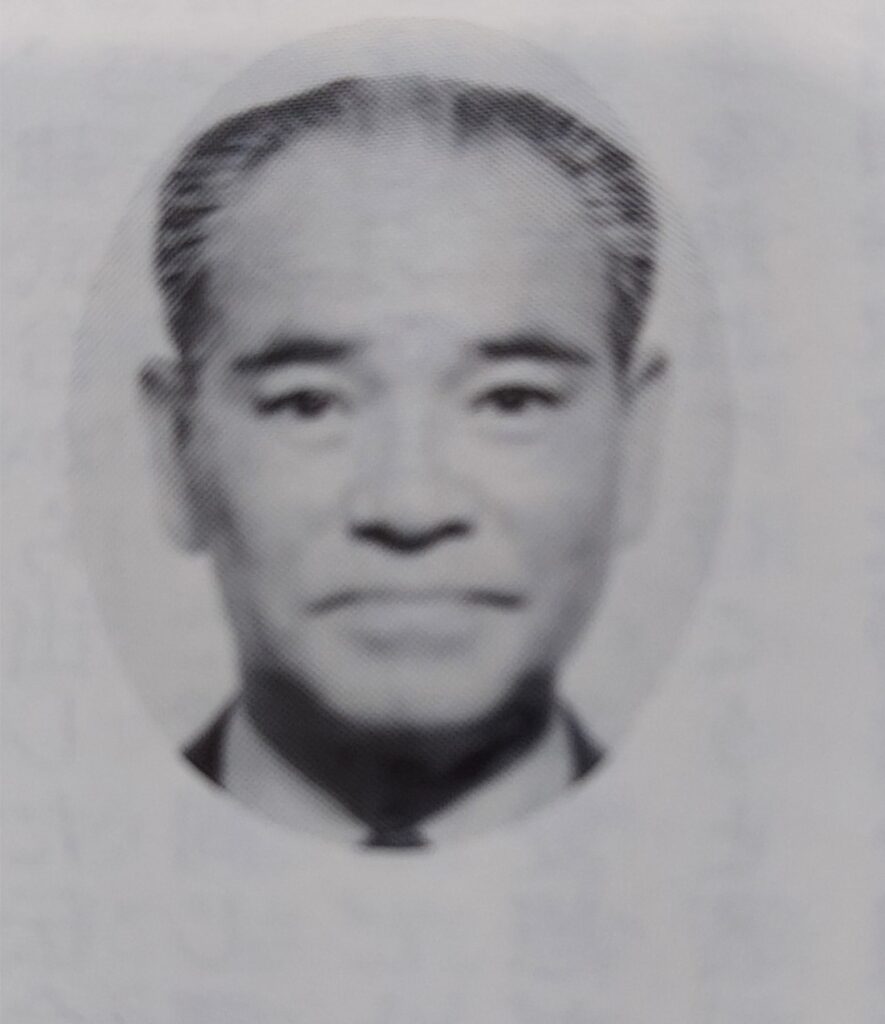
バレテ峠を中心とする聯隊の死闘、それに引き続くカガヤン可谷の転進、それは苦しい、そして苦い苦い思い出。戦友とは気軽く話し合える思い出も、余り生々し戦場の出来事は、戦友以外に話すことは気の重いものです。
然し、バレテの戦闘で、そして転進で多くの戦友を失い、生き残りの者もその数を減じている時、生存者が記憶の一端でも語り継ぐことは亡き戦友の供養であると信じ、拙文を省みず筆を進めることにしたい。
ある空挺隊員の最後
あれはたしか、二十年四月下旬の出来事であった。
バレテ峠正面に対する米軍の圧迫はいよいよ激しく、かつ、聯隊の左第一線大隊(中条大隊)の東側妙高山方面から有力な敵部隊が聯隊本部の左側背親山に進出した。親山を奪われんか、バレテ峠の保持に重大な影響を及ほす要点であり、聯隊として、直ちに奪回の処置を構ずべき地点であったが、既に聯隊にその余力なく、師団は直ちに徳永支隊に親山の敵の攻撃を命じた。
このような、状況の中で聯隊本部医務室の前で起きた一つの出来事は四十年経った今でも鮮明に瞳に焼きついている。第一回の徳永支隊の夜間攻撃は壮絶を極めたが、不成功に終り翌朝負傷者が医務室に運ばれ、三宅軍医以下の医務室関係者により応急処置が行なわれていた。「もう一度攻撃に参加したい。 このままでは死んでも死にきれない。部隊に帰らせて下さい」下顎を砕かれた若い兵長が叫んでいる。
「お前は立派に自分の仕事を成し遂げたのだ。今は先ず傷を治し、再び部隊に帰ることを考えるべきだ」三宅軍医が懇懇と諭している。
こんなやりとりをききながら医務室の前を離れて五、六十米、背後で手榴弾の激しい炸裂音を聞き急ぎ引き返した。そこには胸に手榴弾を抱き自らの命を絶った若い兵長の躰が横たわっていた。
戦場のどこにでも見られる痛ましい出来事であったが深い感銘を受けた。当然誰が考えても戦闘に加わる事か理な負傷をしているのに、尚も今度の第二回の夜間攻撃に参加しょうとする烈々たる闘魂、そして自分の負傷が重く戦友のお荷物になるをよしとせず、親山攻撃で戦死した友の後を追って自らの命を絶った徳永支隊の若い兵長の躯に合掌、改めてバレテ峠の死守を心に誓い、医務室の前を後にした。
敵の道路設定を一人で拒止
二十年三月中旬頃、第一戦の死闘が連日続いていた。左第一線板垣大隊の第三中隊(中隊長大浜中尉)は寡兵よく敵の攻撃を拒止していたが、中隊の損害も増大し陣地の保持も困難な状態に追いこまれつつあった。左第一線は右第一線に比べ樹木が多く、敵は砲爆撃によって虱潰しに陣地を潰した後、プルドーザーを投人し、道路を作って戦車を進出させ蛸つぼを一つ一つ壕減させる戦法をとってきた。
道路啓開のプルドーザーには警戒の歩兵が随伴し作業をするが、 この敵に対し残存する蛸つばに穏れた三中隊の隊員が、小銃の狙撃で警戒の歩兵を一人、 二人と殪した。敵は既に陣地に生存の日本兵はいないものと思っていたのに射撃を受け、損害が出たのに驚き急ぎプルトーザーともども後退してしまった。そしてその日は亦猛烈な砲撃が繰り返された。
翌日は、流石に敵も用心深く警戒の歩兵を先頭に陣地前面に進出したが、こちらと思えばむこうの蛸つぼから正確な狙撃によって数名の敵を殪した。 このように一日に亘って陣地に唯一人残った戦友によって道路の設定を拒止した。
この勇敢な兵の名前は四十数年の記憶が薄れ、丸山上等兵と云ったか、長谷川上等兵であったか定かでない。大浜中隊長が第一線から退かれ、聯隊本部に伝令とともに暫く過された折、中隊長から直接伺った第一線の状況である。思うに、第一線の勇戦敢闘の例は枚挙にいとまがない程と思うが、その多くを伝うべき戦友が相ついで殪れ、その大部分がバレテの山の中に埋もれたままになっており、残念至極に思われてならない。
米軍収容所入りを前に
二十年九月中旬、明日はいよいよ米軍の収客下に入るという日、吾々は約一ヶ月間駐留したピナバガンからウルトーガンに進出していた。米軍の収容下に入ったならばどの様な状態が待受けているのか、誰にも分からない。比島上陸以来、苦楽を共にした戦友とも離れ離れになるのではないか、不安で一杯であったが、反面、ことによったら内地の土を踏めるかも知れないとの淡い希望を持ったのも事実である。
こんな雰囲気の中で吾々は所持していた布類等で土地の比島人から交換で少量の米と食塩を手に入れた。そして今夜は旗護兵の最後の晩餐会にと準備が進められた。ところが思ってもみない事に際会したのである。
それは、A兵長が背嚢の中から米二合と缶詰一箇を出したことである。
カガヤン河谷の転進途中で我々食糧から米は既になくなっていた。
B兵長がマラリヤと大腸炎の為、聯隊主力と行動を共にすることが出来ず、 カガヤン川畔に残った決別の折にも、彼に分けた食糧は山芋の粉だった。一ヶ月滞在したピナバガンでは玉蜀黍は豊富に手に入ったが米はたしか手に入らなかったはずだがと、A兵長の背嚢から出された米二合と缶詰一箇に疑問が次から次へと生れて来た。これらの疑問にしみじみと答えてくれたA兵長の言葉に改めて旗護兵の仲間が眼頭を熱くした。
日く、若しい戦况の中で聯隊が車旗を奉じて、最後の戦闘をする時がくると確信をした。その時、生米をかじっても空腹を凌ぎ悔の無い最後の働きをしたかった。その為最後の食糧として隠し持っていたと。そしてさらに、山の中の苦しい転進間、何度出そうと思った事か。然し最後のそれを必要とする時まで持っていようと心を鬼にしましたと。
A兵長の言葉によき部下を持った喜びをひしひしと感じました。
その夜食べた白い御飯に塩をかけた食事、 それはこの世で食べた最高に美味しい食事であった。焚火に照らされたそげた赤い頬を寄せ合って、その夜の思い出話しはいつまでも、いつまでもつきなかった。
終戦を知らずして山中放浪七ケ月
生還者 (鳥取県智頭町)
生還者で今回(平成2年)巡拝に参加された、智頭町安道靜一さんは「フナ」陣地 (直線距離にして八〇〇米位か) を指差しながら、当時を振り返りながら山中放浪生活七ヶ月を証言される。

「私は (所属第二機関銃中隊) 「カシ」陣地第三回目の攻撃の際、敵迫撃砲弾の為数ヶ所に負傷後退第二野病に入院していたのであるが、 四月下旬戦況不利に依り病院は後方へ移動の為、動ける者は中隊に復帰せよとの命令で足を引きづりながら中隊に復帰した。
当時、 野中中隊長戦死され、後任中隊長多田中尉、 五味小尉と次々と戦死され、 五月に入り敵は「ヤナギ」を突破し 「フナ」陣地も敵に包囲され中隊最後の時が来て、 私達動けない者は、 自決要員として各人手榴弾二発を渡され、 元気な者は大隊本部へと転進して行ったのである。 夜に入り私達動けない者十数名話合った結果、 敵に包囲されている現在どうせ死ぬなら食べるものもない此の陣地で死ぬるより、 マレコの芋畑でも行こうではないかと言う事になり、 五月七日暗闇の中を 「フナ」陣地を這いながら脱出したのであった。
空腹で歩行困難な者たちばかりの行動、十数日かかり最後に着いた者は寺地准尉以下十四名であった。その芋畑で疲労を回復しながらの生活が一か月半続く。その間、寺地准尉戦死される。この芋畑も食い盡し、和田曹長以下十三名は七月十日頃本隊に追及しようということになり、マレコより「カシ」陣地に戻る。陣地内の蛸壺より米軍の缶詰などを発見。約一週間分程あって命をつなぐ。当時五号道路は米軍の自動貨車が頻繁に往来していた。米軍の缶詰が無くなり、妙高山方面に行けば芋畑でもあるのではないかということで話が纏まり、七月下旬頃夜間を利用、デグデグ川を渡り妙義山を経て妙高山の山頂に到着する。
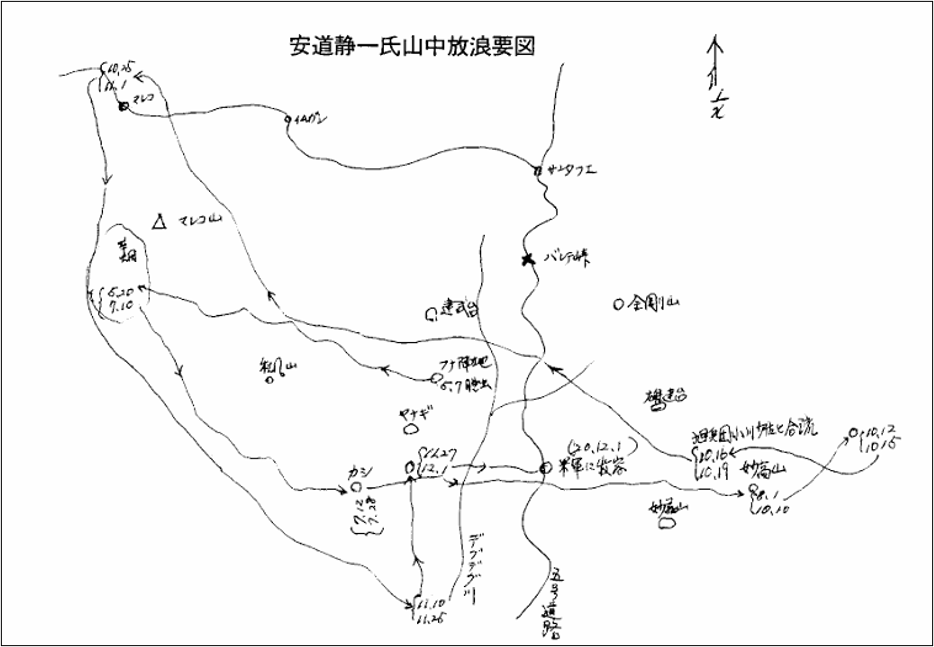
ここにも米軍の缶詰が沢山蛸壺の中に隠されているのを発見、この糧秣で約二か月間命を繋ぐ。食糧も無くなり敵の危険を感じ、二キロ程東の方へ移動せしも食する何物もなく、三日程して再び妙高に戻ると、旭兵団の小川少佐と兵二名おられ、私達十三名は小川少佐の指揮下に入り、食糧を求める為、夜間行動により約一週間程か、十月下旬頃サラクサク峠に到着する。然し、ここにも食する何物も無いので、皆の相談の結果再びマレコの芋畑を通り「カシ」陣地南方二キロ程の所迄行きしも、芋畑らしき物も無く十一月下旬、又、デグデグ川を溯り「カシ」山麓に戻る。
小川少佐が、 一同を集め「戦争は既に終わっているようだ。此の侭の状態では、皆が餓死することは必定なので米軍に投降しようと思う。そして日本に帰り、日本の再建に努力しようではないか」と話されたが、投降しようと言う者と、しない者と半数に意見が分かれたが、小川少佐の説得で全員投降する事に話が纏り、小川少佐は「我々は戦争中の捕虜ではないのだから、日本軍人として堂々と胸を張って投降しようではないか」と言って、自ら先頭に立ち、我々もその後に従い、十二月一日デグデグ川を渡り五号道路で米軍に収容されたのであった。」と話される。
収容された十三名は次の人達である。 (氏名省略)
島根県西郷町 東郷町門田 智頭町西宇塚 淀江町西原 鳥取市伏野 倉吉市三江 佐治村高山 倉吉市大谷 東伯町別宮 鳥取市川端五 赤崎町箆津 倉吉市福田 岡山県勝北町
追憶ーバレテ会結成
生還者 鳥取県淀江町 松永 元一
1.バレテ会のはじまりは、昭和四十二年六月、今皆故人となっているが、 阪神方面の吉村保造(元高級主計)、鈴木良次、池田一行、山根重義の各氏が相携えて広島を訪ね、三宅尉進氏(元高級軍医、三代目バレテ会会長) と一タを共にして、バレテ戦のことどもを昨日のことのように語り合い、話の行き先は、青春を御国に捧げて散華された、二千数百名の鉄六三連隊の亡き戦友の慰霊祭実施のことで、 沢山の生命の消えゆかれた様を見ている我々は、是非共実現すべく地元鳥取方面の協力を得て、 これを実現しようと誓い合われたという。

2.その約一か月後に鳥取市白兎荘に三宅、吉村、鈴木氏のほか、地元から故中山兤逸軍医さん以下七名 (写真1参照) が集まって、バレテ会発起人会を開き、会則案、事務局等を決め、来年の慰霊祭実施を誓い合った。そして、それまでに生還者名簿、市町村別戦没者名簿の作成、 山本照孝氏記述の 「比島バレテの思い出」 の刊行 (一、 二〇〇冊印刷し一年後に八〇〇冊増刷)、 頒布を申し合わせ、 直ちにこれが実施に移った。 その時、吉村氏は私に金がいるときは話してくれと云われ心強く思った。
3.昭和四十三年三月東郷町水明荘に生還者五十三名が集まって創立総会を開き、会則や会長島田安夫氏以下の役職員と、本年慰霊祭実施をと決めた。

4.昭和四十三年九月八日 鳥取市樗谿公園にあった県護国神社で、鉄第五四四七部隊戦没者慰霊祭を行った。(写真2参照)。約二〇〇〇人に案内して、参列者は来賓に古井喜実代議士ほか二十一名、遺族様約四百名、生還者十百十一名だった。その後で午後一時より県庁講堂において戦闘概要報告会を開き、小川清龍、根本直、中原清重、田口英夫各氏の順で報告された。そして 生還者のみ市内の丸茂旅館に移って懇親会を開いた。
5、昭和四十四年からは毎年のように、総会、役員会を開き、 四十五年の総会では、いま私達が慰霊碑を建てなければ、戦友の死は過去の忘れられた存在になる。
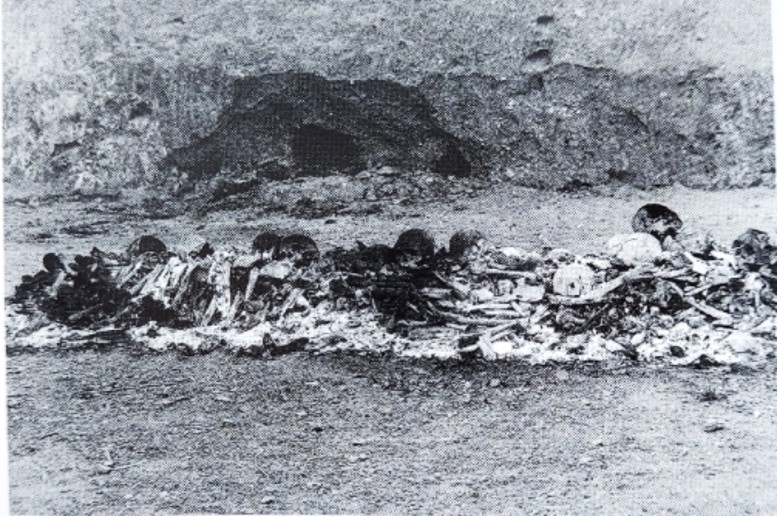
昭和二十年に比島で悪戦苦闘して戦没された、鉄六三将兵の足跡を石に刻んで残せば、遥か異境の地で祖国のため尊い礎となられた戦没将兵の愛国のを至情は、たとえ世代は変わってもこれを後世にに語り伝え、歴史の中に永久にこれを止めることができる。これにより、英霊を始め、遺族様も私達も心の安らぎを得られるでないかということで、戦没者慰霊碑建立につき準備委員会を設け進めることとなった。
そして、建立場所、施工、募金等につき協議し、神社の移転に合わせて推進することとなった。募金は目標の倍額以上のご協力をいたたき、碑石は船岡町の花原卓男石材店により、社産の自然石で格別のご厚志で施工して貰い、敷地三〇坪も地元浜坂地区のご好意をいただいた。碑文は時の総理大臣田中角栄氏書、傍碑の撰文は大阪府立大の文学博士佐中壮氏(境港市出身)に、書は当会副会長故船越正道氏によった。
また、石垣は大成建設、石段造園は栗山組の篤志により施工し、昭和四十九年に竣工した。「白骨のお文」 に 「朝には紅顔ありて、タには白骨となれる身なり」と、およそ人間は儚い夢幻のような一生と説かれているが、死水をとる者もなく、シャングルの中で野ざらしとなって、 一人淋しく逝かれた戦友の悲惨な光景を目にしている私達は、毎年この碑の前で冥福を祈ることとしようと誓った。

6、昭和四十八年十一月に約一ヶ月間、当会の故中原清重氏、故飯塚正氏、山本照孝氏は、政府派遣遺骨収集団に参加され、バレテ峠、サクラサク峠周辺で、 遺骨、 遺品を収集し日本に持ち帰られた。(写真3参照)
遺骨は千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨された三九七体の分骨を、厚生省の特別の計らいで県を通じて本会にいただいた。これと小川少尉が持ち帰られた鉄六三の軍旗のピスと、 英霊名簿をステンレス製のロッカーに納め、慰霊碑台座下の納骨室に納めた。
(写真4参照) また、 九二式重機関銃、 擲弾筒、 鉄帽、 水筒、 飯盒の遺品もバレテ会が譲り受け、 県護国神社に奉納した。

7、 昭和四十九年六月に比島戦没者慰霊碑除幕式、続いて納骨、遺品等奉納の儀及び慰霊祭を行い、 平林知事、 柏井厚生省課長(鉄兵団副官、 元少佐) を始め、 県内外の関係者三百数十名の出席があった。 (写真5参照)
8.昭和五十年八月の総会で遺族様も会員となられるよう会則を改正した。
9.昭和五十一年一月から約一か月間、 政府による遺骨収集があり、 当会の角田唯久、 徳岡喜行氏が参加され、 全体で遺骨八、七九九体を収集されたという。
10.昭和五十二年三月十日から八日間、PICによる比島慰霊巡拝があり、当会より山本照孝氏ら十七名が参加。 また、 昭和五十三年四月には交通公社による巡拝があり、三宅尉進氏、 松永ら一三名が参加した。その後も概ね巡拝が続いている。

11. 昭和五十八年十月からバレテ峠台地を修復し、 埋葬骨灰八袋は碑建立時、 収納室に納骨され、 追悼碑と戦跡碑は船便により輸送し通関の上、 花原石材店により碑石の据付けをし、十字架追悼碑は右側に移した。十 一トンもある碑石を外国に運んで建てるという難事業の中核となられた山本照孝氏のご苦労は大変なことだったと思います。昭和五十九年三月には追悼碑除幕式があ
り、県内から七〇名の参列者があった。鉄撃泉兵団からも参列され盛大に厳修された。(写真6参照)
また、平成二年七月には大地震があり、その後の台風も重なって、戦跡碑の落下、石垣の崩壊があり、これの修復工事をなし平成三年二月末には完工した。
バレテの死
生還者 東京都
いまたえむ いきの下より 萬代を うたうときくに 涙こぼれぬ
これは、東京千鳥ケ淵の、戦没将兵の墓苑に建てられている昭憲皇太后の御歌である。
明治以来、海の彼方の山野で、外国と戦って死んだ戦士の数は多い。その人達が、息を引取る間際の様子は、どうであっただろうか。 ここにかかげた御歌の心を噛みしめていると、私は私なりに、バレテ峠はもとより、 ルソンの山野に散った多くの戦友たちの心が蘇って来るようだ。
一人一人の死がどうであったか、ということはとも角として、戦場に臨み、死に直面していた当時の人々の心は、皆同じであった、といっていいのではないだろうか。 「兵隊は、どういう風にして死んでいったか」ということが、 この頃よく問題にされる。今までにこういう話をよく聞いた。
死ぬ間際に「天皇陛下万歳」といって息を引取っていったというのは嘘で、「お母さん」といって皆死んでいったというのである。私は、この話自体が逆に嘘だと思っている。そうでないと、実際に死んでいった戦友達に叱られそうな気がする。即ち、死ぬ間際がどうであったかということは、実際に死んだ人達の自由にはならない事であったからである。戦友に看取られ、後事を托して死んだ例は、実際に数少く、大部分は砲撃にケシ飛び、火焔放射器に炙られ、無言のうちに、或は苦しみにただうめき、言葉にならぬ言葉を吐きながら、それぞれに息を引取っていった。しかしその心は、皆、萬代をうたい、家族や友人を想いつつ死に臨んでいた筈である。前に掲げた御歌の心は、そういうものだと、私は解したい。
個々の死にざまは、勿論千差万別であった。その死んでいった人達の様子を、ここに描くことが供養になるということならば、生還者が皆でそれを描くこともよいであろう。今生きて帰っている人達は、ただ各人が身近かに死んでいった戦友のことや、偶然に出遇った、心の引緊るような悲しい死にざまの話を、忘れられず今でも想い出しているにちがいない。後頭部の創で、 殆ど出血をしてない綺麗な死体となっておられた垣垣隊長。サンニコラス附近のマニラ平野から射ち込まれて来る長距離の破片で首筋を大きく断ち切られ顔が三角になって仕舞ったN上等兵。負傷の苦しさに耐えられず、手榴弾で自爆したところ、 直径一米位の大きなケシの花のように体が咲き開いてしまったT軍曹。また、命令受領の際、迫撃砲弾の破片で腹が大きく破れ、医薬材料も無い儘に、一晩中「軍医殿、痛い痛い」 と叫びつづけ、明け方遂に亡くなった或る上等兵。
こういった例は数限りなく多い。生還者の人達は、恐ろしい悲惨な極限状態の中で、忘れることの出来ない強い記憶を、皆いつまでも持ちつづけている筈である。
戦争のときの惨烈な憶い出は、何も日本軍だけでなく、当時の米比軍の中にも色々あって、戦後現地を訪れた際、またその時知り合った人達からの手紙の中でも、多くを聞かされた。ただ米比軍の方に無かったのは、猛烈な砲撃や火焔放射の中での「屠殺」に近い殺され方、 および転進中の飢餓行進であったろう。
私の居た大隊正面で、迫撃砲弾は六〇発しか無いことを、当時報らされていたが、米軍の砲撃は、概ね一分間に六〇発であった。そしてそれが終日、時には夜も続いた。当時私は、実際に数えていて、よく憶えている。他隊の正面はとも角、妙義山・ 一の谷の三中隊・一機の第一戦陣地では、戦闘というより、むしろ十把一からげの屠殺といった方が適切な位の、連日に亘る砲撃および 戦車等による火焔放射であった。「近代戦」とか、「猛烈な砲爆撃」ということは、頭の中では仮に理解したと思っても、実際に戦場でそれを体験した場合、全く別物という感じがする。
その場合、人間の身体は、射たれるというより「毀されてしまう」 し、火焔放射で「炙られてしまう」 のである。「近代戦」というのは酷いもので、戦闘中、兵隊が「戦死,する瞬間というものは、 一片の感傷をも差しはさむことを許さない壮烈無惨なものだ、と私は感じている。しかし、陣地にいて、間近に近寄って来ている「死」と、心の中で対決している間は、萬代を思い、家族や友人を想い、美しい故郷の山河を瞼に浮べていた筈である。そして夜が明け、砲撃が始まり、敵戦車が近接し、否応なしに「屠殺」に直面していったその時には、既に「生」はなく「死」 のみがあった。その時には既に戦友を顧みる暇があるというようなものではなく、戦友と共々十把一からげにされて、敵の砲火の下に渦となって巻き込まれ、土砂に埋まり、或は吹き飛ばされていた。
プトランの前進陣地で戦死した林原修一君は、初年兵の時から私と隣り合せの寝台で過ごした、 私の二の戦友であった。彼は自分の中隊が全滅したことを確認後、拳銃で自決したと、当時通報を受けた。私は彼の戦死の約二週間前に 連絡の任務をもってその陣地を訪れた。彼と別れるとき指揮班の壕の傍で、彼の水筒に入っていた「とっておき」の椰子酒を汲み交わし、短かい時間ではあったが、過ぎ来し方の想い出話などをした。
そして五号道路を北へ戻るとき、お互いに姿が見えなくなる迄、手を振り合ったことを憶えている。それは、私がその時、米軍の観測機に見つかったことに気付き、河の傍に隠れねばならなくなるまで続いた。林原隊の陣地は、谷底のような所にあったが、後部上方の大隊本部の一陣地からみていると、その後その陣地は約一週間、砲煙に埋まり続けていた。そして全滅の知らせが届いたのであった。
比島戦没者遺骨収集を終えて
生還者 鳥取県江府町 島根県伯太町
私達は、バレテ会の皆さんのご推挙により政府派遣遺遑骨収集派遣団の一員として去る一月十六日九段会館に於て厚生省の高山援護局長列席のもとに結団式 (団長以下九十六名) を行ない、 五十一年一月十七日羽田空港を出発、二月十一日夕 八、七七九柱と共に無事帰国いたしました。
編成は、政府職員八名、日本遺族会青年部四十八名、戦友四十名、本部柏井団長以下三名で、六ヶ班に分れ、私達は第三班に属し総員二十四名でした。バレテ、スズカ、 サラクサク、バンバン、ビンタワン、 マデラ (旧ピナバガン)、 カシグ地区を担当し、 同一行動では作業能率が低下するので、 更らにABC班に細分し、 私達はB班として、特にバレテ峠周辺の鉄部隊のかつての戦場を中心に終戦を迎えたマデラに至る間の遺骨収集を行ないました。
バレテの戦争中は、 制空権のないため夜の行動が多かったのですが、当時は大密林であった記意の山々が処によっては草原に変り、 谷あいには民家も建ち田圃開け、 小学校も建っている様は驚きの一語であります。こうした中での住民は、 終戦後戦死した戦友の遺留品や弾薬、兵器を集めて十年位生活したと聞かされ、如何に戦死者が多く、戦争が烈しかったか、数多くの戦記にみられるそのものであります。壕は崩れ、蛸壷は埋まり、 三十年の歳月はかくも衰えるものかと目を見張るばかりでありました。
作業開始第一日は雨でしたが、バレテ峠、 椿名山の散兵壕から遺骨と軍靴を掘り出したときには、永い間淋しく異郷の地で我々の迎えを待っていて呉れた、 サアー、一緒に内地へ帰ろうぜと語りかけて班員一同涙せぬ者はありませんでした。遺児の一人は、父の戦死の地名を聞くのみで何の実感も湧かなかったが、戦場を訪れ、遺骨を抱いて、始めて父をひしひしと感じ、父の戦場での苦労を偲んだ。
遺骨と共に帰れることは、誰の遺骨かは判らなくても、 亡き父へのよい供養である。今までは何も知らずに母へも我儘を云ったが、あらためて悔いていると言葉少なに語ってくれ、共に泣いたこともあった。収骨が終ると現地で香を焚き、お供物をしてご冥福をお祈りし一日が終る。二大隊陣地、連隊本部のあった金剛山、一大隊陣地、天王山、地獄谷と遺骨よ、戦友よ、姿を見せてくれ、一諸に内地へ帰ろうぜと毎日山や渓間を懐かしい軍歌等を聞かせながら歩き廻って遺骨を探し求めた。
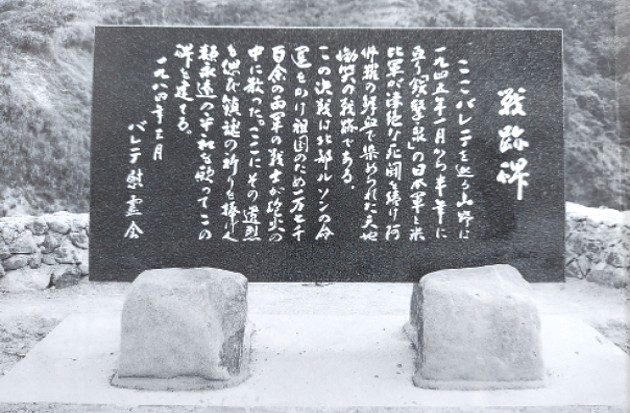
その間に、 予定収骨地のカシグ (転進途中師団駐留地) にも入ったが、 かつての荒野は農地に変わって昔日の面影はなく、 一柱の収骨に止まりました。 唯得ることができたのは、 亡き戦友や私達生存者が残らず経験したカガヤン死の転進地、 ビルク、 ビノン、ブコの山々を涙で遠望し写真に納めたことでした。一月三十日、第三班の第一回現地焼骨追悼をサンタフェで行い、現地町長以下多数の協力援助によって英霊八五五柱の立派な追悼式を行なうことができました。
一月三十一日以後後半は、 ビンタワンに私達B班の基地を置き収肯に努めました。この間にマデラ (旧ピナバガン) の収骨に向いましたが、カガヤン河流域のこの地は、 終戦当時と大変に変っており民家も非常に増加し、町長の話では現在人口は二万二千人と云うことで当時の面影はありませんでした。終戦を知りつつ病魔に倒れた戦友の埋葬場所も見付けられないまま引き返したことは、唯々残念でなりませんでした。この地は、戦後始めての収骨でもあり日時の余裕が得られたならば、現地の人の協力も得られたのではないかと残念でなりませんでした。後半の焼肯追悼も前半と同様に現地町長以下の協力によって、立派に英霊一四二柱の追悼式が出来たことは、 日比政府間の収骨打合せもさることながら、比島の住民が昔の戦争は語らず、今は仲良くしようと非常に親日的であったことによるものと思われました。
二月九日、マニラの日本大使公邸において 八、七九九柱の遺骨を前に沢木特命全権大使を始め柏井団長ほか多数の列席のもとに五十年度フィリピン戦没者合同追悼式を行って帰国いたしました。
戦後三十有余年の永い間、戦場で散華し、あるいはまた、飢えや病魔のため無念の涙を呑んで仆れて、異郷の地で淋しく私達の迎えを待っていたであろうご遺骨を抱いて帰国した私達には、何か今迄の重荷がおりたような感じではありますが、今だに数多くのご遺骨が異郷に残されていることを思うと、今後もなお政府の遺骨収集が継続きれることを切望いたざずにはおられません。
英霊は待っている
生還者
昭和五十二年第一回巡拝以来、今年で十三回目の慰霊巡拝を終り、私達にとってバレテの地は第二の故里の様な気がしてならない。日本に生まれ日本に育ち国民の義務として、国難に対し青春の総てを燃焼し戦った戦友の九十五%が散華した地だからである。持参した塔婆を建てささやかな祭壇を作り香を焚き、「ことしも又やって来たぞー」とかつての陣地に向って叫ぶ生還者の姿に答えは無く、春の微風は枯草をそよぐのみである。
然し私は此の地で戦没した戦友達の霊はきっと喜んで迎えてくれていることだろうと思うのである。霊の存在についての一文を紹介したい。
「生残り唯一人」 という本を自費出版している岡山県苫田郡鏡野町の中尾氏の話
「儂は速射砲中隊の下士官だったが、 比島バレテの戦闘で、 大腿部に砲弾の破片創を受け中隊長命令で、 サンタフェの川谷にある野戦病院に下って行った。来て見ると病院とは名ばかり、薄暗い洞窟のカイコ棚に居るのはいい方で、 ほとんどの負傷兵は山肌に天幕を敷き、 スコールが襲来してもそのままだ。食べ物薬も無ければ薬も包帯すら無い。腐臭があたりをただよいこの世のものとは思えない惨状である。」
「こんな処では殺されてしまう」儂は二、三日で逃げ出し原隊に復帰しようと杖を頼りに中隊への道をたどった。儂が出て間もなく、中隊陣地は敵の集中攻撃を受け、屍が散乱し全滅していた。
どうにもならぬので、敵の飛行機に撃たれて死んじゃろうと思案し、 山頂のよく視界のきく処で大の字に寝転って眠っていた。「班長殿、 班長殿ではないですか」声に覚めてみると、旧所属中隊連隊砲の教え子、 初年兵達数人が心配そうにのぞいている。「俺は中隊唯一人の生き残りだ。今更生きても仕方がない、ここで往生する心算だ、「班長殿、 何を言うのですか。自分達の中隊に来て下さい。自分達がお世話致します。」
彼等が通りかかったのは運命か、 神の加護か、 最後まで彼等の世話になり、運よく生還出来たのである。
心の中でくすぶり続けていた比島慰霊巡拝が出来る様になり、三十年振りかで比島の土を踏んだ。懐かしいバレテの連山、想い出を探りながら涙が滂沱として頬を濡らした。写真を撮り、戦友の斃れた場所の土を飯盒に入れて持ち帰ったのである。
持ち帰った土の事だが、帰ると直ちに我が家の菩提寺に行き、訳を話して土を慰霊してもらい、半分を戦友の墓に、半分はお寺で永代供養して貰うよう頼んだ。「これは良い事をなされた。さだめし戦友の霊も喜ばれるでしょう」
お坊さんは感激して引受けてくれた。ところが、二、三日してお寺から電話があった。
「あの土は私の手に負えません。位の高いお坊さんに供養してもらって下さい」
仕方がないので教えられたお寺を訪ね事情を話したら、心良く引き受けてくれた。
二、三日経つと、またそのお寺から電話がかかってきた。「あの土は私の手に負えません。どこか他のお寺へ頼んで下さい」「それは一体どういうことですか」
「あなたは唯、単に土だと思っておられるようですが、あれは全部死人の霊魂です」
「それがどうして、あなたの手に負えないのですか」
「霊の中には良い霊もあり、悪霊も多いのです。あの土には、内地に帰りたい一心で物凄い数の霊が土の中で犇めいています。若しこれをこのまま放置すると、あなた並びに家族の生命を失うことになるでしょう。一日も早く位の高いお寺の坊さんにお願いして供養してあげて下さい」
結局、教えられた三度目のお寺に行き、留守だった高僧の娘さんに訳を話しお願いして帰ったが、 ここではどうにか納受して貰ったものの、 人間の霊魂の怖ろしさを初めて体験した。
(大河原京太著 昭和の浦島太郎より)
カガヤンの亡骸
生還者
(昭和二十年六月十四日宝満山を発ち、 ヨネスで武装解除を受けるまでの約三か月間に、無念の涙を呑んで逝かれた、鉄六三の将兵約三二〇名の英霊を憶いて)
ポタリ、ポタリ、冷い山の夜露の雫がたれたとき、俺はふと目覚めた。静寂なあたりを見廻すと、 おおなんと、窪んだ瞳に映ったのは、俺の亡俺のムクロではないか。哀れにも叢にうづくまって、氷ついた月の光の中に、硬直して永久に動かない。かっての俺の体驅は、ここに取り残されて、これからどうなるというのだ。
俺が食うべき糧もなく、 マラリヤと下痢に悶え苦しみ、カガヤンのこの山中に、骨と皮で横たわる。もう誰れも通らない、可愛そうな俺の亡骸、俺はお前を凝視して、餓死と知り病死と知ったとき、両親や妻子の慟哭を、また千里の道を遠しとしない、彼等の心を想って哭き続けた。俺は一途に生への執念を燃やし、歯を喰いしばって、必死に頑張ったが、ここで仆れて再び起き上れず、悲しい打ちひしがれた、数日を過して、俺の恐れていたものが、遂にやってきたのだ。皮と肉とは南国の灼執にむくみ、爛れ、頽れ、俺の亡骸は、死臭が鼻をついて、蛆が食い散らした。にぶい蛆の動きを見つめて、俺の戦慄は高まり、俺は声をあげて泣いた。ああ、俺は何故亡骸を、この悪魔の使者達に捧げねばならぬのだ。
地上に打ち捨てられた亡骸の恨みは、湿った山の夜風に、時折りゆらゆらと燐を燃やした。 この寂しい憤りの焔を見た人は、果たして何を想ったであろうか。なけなしの皮と肉が、 スコールに洗われて、俺の亡骸は、次第に形を変えていった、唇はなくなり、息絶えた時の苦痛のままに、食いしばった歯が露れ、落ち窪んだ眼孔に、月の光も届かなくなって、臭気もなく蛆も去った、俺の亡骸は、 地上に一組の白骨を残して、土に還っていった。
だが、この俺の霊魂は、一体何処へ還ろうというのだ。俺の亡骸を置き捨てた人々よ、俺の亡骸の傍を通り過ぎた人々よ、生きて永らえし人々よ、カガヤンの山中には、永久に故郷を恋い続けて、さまよう霊魂のすすり泣きが、夜毎聞こゆると、故郷の人々に、語り伝えくだされ。
戦死に悲し鉄部隊
はじめに
昔の小学唱歌に、戦史に悲し吉野山・・・というのがあったと聞く。歌詞は知らないのだが、 そこはかとなく南朝の哀史が思われ、いつも頭のどこかにある言葉となっている。之また、 それが転じて「戦史に悲し鉄部隊」とつぶやくことがある。それは「鉄」 への供養の心だと自分に言い聞かせている。私が思っている松江六三の「鉄」部隊は、強くて純で頼もしかった。それを見込んだ国軍は、 ここ一番の秋(とき)の懐力として期待をかけた。
ついにその日がやってきた。 日米戦の天王山、比島バレテの攻防戦で峠を死守して果てた。私はバレテの戦友ではなく、戦場体験も特にない。ただ、実兄がこの部隊員でサンニコラスにて戦死だが遺族として筆を取らせて頂くものでもない。
縁あってと言うべきか、 私は長年職業として郷土の部隊史を追ってきた。 その立場で語りたい。戦史に悲しく「鉄」。 それだけに機あるごとその旗風は鮮明にしたいと念じてきた。 ふっと寂しさ漂わすいとしの好漢とでも言いたい六三の「鉄」でもある。 以下、 心からの合掌が捧げたい。
姫路一〇師団満州へ移駐
本筋から逸れるが、 いまも鳥取の年配者が「鳥取地震(十八年九月十日)のとき、四〇聯隊の兵隊さんに助けられた」とよく語る。四〇聯隊と中部四七が同一部隊のように思われて戦後の今に及んでいる一例である。当時の軍事秘がいかに厳しかったかが思われる。なお、念のために・・・。鳥取震災の出動は「中部第四七部隊補充隊」であって、本隊は同年春、ビルマ戦線へ向け出陣した。さて、 この時の西部、中部は耳馴れぬ初の言葉であった。実は、この年、軍機構の大変革が行われ、昭和軍政の確立がなった。この改革により、日本内地は四軍管区に大別され、松江は司令部が福岡に設けられた西部軍の管区へ。鳥取は同じく大阪の中部軍管区となった。
内地の歩兵連隊には、総てこの軍管名を頭に冠して番号を付け、それを通称名とした。東京など関東勢は東部〇〇部隊というわけだ。なお、西部六四は歩兵第一四二聯隊、中部四七は歩兵第一二一聯隊が正式な名前。この正式隊番号が世間に言われだしたのは、戦後の三十年代からである。中部四七はビルマ戦に出陣「兵」(つわもの)部隊と呼ばれて終戦。正式隊番号が表に出たことは一度もなかった。
事実上の 「鉄」鳥取部隊 誕生
さて、中国残留日本人孤児の問題は、戦争の生の傷痕を今の私達に伝え涙を誘う。これら孤児の親に当たる人達が、満蒙開拓移民団として最初に渡満したのは昭和七年。北満三江省チャムスの永豊鎮に弥栄村の名で入植した。
一〇師団移駐の地もこの三江省で司令部はチャムス。松江六三はその北の石炭の村、興山鎮であった。北に黒龍、東にウスリーの両大河その向こうはソ連領。弥栄村入植のころは、満州馬賊が神出鬼没。キツネ、テン、リス、シカ、ノロたちが走り回り、キジは日本のスズメより多かったという。こんな辺境の地で、内地同よう聯隊名を隠し、松江六三は「満州第六七九部隊」の名となって激しい対戦車戦闘訓練と国境線の守りに明け暮れた。
ところで、同時にいま一つ大きい変革が起こっている。鳥取四〇が渡満と同時に一〇師団を離れ、東満の平陽に本部を置いたものだ。林口に司令部を設けた新編二五師団の隷下(鳥取と小倉一西、篠山七〇両聯隊) で「満州第九六〇部隊」と呼ばれた。師団の三単位制実施によるもので、松江・鳥取は全く無縁の軍関係となった。これに、いま一つ追いうちがかかる。補充区の変革である。十六年夏、周知のようにこの夏は「関特演」が発動され、関東軍(満州の権益を守った日本軍)がふくれ上がった。
この発動とほぼ同じ日付けの七月十六日「歩兵第六三聯隊 補充担任部隊所在地 鳥取市 中部四七部」 (戦後、厚生省作製文書)とされ、これにより、長く続いた松江六三の補充区、島根県出雲部と鳥取県の千代川以西は、出雲部と、千代川の境界線が除かれて鳥取全県区と改められることになった。
私ごとで恐縮ながら、実兄(八頭郡郡家町)も十九年二月に岩倉の中部四七へ現役入隊、十日間の在隊で満洲興山の六三へ糘立った。
八頭郡は千代川以東である。前記調査表通りの六三人隊である。転属でなく、六三要員として中部四七入隊と解している。こうした経過で、松江の伝統聯隊の名は消えることのない六三ながら兵員構成という事実上の姿で鳥取部隊に生れ変った。六三は、満州六七九から再び「鉄」五四四七部隊と名前を変えて台湾へ、そして比島の戦場というコースをたどる。鉄五四四七として満州を出発した時の総員は二千三百人。うち、 バレテ峠主体の比島戦没者は鳥取県一千八百六十一人、島根県三十八人、ほか他県の別である。
十指に及ぶ広義の意味での鳥取部隊で、兵員が烏取県人九〇バーセント以上、戦没者もビルマの鳥取部隊を抜いて最多という。 こんな鳥取部隊はほかにない。
なお、烏取四〇は大阪の中部二三部隊が補充担任となったことから、終戦時は完全な大阪部隊(兵員構成)であった。こういう「鉄」鳥取部隊なのだが「鉄」部隊関係者は別として、 ここ二十年間私が接した多くの人でこれを認識していた人はまずいなかった。「 『鉄』というのは松江の部隊でしよう」の声であり、 その松江では「六三の最後のことはよく知りません」とまこと連れない言葉の数々。松江、鳥取の狭間に落ち込んでいる。でも、誰を恨むこともない。「鉄」は薄幸の星を背負っているのだ。補充区改変のころから段々と戦争が激しくなり、県内も国内も皆が勝ち抜くこと、生きることだけで精一杯。 「鉄」が編成されて、中部軍がどうで・・・など、仮りに知らされたとしても、 そんなことに耳傾ける世情ではなかった。そのうち終戦、混乱、占領、食べる問題、価値観の逆転、 アンチ旧軍と続き、 アッという間に十余年が流れた。 この間に軍の公式文書など戦争の遣物は殆んど焼きつくされていた。この流れを考えるとき、「鉄」 への理解を求めても無理ではないかと気づいた。
日米戦の天王山へ
さて、十九年七月二十四日の「鉄」動員発令で一〇師団はいよいよ関東軍を離れ、台湾防衛の任につく。当時、大本営は台湾か比島か、そのどちらが先に攻撃を受けるか迷いに迷う。それが無理からぬように、米軍自体もマッカーサー総帥の陸軍は比島攻撃を、海軍のユミッツ大将は台湾を。両者譲らずついに七月、ルーズベルト大統領がハワイに出向いて三者会議。 「比島の解放は米国の聖戦」というマ総師主張に “軍配”を上げて比島先攻が決まったという記録を残している。
台湾派遣の重要性は、むしろ米軍側のこの記録では、はっきりする思いだ。フィリビン攻撃で一本化した米軍は、十九年十月中旬レイテ島を攻撃目標にして動き始めた。日米戦の天王山である。
十一月十日、台湾の「鉄」は、 レイテ投入と内定され、同二十日に山下比島防衛軍組み込みの戦闘序列が正式に下った。そして“ここ一番” の比島へ走る。この後のバレテ峠死守の敢闘ぶりは、この会報でもよく述べられているところだ。比島奪還の執念の凄さは「マッカーサー回想録」によくみられる。 その主力軍と真っ向四つ。兵力・装備は比較にならない違いだ。そんな攻撃米軍が今もバレテ峠の頂上に立つダルトン記念碑に、「THIS DESPERATE STRUGGLE」 (この絶望的なる争奪戦)と刻んで、自軍ダルトン将軍の戦死を悼んでいる。 この嘆きの一節で、 ここの守備軍の中核、松江六三主力の 「鉄」 の死闘、任務完遂のほどが十分偲ばれると私は思う。
まさに新生日本の礎石だ。 せめてこれを知っているものだけでも「鉄」を忘れてはならない。私は、それが一番の供養だと思っている。
2-2.遺族・関係者の記憶
S氏の思い出
昭和20年2月から始まったバレテ峠の戦闘は、激闘4ヶ月、100日間の攻防戦の末6月1日についに突破され「鉄」 の戦いは終わりを告げた。峠を死守していた日本兵は、1万1千名のうち9割以上の1万名が戦死し、その殆どは砲撃で吹き飛ばされて遺骨も遺品も遺していないという。
平成25年、バレテ会の比島慰霊巡拝行(第35回)で初めてお会いした90歳のS氏は、 鉄兵団、 松江第六十三連隊に所属しており、 1万人が戦死した地獄の戦場からの奇跡の生還者のお一人であった。
S氏から伺った話によると、満州から動員命令が下ってフィリビンへ向かう事となった同氏は、 フィリピン・ルソン島を目前にして乗っていた輸送船が敵潜水艦の攻撃で撃沈されて海上に投げ出された。 一昼夜の漂流の末やっと味方の船に助けられてルソン島に上陸した後に命令でバレテ峠へ。米軍の攻撃が始まって、連日の猛砲撃に晒される中、ある日砲撃によって上官の部隊長がタコツボの中に生き埋めにされてしまい、 これに気付いたS氏が必死に土砂を掘り返して部隊長を助け出したそうである。 この日以来、部隊長はS氏を特別可愛がってくれ、連日連夜繰り出される「斬り込み隊」には最後まで指名されなかった。その事が自分が奇跡的に生還出来た理由だと私達に話してくれた。 その部隊長もバレテ峠で戦死されたとのことである。
高齢と持病のため、マニラから慰霊地へ向かうバスの中では殆ど横になっていたS氏であったが、 バレテ峠へ着くとしっかりと歩いて慰霊碑へ向かわれた。私達一行10名ほどが、慰霊碑の前で祭壇を設えるなど慰霊祭の準備をしていると、S氏は竹竿に付けた日の丸を手にし、慰霊碑の裏側の崖淵へ進まれた。 そこは眼下にバレテ峠を一望できる高台で、1万名の戦友が眠る山々が眼下に拡がっている。S氏はゆっくりと日の丸の旗を左右に振りながら、向かいの山々に向かい、
「おーい、 還ってきたぞ~~!」 と大声で叫ぶと、竹竿を握りしめたまま号泣し始めた。その鳴咽は眼下の谷間にこだまし、10mほど離れた場所にいた我々は、ただその後姿を粛然として見つめるしかなかった。
やがて準備が整い、簡素ではあるが厳粛な慰霊祭が始まっても、S氏の手には溢れる涙を拭うタオルがずっと握られたままであった。
戦後68年という長い歳月が経っても、S氏の脳裏からこの地での激しい戦い、亡くなった戦友や上官の事を忘れた日は1日も無かったのである。同行した他のご遺族の話によると、S氏は20年以上に亘って毎年欠かさずバレテへの慰霊ツアーに参加し、その折には戦争で現地の人々に多大な迷惑をかけた事への償いとして、付近の小学校へ学用品の寄贈を続けているとの事である。
S氏に重なるように思い出されることがある。
現地の現地フィリビンへの敬意を表する為、式典の初めには「君が代」の前に、 必ずフィリビン国歌のテープを流す事にしていた。 日本人ツアーの一行が慰霊の為に昔戦場であった村々を訪れると、 どこからともなく大勢の子供達が集まってくる。 子供達は、慰霊祭の供物として祭壇に供えられたお菓子類が、式典終了後に配られる事を知っており、それをお目当てに集まって来るのである。

しかし、 式典の最初にフィリピン国歌が演奏され始めると、 一度の例外もなく、 子供達全員が直立して不動の姿勢をとり、年長の男の子の中には、 きちんと右手を左胸に当てて表敬している子さえいる。皆着ているものは粗末な服で、貧しさの故か、 中には靴を履いていない裸足の子もいた。だが、そんな子供達が、次が演奏された時の態度、行動は感動的なものであった。
日本に戻ってから、 「君が代斉唱胖の不起立の教師・・・云々」などの不輸快なニュースを耳にする度、あの時のフィリピンの子供達の凛とした姿が思い出される。
新しい軍装に着替えてーサラクサク峠の死
遺族
兄の眠るフィリピンへ、いつか慰霊の旅に出たい、それが唯一の悲願でした。兄の戦死の通知を下さいました元大隊長の佐藤様 (中迫第七大隊長) に連絡を取りたいと思い、 昭和二十一年にいただいたお便りを頼りにお手紙を差し上げたのですが、「転居先不明」で返送され、滋賀県の町役場に電話で問い合わせても、三十六年も前の町名は市町村合併ですっかり変わってしまっていて、 調べていただく手立てもなく、落胆しておりました。
その矢先、今は亡き会員林祥子様に厚生省援護局で隊の生存者を調べていただけるとお聞きし、電話でおたずねしたところ、係の方が親切に、元副官の方の住所を教えて下さいました。とるものもとりあえずお便りをしたため、速達でお返事をいただいた時の嬉しさ。 隊長の佐藤様のご住所も知らせていただくことが出来て、 二重の喜びでした。
佐藤様は、 三十三回忌の供養として 『バレテを偲んで』 というご本を出版され、 遺族に送って下さったのですが、 私の郷里の家が転居したため返送されたとのこと。 「何とかしてお届けしたいと念願していた」とのことで、 私からの連絡をたいへん喜んで下さいました。 兄が最後まで、 心の支えと仰いでいた隊長の佐藤様。 今まで胸の中にたまっていた、戦場での兄の様子を知りたい一心で、 毎日のようにお手紙を書きました。そのたびに、細かい、きれいな字で便箋にびっしりと、戦闘の様子などを記されたお返事が届きました。「兄上は、大隊随一の優秀な人物で、 私はもっとも信頼し、 お互い腹の底まで話し合って、 知己のような間柄だった。戦況急を告げ、 師団命令により、 バレテからサラクサクへ派遣部隊を送ることとなり、塚田中隊長としておもむいていただき、サラクサクの兄上とは、毎日没、伝令を通して連絡を取り合った。」
又、兄の玉砕を悼む私の手紙には、次のように、じゅんじゅんとおし下さいました。「当時の多くの方々は、前述を見越して、生死の悟りを開いておられましたので、家族を超越して、仏の御心となってひたすら皆さんの幸福と健康を祈りつつ、生きて仏となられた方が多いのです。
従って、皆さんが故人を哀れと思われますことは当然ですが、むしろ故人が後に残った皆さんのことを案じつつ、息を引き取るまでひたすら皆さんの幸福と健康を案じておられましたことは真実ですから、亡くなられてからも、必ずや皆さんを守っていて下さることと存じます。御霊をお迎えして、懐かしいわが家で供養に専念されて、仏の御心を体して、楽しい老後を送られますよう。 これが仏の何よりの念願ですから、かなえて上げて下さい。
昭和五十九年、バレテ峠に新しく追悼碑が建立されることになり、慰霊巡拝のお知らせがあったとき、私もそのお仲間に入れていただくになりました。三月二十三日成田空港出発。 二十四日バレテ峠の戦跡碑除幕・追悼式典。八十名近い巡拝団に、現地の方々もおおぜい参加して下さり、私もこの地に眠る一万七千柱の御霊に、心からの祈りを捧げました。
三月二十五日、いよいよ念願のサラクサク峠慰霊。遺族八名、生還の方五名。計十一名。生還者のお一人谷村様は、兄と同じ佐藤様の隊の方で、兄のために心をこめてお仏像さまをお彫り下さり、私に賜りました。サンタフェからジーブニーに乗り、でこぼこの険しい山道を、車の天井に頭がぶつかるほど激しく揺られ、道路の欠損個所はみんなで車を押し上げおしあげして進みました。 二度と通ることのなかったこの道を、部下の方々と共に最前線に向かって歩いた兄を思うと、車から降りて、兄の足あとを一歩一歩、踏みしめて登りたい思いに駆られました。

ようやくマリコ村にたどりつき、そこから歩いてマリコ山の慰霊碑に向かいました。かつて地獄図のような凄絶な死闘がくりひろげられた山々も、今は深い緑にかこまれ、鴬の声が遠くの谷間で聞こえました。ああ、ここがサラクサク峠。夢に見たサラクサク峠です。お兄さん、やっと来ましたよ。兄の眠る山を仰ぎ、慰霊碑の前にひざまづいて、お祈りしました。三十九年間の兄への憶いが、どっと体じゅうにあふれ、ただ泣くだけで立ち上がることもできず、ひざまずいたまま、ただただ泣くだけの私でした。
大黒柱を失った父母の痛哭。遺された姪を抱えての義姉の苦難の道のりと、幸せな現在。亡き兄に代って大黒柱となってくれた次兄。三兄、姉や妹たちの現況・・・心の中で兄に語りながら「お兄さん、お兄さん」とただ涙、涙の私でした。
「さあ、おいとましましょう」と同行の方々にうながされて、やっと我にかえり、「塚田一雄他六十八柱」と記していただいたお塔婆と、六十九巻の写経、家族中の写真をお供えし、兄と部下の方々の、尊い血と汗と涙の染みた土を、つつしんで袋に納めました。そして、ふりかえり、ふりかえり、兄の眠る山に別れを惜しんで帰りました。
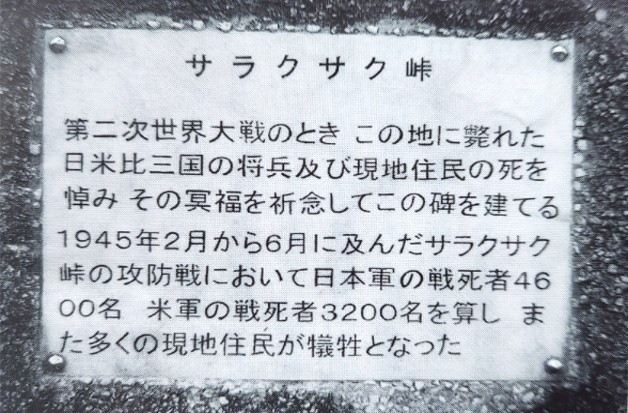
夢にみし サラクサクの峠よ 森よ 谷よ 空よ 声かぎり
兄の名呼べと 応えのなくて 梢吹く 風のそよぎは 母恋いつ
いくさに果てし 兵の鳴咽か ふたたびの 長き岐れの 悲しくて
山峡道を 泣きつつ下りぬ
いただいたお仏像さまを義姉に届けるため、帰国後、郷里の高田に帰りましたが、その車中、たまたま隣の席においでの初老の紳士とお話を交わしました。その方も南方戦線に従事、九死に一生を得て生還され、今日は上官の方のお墓参りに長野へ行かれるとのことでした。私が「兄の慰霊に行って、ただ泣いて来ただけでした。 と申しますと、 「それはあなたが泣かれたのではない。お兄さんが泣かれたのです。お兄さんが泣かれた。そのままの姿なのですよ, としみじみと申されました。
比島巡拝の折、慣れぬ山歩きで無理をしたせいでしようか、以前からあった左下肢静脈瘤が血栓をおこし、帰国後、一か月目に入院、手術。十日後に退院して間もなく、巡拝でご一緒だった谷村様から『サラクサク峠』というご本が届きました。 それはサラクサク戦線から生還された方々の戦記をまとめたご本で、読み進むうちに「サラクサクでの兄の足どりを、どうしても知りたい」という憑かれたような思いに駆られました。まだ痛む足を引きながら、厚生省援護局で調べていただこうと、埼玉県から上京しました。地下鉄霞が関駅から地上までの長い階段を「ヨイショ、ヨイショ」とかけ声をかけながら一段いちだん足を引き上げ、ようやく厚生省にたどりついて、係の方に調査をお願いしました。
しばらくして、その方ガ一冊の書類を持って来られ、とある頁を開かれました。何枚目かの最初の行に書かれてある「塚田一雄」という文字が、まず目に入りました。その名前の上には朱線が二本、縦に引かれてあり、 一番下の欄に、処理済の判のようなものが捺してありました。
四十年近い歳月を経たその書類は、紙の色もすこし黄ばみ、文字もうすくなり、二本の朱線も色あせてはおりましたが、まぎれもなく塚田一雄の文字の上を、非情にも縦に走って、兄の名前を消してしまっていたのです。それを見た瞬間、悲しみがどっと波のように押し寄せ、涙で字が見えなくなってしまいました。
「ここで泣いてはいけない」と自分にいいきかせ、涙を拭きながら一枚いちまい頁をめくってみますと、七、八名ずつ記入されているどの頁のお名前の上にも、朱線、朱線、朱線。朱線で消されているこの一人ひとりのお名前に込められている、どっしりと重い悲しみが私の体を包み、それ以上頁を繰ることは出来ませんでした。「国」に駆り出された時は、たった一枚の赤紙。地獄の戦場で戦いに倒れ、二本の朱線で、永久にこの世から名前が抹消されてしまうとは。「戦争」のむごさ」に胸がつぶれるような思いでした。
「ここではこれ以上のことはわからず、あとは防衛庁の管轄になります」と言われる係の方にお礼を述べて、資料室を出ました。先刻の兄の名前と、その上に引かれた二本の朱線が頭に灼きつき、痛む足と重い心を引きずって帰途につきました。
「いつか必ず防衛庁で調べてみよう」と思いながら二週間ほど過ぎたころ、巡拝で同行した生還者の方からお手紙をいただき、その部下にあたる方のお骨折りで、サラクサクでの兄の隊の行動を教えていただくことが出来ました。
〇昭和二十年三月四日 バレテよりサラクサク派遣。
〇三月十七日 敵一箇大隊の攻撃を受け、これを殲滅することに決定し、塚田中隊その大役を仰せつかる。
〇三月二十日 夕方に攻撃開始。多大の戦果を挙げ、師団長岩仲中将は、三月六日以来初めて満面笑みを浮かべ「塚田中隊してやったり」とその功績を誉め称えられる。
〇四月二十日 敵は猛攻を加え、我が陣地内に侵入。塚田中隊、八紘山東仰に陣地移動。
〇四月三十日 八絋山山頂、敵に占領さる。
〇五月十三日 塚田中尉戦死。
地図を挿入しての細かいご説明の、この貴重なお手紙を。息をのむ思いでくりかえし拝読しました。米軍の迫撃砲二百門に対し、わが軍のそれはわずかに二門。弾丸も数すくなく、思うにまかせぬ状態の中で戦果をあげ、師団長に功績を称えられた兄や部下の方々の喜びはいかばかりだったことか。お手紙をいただいた次の日、満面笑みをたたえ、にこにこ、にこにこ嬉しそうに笑っている兄の夢をはっきりと見ました。しかしこ四月三十日山頂を敵に占領された後は、洞窟陣地にこもって玉砕までの二週間、食糧の補給とてなく、どんなに辛く苦しい日々を送ったことでしょう。
六十一年三月、私たち遺族の心の灯であった隊長の佐藤様がお亡くなりになり、その年の十一月には、心の母とお慕い申しあげていたかがり火の会の仁木悦子先生が急逝されて、私は心の中の二つの大きな柱を失いました。
六十二年十一丹、谷村様からお便りがありました。
「今まで、戦友会の通知を出しても、戦後四十二年間なんの音沙汰もなかった氏から、突然便りが来ておどろいている。氏はサラクサクで塚田隊長の下で戦った人。隊長の妹さんが埼玉におられるので、連絡を取ってほしいと依頼した」とのこと。兄の隊で生還された方! 胸おどらせて、 全身を耳にして郵便配達の、ハイクの音を待ちました。十日・・・十六日目。パイクの音。いそいで飛び出した郵便箱に様からのお便り。まず兄に供え、心を清めて拝読しました。 ここに筆者の方のご了解を得て、再録させていただきます。
「遠く長い年月が過ぎてしまい、私も当時のサラクサクの思い出はだいぶ忘れておりますので、どのくらい思い出せるかと思いますが。私たちは、サラクサクに着いたその日から即、戦闘でしたので、陣地構築も思うようには出来ず、戦いながら構築しなくてはならなかった。なにしろ砲弾と銃弾の飛びかう中でのことで、一瞬たりとも気のやすまることはありませんでした。敵味方の兵の姿こそあまり見えなくても、敵の砲や銃声は谷間に響き、いくら戦地とはいえ、その物凄さにはただ驚きました。しだいに追いつめられて動きの取れない日本軍にひきかえ、物量にものを言わせて攻めて来る敵。 一日おきくらいに来る敵軍の増援部隊、鉄砲弾に向かう肉弾そのもの、想像を絶するものでした。
私たちの陣地壕の下を通り、三百米くらい先の峠を越えて行った兵隊の中で、退いて来る者はひとりとしていなかった。きっと全減してしまったと思う。なにしろ峠付近は友軍の屍体が重なっている位でした。パレテとは違って、 道路がせまく、谷また谷なので、敵も味方も車での輸送とか補給はいっさい出来なくて、兵と兵、 肉弾と砲弾の戦いでした。 そんな中で、一日いちにちと部下を失って行く隊長の心中は、いかほどであったかと思います。
バレテの本隊にはも弾もあり、陣地を築く余裕もあったと思うが、サラクサクにはそんな余裕は全然なかった、私達のような派遣部隊には、限られた鉄砲弾しかないので、これで何日戦えるのかと思う位だったから、隊長としてはなお一層切ない想いをされたことと思います。
こちらの弾には限りがあるのに、敵には無限に近いくらいあり、こちらで一発撃つと敵からは千発ぐらい返って来るので、 一定の陣地で戦うことは出来ず、 一日ごとに陣地移動をしなくてはならず、砲の移動には砲身と砲座で八名はかからなくてはならず、そんなことで日中に射撃するなんてことは、とてもとても出来なかった。なにしろ四方に敵兵、 空では飛行機で見ているので、 壕より外には一歩も出られない。昼日中に射撃をすると、自分の位置を知らせるようなもので、自減するだけのこと。仕方なく、日中標的を定めておいて、日の暮れるのを待って撃つだけ。
何日もしないうちに弾はなくなり、一度、敵から分捕った砲を支給されたが 一日て終わり、とうとう歩兵となる。歩兵といっても銃もない歩兵。本当の肉弾兵。
もうこのころになると、生とか死とか考える者はいなかった。日が暮れて夜が明けて、 その日、 その時があるだけ。分秒後のことも分からん。別に考えるでもない。生きた声を出して言葉を話すだけの、ロポットのような人間になっていたと思う。いくら銃声が近くでも、怖いともなんとも思わん。本能的に身を隠すだけ。私達のような兵隊はそれでもよかった。どうなっても自分一人で済むこと。だが隊長さんは自分一人では済まない。第一に、部下とその家族のことが、いつも念頭にあったようでした。私は塚田本隊の隊員ではなく、桜井小隊だったので、 あまり塚田隊長と顔をあわせることはなかったが、 二度ほどイムガンの川辺で話をしたことがありました。そのときも「もう二度と生きて内地へは帰れまい。誰でも良い、 一人でも多く、なんとか生きて帰ってほしい」と言われました。
もうこの時分に最後の時を定めていたような気がしました。隊長達の陣地は二度砲撃に会い、そのつど何人かの死者が出たと思います。なにしろ物量に勝る敵、わが方にはもう戦うにもなにもない、小銃が二丁や三丁だけでは、隊長としても死んでも死にきれない想いであったと思う。
私は隊長最後の斬り込みに行くときにはいなかったが、谷間で十名ほど集まったときに 「もう終わりだなあ、と言われたそうだ。もうこの時分には、隊長と部下というより、おたがい一個人として話し合うようになっていたと思う。そして四月の終わりごろか五月の初め頃に、自分の軍装を新しいものに着替えて斬り込んで行かれたと聞きました。我々のような一兵卒は一兵卒で済むが、隊長ともなるとその胸中はいかばかりかと思います。
私は幸いにもサラクサクでの生き残りとして帰れたので、 一時も早く皆さんにも知らせる義務があったと思いますが、なにしろ部隊長さんが生存しておられ、すべて知っておられるようでしたので、私がすることでもない、また私がこんなことを知らせるとよくないこともあるような気がしましたので、申し訳ありませんでした。『バレテを偲んで』を読んで、佐藤隊長もあまりサラクサクのことは知らなかったように思います。バレテとはすべてにおいて違っていました。我々は派遣部隊であるため、塚田隊長もどうすることも出来なかったと思います。
私も本当に「最後の一兵」までやって、なお、負傷した桜井隊長と共に置き去りにされた悔しさは、忘れることは出来ません。谷村さんの便りには、サラクサクまで行って来られたそうですが、その当時の面影はなかったと思いますが、峠を越えてからは谷また谷で、私のような山育ちの者でもたいへんな所でした。弾薬はおろか食糧の補給も一切なく「死を覚悟」というより「死してなお」斬り込んでいかなくてはならん位だったと思う。
谷村さんの便りで、皆さんがバレテ・サラクサクに行って来たことを知り、少しでもなにかの参考になればと書きました。戦後何十年過ぎても、あのサラクサクで散った隊長以下皆さんの無念さは、永久に残ることと思います。こんなことを書くのはなかなかむずかしいものです。読みにくいことと思いますが、私の精一杯のところです。知らせたいことは山ほどになっても書けません。本当に申し訳ありません。 M 松岡様」
「過去の戦争の苦しさは二度と思い出したくない。戦友会からも除名してほしいといわれたというM様が固く閉さした心の扉を開き、重い重い筆を運んで、四十二年ぶりに私に記して下さったこのお手紙を拝読し、冷厳な実相の重みに、言葉もなく、電灯を消した暗い部屋の中に、いつまでもうずくまったままの私でした。
「陣地死守」の命令を下した司令部は、最後まで最前線の部隊に撤退の命令をださぬままに、後方に転進してしまいました。敵に占領された山の、陰湿な洞窟陣地にもぐらのようにたてこもり、食糧の補給もなく、砲弾に向かう肉弾で凄絶な闘いを続けなければならなかった兄達。「陣地死守」は「死ぬまで守れ」ではなく、「死んでもなお守れ」の絶対命令だったのです。多くの部下を戦死させた兄の苦衷。部下とその家族を想う兄。派遣部隊の長としての辛い立場。新しい軍装は、散る日のために、兄が大切に取っておいたものでしょうか。
三十三年の生涯を、こんな無残な死で閉じなければならなかった兄の胸中。お手紙を読んだその日から、斬り込み、玉砕する兄の姿が、消えない映像として、私の脳裏に焼きつきました。
終戦後、ラジオの前にきちんと正座し、毎タ復員だよりを聞きながら「兄だけは、どんなことをしてもきっと還って来る。あれほど立派だった兄は、敵の弾丸に当たることは絶対にない。神様が、きっと守ってくださる」と自分に言いきかせていた私。近所の方が次々と復員された頃には、 いつしかその思いは「どんなことをしても還ってきてほしい」の念に変っていました。「たとえ片手片足になっても、ボロボロのからだになっても、這ってでもいいから還ってきてほしい・・・」と。
戦死公報が入り、隊長の佐藤様から詳しい「兄戦死」 のお手紙が届いても、どうしても諦め切れない私は「兄はほんとうは私の兄ではなく、神様だったのだ。少しの間だけ天から降りて、父母にあれほど孝養をつくし、妻子を愛し、弟妹に人の道を教え、心豊かに成長するよう導いて、その務めを果たして天へ呼び返されたのだ。兄と共にあった月日は天与の刻だったのだ。」
そう思うことによって、兄の死を諦めようとつとめたこともありました。でも、天に返されねばならない兄だったのなら、せめて私達の手で、兄のからだを浄め、新しい軍装ではなく、やわらかな新しい白衣を着せて、天に帰してあげたかった。
兄の軌跡をたどっての長いながい私の遍路の旅は、今、終った思いがします。 この筆を取るまでは、「新しい軍装に着替えて、敵中に斬り込み、玉砕する兄の姿」が、 いつもいつも私の胸に映っており、 その映像はどうしても消すことが出来ませんでした。けれど、こうして兄のための紙碑(しひ)を建立させていただいた今、不思議にも、斬り込む兄の姿は消えて、ようやくたどり着いた御み堂に、谷村様から賜いた兄のお仏像さまが、ほのかな金色の光の中に静かに立っていらっしゃる、そのお姿を仰ぐ思いがいたします。いまは亡き仁木先生、かがり火の会の皆様、谷村様、佐藤様、M様はじめ多くの方々に、お導きとお力ぞえをいただきました。敬虔な思いで感謝致しております。
ひとりの肉親を戦争で失った、深くながい悲しみ。この悲しみは私の命が終る瞬間まで、消えることはないでしよう。仁木先生がお創り下さったかがり火の会のお友達と共に、戦争のむごさ、命の尊さを語り継ぎ、平和を守りぬくために、心を結んで歩んでまいりたいと、胸に刻んでおります。
遥か虹の彼方より
遺族
ルソン島・サラクサク峠ー。 母と二人の叔父が、比島戦跡訪問団 (PIC) に参加して祖父終焉の地を訪ねたのは、 四年前のことでした。 のちに、孫の私が、 この慰霊巡拝に参加することになるとは思いもよらぬことでした。
平成十五年三月二十日、奇しくもア米国がバグダット空爆を開始した日に、私はルソン島に向けて出発致しました。翌朝、 事務局の倉津さんから、鳥取バレテ会の山本団長をご紹介頂きました。背筋を真直ぐ伸ばされ、 一徹なご様子は、巡拝団団長としての決意と責任を感じるお姿でした。見廻すと、八十代の矍鑠(かくしゃく)たる生還者をはじめ、遺族・戦友総勢十六名の一行で、今回私はこの方々と、行動を伴にすることとなりました。
激しい戦闘のあった峠、森や海岸で、素朴ではありますが、皆の心の籠もった供養が行われました。一同、静かに御霊に手を合わせ、黙祷する方、語りかける方、山に向かって呼びかける方ー。肉親や同胞へ、それぞれの切なる思いが、祈りとなって届くのでしよう。
以前、ある生還者の方が、亡き戦友のことを偲び、比島の峠に立つたび「これでよかっただろうか。 これで許してもらえるだろうか。」と、問いかけていると、母から聞きました。この言葉は、私の胸を打ち、心に深く刻まれました。生還者のみならづず、人生を真摯に生きようとする者として、最も謙虚な姿勢だと思ったのです。
巡拝三日目、サラクサクに行く日は、未明より激しい雨が降り、ジプニーに乗っても、まだ小雨模様でした。そのような道中、前日のバレテ峠で、会長が読み上げられた慰霊のお言葉が、胸にずっと響いていました。サラクサクの峠に立った時、私は「二十一世紀が始まって三年になります。今こそ私達に日本人の誇りと叡智を、思い出させてください。」と、招魂の言葉を発していました。
慰霊祭のあと、 マリコ部落の皆様との楽しいひと時も過き、ジプニーに揺られ乍ら、峠沿いの山道を帰路に着きました。右に左に、山の頂きや急峻な尾根、深い谷間が現れます。このような場所で戦い、敗退していったのか、と思う胸の中でフツフツと湧き上がる念が、知らずに言葉となっていました。
「こんな所で、草叢す屍となって、眠っていないで、私と一緒に帰って下さい! 今を生きる私達を助けて下さい! 亡霊のまま戻って来るのではなく、雄々しく力強く、聖い志をもって、祖国を出発したその時の姿で、 日本に帰って来て下さい。そして、あなた方の子孫を揺さぶり起こし、この魂の戦いに、今度こそ、勝たせて下さい!」 私の中からほとばしり出た祈りが、私自身を励まし、勇気づけたのです。すると、確かに、何とも云えず温かく、大きな腕に抱き取られたように感じました。
その間も、空は灰色に曇ったままで、薄暮のような光の中を、ジプニーは下って行くのでした。
「虹やが、虹が見えるワ。」 その声で皆、 一斉に窓の外を見ました。霧雨に煙ったような遠くの峰々に、まさに、 虹が掛かり始めているのです。車を止めて、道端の崖の上から眺めていると、少しずつ太く、色濃く、伸びやかに広がり始めた虹は、初々しい若者のようでした。その時、密林の中から、 谷間から、山々の尾根から、英霊が立ち上がり、続々と虹を渡ってゆくのが観えたのです。力強く、祖国を目指して帰って行く姿を、私の魂が獲らえました。虹を見つめ乍ら、私は、静かに、潮が満ちてくるような安堵感と喜びに、満たされていったのです。
帰国の日、遺族として、初めて参加された林さんが、別れ際、「永石さん、ワシは自信がついた。あんたのような若い人が、 こうして巡拝しとる姿を見て、 ワシも、子供や孫らに話してやれる、思うてな。」沁み入るような笑顔で、私の手を握り返しました。
この言葉が、家で、私の無事を祈りながら、待っていてくれた母への、何よりの報酬となったのでした。(二〇〇三・五・十七)
初めて書く父への手紙
遺族 (鳥取県西伯郡)
私の父は、昭和十九年七月に招集されました。昭和二十年七月十五日、ビノンで戦死、三十五才です。
昭和十九年十二月末の台湾からの最後の手紙にフィリピンに渡ることと、もう帰る事ができないと思うから、子供たちのことを頼むという文面が書かれてありました。
一番末の子供であった私は当時二才半でした。父の顔も、思い出もまったくなく、父というものは、私にとって今まで実に遠い、遠い存在でしかありませんでした。十七年生まれの私にとって私の知っている戦争とは、子供三人残されて必死に生きていく母の姿でした。その母の姿がまさに戦争そのものだったと思います。

私たち兄妹は一日も早く成人して母を助けたい、働きたいと思っていました。
“海ゆかば” の歌も知らず、今回の参拝で初めて父を、戦争を、死を知り、そして考える事ができました。
最愛の家族たちを、遠い祖国に残し、知らない国で死んでゆかねばならない無念さは、どんな想像力を働かせて考えてみても、はかりしれないものです。父の悔しさ、 つらさ、寂しさが初めてこの地に立って身に滲みて、心の傷む涙、涙の巡拝でした。この戦争において父を含む多くの方たちの犠牲があって今日の日本の繁栄があるのでしようが、それにしても、何を持ってしても替えることのできない大きな代償であり、戦後何十年経とうとも決して忘れてはならないことだと思います。
初めて書く父への手紙
この旅行で初めて身近に感じることの出来た父へ
お父さん、五十年経ってやっとこの地へ来ることが出来ました。母ももう少し若かったら一緒に来ることが出来たと思うととても残念でなりません、何せ八十才を過ぎていますので。
フィリピンに来るについて母から負ぶってでも、曳きずってでも連れて帰れるものなら連れて帰って来てしいと言われて来ました。その母の気持ちはお父さんもよくわかってくれていることでしよう。でもそうすることの出来ない私はお父さんの魂と一緒に帰りたいと思います。
お父さん、ビノンの丘の見えるイナバンで供養をしていただきました。ビノンはここから十km先だそうです。花、お菓子、果物、水、 コーヒー、 パン、味噌汁、米、思いつくものは全部持って来ました。今まで来れなかった分も。(コーヒーは当時なかったので母が飲ませたいと言ったから)
母のお経、聞こえましたか? 持参していただいた皆様と歌った “ふるさと” 、お父さんの耳に届いたでしょうか? 現地の人たちも大勢来てくださいましたよ。お土産に持っていったボールペンは全員に配っておきましたよ。ビノンから見たイナバンはのどかな田園地帯でどことなく七月頃の鳥取を思い出させるような景色ですね。こんな地でお父さんが眠っていると思うと心が安まります。時間があれば、とぼとぼ歩いてみたかった・・・。
毎年は来られないと思いますが、ぜひまた行きたいと思っています。できれば兄と一緒に。今回の私が参拝したことで母も肩の荷が降りたと思います。母も当時苦労しましたが、現在、孫、曾孫と一緒に元気に暮らしていますので安心下さい。 仁子
父の眠る地を訪れて(一部抜粋)
遺族 鳥取県 気高町
今回で2回目のバレテ会慰霊巡拝、姉妹3人揃っての参加です。
各地を巡拝して、明日はいよいよ最後の日程、父が戦死したコレヒドール島へ行くという日の夜、別れてから五十三年ぶりに父に逢える喜び、または哀しみといいましょうか、私の神経は昂り寝付くことが出来ませんでした。隣の部屋の妹達も同じ思いだったようです。島へは私達だけの別行動の予定でしたが、参加の皆様全員が貴重な一日を費やして一緒して頂き、心のこもった供養をして頂きました。本当に有難うございました。
父は昭和十九年の夏出征し、母は伯耆大山駅まで送っていったそうです。「これが鳥取の水の飲み納めだ」と一口飲んで軍用列車に乗ったのが最後の別れでした。その後、父は佐世保に行き、佐世保の写真館で写した写真を送ってから日本を離れたようです。写真が我が家に届いた頃には、父は遥か洋上であったのでしょう。この一枚が私の父の唯一の写真です。
昭和二十年二月十日に戦死、その直後に下の妹が生まれました。生まれた時にはすでに父のない妹でした。終戦の日の夜、母は私達を前に「お父さんは必ず帰ってくる」と多くは語りませんでしたが、暗い電燈の下で自分自身に言い聞かせるように言った母の言葉と涙が忘れられません。小学一年生の頼りない私を杖に思い、一人で歯を食いしばって頑張ってきた母。働いて働いて身も心もボロボロになりながら、常に明るく強くやさしかった母へ小さい頃よりずっと心に思い続けていたことがあります。 それは、世界中の幸せをかき集めて母にあげたい。こんな夢をずっと持ち続けておりました。果たし得ない夢でしたが、亡くなって二十年以上経つ今でも時々ふっと思うことがあります。その母は、「苦しくて苦しくて何度もくじけそうになったけれども今迄生きてきて良かった。お前たちがいてくれたからここ迄生きて来れた。私は幸せ者だった」と私達に感謝の言葉をたくさん残して亡くなりました。きっと父に逢えたのでしょう。とても美しく安らかな顔でしたから。

コレヒドール島は、戦いの砲弾で島の形が変わったほどの激戦地で、島中焼き尽くして草木が一切生えず、ヘリコプターで草木の種を撒き、今の緑になったとのことです。
島には一時間で着きました。父が眠る島はフィリピン政府管理のもとで美しく整備されていて、日の丸の旗とフィリピン国旗がはためく中央に大きな白い石の慰霊碑が建立されていました。やさしい観音像も安置され、荒野を予想していた私達は少しほっとした気持になりました。祭壇に家から持ってきた水、酒、たばこ、菓子、好きだったお餅などを供えお祈りしました。
「お父さん、輝子が逢いにきました。妹たち二人も来ました。叔父さんもプンカンで戦死されているので叔母さんも一緒です。五十二年もの永い間さぞ淋しかったでしょう。バレテ会の皆様のおかげでこうして来ることができました。本当に嬉しいです。お父さんが戦死された直後に生まれた美佐子も五十二才になり、三人のうち一番お父さんに似ているそうです。一度も抱かれたことのない美佐子です。よく見てやって下さい。お父さんの孫は六人、曾孫も九人です。
戦中戦後のあのきびしい時代にお母さんは歯を食いしばって働き、私達を育ててくれました。心身ともに苦しみながらも常に明るくある時には柱になり、ある時は屏風となって守ってくれました。六十四才で亡くなった母は、苦労したけど生きてきて良かった。私は幸せものだったと、幾度となくありがとうの言葉を残してお父さんの所へ旅立ちました。本当に美しく安らかな顔でした。きっとお父さんに逢えたからでしょう。
今迄生きていてくれたら負ぶってでも一緒に来たかったと思います。どうかお母さんを褒めてやって下さい。そして一緒にいつまでも安らかにお眠り下さい。私達は、お父さん、お母さんのお心に添うように皆力を合わせていきたいきます。また必ず来ます。待ってて下さい。」
何年経ても遺族の悲しみは終わりになりません。生と死をさまよい生還された方々も苦い思いをずっと背負い続けられていらっしゃる。戦いの中に人間の幸せはあり得ません。
疲れもなく、巡拝中いつも父と一緒にいるようで、あったかい父のぬくもりを感じての旅でした。
駄目な顔
遺族(横浜市)
小さい頃から自分の顔には、全然自信がなかった。
従兄からは「鍋の蓋!」とからかわれた。顔が丸く、鼻が低いからである。従兄と喧嘩になると、鍋の蓋、ぐらいでは気が済まぬのか、「新保屋の出来そこない!」と言って、なぶりいじめられたものである。
私は四人姉妹の三番目、長姉は特に可愛く勉強もできた。近所の人達は堀川小町と叫んだのに、私は桁はずれだった。私が小学校の上級生になっても、従兄は相変わらず「出来そこない!」とからかった。
さすがの私もある日、俄然奮起した。顔が駄目なら勉強で物見せると、そのせいもあってか、良い成績で女学校に入った。きれいだった姉は従兄の親友と恋愛し、その後婚約したのだが、かわいそうなことに女学校卒業まもなく胸を病んで天に召されてしまった。
数年後、姉の婚約者が私と結婚しようと言ってくれた。しかし私の心境は誠に複雑で、悩んだ。そして鏡に自分の顔を映してみた。「顔が駄目なら精一杯の真心で尽くそう」という結論を見出すのに相当日数がかかった。
昭和二十年初夏、夫は南の国フィリピンで戦死した。遺書の中の一行に「健康で明るく、しかも自分によく尽くしてくれ、幸せだった。」とあった。涙で読んだ中にも一条の慰めをおぼえ、顔は駄目でもと尽くした四年間の生活を思い出している。
五十年忌を迎えるにあたり
遺族 (姫路市)
四月十八日は、亡夫の比島バレテ峠ヤナギ陣地にて戦死した命日である。
三十三回忌は奇しくも命日の当日に現地比島の地で弔い、来年は、早や五十年忌とは今更乍ら歳月の流れの早いのに驚くと共に、過ぎしあの敗戦後の戦死の悲報、混乱の生活の苦難の日々、日本国民全員がそうであったにせよ、只ひたすら生きた、年毎の苦難の様々も、時といふ流れは、総てのものを浄化し、只々、懐かしい記憶のみを思ひ返すものか、苦しい時程なつかしく思ひ返される。特に私は、主人との縁が人様より短く、一ヶ月余り四十日程で死別した故か。
私も共に渡満した六月から八月迄の南方転出に向け、軍旗を先頭に勇ましく出陣された聯隊長様はじめ主人達の最後の大日本帝國の軍隊の勇姿は忘れることの出来ぬ勇々しい光景でした。
短い夫婦の絆ではありましたが、帝国軍人の妻の誇りと、春の北満の広野の美しい花々 (芍薬、すずらん、ゆり、うつぼかづら、らん等々)、さながら楽園の如き景色は、共に過した、ありし日の思ひ出と共に、美しく、なつかしく思ひ返され、今日迄の私の心の糧とも、支えとも思はれ、六十と九才あと一年で古稀とは、我乍ら感慨一しほ深い思ひがします。子もなく、さりとて財もない自分の今日までつつがなく健やかにある事のみが不思議と思ふ事も度々であるが、十二月十三日付で台湾の高雄からの手紙の末文に、” 神ともなり得れば 恒に守っている ″ の文面のように、主人の加護のお蔭かとも思はれ、残されて余生を、言葉通り謙譲で、健やかに生がいを求めて生き抜き度く思う。
最後に、毎春バレテ会の慰霊巡拝並びに慰霊祭の開催に当り、今日迄の変らぬお世話に相成り会長様、遠路より参拝頂く懇意の生存者の方々のご厚情の数々、遺族として只々有難く深く心より感謝致します。
国の為とは云え若くして命を亡くした主人達の分まで何卒今後健康で一日でも長く長生きをして頂き、来る年の再会を楽しみに筆を擱きます。
我が夫の 御霊もここに集わんと 思へばうれし 今日のみまつり。
栄ゆく 故国のさま いづくにて 知るや知らずや 亡き夫は。
ありし日の 夫の姿を偲ぶなり 常にいとしみ めぐみたまひし。
年毎に こしたがわず 花咲けど 君はかへらず 早や五十年過ぎぬ。
昭和十九年十二月十三日付の台湾高雄から連隊砲中隊長の奥様に宛た最後の手紙
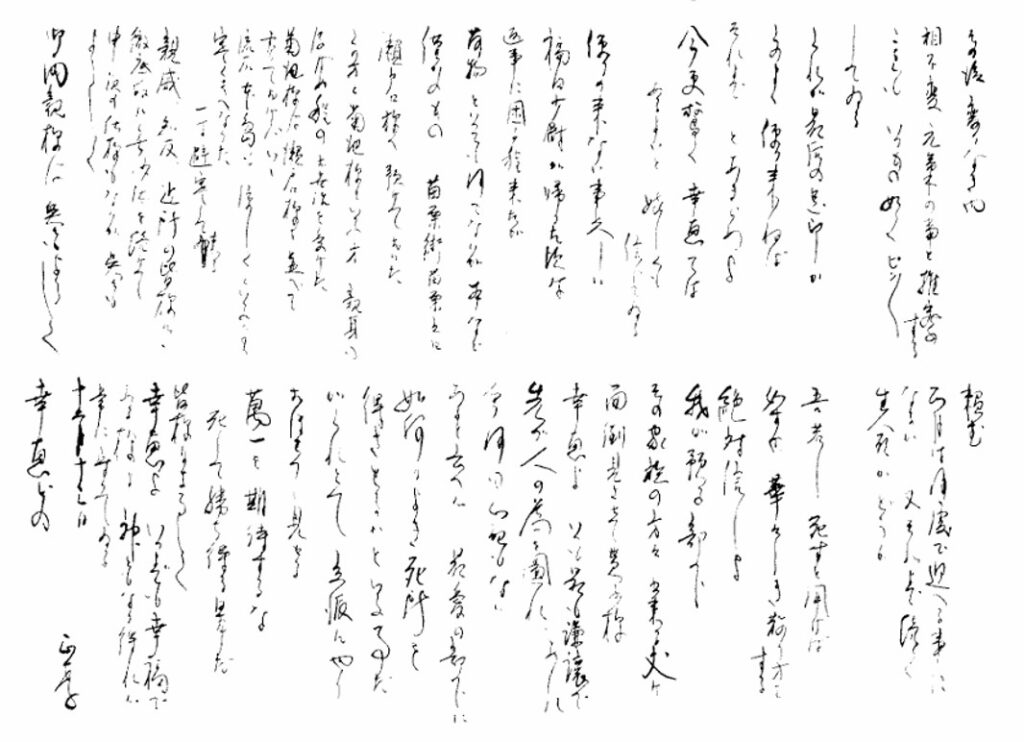
はじめての慰霊祭に参拝して
遺族 鳥取県八東町
生き残りしを贖罪のごと慰霊祭へ 集う老兵の背とうとく拝む
敗を知らなかった日本の歴史を大逆転させたあの第二次世界大戦からもう五十年も過ぎました。十年一昔の諺もあるのに何十年経ってもあの最たる烙印は戦争体験者には墓場までもついて行く。戦後から立ち上り今日の繁栄にまで導いたのも、この方達が不屈の闘魂からの発露に他ならないのに。
戦後生まれが大半を占めようとする昨今、あの辛い戦争体験者は、過去の傷を背おい世の隅へ隅へと葬られようとするかの如き、世相を嘆かわしく思うのも体験者故なのでしょうか。
「比島三十三年目の証言」という本による奇しき縁を以って、戦後五十年目にして始めて護国神社慰霊祭に参拝させて頂きました。義兄が比島で散華したとは聞いていたものの、バレテ会報など目にしていなかったならば、 この私をこれ程までに慰霊祭へ引きつけなかったのではとも思はれます。義兄二人とも比島とビルマで戦没して以後二人の姉達の苦難の人生を見て来た私は、まるで憑かれた者の如く雪の日々戦記物を読み耽りました。少しでも国の為にとの思いのみに従った兄達の足跡が知りたくて・・・。
連休最後の休日五月七日の慰霊祭は五月日和、観光客で賑わう砂丘から薫風が護国神社の境内へも運ばれて来ました。歩兵第六十三聯隊慰霊祭とあって、関西一円からも又鳥取県東中西各地から、比島戦に参加された戦友並びにその戦没者の遺家族方々で、拝殿一杯の参拝者で埋まりました。
戦後五十回忌いや護国の神となられた英霊に対しては五十年祭と申すべきか・・・、私は義兄の遺児にも神となった父に逢わすべく二人の姪達も誘いました。
父応召時十才だった姪も還暦が来たのに、ここに護国神社がある事も知らなかったと言う。 これが民主政治なのであろうか? 社殿にはバレテ会による御献花並びに神饌物が綺麗に飾られて、荘厳の内に神官三人が恭しく祭礼の運び・・・、 その厳粛なる祭礼の中にして生きて帰られた方々の思いや如何に? と、 玉串奉奠に出られる戦友のその老の背に、昔の将兵姿を重ね見る一瞬でもありました。
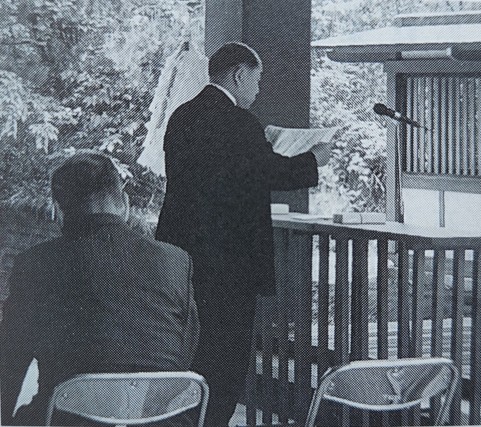
戦没者の未亡人の方々、遠来の御方々、数多くあり、老婦人の拝礼姿に「お母さんも生きていればこの人位の年だろうに」と姪と返らぬ事を呟く。義兄もきっとこの私達をながめてくれてる事だろう。「やっと来てくれて遭えてよかったな。 五十年も経ち、みんな年を寄せたなあ」 と、 拝殿の向うから見られている様にも思えた。
バレテ会会長様の祭文を拝聴しつつ、比島の山野に今なお埋れている屍を想起し、こみ上ぐる熱い泪に胸がふさがれましたが、天空をかけめぐる魂は今この祭場にたち帰り来ましているを思へば、「お義兄さん今日まで知らぬ事とは云えお詣りにも来ませず申し訳もございません」、悔悟の涙が頬を 伝い落ちました。義兄さんの長女はお父さんの出征の時、遺言を十才の私が読める様に、 ひらがなばかりの文字で、「お母ちゃんを助けて弟妹三人のせわも頼む」 と書いてあったと今でも涙で話します。

お父さんが出征の時お母さんの背で眠っていた末弟は、川にはまって亡くなりましたが、残る三人共みなそれぞれの人生を歩いています。護国神社の坂を下りつつ、姪は思い出を語りました。
神社入口に建っている比島慰霊碑の周りに一同集り、ここではテープによる国の鎮めの楽が静かに鳴り響き、やがて君が代と海征かばに合わせて合唱し、 一同神主様に御祓を受けました。バレテ峠慰霊碑前での慰霊祭の模様をビデオで見た折の、あの戦友の呼び声「おーい、又やって来たぞー俺だけ生きて申し訳ないもうすぐゆくから待っててくれー」と、運命の差の叫び声が何とも言えぬ哀しい響となり耳に残りました。
戦後五十年、長い様で短かった思いもする私のこの年月、人それぞれが運命の糸にあやつられながら織りなす人生模様は、神のみが知り給う天命なのかもしれません。今年来よりこの亥年は天変地異があったと言われてますが、符号を合せたかの如く新年早々に未曾有の大震災についで大雪、そして三月には得体の知れぬオウムサリン事件、未だに大量殺人事件の火種はくすぶっているかの世情の様です。
五十年以前より只ひたすらに故国の繁栄と安泰を祈りつつ、犠牲となられた御英霊のかぎりなき御恩を仇で返す様な現代の世情は何たる事か、神のおもわくをお聞かせ願いたい様ですが、余りにも長くつづいた平和ポケに活を入れるべく天罰天啓なるかもと、あの戦争を忘れられない私にはふとそんな思いにかられる時もあります。
御英霊の跡をつぎ行く日本が、どうか末長く平和で安泰であります様に、護国の神とお鎮まり給う御英霊の御加護あらん事を謹んで御祈念申し上げつつべンをおきます。 合掌
フィリピン慰霊ツアーに参加して
先の大戦が終結して68年。終戦の年に生まれた所謂戦後世代が68歳になっていれば、実際に戦地で戦った元日本兵の方々は更に20歳以上の高齢であり、80代後半から90代を迎えている。間もなく、その方達から直接お話を伺う事が出来なくなる日が、もう目の前まで迫っている。
本年(平成25年)3月、 私はフィリピン・ルソン島への慰霊ッアーに参加する機会を得た。 「鳥取バレテ会」というフィリピン戦での遺族会が主催する慰霊ツアーで、この会は元々フィリピン・ルソン島の激戦地バレテ峠で戦った松江六十三連隊の方々が中心となって昭和43年に結成され、バレテ峠周辺で葬られた英霊への慰霊顕彰を目的として現地への慰霊ツアーを毎年続けてきた団体である。しかし生還者の方々の多くが故人となり、近年はその趣旨を引き継いだ遺族の方々が中心となって毎年現地バレテ峠への慰霊ツアーと鳥取県護国神社での慰霊祭を行っているとのこと。
今回のツアーは時期的に時間が自由になる時期であった事、訪問する慰霊地がバレテ峠であった事、そして90歳になるバレテ峠からの生還者の方が1名同行されるという事が慰霊ツアー参加への決め手となった。私にとっては10年ぶりのフィリビン慰霊ツアーであった。
私自身は平成15年に産経新聞社が主催する「牧野弘道氏と行く北部ルソン慰霊の旅」という企画で初めてフィリピン・ルソン島を訪れた。
牧野弘道氏は、平成8年12月8日から4年間に亘り、産経新聞紙上に「あの戦争」というタイトルでパールハーバーに始まった太平洋戦争(大東亜戦争)の4年間を週単位に日を追って克明にたどり、あの戦争はなぜ起きたのか、人々は何を思い何の為に戦ったのか、その時の政治経済、国際関係、国民の生活、社会、思想、 文化などを多方面から分析し、 正しい歴史認識を次の世代に語り伝える秀逸な連載の執筆者で、その後「戦跡案内人」という自称で活躍されている戦史研究家である。
牧野先生の案内で、 フィリピン戦での生還者、 遺族、 有志など一行50名がマニラから北上、神風特攻隊発祥の地「マバラカット飛行場跡」を経て夏のフィリピンの首都・「サマーキャピタル.バギオから北部ルソンの戦跡を一周する10日間の慰霊の旅であった。
そこで私は初めてフィリピンが先の大戦で、 一地域としては最多の戦没者五50万人を出した日本にとって最悪の戦場であることを知った。
更に現地のフィリピン人は、 日米両国の戦争に巻き込まれて110万人もの人々が命を落としたという事実も同時に知った。 それはあたかも2頭の巨象が激しく戦い、 その足元で踏み潰される蟻の如き姿であった。
【大東亜戦争での主な地域別戦没者】(注):牧野弘道氏の資料による)
・フィリピン全域 498,600
・中国本土(支那事変以来) 455,700
・中部太平洋地域 247,200
・ビルマ 164,500
・ニューギニア 127,600
そして北部ルソンでも最大の激戦地となったバレテ峠、サラクサク峠をはじめ、各地の戦跡や慰霊碑を巡り、 この地で戦友を失った生還者の元日本軍兵士の方々、 父を、 兄を、叔父を失ったご遺族の方々と共に慰霊巡拝の10日間を過ごした。
日米戦勃発時の在比米軍の司令官、ダグラス・マッカーサー将軍は、フィリピンに上陸した本間雅晴中将指揮下の日本軍に追われ、 「アイ シャル リターン」 の言葉を残してバターン半島から脱出を余儀なくされた。人一倍自尊心の強いマッカーサーは、自分の軍歴に敗北という汚点をつけられたフィリピンの日本軍への復讐の念に燃えて、膨大な兵力を率い、 昭和19年10月にレイテ島へ上陸して、フィリピン奪還作戦を開始。翌昭和20年1月にいよいよフィリピンの首都マニラを擁するルソン島リンガエン湾に上陸。海軍陸戦隊が激しく抵抗を続ける首都マニラの攻略に手を焼き、無差別砲撃によって日本軍を壊滅させたばかりでなく、この砲撃による10万人と云われるマニラ市民の犠牲者をも厭わなかった。
首都マニラを制圧すれば、もうルソン島での大勢は決した様なもので、北部の山岳地帯へ退いた日本軍を追い詰める戦略的な理由は見当たらない。しかし、 マッカーサーはこの無意味かつ無益な戦いをこの後8ヶ月も続ける事になる。悲惨だったのは日本軍と共に北部山岳地帯への逃避行を強いられた数万の在留邦人である。
マニラから北へ後退した日本軍と在留邦人を追う米軍に対し、山岳地帯への入り口、要衝バレテ峠でこれを迎え撃ったのが姫路の第十師団、通称「鉄」兵団であった。
遠く満州から、決戦場フィリピンへ送られてきたばかりの鉄兵団の兵隊達は、ここにタコツボを掘り、『死守』を命じられた。この峠一帯に陣地を構築して米軍の怒涛の進撃の前に立ちはだかったのである。北部山岳地帯へ逃れた日本軍と在留邦人を守る為、圧倒的な火力と機動力、そして尽きる事のない補給線を持つ米軍に対し、彼らは小銃と手榴弾だけでこの峠を守り続けたのである。猛烈な砲撃と空からの爆撃、そして戦車を先頭に押し寄せて来る米軍の突破を許さなかったのである。
そればかりかこのバレテ峠の戦闘では、 ここに攻め寄せた米軍第25師団の副師団長、ダルトン准将が戦死している。 それ程の激戦がこの峠で展開された。 日中は空からの爆撃と絶え間ない砲撃でタコツボに身を潜めて耐え続け、夜になると「斬り込み隊」と称する決死隊が連日編成されて敵の陣地へ夜襲をかける。ダルトン将軍の戦死も、この日本軍の夜襲によるものとされている。
バレテ峠は今、このダルトン准将の名をとって「ダルトン峠」と改名されているそうである。
昭和20年2月から始まったこのバレテ峠の戦闘は、激闘4ヶ月、100日間の攻防戦の末6月1日についに突破され「鉄」 の戦いは終わりを告げた。峠を死守していた日本兵は、1万1千名のうち9割以上の1万名が戦死し、その殆どは砲撃で吹き飛ばされて遺骨も遺品も遺していないという。
平成15年に初めて訪れた「バレテ峠」の山々は、私の瞼に強烈な印象を植え付けた。そして10年後の本年(平成25年)、 私は再度の訪比が叶い、 このフィリピン慰霊ツアーに参加された90歳のS氏は、 鉄兵団、 松江第六十三連隊に所属しており、 1万人が戦死した地獄の戦場からの奇跡の生還者のお一人であった。
後にS氏から伺った話によると、満州から動員命令が下ってフィリビンへ向かう事となった同氏は、 フィリピン・ルソン島を目前にして乗っていた輸送船が敵潜水艦の攻撃で撃沈されて海上に投げ出された。 一昼夜の漂流の末やっと味方の船に助けられてルソン島に上陸した後に命令でバレテ峠へ。米軍の攻撃が始まって、連日の猛砲撃に晒される中、ある日砲撃によって上官の部隊長がタコツボの中に生き埋めにされてしまい、 これに気付いたS氏が必死に土砂を掘り返して部隊長を助け出したそうである。 この日以来、部隊長はS氏を特別可愛がってくれ、連日連夜繰り出される「斬り込み隊」には最後まで指名されなかった。その事が自分が奇跡的に生還出来た理由だと私達に話してくれた。 その部隊長もバレテ峠で戦死されたとのことである。
高齢と持病のため、マニラから慰霊地へ向かうバスの中では殆ど横になっていたS氏であったが、 バレテ峠へ着くとしっかりと歩いて慰霊碑へ向かわれた。私達一行10名ほどが、慰霊碑の前で祭壇を設えるなど慰霊祭の準備をしていると、S氏は竹竿に付けた日の丸を手にし、慰霊碑の裏側の崖淵へ進まれた。 そこは眼下にバレテ峠を一望できる高台で、1万名の戦友が眠る山々が眼下に拡がっている。S氏はゆっくりと日の丸の旗を左右に振りながら、向かいの山々に向かい、「おーい、 還ってきたぞ~~!」 と大声で叫ぶと、竹竿を握りしめたまま号泣し始めた。
その鳴咽は眼下の谷間にこだまし、10mほど離れた場所にいた我々は、ただその後姿を粛然として見つめるしかなかった。やがて準備が整い、簡素ではあるが厳粛な慰霊祭が始まっても、S氏の手には溢れる涙を拭うタオルがずっと握られたままであった。
戦後68年という長い歳月が経っても、S氏の脳裏からこの地での激しい戦い、亡くなった戦友や上官の事を忘れた日は1日も無かったのである。同行した他のご遺族の話によると、S氏は20年以上に亘って毎年欠かさずバレテへの慰霊ツアーに参加し、その折には戦争で現地の人々に多大な迷惑をかけた事への償いとして、付近の小学校へ学用品の寄贈を続けているとの事である。
2度のフィリピン慰霊ツアーに参加して、私は考え続けている。あの峻険なルソン島バレテ峠で、68年前の若者達は何を思い、何の為に絶望的な環境で戦い続け、そして命を落とさねばならなかったであろう ? 今の日本は、 彼らが命と引き換えに守り通そうとした国になっているであろうか?
人それぞれに考えや意見は異なるかもしれないが、少なくとも、ほんの70年ほど前には、祖国を遠く離れ、空腹に耐え、 砲爆撃に晒され、地獄の戦場で100日間も米軍を食い止め、その殆どの若い命が砲弾に吹き飛ばされて、 一片の骨さえ残さずに散った事実を忘れてはならないと思う。
今一つ、 慰霊ツアーに参加して強く感じた事がある。 我々が現地で行なう慰霊祭は、 参加者に高齢者が多いことや、交通の便の悪い山間僻地を何カ所も廻らねばならない事などから、極めて簡素、短時間のものであった。但し、現地フィリビンへの敬意を表する為、式典の初めには「君が代」の前に、 必ずフィリビン国歌のテープを流す事にしていた。
日本人ツアーの一行が慰霊の為に昔戦場であった村々を訪れると、 どこからともなく大勢の子供達が集まってくる。 子供達は、慰霊祭の供物として祭壇に供えられたお菓子類が、式典終了後に配られる事を知っており、それをお目当てに集まって来るのである。
しかし、 式典の最初にフィリピン国歌が演奏され始めると、 一度の例外もなく、 子供達全員が直立して不動の姿勢をとり、年長の男の子の中には、 きちんと右手を左胸に当てて表敬している子さえいる。皆着ているものは粗末な服で、貧しさの故か、 中には靴を履いていない裸足の子もいた。だが、そんな子供達が、次が演奏された時の態度、行動は感動的なものであった。
日本に戻ってから、 「君が代斉唱胖の不起立の教師・・・云々」などの不輸快なニュースを耳にする度、あの時のフィリピンの子供達の凛とした姿が思い出される。
以 上
【平成25年バレテ会第35回比島慰霊巡拝に参加された東京都の井上孝之様のレポートを転記】
【参考文献】 牧野 弘道著「戦跡を歩く」 「戦跡に祈る」
金井英一郎著:Gパン主計ルソン戦記」
2-3.その他
バレテ峠より発見された認識票
鳥取県護国神社入口 比島戦没者慰霊碑下に奉納
平成六年四月下旬、北九州市門司区清滝 添田氏より事務局に去る四月十七日、比島慰霊巡拝の際、バレテ峠レストランに立寄りし際、店の主人が地獄谷附近で発掘した遺骨並びに認識票を保管して居るとの話があり、同店で同行の僧侶の供養後之を譲り受け帰国。
遺骨は厚生省に連絡引渡し、認識票写真(掲載)を同封、所持者が判明すればご遺族に渡して頂きたいとの来信があり、早速、厚生省に調査方を依頼致しましたが、厚生省に於ても一切不明との連絡を受けましたので、添田氏に「認識票所持者を厚生省で調査致しましたが一切不明にて、当会としては鳥取県護国神社にある比島戦没者慰霊碑下に奉納するのが最善の方策ではないかと考えられる」旨連絡致しましたところ、添田氏も諒承され、認識票の送付を受け、同年九月四日坂口、住谷氏の協力を受け、慰霊碑下に奉納いたしました。
フィリピン山野の至るところに、今も名もなき日本人戦没者たちが眠っている。
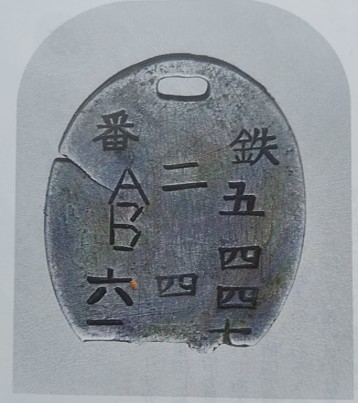
バレテ峠地獄谷より遺骨と共に発見された認識票(鉄5447は63聯隊の戦時通称名)
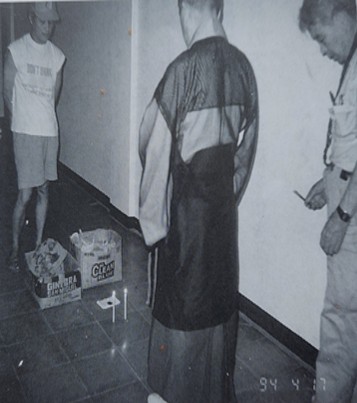
レストランで同行僧侶の読経供養、左帽子の人がレストランの主人
米国より戦利品の写真、遺族に返したい
日本経済新聞大阪本社社会部記者より、昨年八月掲載の写真について依頼がありました。写真三枚は米国の在郷軍人会に所属するゴッドフレイ氏(米二十五師団でルソン戦に従軍)から、酉宮市の戦史研究家に送られて来た写真約二十枚の一部でバレテ、サラクサク戦で戦死した日本兵が所持していたとの事ですが、人手経緯など詳しい事肩は分かりません。
記者は最後迄肌身離さず持っていた肉親の写真だけに、遺族に返してあげたいということで、新聞に掲載して捜す方法もあるが 全国版に掲載するのは難しく、地方版では関係者の目に触れる可能性は少なく、当会の会報に掲載依頼がありました。心当たりの方がありましたら事務局に御一報下さい。
大場 薫様からの手紙ーサンタフェ町へ移住し、地域活動中
フィリピンルソン島サンタフェ町の大場 薫です。
このたびは大変大変お世話になりました。ありがとうございます。サンタフェのバレテの森の再生に真心からの浄財を寄せていただきました。本当に本当にありがとうございます。
いろいろとこれまでにありましたが、 とてもとてもいいかたちで話がまとまったかと思っています。バレテ会の皆様の真心が通じたのは確かだと思います。今後バディリヤ町長を中心として、バレテ峠周辺の整備が進んでいくことと思います。植林も更に進められることでしよう。
サンタフェ町として、公園として整備していくことが約束(?) されたことがすばらしいと私はとてもとてもうれしく思うのです。そして、私の突然のお願いながら、公園の名称を平和公園としていただけることになりました。本当に本当にありがとうございます。来年の2012年においでの時は、整備(公園づくり)がどこまで、進んでいるか、とても楽しみです。楽しみであるとともに心配でもあります。2012年においでのときは、ぜひとも私どもの小さな小学校である、グりグチスクールに児童と一緒に平和の木を記念植樹していただければとも考えています。私どもの学校では、イゴロット族の子どもが学んでいます。毎月一回、森づくりの為の作業もしています。2010年3月・4月の夏休みには、木の種を集めてきて苗木づくりもしました。私どもの学校は"森の学校”でもあるのです。
鳥取といいますと、鳥取砂丘二十世紀梨、大山等々有名ですね。私は山登りが好きです。大山にも2回登りました。登って下りて飲んだビールのおいしさ忘れがたいものとなっています。鳥取環境大学っていうのがありますね。この大学の学生さん2人がサンタフェ町においでになったのは、2005年の10月だったかと思います。私どもの植林の状況を見て帰られました。また、バレテ峠にも行きました。そして、マリコにも行きました。記念植樹として、ナラとマホガニーを植えて帰られました。その木は今はもう5m以上に伸びています。木を見るたびに、この二人の学生さんを思い出します。
毎年のサンタフェ町の学校への教材のプレゼント、ありがとうございます。教科書、教室、先生等々何もかも不足しているのがフィリビンの学校の状況です。しかし工夫によって乗り越えられる面もあるかと思っています。
2011年(今年)、3月3日サンタフ=町でトライシクルのドライバーをしているアルセニオさんと知り合いになりました。アルセニオきんは、 今年で73歳です。バレテ峠に、島取バレテ会の慰霊碑を造る時、石垣づくりの仕事をしたんだ、とも話してくれました。もっともっと詳しい話を聞きたいと思っています。バレテ会の皆様のますますのご健康、ご活躍、 お祈り致します。
2011年3月8日